女性は男性と同じょうに性に貪欲でたくさんの相手を欲していると主張するこれを“積極派”と名付けよう。この派には国籍を超えたたくさんの人々が加わっている。たとえばインドの聖人ヴァーツヤーヤナ『カーマ・スートラ』の中にこう書いている。
 煌きを失った性生活は性の不一致となりセックスレスになる人も多い、新たな刺激・心地よさ付与し、特許取得ソフトノーブルは避妊法としても優れ。タブー視されがちな性生活、性の不一致の悩みを改善しセックスレス夫婦になるのを防いでくれます。
煌きを失った性生活は性の不一致となりセックスレスになる人も多い、新たな刺激・心地よさ付与し、特許取得ソフトノーブルは避妊法としても優れ。タブー視されがちな性生活、性の不一致の悩みを改善しセックスレス夫婦になるのを防いでくれます。
暗黒の大陸

サイモン・アンドレアエ/沢木あさみ=訳
暗黒の大陸
一方の派は、女性は男性と同じょうに性に貪欲でたくさんの相手を欲していると主張するこれを“積極派”と名付けよう。この派には国籍を超えたたくさんの人々が加わっている。たとえばインドの聖人ヴァーツヤーヤナ『カーマ・スートラ』の中にこう書いている。「男性を相手にして達せられないと女性はお互いの肉体を貪りさえする。女性は夫をへいきで裏切る」。
中世ヨーロッパで魔女狩りをしたヤコブ・シュブレンガーとハインリッヒ・クレマーは女性についてこういう記述を残している。
「女性は見た目には美しく、触れると汚れる。そして、手元に置くとこちらの命にかかわる」。
二人は、魔女の秘術は尽きることのない女性の肉欲がもたらすものだと信じていた。
その一方で、女性にたとえ性欲があるとしてもそれをうまく隠すのが普通であり、女性が性にうつつを抜かすことはまずないと主張する一派がいた。これを“受身派”と名付け
よう。この一派の主張は、ヴィクトリア期のイギリスで最高潮に達する。
著名な医者ウィリアム・アクトンが「女性というものは幸いいかなる性欲にもとらわれることがない」と言った時代である。たしかに高まりを覚える女性はいるが、彼によるとそれは「不幸な例外」だった。
そして「精神病院に送られるほどの狂気」に至る可能性があるという。
以来この議論に結論がでることはなかったようだ。なぜなら、決定的証拠が出るはずもないからである。ナギレフの事件の例を別にすれば、女性が男性の介入やコントロールなしに力を持ち自由を謳歌したことはなかった。いかなる時代にも、いかなる場所でも、財産や富の自由、肉体的な強さや政治力を独占してきたのは男たちだったのである。女性が自分の思い通りに振舞う社会は、未だに現れていない。
問題はもう一つある。こうした理論づけを行うのが、つねに男性だということである。そのため女性のセクシュアリティをありのまま見つめるというより、男としての希望や恐れをさしはさまれることになりやすい。
性欲に惑わされない女性のほうが、良き妻に、良き母になってくれそうである。女性が欲望を感じたりしてしまえば、つねにセックスの相手を求め家庭の外に目を向けてしまうかもしれない。
問題はさらにある。どのように客観的な理論づけしようとしても、不確定要素や矛盾からは逃れられない。19世紀や20世紀初頭に活躍した性科学者、リヒャルトメフォン・クラフト・エビングやマグナス・ヒルシュフェルト、そしてヘンリー。ハベロック・エリスなどにしても、しょっちゅう主張を変えていた。
クラフト・エビングは画期的な研究の中で妻の冷淡さに不満を覚えている夫が多いと書きながら、また別の場所では女性の色情狂について延々と述べている。エリスのケース・スタディでも、女性の不感症についての記述が続くかと思えば、女性も性を楽しんでいることを思わせる論調もある。
女性のセクシュアリティに対して
これほど違った見方があるのは、男たちが女性を二つのタイプに分けて考えてきたことの表れだろう。すなわち結婚するにふさわしい“マドンナ”タイプと、外の女にふさわしい“娼婦”タイプである。あるいは、この二つの女性観を一人の女性の中で分ける場合もある。シェイクスピアの戯曲の中で、リア王は言う。「上は女でも腰から下ケンタウロスである」。マグナス・ヒルシュフェルトは二つの見解の妥協点を探って見ようとした。女性の性欲は普段眠っているが、精子の中にある”アンドリン”と呼ばれる物質に呼び覚まされ、花開くのである、と。
こうした後ろ向きで前近代的、しかも男性主体の見解について、20世紀初頭から異議の声が上がるようになった。女性たちが自ら、医者や作家に成ろうとしはじめたときである。けれどもそれからしばらくは、避妊の知識を広め自分で自分の性をコントロールできる女性を増やすのがまず第一の仕事となり、女性の性欲についての研究は置き去りにしがちだった。
初期のフェミニストたちは、快楽を追求すれば自分たちの高邁な思想を疑われるのを恐れ、性欲の問題を避けてきたところがある。「女性には参政権を、男性には純潔を」が、婦人参政権論者のたちのスローガンだった。
1960年、70年代に入り、フェミニストたちの考え方が世の中に広く行き渡ってくると、女性のセクシュアリティを考査する際には女性のものの見方を取り入れなければならないとする意見が、無視できないほど大きくなっていた。
1966年、ウィリアム・マスターズとヴァージニア・ジョンソンという夫婦が女性のセクシュアリティについて行ってきた共同研究を『ヒューマン・セクシュアル・リスポンス』という書物にまとめて出版した。
電子機器とモニターの助けを借りて、二人は女性のオーガズムを観察し
実にリアルに描いて見せた(ロマンティックとはほど遠いが)。それを見てみよう。膣の三分の一(外側)が強い収縮を起こす。最初のころの収縮は二秒から四秒に続き、後のほうの収縮は0.八秒の間をおいて起きる。膣の内側三分の二がやや広がる。子宮が収縮する。絶頂に達し、からだ中が熱くなる。体の様々な箇所で筋肉が収縮し始める。呼吸数、心拍数が高まり、血圧が三割ほども高くなる。声を出す例もみられる。
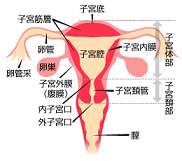
アクトンや彼の信奉者は、怖気をふるっただろう。しかもこの女性の性的興奮に関する詳細な記録は、マスターベーションを観察したものだった。女性のマスターベーション一派にとってはありないものだっただろうし、まさか女性がそこに快楽を見出しているとは思ってみなかっただろう。
彼らの傷口に塩を塗り込むように、調査の報告は続いた。女性の50%が、定期的にオーガズムを経験する。男性がオーガズムに達するよりは時間はかかるが、いったん達すると長く続き、すみやかに繰り返す。
その上、女性は性交しなくてもオーガズムに達する。シェア・ハイトが1976年に出版した『ハイト・リポート』で明らかにしたとおり、女性にとってペニスの挿入よりマスターベーションのほうがオーガズムを得る手段としては有効である。
未だ女性の性欲の存在に疑問を感じている人々がいたとしても、
中には快楽のために夫を必要としない女性さえいるのだという事実が生きた証拠となった。だがそれも“積極派”と“受身派”の議論は終わらなかった。いや、ますます過熱するばかりだった。両方の派閥ともやや意見を変え、敵に譲れるところは譲り、次の対決に備えて刀を磨いて待っていたからである。女性のオーガズムより、その機能へと関心は移っていったのである。いったい何のために、女性はオーガズムを感じるのだろう?
西洋にはギリシャ時代の昔から、この問いに対する答えが二つある。一つは女性のオーガズムがもたらす震えが精液を究極の目的地へ送り込み、妊娠を促進するという答えである。そしてもう一つは、オーガズムは女性の健康全般にいい影響をもたらしているというものである。
フェミニストの精神科医、メアリ・ジェーン・シャーフィーの考え方は後者を少し変形してみせたものである。1972年、議論を呼んだ論文『女性性の進化とその本質』の中でシャーフィーは、人類の始祖たちは性的に奔放な女性の支配する社会を形成したという見解を示している。
この社会の女たちは、好きな男と好きなときに交わり、そこに感じるオーガズムは、骨盤から不要な鬱血を取り除くのに役立ったという。その結果進化論的に見ると、性に積極的で長く強いオーガズムをしょっちゅう感じる女性が有利だっただろう。
この一見放牧歌的な母系制社会、すなわち母の支配をみなが喜んで受け入れる社会があったという考え方は、19世紀すでに、過激なフェミニストたちのお気に入りだった。
だがシャーフィーの説には考古学的な裏付けがなく、近代医学もこの説を受け入れていない。
このためシャーフィーの説は科学者たちに相手にされなかったが、フェミニストたちには大いなるインスピレーションを与え、これをもとに様々な(ありがちな)シナリオが生まれることになった。
中でも有力なのは、サラ・フルディの説だろう。チェコ人の血を引く霊長類学舎のフルディは、インドでフィールドワークを行い、ハヌマンモンキーという野生のサルを観察した。そして、重要な事実を二つ知った。まず一つ目は、雌たちが(他の霊長類と同じように)性に果敢で積極的だということだった。
そして二目は、グループに加わりたての雄が乳を吸っている子どもを殺そうとすることだった。子どもを殺す理由は明らかだった。雌から子どもを奪えば雌はまた性に積極的になり、新たな雄にセックスのチャンスがめぐってくる。
このような厳しい環境の中では、雌も子どもを殺されないよう、きちんと戦略を立てなくてはならない。その結果雌は積極的に相手を探して多くの雄と交わることになった。こうすれば、赤ん坊の父親が誰か解らなくなる。誰の子か解らなくなると、最良の場合は雄が養育に手を貸してくれる。
最悪の場合でも放っておいてくれる。どちらにせよ、子どもを殺されることはない。女性が性に積極的になるのは、男性から生活の糧を引き出すための武器であり、子どもを守るための盾だったのである。
このうち片方でも本当なら、性に積極的な女性が淘汰をくぐり抜けてきても不思議ではない。フルディはこう主張した。“積極派”の主張はもうわかった――そろそろ言いたくなるころかも知れない。
だが積極派は、まだまだ別の手を打ってきた。女性は確かに性に快楽を見出しているが、女性の性欲は男性よりもっと上品なもので、相手の関係や気持ちに大きく左右される。
基本的にこの考え方は、従来の“受身派”に、オーガズムを付け加えただけのものである。そして、この“新受身派”の代表が、前章に出てきたドナルド・サイモンズなのである。
サンタ・バーバラで若かりしり頃の人類学者サイモンズは、女性に強い性欲や、それを満たすためのクリトリスを必要とする理由はないと主張していた。なぜなら、「飽くことのない性欲を満たすための奮闘を続けるのは多大な時間とエネルギーを要し、女性にとっては有利ではない」ためである。
古代ギリシア人がどう考えていたとしても実際は、オーガズムは妊娠に必要なものではない。
性交すれば必ず得られるものではないし、鬱血を防ぐという説はお話にもならない。子どもを守るため多くの男と交わるという説は、サイモンズにとって無知の産物にしか思えなかった。女性の性欲が強ければ、食物の採取や子育てという大事な仕事の妨げになるとサイモンズは主張した。
サイモンズは女性のオーガズムの存在を否定したわけでもないし、女性が性に快楽を感じないと主張したわけではない。けれども彼にとって、快楽は進化の副産物なのだ。性欲が男性にとって進化論的に有利なら、女性にも性欲があった方が都合がいい。だが女性の性欲のほうは、進化によってもたらされるものではない。
“積極派”か“受身派”か? 「飽くなき性欲」か「恥ずかしやりや」か? 70年代から80年代前半にかけて、議論は続いた。霊長類研究者や人類学者、いや、鳥類学者までが意見を述べた。
そして、男性の性欲が心理的に研究されていくのにつれて、そのテクニックが女性にも適用されていくようになった。
つづく 10、量より質
男性の性衝動について考察した際、男性にはできるだけバラエティ豊かな受胎可能な女性と性交したいという欲望がプログラムされていることを確認された。ラッセル・クラークとエレイン・ハットフィールドの実験では、魅力的な女子大生に声を掛けられた男たちが、すぐにセックスできそうな申し込みであればあるほど興味を示すことが解った。