出産は胎児にとっても大事件だろう。9ヶ月間も安全で変わったことの起きない胎内にいたあとで、突然新世界に投げ出されるのである。目は開き、指はあたりを探る、視覚、触覚、嗅覚、聴覚、味覚が突然目覚める。五感が様々な感覚を連れてくる。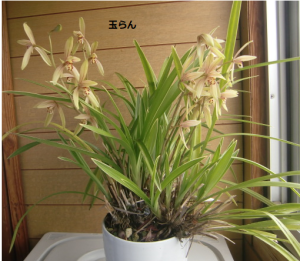 煌きを失った性生活は性の不一致となりセックスレスになる人も多い、新たな刺激・心地よさ付与し、特許取得ソフトノーブルは避妊法としても優れ。タブー視されがちな性生活、性の不一致の悩みを改善しセックスレス夫婦になるのを防いでくれます。
煌きを失った性生活は性の不一致となりセックスレスになる人も多い、新たな刺激・心地よさ付与し、特許取得ソフトノーブルは避妊法としても優れ。タブー視されがちな性生活、性の不一致の悩みを改善しセックスレス夫婦になるのを防いでくれます。
子宮から世界へ

サイモン・アンドレアエ/沢木あさみ=訳
子宮から世界へ
出産は胎児にとっても大事件だろう。9ヶ月間も安全で変わったことの起きない胎内にいたあとで、突然新世界に投げ出されるのである。目は開き、指はあたりを探る、視覚、触覚、嗅覚、聴覚、味覚が突然目覚める。五感が様々な感覚を連れてくる。その中には心地よいものもあれば、一瞬で嫌悪を感じるものもある。この目新しい感覚の嵐を、人はどのように乗り切っていくのだろう? この先どうすればよいのか、どうやって知ろうとするのだろう?

シンディ・ヘイザンはそのヒントを掴んでいる。長年にわたり、彼女は乳児が両親の絆を築くプロセスと、それが上手くいかなかったときの結果について研究してきた。子宮を離れた瞬間から、赤ん坊は助けを求めて手を伸ばして、目の前にいる人をじっと見つめ、注意を求めて泣く、ヘイザンと仲間の研究者によればこれは赤ん坊が、人類が存在していくのに最も強力な武器、すなわち愛着メカニズムを駆使し始めたことにほかならない。
1940年代、心理学者のジョン・ボルドリーやメアリー・エインズワース、ジェィムズ・ロバートソン、ジョイス・ロバートソンなどの心理学者からなるパイオニア的な研究チームが、親と引き離されたときと再会したときの赤ん坊や小さな子どもの反応をフィルムに収めた。
その頃の小児科病棟は統制を重んじる融通の利かない場所で、子どもが興奮するといけないので親の訪問はあまり歓迎されていなかった。スタッフが不親切なわけではなかった。子どもたちは食べ物を与えられ、守られ、温度の保たれた場所にいた。だが赤ん坊たちは、ただ一人も例外なく悲しんだ。
最初は大声を上げたり手を突き出したりして抵抗する。だがそのうち、受け身の失望に陥っていくのである。そしてここまで来てしまうと、いざ両親が帰って来ても喜ぶというより、怒りをぶつけたり、すがり着いたりする。あるいはまた、まったく関心を示さないこともある。
赤ん坊は明らかに、世話をしてくれる人々との交流を望んでいる。そしてそれが得られれば、たとえ食べ物やぬくもりが与えられて生存が脅かされていなくとも、腹を立てるのである。そのうえ大人と交流できなくなると、自覚しているのかどうかは解らないが、大人の注意を引くような振る舞いを始める。
大人をじっと見つめたり、手を伸ばしたり、まとわりついたり、しぐさを真似したり回らない口で何かを喋ろうとしたりするのである。
ロバートソン夫妻と仲間の心理学者たちがこのフィルムで伝えたかったことはこうである。人類は昔から、生存のために愛着という手段をとってきた。それは進化論から見て必要不可欠な手段だった。子どもが親を惹きつける手段を持って生まれてくる。
親を魅惑し、安全で健やかな発育を保証してもらえるように。親と子の愛着はのちの人間関係の土台となるだけではない。赤ん坊によっては、生存するための手段なのである。
たいていの両親は赤ん坊の魅力に捕らえられ、献身的に世話をする。そのとき注ぐ無条件の愛は、人間の根源的なところにプログラミングされているのである。こういう環境では、赤ん坊は予定通りすくすくと成長していく。
赤ん坊は匂いで母親を見分けるが、生まれたての段階ではまだ、母親以外の人々の注意をひきつけておこうとする
だが成長するにつれ、特定の人々だけ、中でもまず世話をしてくれる人(母親であることが多い)にだけ、愛着を示すようになる。生後七ヶ月ほど経って、はいはいを始めるころには、世話をしてくれる人以外では満足できなくなる。そして、見知らぬ人には打ち解けず、警戒心さえ抱くようになる。我儘を言い、すがりつき、大声で叫ぶ愛着行動は、よちよち歩きをする頃ますますつよくなっていく。だんだん広くなっていく世界の中で安全なホームベースとなってくれる世話人に頼ることがますます多くなるからである。だが、自分の要素は叶えられるものだという安心感が子どもにあれば――この世界は恵み深い場所だと子どもが思えているならば――こういった要素は弱くなっていき、やがて少年期を迎えるころには、独立の準備が始まる。
これが理想的なプログラムで、60パーセントの子どもがこのプロセスにたどって成長して行く。世話をしてくれる人(親)との間に健全な絆を築いてきた子どもたちである。
ところが親の中には、子どもが必要とする無条件の愛情や絶え間ない注意を与えられない者もいる。何かの理由で長い間子どもの側にいられない親もいれば、とにかく子どもとの絆を築くことのできない親というのも存在するのである。あるいは親自身が、健康問題や家庭内暴力、家族の問題等を抱えている場合もある。そのような状態の中では、健全で安定した人間関係を作ることはできない。
こういう場合、子どもはまっとうな成長ルートを辿れなくなる。そして人と人との絆作りに際しての障害を抱えるようになり、それが他の人との関係にも大きな影響を及ぼすことになるのである。
世話をしてくれる人の態度が終始一貫せず、要求にこたえてくれることもあれば応えてくれないこともあるとすると、子どもは混乱し、普通よりも甘えん坊になり、側から離れようとしなくなる。メアリー・エインズワースはこれを”不安/アンビバレント状態”と名付けた。また親が子どもの要求を無視続けると、事態はさらにひどくなる。子どもは自分の中に引きこもって親を無視し、接触を持とうとしなくなるのである。
また親が虐待したり、親自身が精神病を抱えているせいで子どもにまちまちな態度を取ると
子どもの行動も乱れていき、あるときは親に甘えるかと思うとあるときは親を避けるようになる。何よりも悲劇的なのは、孤児院の子どもたちである。ボウルビーを始めとする研究者たちによると、親との絆を築く機会が一度も与えられなかったり子どもたちは身体の不調が出たり、うつ病になったり、自殺する傾向があり、大人になっても人間同士の絆を築くのに苦労するという。この障害について研究を重ねたヘイザンと仲間の研究者たちは言う。この研究は、標準的な子どもの成長のメカニズムを究明する鍵になる。それだけではない。大人になってから性的な絆を築くときのメカニズムにも、いくらかヒントを与えてくれる。
公の場でデートして愛を囁き合っている恋人たちは、乳児と親が築く一連の行動パターンと同じパターンが見られるとヘイザンたちは言う。会ったばかりで惹かれ合ったカップルは、複雑な駆け引きをする。まず相手の興味を引き(ここでは耳をつんざくほどの叫び声を上げるのではなくおしゃべりを仕掛けることの方が多い)、軽く触れ合い、恥ずかしげな微笑みを交わし合い、やがてもっとはっきりと視線を交わすと、相手のしぐさなどをなぞって髪をかき上げたり、ワインをすすったりしはじめる。食べ物を分かち合うことさえある。
その後もこうやって始まった関係は、親と子との関係に似た発展をしていく。まず相手にまだあまり慣れていない状態。このときには、色々な相手と付き合う。そして相手を一人に絞った状態。
二人の間には、恋人ならではの深い関係が生まれる、そして結婚し、絆そのものが暮らしの一部になっていくのである。
大人になってからの恋愛シナリオがこれほど親と子の愛着パターンに似ているのなら――同じようなメカニズムで同じようなプロセスを辿っていくのなら――大人になってからの関係には子どものときの関係が色濃く見えるに違いない。
ヘイザンと仲間たちはそう考えた。そしてこの辺りをもっと深く研究するために、ヘイザンと心理学者フィリップ・シェイバーはコロラド州デンバー最大の新聞『ロッキー・マウンテン・ニュース』にアンケートを載せた。大学生が寄せた百件の答えに加え、一般の人々からも六百件答えが寄せられた。
アンケート用紙はまず、親と子の関係の三パターン――安全型、不安型、忌避型――についての説明を載せ、自分がどのパターンを辿って選んでもらった。そしてその後、大人になってからの恋人の関係に関する質問が続いた。
親に無視され、拒否されることが多かったために、忌避型のパターンで育ってきた人々は
恋人とも距離を取りたがるということがわかった。感情の浮き沈みが嫌いで、誰とでも深入りしたくないと思う傾向が強かった。嫉妬もあまり感じないが、親しくなりたいという気持ちも弱い。それに対し、親の愛情が首尾一貫していなかったために不安に駆られながら成長した人々は、まったく違った愛のパターンを見せていた。感情が激しく、焦燥感が強く、相手の注意を引きたがる。嫉妬も思い込むと強いと同時に、一目ぼれや愛の力を信じ、恋人との身体や心の交流を求める気持ちが人一倍強い。
この二種類の人々に比べ、大部分の人たち、自分の育ち方を“安全型”とみなしている人たちは、愛と性に対して前向きに望んでいて、しかも一人の相手と長続きする。“忌避型”の人々が、一人の相手と付き合いの続く期間は平均5・97年、ストレスを感じることの多い“不安型”が4・98年なのに対し、“安全型”の人々の場合は、平均10年続く。
赤ん坊のときの親とのつながりと恋人とのつながりに関係があるとするなら、親しい者同士が赤ちゃん言葉で話すことは不思議ではない。そして、自分の異性のおやと似た容貌、振る舞い、匂いの相手に惹かれるひとが多いのも説明できる。
また、アメリカの心理学者アーサー・アーロンが新婚夫婦を対象に行った実験では、夫も妻も自分の母親に似た相手を選んでいたという結果が出ている。
こうした数々の実験にはたしかに説得力がある。子どものとき親と築いた関係が大人になってからの性的な関係に影響を及ぼすのは確かなようだ。だが、自分の両親との間とはまったく違ったシナリオ、違った関係に惹かれる人は多いのも事実である。
だとすれば、考えられるのは一つである。他にも何かの力が働き、事態を複雑にしているに違いない。
つづく 45、神経のネットワーク・性暴力
人間は幼いうちに性のパターンを身に着けるのだと信じるようになった。幼児は何をすれば快感を、不快感を感じるかを経験させ積み重ね、それを徐々に覚えていく、そしていったん覚えたことは、なかなか忘れ去ることはできない。