煌きを失った夫婦はセックスレスになる人が非常に多い、新鮮な刺激・心地よさを与える特許取得ソフトノーブルは避妊法としても優れ。タブー視されがちな性生活、性の不一致を改善しセックスレスになるのを防いでくれます。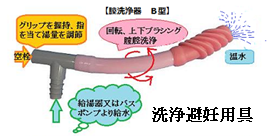
第Ⅴ章 愛の万華鏡
 渡辺淳一著
渡辺淳一著この章では、
一組の愛し合う男女が頂点に登りつめる。
その華麗なる愛の世界の実態と、
それを描写した文章が集められている。
いま、その愛の頂点にいる人はもとより、
それを願う人たちも、
この世界の妖しさを実感するとともに、
その深さを重さについても想像し、
考えるきっかけにしてほしい。
1 セクシイ
(230)最上の褒め言葉「セクシイというのは、男が最も素敵な女性に捧げる最上の褒め言葉だよ」
―うたかた
(231)いい女
「ただの綺麗な女から、いい女になった」
「それ、どういう意味ですか」
「セクシイということさ」
「いやだわ」
「そんなことはない。美しい女は沢山いるけれど、セクシイな女はそうはいない」
―桜の樹の下で
(232)近づいたら
「凄くきちんとしていて、そのくせ、なにか思い詰めている感じで、心配で目を離せないと思って近づいたら‥‥‥」
「そうしたら、どうだったの?」
「たいへんなエッチだった」
―失楽園
(233)ためらい
菊乃の脱ぎ方には、どこか嫋嫋(じょうじょう)として秘めやかなところがある。
やがて脱ぎ終わったのか動きがとまり、いままで立っていた影が小さくなってしゃがみ込み、その位置から、黒い影がゆっくり近づいてくる。
闇の中で白い長襦袢(ながじゅばん)がかすかに揺れて、音もなく近づいてきた菊乃は、ベッドのわきで一瞬ためらい、それから身を屈(かが)めるとそろそろと入ってくる。
―桜の樹の下で
(236)肌に降りる積む桜
ひとひら、そしてまたひとひら、風に追われた花片が舞いこみ、凛子の白く柔らかな肌が徐々に桜の花片で染まっていく。
―失楽園
(237)桜変化
夜のなかで淡く浮き上がる女体を見ながら、遊佐の脳裏に再びさまざまな桜が甦(よみがえ)ってくる。
花曇りの空の下で、枝垂(しだ)れ桜が武家屋敷の黒板塀に降りかかっていた。振り返ると京の八坂の真昼どきの枝垂れ桜は真紅の滝のようで、夜の枝垂れは夜火事のようであった。
―桜の樹の下で
(236)月光の視線
初めて、すべてを剥ぎとられた女体を、上から猛々しく襲うつもりであったのが、美しさに見惚れるうちに惜しくなり、なおしばらくこのまま眺めていたい。
若いときは、ひたすら奪うことしか知らなかったが、年を経たいまはむしろ目で犯す悦びも深い。まさに視姦(しかん)とでもいうのか、自ら月の光になり、白い女体へ浸透(しんとう)するように視線を這わせる。
―失楽園
美しい女は少なくないが、セクシイな女は少ない。同様に、姿のいい男は多いが、セクシイな男は少ない。なぜなら、美しさやハンサムは外見の問題だが、セクシイは内面から滲むものだけに、一朝一夕には成り立たないからである。
2 前戯
(237)愛撫が必要はっきりいって、女性と猫ほど丹念な愛撫を必要とするものはない。
それを充分に与えるかぎり、この二つの生きものは慈雨を受けた草花のように日々新鮮に美しく、艶やかに咲き誇っていく。
―マイセンチメンタルジャーニイ
(238)餌づけ
里子はもう逆らうことはない。求められるままに、自分のほうからそっと唇をさしだす。親鳥が子に餌を口移しに渡すような仕草に似ていると、つい可笑しくなる。
―化粧
(239)乳首と舌
ゆるやかな丘をこえて唇が乳首をとらえると、それをまるごと口のなかに含み、ゆっくり舌を動かす。左右に、そしてときに円(まる)く舌を絡ませながら、久木はいまなにも考えていない。母と子が、生まれたときから乳房と唇で結ばれたように、女と男と舌で未来永劫に結ばれている。
―失楽園
(240)吐息
「抱いて‥‥」
瞬間、滝野はそれを闇の中から浮き出てきた声のように聞く。たしかに梓の口から洩れたと知りながら、それは二人のあいだの濃密な空間から生みだされた吐息のようである。
―かりそめ
(241)優しい感触
秘所の蕾(つぼみ)に添えた手も、指先が触れるか触れないくらいの軽さで、強さはほとんど必要としない。柔らかく、優しければ優しいほど女の感覚は研ぎすまされていく。
よく女性達が、「優し人が好き」というのは、外見でなく、タッチの優しい人、という意味といっていいほど、女性と接するときはまず優しさが武器となる。
―失楽園
(242)反撥
「いやよ」
瞬間、聖子は呟いたが、言葉とは裏腹に、顔は加倉井の胸へ押しつけていた。
いま聖子の言葉に特別の意味はない。
奪われることに、もはや抵抗はない。もしいくらかの反撥があるとすれば、それは恥ずかしい思いをさせたり、じらされたりすることへの恨みである。
加倉井が強引であったから自分は奪われた。その言い訳さえあれば、いまの聖子は素直に加倉井を受け入れることができる。
―夜の出航
時間をかけて丹念に優しく愛撫する。性急で我慢のきかない男にはいささか苦手な作業だが、それが豊かなエロスへ通じる第一の扉である。
3 エクスタシイ
(243)禁断の木の実いま二人が汚濁にまみれた現世にいるのは、性という禁断の木の実を食べたからである。その罪のゆえに神の怒りに触れて、天上からこの世に堕(お)とされたのだとしたら、思いきり性を貧(むさぶ)り、堪能して死にたい。
―失楽園
(244)エクスタシイ
ここであえてエクスタシイを定義すると、性的に完熟した女性が性行為によって興奮の極みに達したとき、激しい快感とともに一時的に雲の上を浮遊するような、ときには意識が虚(うつ)ろになるような絶頂感にとらわれる瞬間のことである。それは肉体的には膣の周りに血液が充満して膣内の温度が上がり、内壁の粘膜が小刻みに痙攣(けいれん)するとともに、男性自身に密着する状態、とでもいえばいいのかもしれません。
―男というもの
(245)花開く
相手を愛し、信頼し、そして当の男性がそれに応えて適切にリードするかぎり、女性の性の性はたしかに花開いていく。
特別異常でもない限り、女体は悦びを感じるようにつくられている。
―新釈・びょうき辞典
(246)弛緩
最後の息絶えるような声をあげた後、冴子は首をのけぞらし、八津の胴にまわしていた手をだらりとベッドの上に投げ出した。軽くあけた口が大きな息を吸い、寄せられていた眉根がゆっくりと開いていく。全身から力が抜けて、萎えたまま、八津はなお惜しげに唇を近づけ、反応のない冴子の舌を吸い続けた。冴子の目は閉じられ、長いまつ毛が蓋(ふた)を伏せたような深々と目のまわりを覆っていた。
―失われた椅子
(247)宙に漂う
体が火となって走っていく。もう止めたりはしない。目をつむり。髪をふり乱して走っていく。男に組みしかれ、悦びに波打つ肢体が少し前、白衣を着て患者の脈をとった、その体と同じとは思えない。
喉から洩れる小さな声とともに倫子は遠い宇宙へと飛び出す。瞬間、きらめくような星座がみえ、やがて広く豊かな宇宙に漂う。
直江がどうであったのか、自分がどんな恥ずかしい声をあげ、どんな動きをしめしたのか、一切が闇の彼方に茫漠(ぼうばく)として定かではない。
―無影燈
(248)愉悦の瞬間
「だめよう‥‥」
気持ちの上では抑えようとしているが、?はすでに走り始めているのか、あるいは?が走り始めたのを知って、せめて言葉だけででも抑えようとしているのか。
一旦、走り出した?は、もはや止まりはしない。熱く、火ぶくれのように燃えた花芯が、小刻みに痙攣を繰り返しながら行き果て、それとともに女の内側がビロードの襞(ヒダ)となって男のペニスに巻きついくくる。まさに。それは男の愉悦の瞬間で、このいっときをえるために男は女に尽くし、優しさを振る舞い、出費する。膨大な時間と金と労力を費やして女に奉仕するのは、ひたすらこの果てるときを共有したいためである。
―失楽園
(249)比例の方程式
女が燃えすぎて、男が困ることはない。女が燃えれば燃えるほど、男の愛しさは増していく。 ―かりそめ
エクスタシイを満喫した女性と、していな女性とでは、男というものへの愛着と認識はまったく異なっている。同様に相手の女性をエクスタシイに導いたことのある男と、導いたことのない男とでは、女に対する愛着と怖れがまったく違っている。
4 後戯
(250)静寂なとき燃えているときはもちろん、燃え尽きたあとの静けさにも味わいはある。
その瞬間、男はすべてが終末に向かうような予感を覚えるが、同時に無の世界に墜ちていくような安らぎも覚える。
ふかくつながり合っている男と女が改めて愛を覚えるのは、この燃えつきたあとの、時が止まったような静寂のときかもしれない。
―うたかた
(251)情事の後
気がつくと、滝野の腕の中に梓はすっぽりとおさまり、女の頭は男の左の肩口にあり、女の上半身はやや覆いかぶさるように男に寄り添い、燃えた余韻の残る女の股間に、男の腿が忍び込んでくる。
その近づき方は情事の前と変わりはないが、いまの姿は、ともに満ち足りたという充足感のせいか、密着していながらどこか余裕があり、その軽く緩んだ抱擁の感覚が、また気怠(けだる)く心地よい。
もはや梓は、どこをさわられても逆らう気配はない。唇はもちろん、乳首も腋(わき)も、柔らかな繁みのまわりも、触れるに任せ、ひっそりと眼を閉じている。
―かりそめ
(252)合体
抱かれながら、多紀はいつも、人間と人間の?は、どうしてこの程度しか密着できないのかと思う。これ以上、触れ合う面を広くできないものなのか。表も裏も、胸も背中も、膝も足の裏も、すべてを重ね合わせたい。
多紀は必死にしがみつく。頭を擦りつけ、下半身をおしつけ、足を絡ませてにじり寄る。まるで親犬のお腹の下に、乳を求めて潜り込む子犬のようである。
―まひる野
(253)人肌
まことに、人肌ほど心地よいものはない。
むろん好き嫌いや相性もあろうが、肌と肌を接している限り男も女も心が休まり、苛々(いらいら)も焦りも、不安も怯(おび)えも、すべてが薄れていく。
この世に生きとし生けるもの、すべて肌を接しているかぎり争うことはないのに、生活や仕事に追われて人々はそれができなくなってしまった。まず会社に行くためには、互いに離れなければならないし、人に会うときを触れたままではまずい。さらには道徳や常識や倫理など、厄介なものができてから、肌と肌とを接したままでいる時間は急速に減ってきた。
―失楽園
(254)散る花
一夜明けて、鉄幹は一段と余裕を見せてゆったりと構え、それに対して。晶子は初々しい花嫁のようにかしずく。
昨夜、二人の初夜を守るように閉じられていた板戸を開けると、雨は完全にあがって鋭い朝日が射し込み、縁に立つと石畳にそっと清水が流れ、その先の椿の葉が陽を照り返して光っている。昨日、晶子が夕暮れの中で見たときは、その椿の根元に真紅の花が一輪落ちていたが、いまその横にさらに一輪くわわり、昨夜、二人が休んでいるあいだに散ったことに、晶子は軽い羞恥を覚える。
―君も雛罌栗(コクリコ)われも雛罌栗
(255)ボディランゲージ
とやかくいっても、男と女のあいだは一夜、しっくりと抱き合えば事情は変わってくる。罵(ののし)り、憎み合っても、一夜明ければときに笑い転げて、昨夜の争いがつまらぬ他愛のないものに思えてくる。
表面の言葉ではわかり合えぬことでも、?ごとぶつかれば、自ずと分かり合えることがある。中途半端な言葉より、直接、?と?で語り合った方がたしかではやい。
まさしく、ボディランゲージに勝るものはない。
―化身
(256)虚飾を捨てる
男が求めていながら、気がつくと女が求め、それに促されて再び男が求めていく。ともに求め合いながら、二人は虚飾のすべてをかなぐり捨てて生まれたままの男と女に戻っていく。
結ばれた後、身軽になったように思うのは、そうした装うさまざまなものを振り払ったせいかもしれない。
―うたかた
情事のあと、肌と肌を触れあわせたまま燃えた余韻に浸っている。それこそまさにボディランゲージで、声に出す言葉はすべて不要である。
5 変貌
(257)魔物「また、違うのよ」
つい少し前と今回と、同じ果てても内容が違うことをいっているようである。
それをききながら久木は、男のすべてをつつみこむふくようかな女体が、突然得体の知れぬ魔物のように思えてくる。
―失楽園
(258)情事の影響
情事ごとに霞の肌はうるおい、和らいでくる。それは顔の表情や、胸元のまろやかさ、手のふとした仕草など、霞の全身から匂ってくる。そんな、日と時によって揺れ動く女体に伊織は驚き、呆れながら、羨ましいとも思う。男の?は冷静といえば冷静だが、常に淡々として波がない。情事によって、匂うように美しくなったり、華やぐこともない。
―ひとひらの雪
(259)口走る
二人だけになったときの高明の愛撫は、若い恋人のそれにも負けぬ激しさと一途さがあった。
接吻さえ知らなかった聖子が、半年もせずに高明のものを愛撫し、瞬間、恥ずかしい言葉を口走るまで変貌を遂げていた。
たぶん、それは「とげさせられた」という言葉のほうがふさわしい。
聖子は自分の?の変化に驚き、慌てながら、?が精神より先に走り出していることを実感する。
―夜の出航
(260)?の奥
いま、美砂はつくづく自分の変貌に驚かされる。
紙谷を知るまで、男はみんな乱暴で、勝手気ままなものだと一人合点していたが、いまはまるで違う。男ほど優しく、懐かしいものはいないと思う。
セックスは不潔でいやらしいものと単純に思い込んでいたが、いまは不潔どころか、はるかに豊かで優しいものに思われる。
正直いって、美砂はこのごろ、性の悦びがなんとなく分かるような気がする。まだ漠然として、とらえどころがないが、?の奥の方でかすかに鳴りだすものがある。
ゆっくりと、しかし確実に、美砂の?は紙谷によって呼び覚まされているようである。
―流氷への旅
(261)肉体と精神
男もセックスに溺れると、精神的にもさらに一段と相手が愛しくなり、離れがたくなってくる。これは女性におこりうることで、最初はそれほど好きではなくても、性的な相性がよく、体が馴染むにつれ、次第に相手のことが好きになってくる。
まさに肉体と精神は、卵が先か鶏が先かと言った感じで、両者が交錯し合い、ともに深まっていく。
―男というもの
結ばれる度に悦びは深まる。このままどこまで墜ちていくのか、女は強しその深さを想像して目を閉じ、男はその怖さに怯えて目をつむる。
6 性の不思議
(262)性の尊厳性を卑(いや)しむものは、自らを卑しんでいるのと同じである。
―風のように(「週刊現代」)
(263)男女の素顔
実際、男と女のことは第三者などにわかりはしない。
男女が裸のまま結ばれるセックスの瞬間を知らないで、外からしたり顔に、とやかくいったところで無駄である。男と女の本当の素顔を知っているのは、性のつながりまでもった当事者だけである。
―化身
(264)生殖本能
人間に限らず、すべての生きものはこの世に永遠には生きていけない。
それを本能的に知っているから、人々は生殖、すなわち子供を残すことに執着するのかもしれません。
―講演録より
(265)裏切り
肉体を過大評価する必要はないけれど、過小評価するのも間違いです。肉体の絆を低く見ることで、大事な関係を失うこともあるし、肉体をあなどり、自分は理性でコントロールできると過信すると、思わぬ深みに入って身動きがとれなくなることもある。つまり肉体はいとも簡単に、それまでの自分を裏切る可能性がある、ということです。
―男というもの
(266)大脳皮質
肉体行為といっても、その実態は脳細胞という果てしないキャパシティをもった器官でコントロールすることですから、その行為で自信ができると、それがまた能力のアップにつながる。そういう意味では肉体行為といっても、実際は極めて知的な作業であって、それだけに人によって大きな差ができると思うんです。いわゆる自信が自信を生む形で、食欲なんかと違って、その気になるとかなりできて、やらないでいると、それはそれでやらなくてもいいものになっていくんでしょうね。
―渡辺淳一の世界(丸谷才一さんとの対談より)
(267)性の嗜好
多分、動物が高等になればなるほど、性のバリエーションは複雑多岐になり、その頂点にいるのが人類だとすると、そこにいろいろな趣向の違いが出てくるのが当然である。
たとえば二人でいるときの会話から心が通い合い、やがて接吻から、衣服を脱いで結ばれる。それまでの過程はもちろん、そのあとの時間の過ごし方から別れまで、十人の男には十通りのやり方があり、十人の女には十通りの好みがある。
これらを合わせて考えると、性はまさしく文化なのかもしれない。
―失楽園
(268)性の普遍
たしかに性ほど普遍的で、その実、個人的で秘密めいたものはない。
何千年前の人々も現代の人々も、同じことを繰り返しているといいながら、細かく見るとそのやり方は千差万別で、感じ方も満たされ方もすべて違う。
おそらくこの世界だけは進歩も後退もない。科学文明が発達した現代人だから巧みで、古代の人はまずかったということもない。みなそれぞれに体験と実感から徐々に学び、よかれと思うことを試み、その結果に一喜一憂する。
まさしくここだけは科学も文明も介入しえない、生身の男と女が裸で触れ合って知る、一代かぎりの知恵であり、文化である。
―失楽園
男女の愛は、性で結ばれた当事者の二人にしかわからない。その性の実態を知りもせず、二人の愛に介入するのは、本の知識だけで人間を知ったと思いこむ、学者の愚かさと同じである。
7 エロスの力
(269)一夜で深まる男女のあいだは、一夜で結ばれただけで急速にお互いの心の垣根が除かれていく。
―源氏に愛された女たち
(270)二つの絆
むろん、愛には精神的なつながりを欠かせないが、同時に肉体的な面での相性も重要である。いや、ときには精神的なつながりはさほどではなく、肉体的な魅力に惹かれて離れがたくなることもある。
―失楽園
(271)変革
いずれにせよ、性というものは、ときにしてそれまでの自分を覆(くつがえ)し、変革させるだけの力をもっています。いいかえると、性を通して今まで知らなかった自分の発見し、開拓していける可能性もあるわけで、それこそが性の豊かさであり、素晴らしさといってもいいでしょう。
―男というもの
(272)出会いの形
一般にわれわれというより日本人は、出会いを大切にする。
一組の男女の結びつきにしても、まず心と心が触れ合い、精神的な愛が高まって、やがて肉体的な関係に入っていくべきだと考える。
たしかにこれで好ましいことで、そういう理想的な形で結婚まですすんだ例も多いだろう。だが出会いや慣れ染めるのにきっかけはいかに貧しくて不潔でも、その過程によっては、深い愛にまで昇華することもある。
誤解されては困るが、出会いなぞどうでもいい、といっているわけではない。できることなら出会いも美しいこしたことはない。
しかし出会いに問題があるかといって、その関係をすべて否定したり、軽蔑するのは行き過ぎというものである。
―風のように・忘れてばかり
(273)耽溺
女も男も、とくに男性にとって、相手の女性との性愛は重要である。それが深いか浅いか、濃いか薄いかによって、男が女に執着する度合いは大きく変わる。
想像するところ、源氏が際立って優れたところもない夕顔に執着したのは、なによりも夕顔に耽溺(たんでき)したからではないか。
―源氏に愛された女たち
男女のあいだでは性愛まですすんで、初めて相手の実態が見えてくる。そこまで行かずに見える相手は、人間というより、外見だけで装われた人形にすぎない。
8 愛は不変
(274)人間そのものこれだけ科学文明がすすんだのに、人間は飽きもせず惚れた憎んだとつまらぬ痴話喧嘩をくり返している、と嘆く人もいるけど、だからこそコンピューターやロボットでなく、人間そのもので素敵なんです。
―淑女紳士諸君
(275)書物の知識
男児のことは、あくまで知識ではなく、体験や実感を通してしか知り得ない。
その証拠に、女が男について書かれた本を何冊読んだところで、本当の男は知り得ないし、逆に男が、女について書かれた本をいくら読んだところで、本当の意味での女性を知ることはできない。
―源氏に愛された女たち
(276)平等な世界
どんなに成績のいい男でも、女をわからない男は永遠にわからないし、学校なんか出ていなくても、わかる人はわかる。いかに貧しい女でも、男がよくわかる女もいれば、裕福な家の奥さんや頭の切れるといわれる女性でも、男について何もわかっていない女もいる。つまり男と女のことは地位や知性や教養などとは関係なく、各々の体験と感性でわかってくる。実に平等な世界だと思います。
―創作の現場から
(277)常識とは別
愛は常識ではない。もっと人間臭く、根深く、計り知れないもので、それを知れば、他人の愛をもっと謙虚で、冷静に見られるはず。
愛を常識で裁くという、そういう思いあがった感覚こそが、まさに現代の愛を不毛で、貧しいものにしている元凶ではないだろうか。
―ふたりの余白
(278)進歩しないからこそ
もう何万年ものあいだ、人間の感性や心情は一代かぎりの知恵として創られ、磨かれ、そして跡形もなく消えていった。それだけ見ると、砂の上に築いた楼閣のように虚しく労力のように思われる。
しかし、見方を変えると、このように進歩しない部分があるからこそ、人間はわかり合える部分もある。
たとえばいまわれわれは、ほぼ千年近く前に書かれた源氏物語を読んだとき、平安貴族の生活背景はわからなくとも、愛する男と女の喜びや別離の哀しみ、さらには嫉妬や怨念や憎しみなどは手に取るようにわかる。
―淑女紳士諸君
(279)永遠のテーマ
どんなに時代が進歩しようとも、男と女の関係はつねに一定の軌道上でうごめいていて、そこから外れず、従って進歩することもない。進歩しないということは、逆にいえば決して古びないということです。
―創作の現場から
(280)死に対抗できるもの
言うまでもなく、死は人間にとって最大の恐怖だけど、それに辛うじて対抗できるのは、愛だけである。これは医師のころに実感したのだが、死を予感して恐れおののいている人も、愛を与えれば多少とも心が落ち着き和む。いずれ死は避けられないとしても、愛する人が横にいて手を握ってくれるとか、背中を擦(さす)ってくれるだけで、一時的にしても安心して穏やかになる。こういう例をいくつも見ていると、死に唯一対抗できるのは愛しかない。愛こそ、人間が一生かけて求め、探している宝石なのだということが、しみじみわかってくる。
人間は死ぬまで愛を追い求める。たとえ得られなくても、追いかけたいと願うあいだは人間で、それを諦めたときから人間は人間でなくなってしまう。
―反常識講座
(284)有終
すべてに終わりがあることは初めからわかっていながら、いっとき、人々は終わりはないものと思い込む。終わりを忘れて楽しみ、遊び惚(ほう)けて、ふと、終りを垣間見て怖気(おじけ)づく。いまの伊織の心はそれに近い。
こんな享楽は長く続くわけはないと思いながら、日夜、この宮殿で遊び惚けた男も女も、やがてときがきて退場し、あとは静寂だけが取り残された。そのときの落日も、今日のように赤く華やかで、体に沁みる程、淋しかったのかもしれない。
―ひとひらの雪
自然科学がこれだけ進んでいるのに、男と女は相変わらず、好きだ嫌いだと、つまらぬ痴話喧嘩をくり返している、といって嘆く人がいる。
しかしだからこそ人間なのであって、そういうところがなくなったら、単なるロボットかコンピューターにてなってしまう。
所詮、男女の愛は体験と実感でしか知り得ない一代かぎりの知恵で、それ故に千年も前もいまも変わらず、これからも大きく変わることはないだろう。
あとがき
ここに集められた文章は、わたしの著書のなかでも比較的最近の作品の中から抽出されたものだが、いずれも短い文章なので、理解しやすいように一部加筆したものもある。また「かりそめ」は十一月末に刊行予定のため、週刊誌に連載したものから、「淑女紳士諸君」は「WINDS」に連載したものをもとにしている。いうまでも私は男性であり、そのため男に関する部分はともかく、女性に関する部分についてはいささか異なるというか、違和感をもつ人もいるかもしれない。また同じ女性でも、その人の受けた教育や躾(しつけ)、体験、感性などによって、愛や性にかかわる知識は大いに異なってくる。
そういう意味では、すべての人に納得してもらうのは難しいが、それでもなお人間の、そして男と女が本然的、かつ根本的な姿を探りたいと願ってきた。
その成果はともかく、これを読むことによって、男と女の愛はさまざまな見方や考え方があり、それを追い求めていくと、人間というものの妖(あや)しさと不思議さ、そして最後に愛(いとお)しさにたどりつくことを知っていただければ、幸いである。
一九九九年八月 渡辺淳一