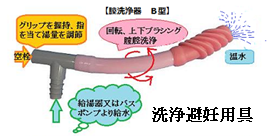煌きを失った夫婦はセックスレスになる人が非常に多い、新鮮な刺激・心地よさを与える特許取得ソフトノーブルは避妊法としても優れ。タブー視されがちな性生活、性の不一致を改善しセックスレスになるのを防いでくれます。
家庭平和を維持「するセックス」、義理的に月一回程度「するセックス」、性欲を処理「するセックス」、このようにするセックスに終始していた夫。妻(六七歳)の隠された性欲が成熟すると、栓をひねれば水が出る如くためらいもなく六七歳にしても、優しく触ってあげれば週二、三回でも「したくなる」「して」と懇願する「楽しむセックス」に変わった
第七 別居生活は長いけれど
 亀山早苗 著
亀山早苗 著別居生活は長いけれど
夫婦は基本的に同居しているものと一般的には思いがちだが、別居して夫婦関係を続けているカップルも、世の中にいる。もちろん、仕事の都合で別居しているだけで、お互い行き来があるとか、なかなか会えないが信頼関係はあると当事者が言うなら、それはとても羨ましいことだと思う。お互い好きな仕事をしながら、相手を信頼し、味方でいられるなんて、とても素敵なことだと思う。
ただ、世の中はさまざまで、「どうして別居して、しかもこういう関係なのに、まだ夫婦でいるのだろう」と思うような二人もいる。関係性が膠着状態になっているとでも言うべきか。もしかしたら夫婦というのは、「話し合い」を避けてもやっていけるのかもしれない。
淳一郎さん(五十五歳)は、すでに十三年あまり妻子と別居している。半別居状態を含めると、二十五年あまりになる。
彼は二十六歳のとき、同い年の妻と結婚し、ひとり娘をもうけた。都心にある企業で、営業職としてばりばり働き、妻ともうまく行っていたが、娘の身体が弱いことだけが気がかりだったという。
「妻の実家は空気のいい北陸地方娘が三歳になったとき、義父が亡くなって義母がひとり暮らしになったんです。それを機に、妻が『娘が丈夫になるまで実家で暮らしたい』と言い出して。娘は喘息で、アトピーもあって、内臓も弱かった。だから僕も空気のいいところで元気に育ってほしいと思たんです」
それでもそのころは、週に一度は妻子に会いに通っていた。娘は小学校、中学校と進むうちにだんだん丈夫になっていく。高校をどうするかと言う話になったとき、娘はアメリカの学校に行きたいと言い出した。
「その頃、今度は義母が亡くなって。すっかり意気消沈した妻は、自分もアメリカに行くと。娘はともかく、妻が一緒に行く必要はないだろうと思っていたのですが、たまたま妻の従姉妹がボストンに住んでいたんですよ。娘もボストンの学校がいいというし、僕は仕事を辞めるわけもいかない。それで二重生活が始まったんです」
妻は実家を処分し、いくばくかの財産を得たようだ。娘の学費はそこから賄うという。住む場所は、従姉妹の家の近くにアパートが空いている。何もかも、すでに決まっている状態で聞かされた。
「娘と妻は一体となっていて、ほとんど妻の従姉妹に相談し、決めてから報告という感じでした。でも、僕が言うのもおかしいけど、僕の娘としてはすごく出来がよかったんです。
だから希望をかなえてやりたいという気持ちはありました。それと同時に、僕もそれなりに収入があったから、二重生活でもやりくりすれば何とかなると思って」
それが十三年前のこと。以来、ずっと別居状態が続いている。娘は現在、二十八歳。大学院まで出て、研究者となっている。妻はといえば、なぜか妻もアメリカの大学で学び直し、今はニューヨークに在住、芸術関係の分野で仕事をしている。ふたりとも、アメリカの永住権をとっており、もう日本に戻ってくる気もないらしい。
「最近は、年に一回くらい会えばいいほうかなあ。以前、妻に会いにニューヨークに行ったとき、彼女はものすごく仕事が忙しくて、ほとんどほったらかしだったんです。娘は出張だとかで会えなかったし。妻は会うたびに、別人のように生き生きして若くなっていく。よかったなあと思う反面、何のために今も仕送りを続けているのかなあとも思うんです」
そう、淳一郎さんは、妻子が自立した今も仕送りを続けている。実際は淳一郎さんの生活も厳しくなっているのだが、それでも妻への仕送りはやめていない。
「仕送りしなくてもいいよと言われるまでは、してあげようと思っているんです。親しい友人にも言われます。もういいんじゃないか、と。自分でも、なぜかよく分からないんだけど、ずっと送り続けて来たのに、今さら急に辞めるとも言いづらくて。仕送りをすることで、家族であることを確かめたいという気持ちもあるのかもしれませんね」
年に数日間、会ったとき、彼は妻のアパートに泊まるが、すでにセックスの関係はない。妻と娘が、妻の実家に戻ったころも、ほとんどセックスはしていなかった。田舎の家は夜になるとしーんと静まりかえり、些細な物音でも木造の家では響く。義母と娘のことを気にしながらすることに、お互いに遠慮があった。
長い別居生活だから、淳一郎さんが恋愛したこともあるのではないか。
「それがねえ、長続きするような関係はありませんでしたね。せいぜい数ヶ月間のつき合いで、お互い寂しいときに体を求め合うような感じでした。
いつも自然消滅というか、女性が去っていったというか。たとえ不倫でも、実生活は独身みたいなものだから、周りの友人たちは『何でもやりたい放題でいいなあ』といわれこともありました。ただ、頭のどこかで、『オレは既婚者だ』という意識があったし、のめり込まないようにしていた気がします。
ひとりで暮らして恋愛にはまったら、あとでよけいに面倒なことになりそうだし。自己防衛が強かったんでしょう。そんな僕の気持ちを女性たちは察して去っていったんだと思います」
彼には、「結婚したら離婚しない」という思いがあったのだろうか。そう尋ねてみると、特に意識したことはなかったけれど、と前置きしながらも、しばらく考えてから、口を開いた。
「最初は、娘の健康のためにやむを得ない選択だったんですが、そのうち、一緒に暮らすという発想がお互いなくなっていったのかもしれません。だからといって、じゃあ離婚、とも思わなかった。世間に離婚は多いし、友人にも離婚したヤツはいますけど、自分に限っては離婚するかもしれないという考え自体がなかったんです」
それでは、淳一郎さんにとって、「結婚とは何か」「夫婦とは何か」を聞いてみる。これには、彼も口をつぐみ、しきりに考え込んでいた。
「難しいなあ……。正直言って、わかりません。うちは他の家庭とは大きく違っているだろうし、それでいいと夫婦で決めてそうなったわけでもない。気がついたら、こんな形になっていただけ。それじゃあ、全然心のつながりがないのかと言われると、娘と妻とも、ときどきメールのやり取りはしているし、心のどこかに『家族』だというものはあるんです。
普通とは違うけどね。家族だからどういうわけじゃないんだけど、最悪、僕が死んだとき、葬式をしてくれる人はいるだろう、と。世の中に一人ぼっちではないという気持ちかな。そこに縋るつもりはないけれど、心まで荒まなくてすむというか」
私には彼の気持ちがよく分かった。一緒に居なくても「家族がいる」というのは、気持ちを少し豊かにしてくれるのではないだろうか。私などは、荒んだらどこまでも荒みそうな気がしているだけに、「家族が居る」ということで支えられている彼の心を察することはできる。ただ、「存在している家族」なのに、心のやりとりが密でないことに対しての苛立ちはないのだろうか。
「こんなものだと思って長い期間が経ってしまっているんですよね。だから、細々としたつきあいが、僕にとっての家族なのかもしれない。ただ、これからどうするかと言うことは、全く考えないんです。僕もあと五年で定年。そろそろその先をどうするのか考えなくてはいけないんだろうけど、ずっと先延ばしにしていますね」
淳一郎さんは、定年になってからアメリカに住む気はないという。妻に帰国の意志があるかどうかは不明だ。ただ、お互い元気なうちにはこのままでいいかなあと思うこともあるらしい。
宙ぶらりんな関係、不明瞭な状態というのは人を不安にするものだが、淳一郎さんは家族にとっては、もはやこの状態が普通になっている。今さら、何かを変えることのほうが大変かもしれない。
日常的な接触はなくても、夫婦はやっていける。憎むわけでもなく、淡々と。しかし、そうなると夫婦の「意味」を考えたくなってしまうのだが。
「意味を考え始めたら、殺伐とした気持ちになるでしょうね。僕は、うちは三人が三人とも、自分のことは自分で考えて自分で選択してきた。ただ、娘が大学に受かったときは、よかったねと一緒にお祝いしたし、妻の仕事が決まったときも、心からおめでと言いましたよ。
家族が一緒に居なくてはいけないもの、常に話し合っていく形を決めていくものと考えたら、うちはそういう形からはすでに逸脱していますから、結論は離婚しかなくなっちゃう。だからといって、形じゃないんだ、気持ちなんだと断言もできませんけど、僕自身が夫婦だという実感がないから」
夫婦だという実感がもないけど、独身だとは思っていない。家族はいるのだから、現実として。
終始、淡々と話してくれた淳一郎さん。その年齢には見えない引き締まった身体をしているが、自分の時間がもてるから、ジム通いを欠かさないのだという。最近はスカッシュにはまっていて、仲間もたくさんいるんですと笑う。
「誰に話してもおかしいと言われるから、最近は家族の話はしなくなりました。面倒だから。スポーツ仲間は、家族とは関係なく、さっぱり付き合えるからいいですね」
また近々、飲みに行きましょうとさわやかに手を振って、淳一郎さんは帰っていった。私はこういとき、必ずその背中を見送る。男性の場合、特に背中が何かを物語ることがあるからだ。威勢のいいことを言っていたわりには、背中が妙に寂しい男性もいれば、弱弱しいことを言いながら背中が何かを主張している男性もいた。
淳一郎さんの背中は飄々としていた。彼自身が、そのまま表れたような背中だった。彼の話を反芻しながら、人間の営みというのは面白いなあと私は思っていた。形にとらわれて苦しむ人、形を自ら壊して自由を求める人、そして形は形として維持しながら模索している人。
もちろん。本当は誰もが、自分の求めるような生き方ができればいいだけの話なのだけれど、そうするには、私たちはいろいろなものに縛られすぎているのかもしれない。
冷えた関係ではあるけれど
男性たちが離婚しない理由も、女性たち同様さまざまあるが、ひょっとしたら女性ほど真剣に「離婚」そのものを考えたことがないのかもしれない。結婚したら、そのまま「たいして何も考えずに」家庭は維持され、末は夫婦二人で旅行しながらのんびり暮らす、と無意識に思っている人が多いのではないだろうか。女性たちは、その間、夫と密なコミュニケーションが取れないことで悩み、育児に非協力的な夫を恨み、それが積み重なって愛想を尽かすようになっていくことが少なくないのに。
実際、今は女性からの離婚申し出の方が夫からのそれより多いと聞く。
夫が妻に「離婚」を言い出すのは、外での恋愛に本気ではまったときだろう。
「妻に『離婚してほしい』と言ったら、『いいわよ』という返事が返ってくるものだと思っていたんですよ。ところがそうはいかなかった。『絶対に離婚しない』と言われて、少し驚きました」
都内のメーカーに勤める信孝さん(五十歳)は苦笑しながらそう言った。歯切れのよい口調で、営業部長という肩書に釣り合っているように感じられる。妻も仕事を持っており、ひとり娘は高校二年生だ。
四年ほど前、信孝さんは仕事関係で知り合った三十代半ばの愛美さんと恋に落ちた。
「彼女は可哀そうな人生を送っている人なんですよ。小さいときに両親が離婚して、親戚をたらいまわしされて。高校を出て、ある中小企業に就職したら、そこの社長に手を付けられて。
断ったら仕事も辞めなくてはいけなくなる。それで断れずに、愛人生活を続けていた。でも結局、社長が亡くなって会社を追い出され‥‥。ドラマや小説にしたら嘘だろうと言われるくらい、波乱に満ちた人生を送ってきたんです」
彼女は二十代後半で結婚し、子どもをもうけたが、その子が二歳の時とき病死。それをきっかけに夫婦仲がぎくしゃくして離婚、仕事を転々としながら生きて来たという。
「僕と知り合ったときは、取引先の事務をやっていました。どこか寂しそうな感じがして、気になっていたんです。あるとき、先方の会社に行くと、会うはずの部長の帰社が遅れているという。
応接室で待たされたんですが、彼女が気を遣ってくれて、何度もお茶を持ってきてくれた。それで少し話をしました。その時はそれだけだったんですが、とても感じのいい人だなあと」
数日後、別の取引先に行くとき、偶然、彼女の会社近くを通りかかり、ばったり会った。お互いに急いでいたのでひと言ふた言交わしただけで終わったが、その一週間後、また別の場所でばったり会う。
「妻の誕生日が近かったので、スカーフでもと思って、会社帰りにデパートへ行ったんです。入り口でばったり愛美に会って。『このところよく会いますね』という話から、『時間があれば食事でも』ということになって、自然な流れでした。おかげでその日、プレゼントは買い損ないましたが」
運命などは感じなかった。ただ、彼女を見ると、自分の心の奥深く疼くような感じが消えず、その正体を探りたかったというのが本当のところかもしれないと、信孝さんは言った。
男女が惹かれあうときは「好き」という感情以前に。もっと動物的な本能のどこかが強烈に刺激されるのではないかと私は思う。自分でも表現のしようがない不安にも似た高揚感、無条件に近づきたくなる、触りたくなる欲求、相手の何に惹かれているのかもわからない。いや、惹かれているのかもわからない。
そういうところですでに恋は始まっているのではないだろうか。そして、そういう恋は一気呵成になだれ込んでいく感覚で始まっていく。
「たしかに一気に始まりました。その日、食事をして、ちょっと飲みに行って、そのまま彼女の部屋になだれ込んで…‥。そんなつもりはなかったんですよ。言い訳するわけじゃないけど、本当に最初は軽い気持ちだった。だけど一緒にいるうちに時間を忘れ、もっと一緒にいたくてたまらなくなって」
それから彼は、週に二、三回、彼女の部屋に寄った。自分でも「ずぶずぶになっている」と感じるほどだった。朝まで一緒にいて、彼女の部屋にから出勤することもあった。彼女はいそいそと、ネクタイ、ワイシャツ、下着、靴下などを用意してくれた。
「今思えば、すごく無防備でした。繁華街で腕を組んで歩いていたこともあるし、彼女の家の近くの居酒屋にも、しょっちゅうふたりで行っていた。居酒屋のおやじは、僕らを見ては『いつも仲がいいね』なんて言ってて。関係を問われたりしたことはなかったけど、彼は気づいていたんじゃないでしょうか」
半年ほどは濃密で、仲のいい状態が続いていた。彼女も以前と比べて、明るい笑顔がよくみられるようになっていった。
「彼女はしっかりしているところもあるけど、やはり不安もあったんでしょう。明るく笑ったりしているかと思うと、急に『あなたがいなくなったら、私、生きていけない』と泣き出したりもする。『オレは絶対に、きみに寂しい思いをさせたりしない』といつも言っていました。
そうすると、彼女はとびっきりの笑顔を見せてくれるんです。だけど付き合って半年ほど経つうちに、だんだん彼女が暗くなっていった。あるとき、『私は結局、いつもひとりぼっち。あなたは帰るところがあるんだもの。これ以上、一緒に居ると、かえってつらくなるから別れて』と言われたんです。
どこまで本気かわかりませんが、この女を幸せにできるのは自分しかいない、と思ったんです。だから離婚するから待ってくれと言いました」
これも男の幻想というものか。男の中には、信孝さんのように、「彼女にはオレしかいない」という思いにとらわれて、発奮する人たちがいる。今の若い男性だと、かえって引いてしまうだろうが、この世代だと、まだまだ「頼られ馬力を発揮する」タイプが多いのかもしれない。だが、彼には妻子が居る。他の女性に「幸せにする」と言える状態ではない。そこが問題だった。
「ただ、うちの妻には経済力がありますし、今までだって僕を束縛するようなことは一切なかったんですよ。遅く帰っても、特に文句を言われたこともない。
お互い家事も育児も協力しながらやってきましたけれど、男女という意味では、妻が僕に嫉妬するなんてことも考えられなかった。だから、離婚を申し出たとしても反対されないんじゃないかと思ったんです」
とはいえ、当時で結婚して十五年以上経っている。その時間の長さを思えば、なかなか言い出せなかった。そのうち、愛美さんのほうが情緒不安定になっていく。外で食事をしていても急に泣き出すし、彼が部屋を訪ねても入れないことさえあった。かと思うと、抱き合った後に急に暴れ出し、朝まで号泣したこともある。
「このままじゃ、愛美がダメになる。そう思って、付き合ってから一年後、妻に離婚してほしいと言ったんです」
妻の返事は、彼にとっては意外だった。
「普通だったら『どうして?』『他に好きな人ができたの』なんていうはずでしょう。それを理由も聞かず、『私は絶対離婚しないから』とひと言。あまり決然とした言い方だったので、獏もそれ以上。その場では言葉が出ませんでした」数日後の夜、信孝さんは再度、妻に離婚話を切り出した。すると妻は、ほとんど表情を動かさず、淡々と言った。
「私は今まで、ずっとあなたを愛してきた。これからも変わらない」
と。そのときの妻の表情が、彼には忘れられないという。
「凍りついたように表情が動かないんです。無表情というのとは違うんです。あんな顔を見たのは初めてですね。だけど、言い終わったあと、妻の目からとめどなく涙があふれている。妻はそれを拭おうともせず、表情を変えず、ただひたすら涙だけが別物のように流れている。
妻の心の内はよくわからないけれど、なんだか『妻は本気だ』ということだけはわかった。半端じゃない気概を感じたんです」
もちろん、信孝さんにも協力してやってきたという意識は強かった。妻は同志のようなものだとも思っていた。だからこそ、逆に開放して好きなようにさせてくれるのではないかと甘えがあったのだろう。
男が妻を「同志」と言うとき、対等な意識よりむしろ「わがままを許してくれる母親的なもの」を感じているのではないかと私は思う。
信孝さんは、妻の強硬な態度に驚き、それ以上、他に好きな女ができたとも言えなくなった。どんな理由があろうとも、妻が離婚を承諾してくれるとは思えなかったからだ。
「そうなると、残りの選択肢はいくつかなんです。離婚しないまま僕が家を出て愛美と同居する、愛美に現状を我慢してもらう、あるいは愛美と別れる。この三つしかない。
もちろん、僕としては現状維持がいちばん都合はよかったのだけれど、愛美の精神状態を考えると、いつまでもグレーゾーンで曖昧な関係を続けていられなかった。それで、愛美には正直に話しました。選択肢のことも。愛美は、一週間ほど時間が欲しい、考えさせてほしいと言ったんです」
翌日から、愛美さんの電話攻撃が始まった。昼は妻の会社に、夜は自宅にかかってくる。妻は、会社では居留守を使い、家では留守電に切り替えて、夫の愛人との接触を拒んだ。
「ただ、妻はそのことを僕には言わなかった。愛美も、実は会社を一週間も休んで、ひたすら電話攻撃していたらしいんだけど、それを僕には言わなかった。
一週間たって、僕が愛美の部屋に行くと、愛美はげっそり痩せ細っていました。ぼくの顔を見ると、泣きじゃくりながら『離婚して』と叫ぶだけ。その目がちょっと尋常じゃなかったので、その日は愛美の部屋に泊まって、翌日、病院に連れて行きました」
衰弱しているので、少し入院させたほうがいいということになり、愛美さんはそのまま入院。その日、信孝さんは休みを取り。入院の手続きをしたり、彼女の身の回りのものを病院に運んだりした。
「夜、ぐったりして帰ると、妻が『ずっと黙っていようと思ったんだけど』と言いつつ、その一週間の顛末を話してくれました。もう話すしかないと思ったんでしょう。
僕としては謝るしかなかった。特に妻の職場では、受付で電話をつながらないようブロックしてくれたものの、『ヘンな電話がかかってきている』と噂になり、とうとう上司にまで聞かれたとか。
『とにかく会社に電話されるのは困るのよ』と言われて、返す言葉もありませんでした。妻の社会的な立場に迷惑はかけられない。もう自分の手に追える状態ではなくなっていると思ったので、翌日、愛美の病室に行って、すべて打ち明けました。彼女は電話したことも認めないんです。
だけどうちの留守電には明らかに彼女の声で、『奥さん、あんたが身を引けばいいのよ』とか『娘さんの身の安全は保証できないわよ』とか物騒な文言が入っている。
これを訴えて出れば、明らかに脅迫です。すると彼女は激昂して、『もう出て行って。二度と顔も見たくない』と叫びました。しかたなく、そのまま彼女の部屋の鍵を返して出ました」
彼女とはそれっきりになった。噂によれば、退院した彼女は会社を辞めたという。どこへ行ったのかわからない。
「彼女と再婚しようとまで思っていたのですから、ものすごく辛かった。自分が彼女を追いこんでしまったという罪悪感もあるし、僕自身、それから一年くらい心療内科に通いました」
ぎくしゃくしている夫婦関係
一方で、妻との関係もしっくりとはいかない。日常生活はごく普通に続いているが、妻は、あのとき「私はずっとあなたを愛していた。これからも変わらない」という言葉を発したとは思えないほど、淡々としている。「彼女の行方分からなくなったこと、すべて自分が悪いと思っていることなどを、あのころ妻に話したんです。謝り倒して、もう一度、やり直してほしいとも言いました。
妻は短く『わかった』と言っただけ。その後、いっさいその話に触れようとはしない。だからといって、会話があるわけでもない。この件がばれるまでは、妻とはけっこう会話はあったんですよ。今は妻が話すのを避けているような気がしますね」
誰も彼もが不幸になってしまった。夫には好きな人ができても、離婚はしないという妻の気持ちはわかる。離婚したくないほど愛しているのなら、会話もない今の状態は、妻にとってもつらいだろう。
信孝さんの言い分では、なんとか元通りになれるよう、妻に気を遣って、妻の好きなものを買って帰ったりするらしいが、妻は『ありがとう』と言うだけだ。
「針の筵(むしろ)って、こういう状態を言うんでしょうね。僕が恋愛していたのは一年ですが、妻との冷戦は三年近くなる。むしろ今、離婚したいくらいです」
とはいえ、すべて自分が蒔いた種でもあるから、さらに重ねて、今、離婚したいとは言えない。信孝さんは、加害者である実感を持ちながらも、現在は被害者的な感情にも陥っている。
妻の立場を察すれば、見て見ぬふりをして過ごそうとしていたのに、ことが明るみに出てしまった。しかも社会的にも自分がひどい目に遭ったと感じている。それはすべて夫のせいでもある。長い結婚生活で培ってきたものを、夫が目の前で壊して見せたという思いがあるだろう。
許したい気持ちはあっても、夫が底なし沼に足を取られているように恋にはまっていた一年間を、どうしても受け入れられないのかもしれない。夫が心療内科に通っていたときも、おそらく、妻から見れば夫が「未練を断ち切るために病院にかかっていた」と思えただろう。
信孝さんにしてみれば、結果的に自分は妻を選んだということを、妻に分かってほしい気持ちもある。心療内科に通ったのは、愛美さんへの未練からではなく、どうしょうもない罪悪感からだったし、そこには妻への気持ちも含まれていた。愛していると断言するなら、もう許してくれてもいいのではないかと思っている。
客観的に見れば、ふたりの気持ちはそれぞれ分かるのだけれど、当事者としては、もっと感情が生々しいだけに、許す許さないの問題ではなくなっている。妻にしてみればプライドを傷つけられているから、おいそれと素直にはなれない。
「こんな状態があとどれくらい続くのかと思うと、暗澹(あんたん)たる気分になります」
信孝さんはそう言う。今、離婚したらほっとするか分からない、お互い精一杯、頑張ってやり直そうとして、それでもダメだったら別れようと言うならいざ知らず、今の冷戦状態のまま別れたら、ふたりともすっきりした気持ちにはなれないはずだ。
「娘の前では、普通にしているんですが、当然、娘だっておかしいと思っていますよね。一度ちゃんと話したいと思っていますが、来年受験だし、あまり動揺させたくないんです」
いっそ、このありで妻に対して強気に出てみるのも一つの方法かもしれない。強気と言っても居丈高になるのではなく、「きちんとやり直す」というコンセンサスを得るために、ふたりでじっくり話し合ってみるしかないのだろうか。妻が冷たくあしらっても、そこはめげずに何度でもアプローチする。もしかしたら、妻はそういう夫の態度の変化を待っているのかもしれない。
何かを変えようと自分が動かなければ、結果として何も変わらない。
何度も言うようだが、関係を固定しやすい。何かあったとき、そこに立ち止まったら、関係も進みもせず後退もしない。誤解があるならそれを解き、もう一歩、関係を進めたかったら自ら動く。
恋人同士なら、きっと無意識のうちに、そうやって関係を進めていくのだと思う。だが、夫婦になると、人は案外、そういうことに鈍感になる。
夫婦という形があるだけに、特別なことをしなくても日常は進んでいくからだ。だが、日常生活が進むことと、夫婦の関係が進むこととは違う。お互いに、生身の人間であること、だが考え方の違う個人と個人であること、さらに性差のある男女であること。それを常に頭の隅においた方がいいのではないかと思う。
つづく 第八 四章それでも夫婦は続いていく!?