種彦の「偽紫田舎源氏(にせむらさきいなかげんじ)」が、江戸末期の女性たちに大いにうけたとすると、男性たちに熱狂的に愛読されたのは、滝沢馬琴(ばきん)の「南総里見八犬伝(なんそうさとみはっけんでん)」ではありますまいか。これはまさに男とのよみものです。
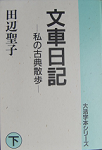 田辺聖子著
田辺聖子著
失われた夢
仁義礼智忠信孝悌の八字を彫った水晶の珠は八方に飛んで、やがて八犬士が生まれ、数奇な運命を辿って里見家を再興します。八犬士がたがいに織りなす波乱万丈(はらんばんじょう)の物語、義士の奮闘あり、悪人の奸計(かんけい)あり、妖怪の幻術あり、美女の貞節あり、毒婦の淫乱あり、忠臣の苦節あり、一巻は一巻と、目もあやな興趣ぶかい場面がくりひろげられ、巻をおくあたわず、手に汗をにぎるシーンの連続です。
量からいっても、九十八巻、百六冊の大長編です。稿(コウ=わら)を起こしたのは文化十年(一八一三年)馬琴が読本(よみほん)作者として脂ののりきった四十六歳の男盛りでしたが、完結したときは七十四歳になっていました。
前後二十八年かかって書き上げた超大作でした。
しかもその間、馬琴の人生は平坦ではありませんでした。暮らし向きは楽ではなく、気の強い妻とは折り合わず、頼りにする息子は病没し、あまつさえ馬琴自身、失明するという不幸にまで見舞われました。
彼はそれにもめげず、嫁に口述筆記をさせ、血のにじむ努力を払って書き上げました。この一作に、彼は生涯の夢と情熱と才能のありたけをこめて書きました。永遠にのこる大作品、と信じて心魂こめて、書いたのでした。
しかし、いま、悲しいことに、馬琴の原作を読もうとする人は、ありません。
そのむつかしい漢字の羅列、(馬琴は和漢の教養がふかく、つい作品の中に、その知識をつぎ込むのです)それにもまして、登場人物は善玉悪玉にわかれ、善玉は修身の教科書のようなことをしゃべり、悪玉はまた全くの悪人です。そうです。馬琴は、善を勧め、悪をこらすという、人の道のお手本としての骨格を、小説に打ち出し、それが彼の、自分は他の凡百の戯作者(げさくしゃ)とちがう、というプライドでした。
それゆえ、西洋の小説の概念が、明治になってわが国に入って来たとき、まっ先に槍玉に上がり、貶められたのは馬琴の小説でした。
あんなに彼が心をこめて書いたのに‥‥。
「八犬伝」はそんな、つまらない物語でしょうか。この長々しい物語をルビにたよりつつ読む内に、私は登場人物の運命の推移から、この世は因と果で 対立しているといった人生の一大パノラマが展開されているのに気付きました。とくに楽しいのは紙芝居みたに華やかな、極彩色の場面です。
「八犬伝」巻の三、第六十六回、庚申山(こうしんやま)の怪猫退治。年へた山猫は、赤岩一角を食い殺し、みずから一角に化けて人々をたぶらかしています。八犬士の一人、犬飼現八と、角太郎は怪猫を討ち取ろうとします。
「死せして見えたる仮(にせ)一角は、忽地呻(たちまちうめ)く声震動して、障子紙戸(ふすま)も裂るが如く、雙手(もろて)を張って身を起こせば、はじめに異なる奇怪の相貌(そうぼう)。既に年老る山猫の、形体(すがた)を露(あらは)す面部の斑毛(まだらけ)、眼(まなこ)の光は百煉(れん)の、鏡を並掛たる如く、髟然(ひゅうねん)として長く鋭き、髯(ひげ)は宛(さながら)、雪を串(つらぬ)く枯野の芒(すすき)に異ならず。
耳まで裂て凄じき、口は血を装(も)る盆に似て、牙を鳴らし爪を張り、四下(あたり)を疾視(にらん)で吻(つ)く息は、狭霧(さぎり)となりて朦朧(もうろう)たる‥‥」という妖怪のすさまじいおそろしさ。二勇士はひるまず勝負を決せんと近づきます。
「頻(しき)りに哮(たける)妖怪は、人語自由の声高やかに、『朽(くち)をしやこの年来(としごろ)、われ人間に交参(まじらひ)て、妻に狎(な)れ子を産せ、夥(あまた)の人に敬れて、快楽(けらく)に光陰(つきひ)を送りしに、角太郎が秘蔵の玉は、雛衣(ひなきぬ「ヒロインの一人の名前」)が呑しより、そが腹中に在るを思はず、胎を求めて自殺を薦めし、只この一じにわがうへ敗れて、深でを負へるのみならず、牙二郎(がじろう「怪猫の気を享けた息子)さへに命を隕(おと)せし、累(かさな)る怨は礼儀(まさのり)・信道、犬士と唱(となふ)る名詮自性(みょうせんじしょう)、犬はわが身の仇なりけり。‥‥(以下3頁割愛)
馬琴は、字を自分で作った字を使ったので、不思議な字がいっぱい出てきます。字の選び方に、語句の選び方に、馬琴なりの強い嗜好があり、それからたちのぼる妖しい香気が、読者を酔わせてしまいます。そうして次々と覆る運命の転変に、人々はため息ついて読み痴(し)れてゆくのでした。
近代文学は勧善懲悪や義理人情を否定することからはじまりました。しかし、それと同時に、私たちは馬琴の作品の持つ、たぐいまれなエネルギー、行間にみなぎる情熱、すじはこびの奇想天外な面白さ、巧緻(こうち)な趣向、小説をよんで血湧き肉おどるといった夢やロマンをも、失ったような気がして、なりません。
なんという、しゃれた、心にくいばかりに洗練された書き出しでしょう。
「伊勢物語」はほとんど全編、みじかい章ごとに、この冒頭からおはなしがはじまります。「をとこ」は、美男ですばらしい歌よみである、在原業平(ありはらのなりひら)、名だたる色ごのみです。
彼の歌を中心に、それにまつわる物語をまとめてたのが「伊勢物語」ですが、私はこの文章が大好きです。
簡潔で古雅で、さらっとひと筆がきに仕上げ、ぽつぽつと、アクセントに濃い墨いろをおとすごとく、珠玉のような歌を点綴(てんてつ)してあります。書きぶりから物がたりから、みんなしゃれて美しい。
ういういしい少年の日の恋、若い日の情熱の恋、やがて世ごひろつき、男女の機微に通じた大人の恋。さまざまの恋が展開され、私は「伊勢物語」を、「恋の見本帳」と呼ぶのです。
在原業平は、決して柔媚(じゅうび)軟弱なだけの魚色漢ではありませんでした。皇族の出身の彼は、政治的には不遇でしたが、政権を握りはじめた藤原氏に屈しない、男の気骨をもっていました。その剛直な男っぽさが、彼の恋物語を色ふかく染めあげています。
在原業平は若い日に、生涯を狂わせてしまうような激しい恋をしました。恋しては成らぬ在原業平人を恋したのです。それは清和天皇の后、藤原高子(たかこ)でした。まだ帝と結婚される前の姫君のころですが、父君兄君たちが后がねと大切にかしずいていらした姫でした。第六段には、それを潤色した話が語られています。

下巻212写真
「むかし、をとこ、ありけり。女の、え得(う)まじかりけるを、年をへて、よばひわたりけるを、からうじてぬすみ出でて、いと暗きにきけり。あくたがはといふ河をゐていきければ、草のうへにおきたりけるつゆを、『かれにはなにぞ』となん、をとこにとけひる」
奈良にある大和文華館には、俵屋宗達(たわらやそうたつ)の筆といわれる「伊勢物語芥川(あくたがわ)図」という絵があり、美しい絵葉書にしてあるのを買うことができます。烏帽子・直衣(のうし)姿の男が、姫を背負って川辺にいます。あどけないばかり若々しい姫なのでした。
深窓にとじこめられていて男には手も届かぬような佳人を、長いことかかって求愛しつづけていたのです。やっとのことで盗み出すように姫をさそい、夜の暗闇にまぎれて逃げてきました。芥川という川のそばまでつれていったら、草の上いちめんに露がおりていて、それがキラキラと光っています、野原いっぱいの露でした。奥深い邸ぐらしの身の姫には、はじめてみる驚きだったでしょう。
美しく、珍らかに思われたでしょう。姫はびっくりして目をみはり、「あれは何ですの?」と、男にきくのでした。男の方は追手が気になり、それ所ではありません。行先は遠し、夜は更け、雷まで鳴りはじめたので、鬼のいる所とも知らず、がらんとした蔵の奥に、姫を入れて、弓矢をもって男は戸口を守っていました。
「はや夜もあけなんと思ひつつゐたりけるに、鬼、はやひとくちにくひけり。あなや、といひけれど、かみなるさわぎに、え聞かざりけり。やうやう夜もあけゆくに、みれば、ゐてこし女もなし。あしずりをして泣けどもかひなし。『しらたまか何ぞと人のひしとき つゆとこたへて消えなましものを』」
男が、夜の早くあけることを念じつつ守っているうち、鬼は一口に姫をたべてしまっていたのです。雷の音に、姫の叫びも聞こえません。
夜があけ、ふとかえりみると姫の姿はなく、足ずりをして泣き悲しんでももはや、取り戻すすべもありませんでした。
「あれは何なの、白玉なの、とあの人がたずねたとき、あれは露だよ、と答えて、もろともに露のように消えてしまえばよかったものを‥‥」
原文は、この歌のあと、姫の兄君たちが追って来て姫をとり返した、それを鬼といったのだ、とあります。姫は連れられて帰られ、在原業平は遂(お)われ、わかい恋人たちは仲を裂かれました。
のち、姫が清和天皇の后となられてから、藤原氏の氏神である大原野(おおはらの)神社へ参詣(さんけい)されることがありました。
美々しくきらびやかな供奉(ぐぶ)の行列のはるか後方に、かつての恋人も近衛府の官人として供に加わっているのでした。
遠くからそれをみとめられた姫のお心はどんなであったか――業平は、后に歌をさし上げたのでした。
大原や小塩(をしお)の山も今日こそは神代のことも思い出づらめ
大原の小塩の山に鎮座される神も、今日は、遠い子孫である后のご参詣を受けられて神代の昔のことをなつかしく思い出されることでありましょう。
表面は公式儀礼として后の行啓をことほぎつつ、その裏に、男は、万感の意味をこめています。
〈あなたは、あの日、あの夜の契りをおぼえていますか。思い出していられるでしょうね‥‥〉
業平はこの失恋に傷つき、東国を放浪しました。彼は恋の狩人ではなく、恋の手練れでもありませんでした。恋の深みにはまることのできた人です。それゆえにこそ、「伊勢物語」は、「恋の見本帳」の権威を失わないのです。
これも、「今昔」に劣らず、面白いお話がいっぱい盛られています。
ただ、この本は、仏教説話集であるところに特徴があります。奈良時代は仏教の盛んな時代でしたが、末になるにつれて世はみだれ人心はすさみ、仏の教えを守る人が少なくなりました。世を救い、人を教化すべき僧尼の中でさえ、むざんな堕落僧、破戒尼が出るしまつでした。
奈良の薬師寺に景戒(きょうかい)というお坊さんがいました。
彼はそんな世の中に心をいため、仏の道を少しでも広めるためにと、筆をとって物語をかき集めました。景戒は想像力のゆたかな、好奇心のつよい、弾力ある心の人でしたから、古い中国の本や、民衆の間に伝わる伝説を拾い、縦横に脚色し、翻案(ほんあん)して、その時代の人々に共感できるような話につくりかえました。
そうして、物語を通じて、仏の功徳、因果応報のことわり、仏教徒として生きる道など説きました――そういうと、いかにも抹香(まっこう)くさく、形式的な説教集のように思われがちですが、一つ一つのお話が、とてもいきいきして面白いのです!
正史には出てこない奈良時代の民衆の日常生活や考え方が、目前にみるように、ありありと浮かぶ。たのしい本なのです!
文章は漢文ですが、正式の漢文ではなく、和風の漢文というべきか、ゴツゴツして、そして素直な文体が、古拙でいいかんじです。
私の大好きなお話は、閻魔(えんま)大王のお使いできた、ユーモラスな鬼の話。
中巻、巻二十四、「閻羅(えんら)王の使の鬼、召さるる人の賂(まひなひ)を得て免(ゆる)す縁」というくだりです。
聖武天皇の御代、楢磐嶋(ならいわしま)という人がいました。
彼は商用で越前まで旅をし、ひとり家へ帰る途中、志賀(しが)の唐崎(からさき)でふとふりかえると三人の男が一町ほどうしろを歩いていました。宇治まで来たとき、男たちが追いつき、一緒になりました。磐嶋(しわしま)は何気なく、どちらまでいかれますか、と聞きますと、驚くべき答えが返ってきました。
「閻羅王の闕(みかど)の、楢磐嶋を召しに往(ゆ)く使なり」
磐嶋(しわしま)は仰天しました。
〈それは私でございます、何のためにお召しになるのですか〉
使いの鬼はいいました。
〈知れたこと、寿命が尽きたせいだ。われわれは先に、お前の家へいってたずねたら、商用で出ているという。やっと出先で捕まえたのだ。家へかえるまでしばらく猶予してやる。お前を捜してあちこち奔走して飢え疲れた。何か食い物はないか〉
〈ここに干し飯(いい)がございます〉
磐嶋は大急ぎで差し出しました。きっと磐嶋はさまざまの感慨が胸にあふれて、顔色も変わっていたかもしれません。使いの鬼は親切な鬼だとみえて、
〈あんまりわれわれに近づくと毒気にあてられて病気になるから、近寄らぬ方がよい。それに、怖がらなくてもよい〉
などと注意してくれます。怖がらなくともよい、といわれたって、閻魔の庁からお迎えがきて、もうすぐ命運が尽きようとしているのに、怖がらずにいられるでしょうか。
いわれたって、家につくなり、大宴会をして鬼たちにご馳走しました。鬼はだんだんあつかましくなり、
〈おれは牛肉が好きだ。牛肉を食わせろ〉
などといいます。磐嶋は、こうなると何の肉でも差し出したい気持です。
〈わが家に斑(まだら)牛が二頭ございます。これをさし上げますから、閻魔庁へ曳き立てられるだけはお許しお願いたいのですが〉
鬼たちは考えました。
〈そうだな、我々はいまお前のご馳走をたらふく食った。そのお返しに許したいのだが、そうすると、我々は重い罪になって、鉄の杖で百回打たれてしまう。もし、お前と同じ年の人があれば、それを身代わりにするのだが〉
鬼たちはひたいをあつめてはかり、結局、同じ年の生まれの身代わり男を捜し出して、連れて行くことになりました。
〈その代わりに、金剛般若経を百回読め、お前の牛を収賄したために我々が罪に落とされるかもしれないからな〉
と鬼はいい置いて消えました。磐嶋は、早速、尊い法師のもとへゆき、心をこめて鬼のために共養し、おかげで九十までの齢(よわい)を保ちました。

この鬼は人間臭く、とぼけたおかしみがあって、当時の人々の心がいきいきと反映しています。
狐を妻にする話はわが国には多いのですが、それも「日本霊異記」からでしょうか。上巻第二のお話――
欽明天皇の御代、美濃の国大野郡の男が、広野の中で美少女に出会いました。男たちはたちまち彼女に恋して、妻にするために連れ帰りました。
二人はむつまじく暮し、男の子さえ生まれました。
ところがその家の犬の子が、いつもこの妻に歯をむき、唸るのです。妻は怖がって、あの犬を殺してくださいと夫に言うのですが、夫は犬を可愛がっていたので、殺しませんでした。あるとき、犬が酷く妻にほえかかり、かみつこうとして追いかけました。妻は怯えて惑い、たちまち狐の姿をあらわして垣の上に登って逃げました。
男の驚きは、いかばかりだったでしょう。
狐は、かなしげに去りもやらず、家のまわりをめぐって鳴きます。
男は叫びました。
〈お前とおれは、子まで生した仲ではないか。おれはお前を忘れないぞ、ここを住みかとして、つねに来て寝よ〉
狐はその言葉にしたがい、来て寝ました、それで〈きつね〉という名になりました。昔は、野干(やかん)といっていたのです。
でも男にとって、いつまでも、まなかいに残るのは、狐ではなく、赤い裳(も)をひく、なよやかな、細腰の美しい妻でした。男は妻恋しさに堪えかねて歌います。
恋は皆我が上(へ)に落ちぬたまかぎるはろかに見えて去(い)にし子ゆゑに
人外の生をうけたものとの間にも、真の愛は育つと、古い世の人々は夢想したのでしょうか。恋はみな、私の上になだれおちた。という表現のある仏教説話集なんて、ほんとうにすばらしいと思います。
みずみずしい若い心には、ほんとうによくわかる、しみ通りやすい宗教です。そして文学趣味のある若ものには、ことにもとけこみやすい教えのように思われます。それは聖書の文章も、讃美歌の歌詞も、まことに美しく、文学性がたかいからです。
明治のはじめ、長い禁制をとかれたキリスト教はたちまち日本の若者心を捉えて、すぐれた神学者や、敬虔(けいけん)なキリスト教の思想家、文学者をたくさん生みました。富士見町教会の牧師・植村正久も、その一人でした。彼の功績は、松山高吉らと供に新・旧約聖書を翻訳したことです。
第二次世界大戦後、聖書は口語体になったものが行われています。でも私には、明治に訳された文語体の美しさが忘れがたいのです。
「そのとき或るパリサイ人らイエスに来たりて言ふ『往きてかの狐に言へ。視よ、われ今日明日、悪鬼を遂(お)ひ出(いだ)し、病を医(いや)し、而(しか)して三日めに全うせられん。されど今日も明日も次の日も我は進み往くべし。それ預言者のエルサレムの外にて死ぬることは有るまじきなり、噫(ああ)エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し、遣(つかは)される人々を石にて撃つ者よ、牡鶏(めんどり)のおのが雛(ひな)を翼のうちに集むるごとく、我なんぢの子供を集めんとせしこと幾たびや。されど汝らは好まざりき』」…‥
強くはりつめたキリストの生涯、使徒たちの心は、この高鳴るしらべのような文体によく調和し、聖書のどこをひらいても、精神の高揚を感じないではいられません。そして若い私は、遠いはるかな昔の異国の風趣を聖書の中から想像し、うっとりするのでした。
葡萄。無花果(いちじく)。使途たちの風になびく長衣。海の上をあるくキリスト。長い髪で主の足を拭く女。エルサレムの神殿の空に舞う鳩。石膏の壺にたたえられた香油。‥‥
「われ更に汝らきくものに告ぐ。なんぢの仇を愛し、汝らを憎む者を善くし、汝らを詛(のろ)ふ者を祝し、汝らを辱(はづ)かしむる者のために祈れ。
なんぢの頬を打つ者には、他の頬をも向けよ。なんぢの上衣を取る者には下衣をも拒むな。すべて求むる者に与へ、なんぢの物を奪ふ者にまた求むな。なんぢら人にらせれんと思ふごとく、人にも然(しか)せよ」
(ルカ伝第六章)
くり返しくり返し読んであきない名訳ではありました。
ことにも美しいのは、旧約聖書の詩編です。これは古代ヘブライ人が神をたたえた歌ですが、その中の「雅歌」…‥イスラエルの民の古い恋歌です。
「われはシャロンの野花、谷の百合花(ゆり)なり 女子等(をうなごら)の中にわが佳(と)ものあるいは荊棘(いばら)の中に百合花のあるごとし わが愛する者の男子等(をのこら)の中にあるは林の樹の中に林檎(りんご)のあるごとし 我ふかく喜びてその陰にすわれり その実は口に甘かりき
彼われをたづさへて酒宴(さかもり)の室(いへ)に入れたまへり そのわが上にひるがへしたる旗は愛なりき」
「エルサレムの女子等(をうなごら)よ我なんぢらにしかと野の鹿をさし誓ひて請ふ愛のおのづから起るときまでは殊更に喚起(よびおこ)しかつさますなかれ わが愛する者の声きこゆ みよ山をとび岡を躍りこえて来たる わが愛する者はしかのごとくまた小鹿のごとし」
「視よ冬すでに過ぎ 雨もやみて はやさりぬ もろもろの花は地にあらはれ 鳥のさへづる時すでに至り 斑鳩(やまばと)の声われらの地にきこゆ 無花果樹はその青き果(み)を赤らめ 葡萄の樹は花さきてその馨(かぐ)はしき香気(にほひ)をはなつ わが佳(と)もよ
わが美(うる)はしき者よ 起ちていできたれ 磐間(いはま)にをり 断崖(がけ)の匿処(かくれどころ)にをるわが鴿(はと)よ 我になんぢの面(かほ)を見させよ なんぢの声をきかしめよ なんぢの声は愛らしくなんぢの面はうるはし われらのために狐をとらへよ 彼の葡萄園をそこなふ子狐をとらへよ 我等の葡萄園は花盛なればなり‥‥」
明治の青春と情熱が結晶したこの美しい翻訳文学を、私はこよなく愛し、日本の古典の中へ加えるのを誇りに思います。
日本には、俳句・短歌という、手身近な表現形式があって、たいそう便利なせいもあります。
見渡してみると、俳句・短歌の素養のあるひと、そこまでいかなくても親近感をもっているひと、なだらかな五七調の浪に身を委ねて快いひと(五七調に抵抗を感ずる人は、また、そのひとなりの詩の波長を持っています)がなんと多いことでしょう。こんなに文学的に民族が、世界にあるでしょうか。ちまたに住む、名もなき人が、それぞれの感懐を託して、みじかい詩形にまとめようと努力します。まとめるべき芸術的衝動を多くの人がもっているというのは、民族文化のレベルが高いことではないでしょうか。
私がことにおもしろく思うのは、芸術的衝動という志のたかいものとべつに、日本人には独特のユーモア感覚があることです。
世態人情のおかしみ、機微をとらえて、うまくうがった短詩が発達しました。それを、「川柳」といいます。そして、これこそ庶民のたのしみとなって、どんな人々でも手軽に作れる、身近でたのしい庶民文化となりました。
江戸時代、一七〇〇年代の後半から盛んになりました。宝暦、明和、安永といったところ、将軍家重(いうしげ)や家治(いえはる)の時代です。
もとは前句付けといいました。たとえば、「飽かぬことかな乀」
という前句を出して一般から付句を募集します。撰者がいて、入選した句をすりものにして発表するのでした。その選者(点者)というか、先生の一人が、江戸は浅草の名主だった、柄井川柳(からいせんりゅう)でした。この前句付けばかりをあつめたものがのちに「誹風柳多留(はいふうやなぎだる)」として出版されました。前句付けはやがて川柳という名でよばれ独立した一つの詩形になりました。
さきの「飽かぬことかな乀」につけられたのは、
これ小判たった一晩いてくれろ
庶民の家には、小判一両など、めったに長く滞在しない、右から左へ御通過あそばすのです。庶民は小判をひたいに当て、一晩でもとどまってほしいとねがう心地、一両は当時米一石買えたといいます、金ピカの小判をじっくりとっくりながめて飽きぬ心地のおかしみがよく出ています。

川柳は人のなさけのあたたかさを格好のテーマにします。川柳の根本にあるのは、人情の共感だからです。
母親はもったいないがだましよい
ころりと子供に騙される昔のお袋は、さぞやさしいお袋だったのでしょう。無学だけれどもやさしくて、子供のいうことは尤(もっと)も尤も、と頷いてくれる、親爺(おやじ)にだまって小遣いをくれるお袋なのでしょう。そして、どら息子も、ちょっぴり良心の呵責(かしゃく)をかんじています。
親をだましてはバチが当たるのだが、と重々わきまえながら、うるさい親爺よりはだましよいとお袋にうまいことをいって泣きつくのでしょう。
貫之(つらゆき)は猫をおひおひ荷をほどき
川柳作家にかかっては史上の有名な文学者も現実の日常卑近な生活者に引きずり落とされてしまいます。紀貫之は、かつて「土佐日記」のくだりでのべたように、土佐守として赴任していました。任はてて都へかえってきたときの土産は、さぞかし、土佐名物のかつおぶしだったのではあるまいか、とすれば、荷をほどくとき猫が寄って来ただろう、というおかしみです。彼らはそうやって、武蔵坊や清盛や義経ら、英雄豪傑までみんな、親愛にみちた揶揄(やゆ)の対象にします。
なまつばき吐き吐き巴打って出る
巴御前は男まさりの武勇もの、それでもさすが女ゆえ、打ちものとって勇ましく打って出ながらなま唾を吐くのは、おめでたのしるしでもあるのでしょうか。
さがしましたと仲国(なかくに)馬を下り
これもいうまでなく小督(こごう)の局を勅命でさがしてきた仲国の奉答です。
やわやわと重みのかかる芥川
業平(なりひら)をやわらかく暖かく、からかっています。
日本の庶民の心の中には、大きなユーモア感覚のながれがあります。現実の生活が苦しいときにも、人々は一方でたえず、ふしぎな距離感をもって、われとわが身をわらうおかしみを忘れませんでした。現代もの一見、そういうものがありげですが、実際は、単なる道化や、冷たい嘲笑や、才走った裁きの笑いにすぎないような気がします。
古(こ)川柳のもつ、おとなの距離感をもった暖かい笑いから遠いような気がします。
王朝時代のひいな遊びは、こんにちでいう「ままごと」でした。三月三日の雛まつりに、雛人形をかざる風習は、時代もずっと下って、江戸時代に入ってからです。
貴族や皇族の姫たちが遊んだ雛人形は、小さな人形は、小さな人形のお邸や調度も作られたらしく、「源氏物語」には、かの紫の上の幼かったころの場面に出ています。
六条御息所(みやすどころ)との愛執につかれ、義母、藤壺(ふじつぼ)の宮との罪ふかい恋になやむ源氏の心に、ぱっと明るく灯をともしてくれたのは、いたいけな紫の上でした。
「源氏物語」という一大交響楽には、明暗・悲喜こもごもの二つのテーマが鳴りひびいていますが、紫の上があらわれてくると、そのページにさっと、さわやかな風がかおり立ちます。
源氏がはじめて紫の姫君をかいま見たのは北山の小さな住居でした。この美少女は、祖母にあたる尼君と共にいおりに仮住まいしていました。
「十ばかりにやあらむと見えて、白ききぬ、山吹などのなれたる着て、走りきたるをんな子、‥‥いみじく生ひさき見えて、美しげなるかたちなり。髪は、扇をひろげたるやうに、ゆらゆらとして、顔は、いと赤くすりなして立てり」

どうしたの、けんかでもしたの、と物静かに問う尼君に、女の子はくやしそうに、
「雀の子を、犬君(いぬき)が逃がしつる。伏籠(ふせご)の中に、こめたりつるものを」
といいつけます。尼君はこの姫がこんなに心もとなく幼くては、残しては死ぬこともできないとなげくのでした。
少女の美しさを忘れかね、かつ藤壺の宮のゆかりとて、恋しい人の面影を宿していることにも心そそられた源氏は、尼君の死後、手もとへ紫の姫を引き取って育てます。
心のままに、理想的な女に育てて見ようと思い、かつ、姫も、さかしく素直に、その期待にそむかぬようにみえました。
しかし何といっても、十あまりの少女でした。
源氏と琴をひいたり、絵などを見て遊んだりしているうち、夕方になり、源氏がよその女のもとへ出かける時間になると、幼い姫は心細そうにうつぶしてしおれ、それを見ると源氏もかわいくて立てません。
〈私がよそへいっていると、さびしいですか〉ときくと、姫はうなずくのでした。そのうち源氏の膝によりかかって眠ってしまうといういじらしさ、今夜は出かけるのを止めましたよ、と姫君を起こすと、元気になって、共に膳をかこみ、それでも、まだ源氏が外に出ないかと心もとながるありさまに、源氏はますます、そばを離れにくくなります。
正月元旦、源氏の君は宮中の朝拝に参上のため、美々しく装束をつけた姿でも紫の姫の居間をのぞくと、姫君はひいな遊びに夢中なのでした。三尺の御厨子(みずし)にいろいろの品を飾り立て、また小さな御殿のおもちゃまでそのへん足の踏み場もないほどひろげて遊んでいるのでした。
〈犬君がこれをこわしたので、直しているところなの〉と姫は一大事のようにいい立てます。〈よしよし、しようのない人だね、早速直させよう。今日はおめでたい日だから泣いてはいけないよ〉と源氏はあやします。
あどけなく心なよらかな紫の君は、やがておとめとなり、源氏の正妻となりました。美しく怜悧(れいり)でやさしい彼女は女の理想ともいうべきすぐれたひとでありながら、子供には恵まれませんでした。それは、紫の上自身、あまりにすばらしく美しい少女時代を持っていたかではありますまいか。‥‥少女のあどけなさ、子供の可愛らしさが紫の上の幼時に凝縮され、永遠の象徴とさえなってしまいました。そのあと、紫の上はもう自分で子供をもつ必要はなかったのです。作者の周到な用意です。それだけに、幼い少女の愛らしさは、いつまでも私たちの胸に、焼き付けられて消えないのです。
作者は山東京伝(さんとうとうきょうでん)。江戸中期、一七〇〇年代の終わりごろ活躍した人気作家です。
彼は浮世絵師でもありましたので、このさしえも自分でかいています。さしえというより、このころの大衆小説である「黄表紙」とよばれた本は、今日の劇画のように、絵を中心で、地の文や会話は、つけたりのように、余白にびっしり書き込んでありました。
これらの本は、町人たち、熊さん八ちゃんや女たちもよろこんでよむ通俗小説、ということになっていましたから、プライド高いインテリたちや武家は手に取るのも潔しとしない風でした。でもそれはうわべのことで、ほんとうは、みんな、内内で読んで腹を抱えて笑ったり、思わず吹き出して、まわりを見廻したり、していたにちがいないのです。
私は謹厳なさむらいが、非番の日の長屋で、こっそり、「江戸生艶気蒲焼」などよんで、つい頬の筋肉をゆるめたりしているのを想像するのが好きです。
劇画ですから、絵と文章と一致しなければ、その効果が上がらないのは当然です。
その点からも、自分で絵を描けたら京伝の本は面白いのです。
この小説は、京伝二十五歳の、まさに才気とエネルギーの充溢(じゅういつ)していたころの作品です。
百万長者のひとりむすこ、仇木屋(あだきや)、艶二郎というのが主人公の青年。自分ではいっぱしの色男きどり、ところが挿絵の艶二郎は、色男なんて顔ではなく、梅の花形を二つに割ったような団子鼻に「へ」の字眉、それがまず、ふき出させます。艶二郎は日頃、

「とんでもなく浮名のたつ仕打ちがありそふなものだ」
なんとか、世間にもてはやされる浮名の主人公になりたい、と考えるのはそのことばかり、腕もおりもせぬ女の名を彫って、さも言い交わした恋人がいるごとく見せかけ、更にそれを嫉妬して灸で消す女がいたようにみせかけ、痛いやら熱いやら、
「色男になるも、とんだつらいものだ」
芸者をやとって、家へかけこませ、どうぞして若旦那といっしょになりたいと泣かせる。家の下女たちも、あの若旦那にほれるとは物好きな女もあるもんだねえ、とあきれ顔ですが、艶二郎はいい気分。
「もふ十両やらふから、もちっと大きな声で、隣あたり、聞こへるやうに、たのむたのむ」
ところが、町内では何も知らず、かわら版にたのんで「評判評判。仇気屋のむすこ艶二郎といふ色男に、うつくしい芸者がほれて駈けこみました‥‥ただじゃ、ただじゃ」とひろめてもらっても、ただでもそのすりものを買うものもいないありさま。
この上は遊里で浮名をあげんものと、𠮷原へかよいつめ、金をやって新造(しんぞう)・禿(かむろ)に袖をひっぱらせ、色男きどりで、「これさ、まァ、はなしてくれろ」などと悦に入っております。
さらに色男というものは、そねまれて、殴られるものだと、地廻りの若い衆に金でやとって、ぶち所わるく、片息になって「気付けよハリよ」とさわぐありさま。ようよう「よっぽど馬鹿ものだといふ浮名をすこしばかり立ちけり」
さらにこの上はと、親にねがって勘当され、親が勘当せぬというものをむりに七十五日と期限つきで勘当してもらい、遊女と狂言心中‥‥読者は、ありうるはずもないこっけいの連続に、「うそつけ、うそつけ」と思いながら、つい読み通し、腹を抱えて笑ってしまいます。切れ味のいいおかしみは、主人公が徹頭徹尾、「よっぽど馬鹿もの」まるでダメな男、という設定からきています。
京伝はすっきりした江戸前のしゃれっけと風を捲いて舞い上がるような才気で、さっと書き上げるのでした。――おかしけりゃ笑いな。おれは教訓はくついきらいさ――京伝はそういっているようにみえます。京伝は現実を一度ほぐして、また笑いにくみたてる作家でした。
私は、そんな歌詞は、彼女たちの即興かと思っておりました。
ずっとのちになって、「閑吟集(かんぎんしゅう)」という室町時代の小唄を集めた本を読んでいたら、
「宇治の川瀬の水ぐるま なにと浮世をめぐるらう」
というのがありまして、古い唄なんだなあ、とびっくりしました。四百五十年も昔から私たちの遠い祖(おや)たちは、うれしいにつけ悲しいにつけ口ずさんできた小唄らしいのでした。
「閑吟集」は室町ごろにはやって歌われた小唄・庶民の愛唱歌謡をとりあつめて、書き残したものです。偏者の名はわかりませんがお坊さんのようです。昔、春秋のおりふしに遊宴の席でともに歌いあそび、「声をもろともに老若、なかば古人となりぬる懐旧のもよほしに」「忘れがたみにもと思ひ出づるにしたがひて、閑居の座右にしるしをく」と、序に書かれています。永正十五(一五一八年)に、出来たこともわかります。
これらの短い歌は扇で拍子をとり、また一節切(ひとよぎり)の尺八の伴奏で歌われたのです。のちにこれに踊りがつき、やがて海の彼方から渡来した三味線が入り、歌も長くなって、舞台や色町の芸能に流れてゆくようになります。
私の好きな歌がここにはたくさんあって、「閑吟集」はたのしい歌の本なのです。

「憂きもひととき うれしいきも思
ひさませば ゆめ候よ」
どんな男や女が、半びらきした扇のかげで口ずさんだのでしょうか。
「世のなかは霰(あられ)よの さきの葉の 上のさらさらさっと降るよの」
凄艶(せいうん)な室町の色若衆の、色ざかりをすぎたころおい、唇からもれる吐息でしょうか。
「あまり言葉のかけたさに あれ見さいのう 空ゆく雲のはやさよ」
応仁の乱後五十年、京も地方も動乱につぐ動乱、その中で庶民はしぶとく根強く生き抜いています。どんな焼跡にでも根を下ろし、食べ、歌い、恋をし、笑うのです。
あまり見たさに そと隠れて走ってきた まづ放さいのう 放して物を言はさいの
そぞろいとしゅうて 何とせうぞの
いま結た髪がはらりととけた
いかさま心も 誰そにとけた
身は破れ笠よの 着もせで 掛けてをかるる
ただ人には馴れまじものじゃ 馴れたののちに はなるヽるるる
るるるが大事ぢゃるもの
身はさび太刀、さりとも一度、とげぞしょうずらふ
ただ置いて霜に打たせよ 夜ふけて来たが にくいほどに
ここには、ほんの一行半句の、いい歌がたくさんあります。
これは、物思いする男や女の、ためいきがわりの歌だったのでしょうか。
梅花は雨に、柳絮(りゅうじょ)は風に、世はただ嘘にもまるる
ただ人は情(なさけ)あれ 槿(あさがほ)の花の上なる露の世に うらやましやわが心
夜昼 君に離れぬ
よしやたのまじ行く水の 早くも変る人のこころ
酒の酔いが虹のように立ちこめ、あでやかな小袖がひるがえり、若衆の緑の黒髪が灯に映えます。女の流し目、ふみしだれる衣のすそや帯のはし、宴のたのしみはきわまりをすぎようとして、一座が声合せて歌ったのは、こんな歌だったでしょうか。
なにせうぞ くすんで
一期(いちご)は夢よ ただ狂へ
それに、ときどき、何でこれが俳句だろう? と頭をひねるようなものもありました。「あら何ともなや昨日はすぎふぐと汁」「夏の月御油(ごゆ)よりいでて赤坂や」「枯枝に鳥のとまりたるや秋の暮」――若い私にとって芭蕉はへんにもったいぶった趣味人のじいさん、という感じでした。それに、一種の芭蕉信仰というか、神様扱いで、おびただしい研究書や注釈書があるのも、却って若者を鼻白ませるのでした。芭蕉は長いこと、私にとって縁なき人でした。
私は蕪村から俳句の面白みを学びました。そうして読みすすむうちに、やっぱり芭蕉へ辿り着いてしまいました!
芭蕉はもともと、おかしみ、あそび、言葉のたわむれであった俳諧を、高雅な文芸にまでたかめた人、というのが、私どもに与えられた知識(それは多分に受験勉強用のもの)ですが、その知識を一応とり落とした中年になってから読むと、まさに、彼の句は、「おとなの句」でした。
芭蕉の経歴を知るにつれて、「あら何ともなや‥‥」や「夏の月‥‥」の句は、彼が自分の真骨頂を発揮するまでの、談林風(だんりんふう)時代の過度期の作品だということがわかりました。
中年の彼は俳諧宗匠として充分、らくに食べていける名声や経済的基盤ができていました。しかし彼は俗世的栄誉や富に心を傾けられないたちの人でした。
ひとつところに安住せず、さらに高い境地をもとめて、芭蕉はたえずとびたちます。旅をすみかとし、風狂漂白に身を置く心のたかぶりが、そのまま「野ざらしを心に風のしむ身かな」の決意になってわく過程も、わかる気がしました。
芭蕉は「寸々の腸をさく」ばかり一句に思いをこらし、推敲(すいこう)に推敲をかさねます。その熱い緊張と気負いが、寸分スキのない、格調たかい句になって「奥の細道」できわまります。

荒海や佐渡によこたふ天の河
芭蕉の句の中で、私の好きなものの一つです。私は、この句は実景そのままでなくて、芭蕉のイメージでくみたてられた句だと思います。この地へ旅したことは事実なのですが、芭蕉の眼に映るのはイメージの中の荒海や島かげでした。それが上滑りにならず理詰めにならず、現実以上の真実として美しく結晶しています。この銀漢のもとの荒海の佐渡は波しぶきに打たれながら、実在の島よりも現実的に私たちの心に影を落とします。
四方より花吹き入って鳰(にほ)の海
鳰(にお=別名カイツブリ)の海は琵琶湖の別名です。琵琶湖には多く見られるので、こんな愛称がつけられたのでした。
春。まんまんたる琵琶湖の水に、四方から花吹雪が舞い散るありさまです。芭蕉は故郷の伊賀上野へ往還のみちすがら、京や大津に杖を曳いて、たびたび、琵琶湖のそばに足をとどめています。「ゆく春を近江の人と惜しみける」という句も、湖の駘蕩(たいとう)たる春色と湖国にすむ人のあたたかい人情に、かくべの感懐をもよおしたからでしょう。
やがて芭蕉は、風雅の道を究めつくして、「軽み」という境地にたどりつきます。肩をおとし、肘のかまえをすて、高く悟りながら俗にかえる体(てい)の句の心を、しきりにさぐり求めます。ひとときも現状に狎(な)れたり安閑と満足したりしない芭蕉の潔癖な芸術家魂なのでした。
此の秋は何で年よる雲に鳥
私の最も好きな芭蕉の句です。多年の漂泊にさすが老いを感じはじめた五十一歳の芭蕉は、浮雲や鳥に生涯の夢を賭けた自分を思いかえしています。
芭蕉は生涯に五度も旅に出ました。その最後の旅は東北から裏日本をたずねる行程六百里、六カ月にわたる長い長い旅でした。
芭蕉はその折の紀行文と発句をまとめて「奥の細道」と名づけました。彼はこの作品を愛し、誇りに思い、幾度も幾度も、くり返しくり返し推敲(すいこう)しました。世に発表して名声を博そうとか、お金をもうけようなどという気は全くない彼は、手元においたまま、心ゆくまで書き改めるのでした。(「奥の細道」が出版されたのは、彼の死後です)
詩人がそんなに心魂かたむけて書き上げた「奥の細道」は、だから、たるみもくもりもなく、ぴいんと張りつめて鳴りひびくような硬い美しさを持っています。漢文まじりで簡潔に力強く、そのくせ和んだあたたかみをたたえ、ふしぎな魅力のある文章です。ふんだんにちりばめられた、冴えた一句一句が、また文章とにおいうつり、ひびき交わし、照りはえあって、魅力をたかめています。源氏、枕といった女流の文学とは全く異質の男性の文章の流れを、芭蕉は創り出したのでした。
この旅には弟子の曾良(そら)が従いました。彼も自分で随行日記を書きのこしていますが、それと照合すると、「奥の細道」は必ずしも現実通りの旅日記ではないそうです。現実は雨降りなのに、芭蕉はそれでは、日光さんさんといった句が残ったり、数日逗留したのに、すぐ出発したように書かれてあります。
それはむろん、そうあるだろうことで、芭蕉の書きとどめる現実は、「詩人の感じた現実」だったのです。現実と虚構のあいだを、詩人のイメージで自在にかけめぐり、あらたな別の現実をつくり上げるのでした。
「奥の細道」は、この調子高い名文からはじまります。
「月日は百代の過客にして、行かふ年も又旅人也。舟の上に生涯をうかべ、馬の口とらへて老をむかぶる者は、日々旅にして旅を栖(すみか)とす。
古人も多く旅に死せるあり。予もいづれの年よりか、片雲(へんうん)の風にさそはれて、漂泊の思ひやまず‥‥」
元禄二年(一六八九年)も初夏のころおい、「奥羽長途の行脚(あんぎゃ)ただかりそめに思ひたちて」「もし生きて帰らばと定めなき頼みの末をかけ」紙子ひとつ、ゆかた、雨具、墨筆のたぐいのみを肩に、出発した芭蕉は、ときに四十六歳でした。
折々は辺土のむさくるしい貧家に一夜の宿を乞い、「灯(ともしび)もなければゐろりの火かげに寝床をまうけて臥(ふ)す。夜に入って雷鳴、雨しきりに降りて臥せる上よりもり、蚤蚊(みのか)にせせられて眠らず。持病さへおこりて消入るばかりになん」という苦労も重ねつつ、「はるかなる行末をかかへて、かかる病おぼつかなしていへど、羈旅(きりよ)辺土の行脚、捨身無常の観念、道路に死なん、是れ天の命なりと、気力いささかとり直し、路、縦横にふんだ伊達(だて)り大木戸をこす」
あるいは平泉(ひらいずみ)で、藤原三代の栄華のあと、義経討死のあとを見、
「さても義臣すぐつて此城にこもり、功名一時の叢(くさむら)となる。『国破れて山河あり、城春にして草青みたり』と笠うち敷きて、時のうつるまで涙を落として侍(はべ)りぬ。
夏草や兵(つはもの)どもが夢のあと」
芭蕉はぞんぶんに、声をあげてうたっています。朗々と心ゆくまでうたい上げています。その純一な陶酔は、文学的節度と、芭蕉の美意識によって、美しくととのえられ、かえって文章に強さを与えています。
そればかりか、読むものにも酩酊がのりうつって、いつしか、芭蕉の自己陶酔に同化してゆくのです。私が芭蕉をちかしいものと考え、その句や文章を味わうことに楽しみを覚えたのは、この自己陶酔の余派を共にかぶって心を昂らせる快さをみつけたからに、ほかなりません。
芭蕉はふしぎな世界へ私たちを連れて行ってくれる案内者なのです。
永いあいだの、私の古典への愛着を、自由に思いつくまま、とりあげてみたいと思いました。
古典への片思いともあこがれとも、秘めたる恋とでも申しましょうか。今までの人生で私は、一つ、また一つと、大好きな古典作品を心の底にためていたのでした。その秘めごとの露がいっぱいたまって、ひとつの雫となり、ぽつん、としたたりおちました――それが、いわば、この本です。
私の好みに偏って申し訳ないのですが、ここには私の好きなものばかり、蒐(あつ)めてあります。物語や、その主人公や、歌や、文章など、私の好きなもの、そして無類に美しい宝玉のように、てのひらにじっと暖めて愛しんできたものばかりです。それらをちりばめて作ったのがこの本です。
それゆえ、おのずからこの本には、わが秘宝を自慢するような、独りよがりの口吻も出たかもしれません。
――偏ったわが嗜好を、読者に押し付ける不遜も、思わないではありませんでしたが、他面考えてみますと、わが熱愛や執着もまた、あるいは古典嫌いな方、古典に不案内な方への、おのずからなる道しるべになるかもしれぬと思うようになりました。
私としては、同じき愛好の人々をたくさん作って、あの作品が好き、あの人物を愛するとかたみに言いあいたいのです。
人生を生きるのに、愛するもの、好きなことを一つでも多く増やすのは、たいへん、たのしい重要なことですから‥‥
文学史的に大切な作品とか、文学的評価が定まっているものという基準ではえらびませんでした。
ただただ、自分の好きな、という一点だけで取り上げました。専門の先生方からはご批判があるかもしれません。私は国文学を専攻したといっても、終戦後、旧制女専に籍を置いただけの、まずしい学力で、注釈書をたよりに読みかじっただけです。思いつかれた点など、今後も専門の方々にご教示賜ればうれしいと思います。
私はいま、「萬葉集」や「古事記」などに、今まで縁もゆかりもなかった方々に、好きな指輪やブローチのように身近に手馴れ、いつくしんで頂きたいと思ったりしています。
好きな着物をひろげて、あれを着ようか、これにしようかと思いまどうように、木曾義仲や、紫の上など、ヒーロー、ヒロインたちを愛し、人生にまつわりつかせて頂きたいと思うようになりました。
そしてまた、恋人の手紙を、ひめやかに諳(そら)んじているように、「方丈記」や「平家物語」の一節を、心の中でおぼえていて欲しい、とも‥‥。
古典の世界は、ゆたかで奥深く、変化に富んでいます。私たちはおびただしい古典の中で、きっと、自分の人生にとって必要なものとめぐりあうことができます。
それにしても、民族遺産としてこんなにすぐれた古典を多くもつ日本という国は、何と素晴らしい国でしょう、私は母国・日本をとても誇りに思い、また好きです。
取り上げた作品や場面がまちまちであるように、書き方もまちまちで、小説風にしたのも混じっています。
大半は朝日新聞に連載したものですが、紙面の都合上短くしていたので、この機会に、いくつかは加筆しました。
そのほか、「額田女王の恋」「あね・おとうと」は「教育ノート」に載せたものをすこし補いました。「わが愛の磐之媛」「恋の奴」は、同人雑誌「航路」に掲載したものです。
なお、新聞連載中からお世話にになった長谷川青澄画伯の流麗な挿絵で、拙作を飾っていただくことができました。気品ある美しいお作品を得たのはこの上ない喜びです。
(昭和四十九年九月) 著者 田辺聖子
一九九六年12月20日発行 限定500部数 定価3、400円
恋愛サーキュレーション図書室の著書
量からいっても、九十八巻、百六冊の大長編です。稿(コウ=わら)を起こしたのは文化十年(一八一三年)馬琴が読本(よみほん)作者として脂ののりきった四十六歳の男盛りでしたが、完結したときは七十四歳になっていました。
前後二十八年かかって書き上げた超大作でした。
しかもその間、馬琴の人生は平坦ではありませんでした。暮らし向きは楽ではなく、気の強い妻とは折り合わず、頼りにする息子は病没し、あまつさえ馬琴自身、失明するという不幸にまで見舞われました。
彼はそれにもめげず、嫁に口述筆記をさせ、血のにじむ努力を払って書き上げました。この一作に、彼は生涯の夢と情熱と才能のありたけをこめて書きました。永遠にのこる大作品、と信じて心魂こめて、書いたのでした。
しかし、いま、悲しいことに、馬琴の原作を読もうとする人は、ありません。
そのむつかしい漢字の羅列、(馬琴は和漢の教養がふかく、つい作品の中に、その知識をつぎ込むのです)それにもまして、登場人物は善玉悪玉にわかれ、善玉は修身の教科書のようなことをしゃべり、悪玉はまた全くの悪人です。そうです。馬琴は、善を勧め、悪をこらすという、人の道のお手本としての骨格を、小説に打ち出し、それが彼の、自分は他の凡百の戯作者(げさくしゃ)とちがう、というプライドでした。
それゆえ、西洋の小説の概念が、明治になってわが国に入って来たとき、まっ先に槍玉に上がり、貶められたのは馬琴の小説でした。
あんなに彼が心をこめて書いたのに‥‥。
「八犬伝」はそんな、つまらない物語でしょうか。この長々しい物語をルビにたよりつつ読む内に、私は登場人物の運命の推移から、この世は因と果で 対立しているといった人生の一大パノラマが展開されているのに気付きました。とくに楽しいのは紙芝居みたに華やかな、極彩色の場面です。
「八犬伝」巻の三、第六十六回、庚申山(こうしんやま)の怪猫退治。年へた山猫は、赤岩一角を食い殺し、みずから一角に化けて人々をたぶらかしています。八犬士の一人、犬飼現八と、角太郎は怪猫を討ち取ろうとします。
「死せして見えたる仮(にせ)一角は、忽地呻(たちまちうめ)く声震動して、障子紙戸(ふすま)も裂るが如く、雙手(もろて)を張って身を起こせば、はじめに異なる奇怪の相貌(そうぼう)。既に年老る山猫の、形体(すがた)を露(あらは)す面部の斑毛(まだらけ)、眼(まなこ)の光は百煉(れん)の、鏡を並掛たる如く、髟然(ひゅうねん)として長く鋭き、髯(ひげ)は宛(さながら)、雪を串(つらぬ)く枯野の芒(すすき)に異ならず。
耳まで裂て凄じき、口は血を装(も)る盆に似て、牙を鳴らし爪を張り、四下(あたり)を疾視(にらん)で吻(つ)く息は、狭霧(さぎり)となりて朦朧(もうろう)たる‥‥」という妖怪のすさまじいおそろしさ。二勇士はひるまず勝負を決せんと近づきます。
「頻(しき)りに哮(たける)妖怪は、人語自由の声高やかに、『朽(くち)をしやこの年来(としごろ)、われ人間に交参(まじらひ)て、妻に狎(な)れ子を産せ、夥(あまた)の人に敬れて、快楽(けらく)に光陰(つきひ)を送りしに、角太郎が秘蔵の玉は、雛衣(ひなきぬ「ヒロインの一人の名前」)が呑しより、そが腹中に在るを思はず、胎を求めて自殺を薦めし、只この一じにわがうへ敗れて、深でを負へるのみならず、牙二郎(がじろう「怪猫の気を享けた息子)さへに命を隕(おと)せし、累(かさな)る怨は礼儀(まさのり)・信道、犬士と唱(となふ)る名詮自性(みょうせんじしょう)、犬はわが身の仇なりけり。‥‥(以下3頁割愛)
馬琴は、字を自分で作った字を使ったので、不思議な字がいっぱい出てきます。字の選び方に、語句の選び方に、馬琴なりの強い嗜好があり、それからたちのぼる妖しい香気が、読者を酔わせてしまいます。そうして次々と覆る運命の転変に、人々はため息ついて読み痴(し)れてゆくのでした。
近代文学は勧善懲悪や義理人情を否定することからはじまりました。しかし、それと同時に、私たちは馬琴の作品の持つ、たぐいまれなエネルギー、行間にみなぎる情熱、すじはこびの奇想天外な面白さ、巧緻(こうち)な趣向、小説をよんで血湧き肉おどるといった夢やロマンをも、失ったような気がして、なりません。
恋の見本帳
「むかし、をとこ、ありけり」なんという、しゃれた、心にくいばかりに洗練された書き出しでしょう。
「伊勢物語」はほとんど全編、みじかい章ごとに、この冒頭からおはなしがはじまります。「をとこ」は、美男ですばらしい歌よみである、在原業平(ありはらのなりひら)、名だたる色ごのみです。
彼の歌を中心に、それにまつわる物語をまとめてたのが「伊勢物語」ですが、私はこの文章が大好きです。
簡潔で古雅で、さらっとひと筆がきに仕上げ、ぽつぽつと、アクセントに濃い墨いろをおとすごとく、珠玉のような歌を点綴(てんてつ)してあります。書きぶりから物がたりから、みんなしゃれて美しい。
ういういしい少年の日の恋、若い日の情熱の恋、やがて世ごひろつき、男女の機微に通じた大人の恋。さまざまの恋が展開され、私は「伊勢物語」を、「恋の見本帳」と呼ぶのです。
在原業平は、決して柔媚(じゅうび)軟弱なだけの魚色漢ではありませんでした。皇族の出身の彼は、政治的には不遇でしたが、政権を握りはじめた藤原氏に屈しない、男の気骨をもっていました。その剛直な男っぽさが、彼の恋物語を色ふかく染めあげています。
在原業平は若い日に、生涯を狂わせてしまうような激しい恋をしました。恋しては成らぬ在原業平人を恋したのです。それは清和天皇の后、藤原高子(たかこ)でした。まだ帝と結婚される前の姫君のころですが、父君兄君たちが后がねと大切にかしずいていらした姫でした。第六段には、それを潤色した話が語られています。

下巻212写真
「むかし、をとこ、ありけり。女の、え得(う)まじかりけるを、年をへて、よばひわたりけるを、からうじてぬすみ出でて、いと暗きにきけり。あくたがはといふ河をゐていきければ、草のうへにおきたりけるつゆを、『かれにはなにぞ』となん、をとこにとけひる」
奈良にある大和文華館には、俵屋宗達(たわらやそうたつ)の筆といわれる「伊勢物語芥川(あくたがわ)図」という絵があり、美しい絵葉書にしてあるのを買うことができます。烏帽子・直衣(のうし)姿の男が、姫を背負って川辺にいます。あどけないばかり若々しい姫なのでした。
深窓にとじこめられていて男には手も届かぬような佳人を、長いことかかって求愛しつづけていたのです。やっとのことで盗み出すように姫をさそい、夜の暗闇にまぎれて逃げてきました。芥川という川のそばまでつれていったら、草の上いちめんに露がおりていて、それがキラキラと光っています、野原いっぱいの露でした。奥深い邸ぐらしの身の姫には、はじめてみる驚きだったでしょう。
美しく、珍らかに思われたでしょう。姫はびっくりして目をみはり、「あれは何ですの?」と、男にきくのでした。男の方は追手が気になり、それ所ではありません。行先は遠し、夜は更け、雷まで鳴りはじめたので、鬼のいる所とも知らず、がらんとした蔵の奥に、姫を入れて、弓矢をもって男は戸口を守っていました。
「はや夜もあけなんと思ひつつゐたりけるに、鬼、はやひとくちにくひけり。あなや、といひけれど、かみなるさわぎに、え聞かざりけり。やうやう夜もあけゆくに、みれば、ゐてこし女もなし。あしずりをして泣けどもかひなし。『しらたまか何ぞと人のひしとき つゆとこたへて消えなましものを』」
男が、夜の早くあけることを念じつつ守っているうち、鬼は一口に姫をたべてしまっていたのです。雷の音に、姫の叫びも聞こえません。
夜があけ、ふとかえりみると姫の姿はなく、足ずりをして泣き悲しんでももはや、取り戻すすべもありませんでした。
「あれは何なの、白玉なの、とあの人がたずねたとき、あれは露だよ、と答えて、もろともに露のように消えてしまえばよかったものを‥‥」
原文は、この歌のあと、姫の兄君たちが追って来て姫をとり返した、それを鬼といったのだ、とあります。姫は連れられて帰られ、在原業平は遂(お)われ、わかい恋人たちは仲を裂かれました。
のち、姫が清和天皇の后となられてから、藤原氏の氏神である大原野(おおはらの)神社へ参詣(さんけい)されることがありました。
美々しくきらびやかな供奉(ぐぶ)の行列のはるか後方に、かつての恋人も近衛府の官人として供に加わっているのでした。
遠くからそれをみとめられた姫のお心はどんなであったか――業平は、后に歌をさし上げたのでした。
大原や小塩(をしお)の山も今日こそは神代のことも思い出づらめ
大原の小塩の山に鎮座される神も、今日は、遠い子孫である后のご参詣を受けられて神代の昔のことをなつかしく思い出されることでありましょう。
表面は公式儀礼として后の行啓をことほぎつつ、その裏に、男は、万感の意味をこめています。
〈あなたは、あの日、あの夜の契りをおぼえていますか。思い出していられるでしょうね‥‥〉
業平はこの失恋に傷つき、東国を放浪しました。彼は恋の狩人ではなく、恋の手練れでもありませんでした。恋の深みにはまることのできた人です。それゆえにこそ、「伊勢物語」は、「恋の見本帳」の権威を失わないのです。
きつね妻
「日本のアラビアンナイト」といわれる「今昔物語」の、タネ本になったのは、それより三百年も前の、奈良朝の末に書かれた「日本霊異記(りょういき)」です。これも、「今昔」に劣らず、面白いお話がいっぱい盛られています。
ただ、この本は、仏教説話集であるところに特徴があります。奈良時代は仏教の盛んな時代でしたが、末になるにつれて世はみだれ人心はすさみ、仏の教えを守る人が少なくなりました。世を救い、人を教化すべき僧尼の中でさえ、むざんな堕落僧、破戒尼が出るしまつでした。
奈良の薬師寺に景戒(きょうかい)というお坊さんがいました。
彼はそんな世の中に心をいため、仏の道を少しでも広めるためにと、筆をとって物語をかき集めました。景戒は想像力のゆたかな、好奇心のつよい、弾力ある心の人でしたから、古い中国の本や、民衆の間に伝わる伝説を拾い、縦横に脚色し、翻案(ほんあん)して、その時代の人々に共感できるような話につくりかえました。
そうして、物語を通じて、仏の功徳、因果応報のことわり、仏教徒として生きる道など説きました――そういうと、いかにも抹香(まっこう)くさく、形式的な説教集のように思われがちですが、一つ一つのお話が、とてもいきいきして面白いのです!
正史には出てこない奈良時代の民衆の日常生活や考え方が、目前にみるように、ありありと浮かぶ。たのしい本なのです!
文章は漢文ですが、正式の漢文ではなく、和風の漢文というべきか、ゴツゴツして、そして素直な文体が、古拙でいいかんじです。
私の大好きなお話は、閻魔(えんま)大王のお使いできた、ユーモラスな鬼の話。
中巻、巻二十四、「閻羅(えんら)王の使の鬼、召さるる人の賂(まひなひ)を得て免(ゆる)す縁」というくだりです。
聖武天皇の御代、楢磐嶋(ならいわしま)という人がいました。
彼は商用で越前まで旅をし、ひとり家へ帰る途中、志賀(しが)の唐崎(からさき)でふとふりかえると三人の男が一町ほどうしろを歩いていました。宇治まで来たとき、男たちが追いつき、一緒になりました。磐嶋(しわしま)は何気なく、どちらまでいかれますか、と聞きますと、驚くべき答えが返ってきました。
「閻羅王の闕(みかど)の、楢磐嶋を召しに往(ゆ)く使なり」
磐嶋(しわしま)は仰天しました。
〈それは私でございます、何のためにお召しになるのですか〉
使いの鬼はいいました。
〈知れたこと、寿命が尽きたせいだ。われわれは先に、お前の家へいってたずねたら、商用で出ているという。やっと出先で捕まえたのだ。家へかえるまでしばらく猶予してやる。お前を捜してあちこち奔走して飢え疲れた。何か食い物はないか〉
〈ここに干し飯(いい)がございます〉
磐嶋は大急ぎで差し出しました。きっと磐嶋はさまざまの感慨が胸にあふれて、顔色も変わっていたかもしれません。使いの鬼は親切な鬼だとみえて、
〈あんまりわれわれに近づくと毒気にあてられて病気になるから、近寄らぬ方がよい。それに、怖がらなくてもよい〉
などと注意してくれます。怖がらなくともよい、といわれたって、閻魔の庁からお迎えがきて、もうすぐ命運が尽きようとしているのに、怖がらずにいられるでしょうか。
いわれたって、家につくなり、大宴会をして鬼たちにご馳走しました。鬼はだんだんあつかましくなり、
〈おれは牛肉が好きだ。牛肉を食わせろ〉
などといいます。磐嶋は、こうなると何の肉でも差し出したい気持です。
〈わが家に斑(まだら)牛が二頭ございます。これをさし上げますから、閻魔庁へ曳き立てられるだけはお許しお願いたいのですが〉
鬼たちは考えました。
〈そうだな、我々はいまお前のご馳走をたらふく食った。そのお返しに許したいのだが、そうすると、我々は重い罪になって、鉄の杖で百回打たれてしまう。もし、お前と同じ年の人があれば、それを身代わりにするのだが〉
鬼たちはひたいをあつめてはかり、結局、同じ年の生まれの身代わり男を捜し出して、連れて行くことになりました。
〈その代わりに、金剛般若経を百回読め、お前の牛を収賄したために我々が罪に落とされるかもしれないからな〉
と鬼はいい置いて消えました。磐嶋は、早速、尊い法師のもとへゆき、心をこめて鬼のために共養し、おかげで九十までの齢(よわい)を保ちました。

この鬼は人間臭く、とぼけたおかしみがあって、当時の人々の心がいきいきと反映しています。
狐を妻にする話はわが国には多いのですが、それも「日本霊異記」からでしょうか。上巻第二のお話――
欽明天皇の御代、美濃の国大野郡の男が、広野の中で美少女に出会いました。男たちはたちまち彼女に恋して、妻にするために連れ帰りました。
二人はむつまじく暮し、男の子さえ生まれました。
ところがその家の犬の子が、いつもこの妻に歯をむき、唸るのです。妻は怖がって、あの犬を殺してくださいと夫に言うのですが、夫は犬を可愛がっていたので、殺しませんでした。あるとき、犬が酷く妻にほえかかり、かみつこうとして追いかけました。妻は怯えて惑い、たちまち狐の姿をあらわして垣の上に登って逃げました。
男の驚きは、いかばかりだったでしょう。
狐は、かなしげに去りもやらず、家のまわりをめぐって鳴きます。
男は叫びました。
〈お前とおれは、子まで生した仲ではないか。おれはお前を忘れないぞ、ここを住みかとして、つねに来て寝よ〉
狐はその言葉にしたがい、来て寝ました、それで〈きつね〉という名になりました。昔は、野干(やかん)といっていたのです。
でも男にとって、いつまでも、まなかいに残るのは、狐ではなく、赤い裳(も)をひく、なよやかな、細腰の美しい妻でした。男は妻恋しさに堪えかねて歌います。
恋は皆我が上(へ)に落ちぬたまかぎるはろかに見えて去(い)にし子ゆゑに
人外の生をうけたものとの間にも、真の愛は育つと、古い世の人々は夢想したのでしょうか。恋はみな、私の上になだれおちた。という表現のある仏教説話集なんて、ほんとうにすばらしいと思います。
シャロンの野の花
私は本来、仏教徒ですが、幼いころ、大阪の下町の日曜学校へかよい、また女学校のころも小さな裏町の教会になじみました。それゆえ、キリスト教は肌と心に、匂いのようにしみつきました。みずみずしい若い心には、ほんとうによくわかる、しみ通りやすい宗教です。そして文学趣味のある若ものには、ことにもとけこみやすい教えのように思われます。それは聖書の文章も、讃美歌の歌詞も、まことに美しく、文学性がたかいからです。
明治のはじめ、長い禁制をとかれたキリスト教はたちまち日本の若者心を捉えて、すぐれた神学者や、敬虔(けいけん)なキリスト教の思想家、文学者をたくさん生みました。富士見町教会の牧師・植村正久も、その一人でした。彼の功績は、松山高吉らと供に新・旧約聖書を翻訳したことです。
第二次世界大戦後、聖書は口語体になったものが行われています。でも私には、明治に訳された文語体の美しさが忘れがたいのです。
「そのとき或るパリサイ人らイエスに来たりて言ふ『往きてかの狐に言へ。視よ、われ今日明日、悪鬼を遂(お)ひ出(いだ)し、病を医(いや)し、而(しか)して三日めに全うせられん。されど今日も明日も次の日も我は進み往くべし。それ預言者のエルサレムの外にて死ぬることは有るまじきなり、噫(ああ)エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し、遣(つかは)される人々を石にて撃つ者よ、牡鶏(めんどり)のおのが雛(ひな)を翼のうちに集むるごとく、我なんぢの子供を集めんとせしこと幾たびや。されど汝らは好まざりき』」…‥
強くはりつめたキリストの生涯、使徒たちの心は、この高鳴るしらべのような文体によく調和し、聖書のどこをひらいても、精神の高揚を感じないではいられません。そして若い私は、遠いはるかな昔の異国の風趣を聖書の中から想像し、うっとりするのでした。
葡萄。無花果(いちじく)。使途たちの風になびく長衣。海の上をあるくキリスト。長い髪で主の足を拭く女。エルサレムの神殿の空に舞う鳩。石膏の壺にたたえられた香油。‥‥
「われ更に汝らきくものに告ぐ。なんぢの仇を愛し、汝らを憎む者を善くし、汝らを詛(のろ)ふ者を祝し、汝らを辱(はづ)かしむる者のために祈れ。
なんぢの頬を打つ者には、他の頬をも向けよ。なんぢの上衣を取る者には下衣をも拒むな。すべて求むる者に与へ、なんぢの物を奪ふ者にまた求むな。なんぢら人にらせれんと思ふごとく、人にも然(しか)せよ」
(ルカ伝第六章)
くり返しくり返し読んであきない名訳ではありました。
ことにも美しいのは、旧約聖書の詩編です。これは古代ヘブライ人が神をたたえた歌ですが、その中の「雅歌」…‥イスラエルの民の古い恋歌です。
「われはシャロンの野花、谷の百合花(ゆり)なり 女子等(をうなごら)の中にわが佳(と)ものあるいは荊棘(いばら)の中に百合花のあるごとし わが愛する者の男子等(をのこら)の中にあるは林の樹の中に林檎(りんご)のあるごとし 我ふかく喜びてその陰にすわれり その実は口に甘かりき
彼われをたづさへて酒宴(さかもり)の室(いへ)に入れたまへり そのわが上にひるがへしたる旗は愛なりき」
「エルサレムの女子等(をうなごら)よ我なんぢらにしかと野の鹿をさし誓ひて請ふ愛のおのづから起るときまでは殊更に喚起(よびおこ)しかつさますなかれ わが愛する者の声きこゆ みよ山をとび岡を躍りこえて来たる わが愛する者はしかのごとくまた小鹿のごとし」
「視よ冬すでに過ぎ 雨もやみて はやさりぬ もろもろの花は地にあらはれ 鳥のさへづる時すでに至り 斑鳩(やまばと)の声われらの地にきこゆ 無花果樹はその青き果(み)を赤らめ 葡萄の樹は花さきてその馨(かぐ)はしき香気(にほひ)をはなつ わが佳(と)もよ
わが美(うる)はしき者よ 起ちていできたれ 磐間(いはま)にをり 断崖(がけ)の匿処(かくれどころ)にをるわが鴿(はと)よ 我になんぢの面(かほ)を見させよ なんぢの声をきかしめよ なんぢの声は愛らしくなんぢの面はうるはし われらのために狐をとらへよ 彼の葡萄園をそこなふ子狐をとらへよ 我等の葡萄園は花盛なればなり‥‥」
明治の青春と情熱が結晶したこの美しい翻訳文学を、私はこよなく愛し、日本の古典の中へ加えるのを誇りに思います。
これ小判
日本人て、ちょっといいな、と私が思うのは、私たち日本人は、あげて詩人の要素があるように思えるからです。日本には、俳句・短歌という、手身近な表現形式があって、たいそう便利なせいもあります。
見渡してみると、俳句・短歌の素養のあるひと、そこまでいかなくても親近感をもっているひと、なだらかな五七調の浪に身を委ねて快いひと(五七調に抵抗を感ずる人は、また、そのひとなりの詩の波長を持っています)がなんと多いことでしょう。こんなに文学的に民族が、世界にあるでしょうか。ちまたに住む、名もなき人が、それぞれの感懐を託して、みじかい詩形にまとめようと努力します。まとめるべき芸術的衝動を多くの人がもっているというのは、民族文化のレベルが高いことではないでしょうか。
私がことにおもしろく思うのは、芸術的衝動という志のたかいものとべつに、日本人には独特のユーモア感覚があることです。
世態人情のおかしみ、機微をとらえて、うまくうがった短詩が発達しました。それを、「川柳」といいます。そして、これこそ庶民のたのしみとなって、どんな人々でも手軽に作れる、身近でたのしい庶民文化となりました。
江戸時代、一七〇〇年代の後半から盛んになりました。宝暦、明和、安永といったところ、将軍家重(いうしげ)や家治(いえはる)の時代です。
もとは前句付けといいました。たとえば、「飽かぬことかな乀」
という前句を出して一般から付句を募集します。撰者がいて、入選した句をすりものにして発表するのでした。その選者(点者)というか、先生の一人が、江戸は浅草の名主だった、柄井川柳(からいせんりゅう)でした。この前句付けばかりをあつめたものがのちに「誹風柳多留(はいふうやなぎだる)」として出版されました。前句付けはやがて川柳という名でよばれ独立した一つの詩形になりました。
さきの「飽かぬことかな乀」につけられたのは、
これ小判たった一晩いてくれろ
庶民の家には、小判一両など、めったに長く滞在しない、右から左へ御通過あそばすのです。庶民は小判をひたいに当て、一晩でもとどまってほしいとねがう心地、一両は当時米一石買えたといいます、金ピカの小判をじっくりとっくりながめて飽きぬ心地のおかしみがよく出ています。

川柳は人のなさけのあたたかさを格好のテーマにします。川柳の根本にあるのは、人情の共感だからです。
母親はもったいないがだましよい
ころりと子供に騙される昔のお袋は、さぞやさしいお袋だったのでしょう。無学だけれどもやさしくて、子供のいうことは尤(もっと)も尤も、と頷いてくれる、親爺(おやじ)にだまって小遣いをくれるお袋なのでしょう。そして、どら息子も、ちょっぴり良心の呵責(かしゃく)をかんじています。
親をだましてはバチが当たるのだが、と重々わきまえながら、うるさい親爺よりはだましよいとお袋にうまいことをいって泣きつくのでしょう。
貫之(つらゆき)は猫をおひおひ荷をほどき
川柳作家にかかっては史上の有名な文学者も現実の日常卑近な生活者に引きずり落とされてしまいます。紀貫之は、かつて「土佐日記」のくだりでのべたように、土佐守として赴任していました。任はてて都へかえってきたときの土産は、さぞかし、土佐名物のかつおぶしだったのではあるまいか、とすれば、荷をほどくとき猫が寄って来ただろう、というおかしみです。彼らはそうやって、武蔵坊や清盛や義経ら、英雄豪傑までみんな、親愛にみちた揶揄(やゆ)の対象にします。
なまつばき吐き吐き巴打って出る
巴御前は男まさりの武勇もの、それでもさすが女ゆえ、打ちものとって勇ましく打って出ながらなま唾を吐くのは、おめでたのしるしでもあるのでしょうか。
さがしましたと仲国(なかくに)馬を下り
これもいうまでなく小督(こごう)の局を勅命でさがしてきた仲国の奉答です。
やわやわと重みのかかる芥川
業平(なりひら)をやわらかく暖かく、からかっています。
日本の庶民の心の中には、大きなユーモア感覚のながれがあります。現実の生活が苦しいときにも、人々は一方でたえず、ふしぎな距離感をもって、われとわが身をわらうおかしみを忘れませんでした。現代もの一見、そういうものがありげですが、実際は、単なる道化や、冷たい嘲笑や、才走った裁きの笑いにすぎないような気がします。
古(こ)川柳のもつ、おとなの距離感をもった暖かい笑いから遠いような気がします。
永遠の少女
「すぎにしかた、恋しきもの」という、清少納言の「枕草子」の一節には、去年(こぞ)の扇や、昔の恋文のほかに、「ひいなあそびの調度」をあげています。王朝時代のひいな遊びは、こんにちでいう「ままごと」でした。三月三日の雛まつりに、雛人形をかざる風習は、時代もずっと下って、江戸時代に入ってからです。
貴族や皇族の姫たちが遊んだ雛人形は、小さな人形は、小さな人形のお邸や調度も作られたらしく、「源氏物語」には、かの紫の上の幼かったころの場面に出ています。
六条御息所(みやすどころ)との愛執につかれ、義母、藤壺(ふじつぼ)の宮との罪ふかい恋になやむ源氏の心に、ぱっと明るく灯をともしてくれたのは、いたいけな紫の上でした。
「源氏物語」という一大交響楽には、明暗・悲喜こもごもの二つのテーマが鳴りひびいていますが、紫の上があらわれてくると、そのページにさっと、さわやかな風がかおり立ちます。
源氏がはじめて紫の姫君をかいま見たのは北山の小さな住居でした。この美少女は、祖母にあたる尼君と共にいおりに仮住まいしていました。
「十ばかりにやあらむと見えて、白ききぬ、山吹などのなれたる着て、走りきたるをんな子、‥‥いみじく生ひさき見えて、美しげなるかたちなり。髪は、扇をひろげたるやうに、ゆらゆらとして、顔は、いと赤くすりなして立てり」

どうしたの、けんかでもしたの、と物静かに問う尼君に、女の子はくやしそうに、
「雀の子を、犬君(いぬき)が逃がしつる。伏籠(ふせご)の中に、こめたりつるものを」
といいつけます。尼君はこの姫がこんなに心もとなく幼くては、残しては死ぬこともできないとなげくのでした。
少女の美しさを忘れかね、かつ藤壺の宮のゆかりとて、恋しい人の面影を宿していることにも心そそられた源氏は、尼君の死後、手もとへ紫の姫を引き取って育てます。
心のままに、理想的な女に育てて見ようと思い、かつ、姫も、さかしく素直に、その期待にそむかぬようにみえました。
しかし何といっても、十あまりの少女でした。
源氏と琴をひいたり、絵などを見て遊んだりしているうち、夕方になり、源氏がよその女のもとへ出かける時間になると、幼い姫は心細そうにうつぶしてしおれ、それを見ると源氏もかわいくて立てません。
〈私がよそへいっていると、さびしいですか〉ときくと、姫はうなずくのでした。そのうち源氏の膝によりかかって眠ってしまうといういじらしさ、今夜は出かけるのを止めましたよ、と姫君を起こすと、元気になって、共に膳をかこみ、それでも、まだ源氏が外に出ないかと心もとながるありさまに、源氏はますます、そばを離れにくくなります。
正月元旦、源氏の君は宮中の朝拝に参上のため、美々しく装束をつけた姿でも紫の姫の居間をのぞくと、姫君はひいな遊びに夢中なのでした。三尺の御厨子(みずし)にいろいろの品を飾り立て、また小さな御殿のおもちゃまでそのへん足の踏み場もないほどひろげて遊んでいるのでした。
〈犬君がこれをこわしたので、直しているところなの〉と姫は一大事のようにいい立てます。〈よしよし、しようのない人だね、早速直させよう。今日はおめでたい日だから泣いてはいけないよ〉と源氏はあやします。
あどけなく心なよらかな紫の君は、やがておとめとなり、源氏の正妻となりました。美しく怜悧(れいり)でやさしい彼女は女の理想ともいうべきすぐれたひとでありながら、子供には恵まれませんでした。それは、紫の上自身、あまりにすばらしく美しい少女時代を持っていたかではありますまいか。‥‥少女のあどけなさ、子供の可愛らしさが紫の上の幼時に凝縮され、永遠の象徴とさえなってしまいました。そのあと、紫の上はもう自分で子供をもつ必要はなかったのです。作者の周到な用意です。それだけに、幼い少女の愛らしさは、いつまでも私たちの胸に、焼き付けられて消えないのです。
黄表紙の色男
「江戸生艶木樺焼(えどうまれうはきのかばやき)」という、江戸時代のユーモア小説があります。作者は山東京伝(さんとうとうきょうでん)。江戸中期、一七〇〇年代の終わりごろ活躍した人気作家です。
彼は浮世絵師でもありましたので、このさしえも自分でかいています。さしえというより、このころの大衆小説である「黄表紙」とよばれた本は、今日の劇画のように、絵を中心で、地の文や会話は、つけたりのように、余白にびっしり書き込んでありました。
これらの本は、町人たち、熊さん八ちゃんや女たちもよろこんでよむ通俗小説、ということになっていましたから、プライド高いインテリたちや武家は手に取るのも潔しとしない風でした。でもそれはうわべのことで、ほんとうは、みんな、内内で読んで腹を抱えて笑ったり、思わず吹き出して、まわりを見廻したり、していたにちがいないのです。
私は謹厳なさむらいが、非番の日の長屋で、こっそり、「江戸生艶気蒲焼」などよんで、つい頬の筋肉をゆるめたりしているのを想像するのが好きです。
劇画ですから、絵と文章と一致しなければ、その効果が上がらないのは当然です。
その点からも、自分で絵を描けたら京伝の本は面白いのです。
この小説は、京伝二十五歳の、まさに才気とエネルギーの充溢(じゅういつ)していたころの作品です。
百万長者のひとりむすこ、仇木屋(あだきや)、艶二郎というのが主人公の青年。自分ではいっぱしの色男きどり、ところが挿絵の艶二郎は、色男なんて顔ではなく、梅の花形を二つに割ったような団子鼻に「へ」の字眉、それがまず、ふき出させます。艶二郎は日頃、

「とんでもなく浮名のたつ仕打ちがありそふなものだ」
なんとか、世間にもてはやされる浮名の主人公になりたい、と考えるのはそのことばかり、腕もおりもせぬ女の名を彫って、さも言い交わした恋人がいるごとく見せかけ、更にそれを嫉妬して灸で消す女がいたようにみせかけ、痛いやら熱いやら、
「色男になるも、とんだつらいものだ」
芸者をやとって、家へかけこませ、どうぞして若旦那といっしょになりたいと泣かせる。家の下女たちも、あの若旦那にほれるとは物好きな女もあるもんだねえ、とあきれ顔ですが、艶二郎はいい気分。
「もふ十両やらふから、もちっと大きな声で、隣あたり、聞こへるやうに、たのむたのむ」
ところが、町内では何も知らず、かわら版にたのんで「評判評判。仇気屋のむすこ艶二郎といふ色男に、うつくしい芸者がほれて駈けこみました‥‥ただじゃ、ただじゃ」とひろめてもらっても、ただでもそのすりものを買うものもいないありさま。
この上は遊里で浮名をあげんものと、𠮷原へかよいつめ、金をやって新造(しんぞう)・禿(かむろ)に袖をひっぱらせ、色男きどりで、「これさ、まァ、はなしてくれろ」などと悦に入っております。
さらに色男というものは、そねまれて、殴られるものだと、地廻りの若い衆に金でやとって、ぶち所わるく、片息になって「気付けよハリよ」とさわぐありさま。ようよう「よっぽど馬鹿ものだといふ浮名をすこしばかり立ちけり」
さらにこの上はと、親にねがって勘当され、親が勘当せぬというものをむりに七十五日と期限つきで勘当してもらい、遊女と狂言心中‥‥読者は、ありうるはずもないこっけいの連続に、「うそつけ、うそつけ」と思いながら、つい読み通し、腹を抱えて笑ってしまいます。切れ味のいいおかしみは、主人公が徹頭徹尾、「よっぽど馬鹿もの」まるでダメな男、という設定からきています。
京伝はすっきりした江戸前のしゃれっけと風を捲いて舞い上がるような才気で、さっと書き上げるのでした。――おかしけりゃ笑いな。おれは教訓はくついきらいさ――京伝はそういっているようにみえます。京伝は現実を一度ほぐして、また笑いにくみたてる作家でした。
ただ狂へ
「淀の川瀬の水ぐるま だれをまつやらくるくると」という歌のひとふしは、浪速の、それも淀川べりに生い育った私などには、耳になれた子守唄のようなかんじでした。曾祖母や老いた乳母、女中衆(おなごし)たちは自分なりのふしをつけて、台所のすみや隠居部屋や縁先で、ちいさくうたうのでした。あるときそれは、ためいきのようにも聞こえましたし、またあるときは心弾む日の鼻歌のようにいそいそとしていました。私は、そんな歌詞は、彼女たちの即興かと思っておりました。
ずっとのちになって、「閑吟集(かんぎんしゅう)」という室町時代の小唄を集めた本を読んでいたら、
「宇治の川瀬の水ぐるま なにと浮世をめぐるらう」
というのがありまして、古い唄なんだなあ、とびっくりしました。四百五十年も昔から私たちの遠い祖(おや)たちは、うれしいにつけ悲しいにつけ口ずさんできた小唄らしいのでした。
「閑吟集」は室町ごろにはやって歌われた小唄・庶民の愛唱歌謡をとりあつめて、書き残したものです。偏者の名はわかりませんがお坊さんのようです。昔、春秋のおりふしに遊宴の席でともに歌いあそび、「声をもろともに老若、なかば古人となりぬる懐旧のもよほしに」「忘れがたみにもと思ひ出づるにしたがひて、閑居の座右にしるしをく」と、序に書かれています。永正十五(一五一八年)に、出来たこともわかります。
これらの短い歌は扇で拍子をとり、また一節切(ひとよぎり)の尺八の伴奏で歌われたのです。のちにこれに踊りがつき、やがて海の彼方から渡来した三味線が入り、歌も長くなって、舞台や色町の芸能に流れてゆくようになります。
私の好きな歌がここにはたくさんあって、「閑吟集」はたのしい歌の本なのです。

「憂きもひととき うれしいきも思
ひさませば ゆめ候よ」
どんな男や女が、半びらきした扇のかげで口ずさんだのでしょうか。
「世のなかは霰(あられ)よの さきの葉の 上のさらさらさっと降るよの」
凄艶(せいうん)な室町の色若衆の、色ざかりをすぎたころおい、唇からもれる吐息でしょうか。
「あまり言葉のかけたさに あれ見さいのう 空ゆく雲のはやさよ」
応仁の乱後五十年、京も地方も動乱につぐ動乱、その中で庶民はしぶとく根強く生き抜いています。どんな焼跡にでも根を下ろし、食べ、歌い、恋をし、笑うのです。
あまり見たさに そと隠れて走ってきた まづ放さいのう 放して物を言はさいの
そぞろいとしゅうて 何とせうぞの
いま結た髪がはらりととけた
いかさま心も 誰そにとけた
身は破れ笠よの 着もせで 掛けてをかるる
ただ人には馴れまじものじゃ 馴れたののちに はなるヽるるる
るるるが大事ぢゃるもの
身はさび太刀、さりとも一度、とげぞしょうずらふ
ただ置いて霜に打たせよ 夜ふけて来たが にくいほどに
ここには、ほんの一行半句の、いい歌がたくさんあります。
これは、物思いする男や女の、ためいきがわりの歌だったのでしょうか。
梅花は雨に、柳絮(りゅうじょ)は風に、世はただ嘘にもまるる
ただ人は情(なさけ)あれ 槿(あさがほ)の花の上なる露の世に うらやましやわが心
夜昼 君に離れぬ
よしやたのまじ行く水の 早くも変る人のこころ
酒の酔いが虹のように立ちこめ、あでやかな小袖がひるがえり、若衆の緑の黒髪が灯に映えます。女の流し目、ふみしだれる衣のすそや帯のはし、宴のたのしみはきわまりをすぎようとして、一座が声合せて歌ったのは、こんな歌だったでしょうか。
なにせうぞ くすんで
一期(いちご)は夢よ ただ狂へ
野ざらしの人
若いころ、私は芭蕉の名句といわれるものに親しみがもてませんでした。わび、さび、しをり、などというムードに反撥をかんじていました。「古池や蛙(かはづ)とびこむ水の音」も、芭蕉開眼悟達の名句と教えられたせいか、よけいきらいになりました。「野ざらしを心に風のしむ身かな」も、わざと悲壮がっている気がしましたし、そう思ってみると、「芭蕉野分して盥(たらい)に雨を聞く夜かな」もポーズができすぎている感じがしました。それに、ときどき、何でこれが俳句だろう? と頭をひねるようなものもありました。「あら何ともなや昨日はすぎふぐと汁」「夏の月御油(ごゆ)よりいでて赤坂や」「枯枝に鳥のとまりたるや秋の暮」――若い私にとって芭蕉はへんにもったいぶった趣味人のじいさん、という感じでした。それに、一種の芭蕉信仰というか、神様扱いで、おびただしい研究書や注釈書があるのも、却って若者を鼻白ませるのでした。芭蕉は長いこと、私にとって縁なき人でした。
私は蕪村から俳句の面白みを学びました。そうして読みすすむうちに、やっぱり芭蕉へ辿り着いてしまいました!
芭蕉はもともと、おかしみ、あそび、言葉のたわむれであった俳諧を、高雅な文芸にまでたかめた人、というのが、私どもに与えられた知識(それは多分に受験勉強用のもの)ですが、その知識を一応とり落とした中年になってから読むと、まさに、彼の句は、「おとなの句」でした。
芭蕉の経歴を知るにつれて、「あら何ともなや‥‥」や「夏の月‥‥」の句は、彼が自分の真骨頂を発揮するまでの、談林風(だんりんふう)時代の過度期の作品だということがわかりました。
中年の彼は俳諧宗匠として充分、らくに食べていける名声や経済的基盤ができていました。しかし彼は俗世的栄誉や富に心を傾けられないたちの人でした。
ひとつところに安住せず、さらに高い境地をもとめて、芭蕉はたえずとびたちます。旅をすみかとし、風狂漂白に身を置く心のたかぶりが、そのまま「野ざらしを心に風のしむ身かな」の決意になってわく過程も、わかる気がしました。
芭蕉は「寸々の腸をさく」ばかり一句に思いをこらし、推敲(すいこう)に推敲をかさねます。その熱い緊張と気負いが、寸分スキのない、格調たかい句になって「奥の細道」できわまります。

荒海や佐渡によこたふ天の河
芭蕉の句の中で、私の好きなものの一つです。私は、この句は実景そのままでなくて、芭蕉のイメージでくみたてられた句だと思います。この地へ旅したことは事実なのですが、芭蕉の眼に映るのはイメージの中の荒海や島かげでした。それが上滑りにならず理詰めにならず、現実以上の真実として美しく結晶しています。この銀漢のもとの荒海の佐渡は波しぶきに打たれながら、実在の島よりも現実的に私たちの心に影を落とします。
四方より花吹き入って鳰(にほ)の海
鳰(にお=別名カイツブリ)の海は琵琶湖の別名です。琵琶湖には多く見られるので、こんな愛称がつけられたのでした。
春。まんまんたる琵琶湖の水に、四方から花吹雪が舞い散るありさまです。芭蕉は故郷の伊賀上野へ往還のみちすがら、京や大津に杖を曳いて、たびたび、琵琶湖のそばに足をとどめています。「ゆく春を近江の人と惜しみける」という句も、湖の駘蕩(たいとう)たる春色と湖国にすむ人のあたたかい人情に、かくべの感懐をもよおしたからでしょう。
やがて芭蕉は、風雅の道を究めつくして、「軽み」という境地にたどりつきます。肩をおとし、肘のかまえをすて、高く悟りながら俗にかえる体(てい)の句の心を、しきりにさぐり求めます。ひとときも現状に狎(な)れたり安閑と満足したりしない芭蕉の潔癖な芸術家魂なのでした。
此の秋は何で年よる雲に鳥
私の最も好きな芭蕉の句です。多年の漂泊にさすが老いを感じはじめた五十一歳の芭蕉は、浮雲や鳥に生涯の夢を賭けた自分を思いかえしています。
芭蕉は生涯に五度も旅に出ました。その最後の旅は東北から裏日本をたずねる行程六百里、六カ月にわたる長い長い旅でした。
芭蕉はその折の紀行文と発句をまとめて「奥の細道」と名づけました。彼はこの作品を愛し、誇りに思い、幾度も幾度も、くり返しくり返し推敲(すいこう)しました。世に発表して名声を博そうとか、お金をもうけようなどという気は全くない彼は、手元においたまま、心ゆくまで書き改めるのでした。(「奥の細道」が出版されたのは、彼の死後です)
詩人がそんなに心魂かたむけて書き上げた「奥の細道」は、だから、たるみもくもりもなく、ぴいんと張りつめて鳴りひびくような硬い美しさを持っています。漢文まじりで簡潔に力強く、そのくせ和んだあたたかみをたたえ、ふしぎな魅力のある文章です。ふんだんにちりばめられた、冴えた一句一句が、また文章とにおいうつり、ひびき交わし、照りはえあって、魅力をたかめています。源氏、枕といった女流の文学とは全く異質の男性の文章の流れを、芭蕉は創り出したのでした。
この旅には弟子の曾良(そら)が従いました。彼も自分で随行日記を書きのこしていますが、それと照合すると、「奥の細道」は必ずしも現実通りの旅日記ではないそうです。現実は雨降りなのに、芭蕉はそれでは、日光さんさんといった句が残ったり、数日逗留したのに、すぐ出発したように書かれてあります。
それはむろん、そうあるだろうことで、芭蕉の書きとどめる現実は、「詩人の感じた現実」だったのです。現実と虚構のあいだを、詩人のイメージで自在にかけめぐり、あらたな別の現実をつくり上げるのでした。
「奥の細道」は、この調子高い名文からはじまります。
「月日は百代の過客にして、行かふ年も又旅人也。舟の上に生涯をうかべ、馬の口とらへて老をむかぶる者は、日々旅にして旅を栖(すみか)とす。
古人も多く旅に死せるあり。予もいづれの年よりか、片雲(へんうん)の風にさそはれて、漂泊の思ひやまず‥‥」
元禄二年(一六八九年)も初夏のころおい、「奥羽長途の行脚(あんぎゃ)ただかりそめに思ひたちて」「もし生きて帰らばと定めなき頼みの末をかけ」紙子ひとつ、ゆかた、雨具、墨筆のたぐいのみを肩に、出発した芭蕉は、ときに四十六歳でした。
折々は辺土のむさくるしい貧家に一夜の宿を乞い、「灯(ともしび)もなければゐろりの火かげに寝床をまうけて臥(ふ)す。夜に入って雷鳴、雨しきりに降りて臥せる上よりもり、蚤蚊(みのか)にせせられて眠らず。持病さへおこりて消入るばかりになん」という苦労も重ねつつ、「はるかなる行末をかかへて、かかる病おぼつかなしていへど、羈旅(きりよ)辺土の行脚、捨身無常の観念、道路に死なん、是れ天の命なりと、気力いささかとり直し、路、縦横にふんだ伊達(だて)り大木戸をこす」
あるいは平泉(ひらいずみ)で、藤原三代の栄華のあと、義経討死のあとを見、
「さても義臣すぐつて此城にこもり、功名一時の叢(くさむら)となる。『国破れて山河あり、城春にして草青みたり』と笠うち敷きて、時のうつるまで涙を落として侍(はべ)りぬ。
夏草や兵(つはもの)どもが夢のあと」
芭蕉はぞんぶんに、声をあげてうたっています。朗々と心ゆくまでうたい上げています。その純一な陶酔は、文学的節度と、芭蕉の美意識によって、美しくととのえられ、かえって文章に強さを与えています。
そればかりか、読むものにも酩酊がのりうつって、いつしか、芭蕉の自己陶酔に同化してゆくのです。私が芭蕉をちかしいものと考え、その句や文章を味わうことに楽しみを覚えたのは、この自己陶酔の余派を共にかぶって心を昂らせる快さをみつけたからに、ほかなりません。
芭蕉はふしぎな世界へ私たちを連れて行ってくれる案内者なのです。
あとがき
私はこの本でとりあげた古典作品を年代順に並べませんでした。それは、古典への入門とか手引きとか啓蒙書を作る意図で書いたのではなく、文字通り、気ままな古典散歩をしてみたかったからです。永いあいだの、私の古典への愛着を、自由に思いつくまま、とりあげてみたいと思いました。
古典への片思いともあこがれとも、秘めたる恋とでも申しましょうか。今までの人生で私は、一つ、また一つと、大好きな古典作品を心の底にためていたのでした。その秘めごとの露がいっぱいたまって、ひとつの雫となり、ぽつん、としたたりおちました――それが、いわば、この本です。
私の好みに偏って申し訳ないのですが、ここには私の好きなものばかり、蒐(あつ)めてあります。物語や、その主人公や、歌や、文章など、私の好きなもの、そして無類に美しい宝玉のように、てのひらにじっと暖めて愛しんできたものばかりです。それらをちりばめて作ったのがこの本です。
それゆえ、おのずからこの本には、わが秘宝を自慢するような、独りよがりの口吻も出たかもしれません。
――偏ったわが嗜好を、読者に押し付ける不遜も、思わないではありませんでしたが、他面考えてみますと、わが熱愛や執着もまた、あるいは古典嫌いな方、古典に不案内な方への、おのずからなる道しるべになるかもしれぬと思うようになりました。
私としては、同じき愛好の人々をたくさん作って、あの作品が好き、あの人物を愛するとかたみに言いあいたいのです。
人生を生きるのに、愛するもの、好きなことを一つでも多く増やすのは、たいへん、たのしい重要なことですから‥‥
文学史的に大切な作品とか、文学的評価が定まっているものという基準ではえらびませんでした。
ただただ、自分の好きな、という一点だけで取り上げました。専門の先生方からはご批判があるかもしれません。私は国文学を専攻したといっても、終戦後、旧制女専に籍を置いただけの、まずしい学力で、注釈書をたよりに読みかじっただけです。思いつかれた点など、今後も専門の方々にご教示賜ればうれしいと思います。
私はいま、「萬葉集」や「古事記」などに、今まで縁もゆかりもなかった方々に、好きな指輪やブローチのように身近に手馴れ、いつくしんで頂きたいと思ったりしています。
好きな着物をひろげて、あれを着ようか、これにしようかと思いまどうように、木曾義仲や、紫の上など、ヒーロー、ヒロインたちを愛し、人生にまつわりつかせて頂きたいと思うようになりました。
そしてまた、恋人の手紙を、ひめやかに諳(そら)んじているように、「方丈記」や「平家物語」の一節を、心の中でおぼえていて欲しい、とも‥‥。
古典の世界は、ゆたかで奥深く、変化に富んでいます。私たちはおびただしい古典の中で、きっと、自分の人生にとって必要なものとめぐりあうことができます。
それにしても、民族遺産としてこんなにすぐれた古典を多くもつ日本という国は、何と素晴らしい国でしょう、私は母国・日本をとても誇りに思い、また好きです。
取り上げた作品や場面がまちまちであるように、書き方もまちまちで、小説風にしたのも混じっています。
大半は朝日新聞に連載したものですが、紙面の都合上短くしていたので、この機会に、いくつかは加筆しました。
そのほか、「額田女王の恋」「あね・おとうと」は「教育ノート」に載せたものをすこし補いました。「わが愛の磐之媛」「恋の奴」は、同人雑誌「航路」に掲載したものです。
なお、新聞連載中からお世話にになった長谷川青澄画伯の流麗な挿絵で、拙作を飾っていただくことができました。気品ある美しいお作品を得たのはこの上ない喜びです。
(昭和四十九年九月) 著者 田辺聖子
一九九六年12月20日発行 限定500部数 定価3、400円
恋愛サーキュレーション図書室の著書