資盛は重盛の次男、入道相国清盛の孫になります。正妻もいる身で人目をはばからねばならぬ、物思わしい恋でしたが、彼女にも資盛にも、いちずな、真剣な恋でした。
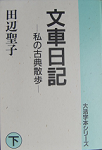 田辺聖子著
田辺聖子著
さめやらぬ夢
寿永四年(一一八五年)春、平家一門が西海の藻くずと消えたとき、都にのこされたゆかりの人々の心もまた、生涯消えぬ悲しみを味わいました。
もと建礼門院(けんれいもんいん)に仕えた、右京太夫とよばれていた彼女もその一人でした。彼女の恋人、平資盛(すけもり)も、海に沈んだのです。
右京太夫は、教養ゆたかな父母の才能をうけついで、歌にも音楽の道もたけた、わかい美しい女でした。
はじめて高倉帝の中宮・建礼門院徳子の宮廷に出仕したのは十六七のころ。わかい帝と中宮を中に、世は平家のおごりの春、全盛時代でした。ときめく平家の公達や殿上人(でんじょうびと)があまたある中で、彼女は、ひとつづきです。二つ年下の資盛と恋におちました。――華やかな、宮廷ぐらしをしていても、浮ついたことはするまいと、かたく思いきめていたのに‥‥。
「おもひのほかに物思はしきことそひて、さまざま思ひみだれしころ」と、彼女はのちに、自分の歌日記「建礼門院右京太夫集」に書いています。
資盛は重盛の次男、入道相国清盛の孫になります。正妻もいる身で人目をはばからねばならぬ、物思わしい恋でしたが、彼女にも資盛にも、いちずな、真剣な恋でした。
しかし世はただらぬさわぎにまきこまれていました。高倉帝の崩御、清盛の死去をさかいに、栄華を誇った平家は、音を立てて没落していきます。
ついに寿永二年七月、平家は、幼帝・安徳天皇を奉じて都を落ちます。「寿永元暦などのころ世のさわぎは、夢ともまぼろしとも、あはれとも、なにとも、すべてすべていふべき際(きは)にもなかりしかば、よろづかいかなりしとだにおもひわかれず、中々おもひも出(い)でじとのぞみ今までもおぼゆる」
宮仕えもやめ、家に引きこもっている彼女を置いて、親しかった人々は都を落ちてゆきました。その惑乱と悲しみは、今思い出すのも辛いほどだ、と彼女は書いています。
あんなに華やかに時めいた平家の一門の人々が一転してこんな運命になろうとは‥‥。

世の人はみな、夢かうつつかと、惑いました。
今日も明日も、都を捨ててゆく人々‥‥。あの人も、この人も。
恋人の資盛も例外ではありませんでした。彼はこのとき、二十四歳、蔵人頭(くろうどのとう)という要職にあって公務が忙しい上に、世の騒がしさもあり、つねによりも人目をしのんで、あわただしく彼女と別れを惜しみました。資盛は沈痛に申しました。
〈もう生きては都へもどれないだろう。これから先は、便りもしない。だが、決してあなたをおろそかに思ってのこととは考えないでくれ。自分でそう気強く思い切らないと、未練が残って辛いのだ。死んだと聞かれたら、せめて菩提(ぼだい)を弔ってください〉
彼はさすが、嫡々の平家の大将、男らしくそう言いすてて、別れてゆきました。
それが今生の別れになりました。
平家があそこで討たれた、ここへ落ちた、と聞くたびに、右京太夫の胸は不安とかなしみに張り裂けます。
「夜明け、日の暮れ、なに事を見きくにも、かたとき思ひたゆむ事は、いかにしてか、あらむ」
どうかしてせめてもう一目、と思うこころが通じたのか、ある夜彼女は、恋人がいつもと同じ姿で、何かもの思わし気に沈んだようすでいる夢を見ました‥‥あたりには、風がひどく吹いていました。目がさめ、彼女はしばらく、胸騒ぎが静まりませんでした。もしや、あのひとの身に変事でも‥‥。それとも、ただ今の今、あのひとは、夢の通りの姿で、どこかの空で物思いに沈んでいるのかしら…‥。
なみ風のあらき騒ぎにただよひてさこそはやすき空なかるらめ
「おそろしき武士(もののふ)ども、いくらもくだる」
平家を討つ源氏の武者たちが、たくさん西へ下ります。平家敗戦の悲報は次々ともたらされました。あるいは生け捕りになった人、‥‥ついに恐れていた時がきました。寿永四年春、平家一門は、壇ノ浦に沈んだというのです。
資盛は、弟の有盛、いとこの行盛らと共に手をとって海へ入ったとききました。二十六歳の花のいのち――覚悟はしてたけれど、右京太夫は呆然として、涙さえ出ないほどでした、長いこと泣きくらし、どうかして忘れたいと思いつつ、「あやにくにおもかげは身にそひ、言(こと)の葉(は)ごとにきく心地して」悲しみは言いようもありませんでした。
資盛は、死んだと聞いたら菩提を弔ってほしいといい遺してゆきました。けれど世は平家ゆかりということさえ、憚らねばならぬ有様でした。右京太夫は悲しみに暮れる心を励まして、ひそかに志ばかりの弔いをします。彼からの古い恋文を料紙に漉(す)き直させてお経を写し、また仏のお姿を手ずからかきとどめて、尊い聖にお供養をたのんだりしました。
その紙に、なお恋人の手蹟(しゅせき)が残るのも、目もくれ魂も消える悲しさでした。長い年月に、たまり、たまったおびただしい恋文。そのとき、かのおり、あのひとはこう誓い、ああも契った、そのうれしい思いの名残りの文がらを、いま漉きかえして、尊勝陀羅尼(そんしょうだらに)、かなしいお経の文字を書こうとは。
かなしさのいとどもよほす水ぐきのあとはなかなか消えねとぞ思ふ
かばかりの思ひにたへてつれもなくなほながらふる玉の緒も憂し
平家の人々の哀れな最期も、いくつも聞きました。ことにおいたわしいのは女院――海に沈まれたのを引き上げられ、心ならずも生き長らえてご落飾、大原の里にお住まいになっていられるのを彼女はたずねます。昔の雲居(くもい)の奥ふかく華やいでおわしたお姿を知る身には、山道のけしき、御(おん)いおりの粗末なたたずまい、「夢うつつともいふかたなし」
そのかみは六十人あまりの上臈(じょうろう)女房たちにかいずかれておわしたのに、いまはお仕えする尼三四人ばかり、その人々も、いずれが誰であったか見分けられぬほど、やつれ果てているのでした。
「花のにほひ、月の光」にたぐえられた美貌の女院も、いとし子を西海に失いたまい、はらからや親に後(おく)れられた悲痛な運命に、別人のごとく面がわりしていられます。右京太夫の真心こめたおなぐさめに女院も共に新しい涙をもようされたことでしょう。
今や夢昔やゆめとまよはれていかに思へどうつっとぞなき
生きて甲斐ない命と思いつつ生きながらえてしまいました。来る年も来る年も、思い出はいよいよ鮮やかに、悲しみは深くなるばかりでした。そのうち、思いもかけぬことでしたが、たって人にすすめられて、再び宮仕えすることになりました。
世は後鳥羽上皇の御代(みよ)になっていました。昔は身分の低かった殿上人のだれかれが、今では押しも押されもせぬ上達部(かんだちめ)になっているのを見つけても、資盛が生きていたら、ああもあったろう、こうもあったろうと思われるのでした。新帝。後鳥羽天皇が、昔お仕えした、おん父みかど高倉帝によく似ておわすいのも感慨ふかいものがありました。
公の古い書類に、かの「さめやらぬ夢とおもふ人」、資盛の署名が、蔵人頭としてとどめられてあるのも、彼女を悲しませるものでした。そうして彼女は老いました。
水の泡と消えにし人の名ばかりをさがすがにとめてきくも悲しき
老いてのち、藤原定家が、新勅撰集の歌を選び集めるために、彼女のもとへ、「書きおいたものがありますか」と訪ねてくれました。そして、その折、「どちらの名にしようと思われますか」と聞かれたのも、うれしい思いやりでした。晴れの勅撰集に入れられるときの、彼女のよび名を、その昔、建礼門院にお仕えしていたときの名が、のちに後鳥羽院にお仕えしてからの名か、どちらを取りましょうかというのです。
「なをただ、へだててしまいました。はてにし昔のことの、わすれがたければ『その世のままに』など申すとて、言の葉のもし世にちらば忍ばしき昔の名こそとめまほしけれ」
そのとき、右京太夫は七十六歳でした。のちになって二十年も仕えた後鳥羽院時代のよび名より、若かりし日に、ほんの五六年呼ばれた、建礼門院右京太夫という名のほうを彼女は望んだのです。—-そして、その名は歌集に、いまもとどめられことになりました。
この右京太夫の悲しみは、先頃の戦争で愛する者を失った何十万の女たちにそのままかよいます。いま、彼女たちはその思い出を抱いてつつましく老いてゆきつつあります。
第二次大戦に出征した若者たちも、さながら資盛のように、故郷の恋人や妻にあてて、ひそかな便りを托し、万感の思いをこめて死地に赴いたのでした。
「昨夜、月光をあびて静かに眠りにはいらんとする東京を離れた。…‥今日の君の胸中を思うて、心中ひそかに哭(こく)し、君健在なれと熱き祈りをおくる。今は君の手でしるされる日記の文まで想像できるような気がする。
君、健在ならんことを。(とも子に)」
(宮崎竜夫、東大理学部人類学科学生。昭和二十年七月二十日マニラ東方四十キロの地にて戦病死。二十六歳)
「昭和十七年師走。戦況日々に激しい南の戦線に出ることとなる。‥‥目をつぶってみる。頭に浮かぶものは愛らしい子供、妻、父、母、妹等々。門出の前夜『私を未亡人にしてはいや』と言ったきみの顔が、目が、忘れられない。…‥きみの顔が浮かぶ。情熱的に黒目がちの目、きりっとした中にも愛くるしいまで引き締まった口、ふくよかな胸のあたり、きみのまぼろしが浮かんで消えない。
ああ! めめしい気持を去らねばならぬ。
後願の憂いさらになし。身体の調子も至極順調、一意待機任務の任を終え、命に依り、椰子茂る方面にでることになったこと、全く男子の本懐、御召しとあらば皇軍の一人として誓って恥じざる覚悟にいる。苦しい覚悟に。
すべて時の流れに、運命に委(まか)せ征く」
(篠崎二郎、同志社大学文学部英文科卒業。昭和十九年一月東部ニューギニアにて戦死。三十四歳)
(『きけわだつみのこえ――日本戦没学生の手記』光文社刊、より)
のこされた女たちの悲愁は、右京太夫のように、生涯消えることはありますまい。冷めやらぬ夢を抱いて老いるのが、女のロマンなのでしょうか。
この、若山牧水の歌に、心をしびれさせなかった昔の女学生がいたでしょうか。この歌は、秋の匂いをさながらももたらすような歌でした。少女の私には、秋は、この歌と共に訪れました。
若者の心に、ぽとりとしずくをおとして、その水滴がやわらかい紙ににじむように、心をぬらしてゆく歌でした。
牧水は、昭和三年に亡くなった歌人ですが、もう古典の中に入れてもよいように思われます。そのしらべの美しさ、純粋さ。そのくせ、芯に強い線が男っぽく通っていて、いかにもゆったりと、おおらかな味わいのする歌です。
今読んでみても、その新鮮さはちっとも失せていません。そして、牧水の歌を、一つと夢中でおぼえていたころの思い出も、もろともに、レモンのように匂い立ちます。
いざ行かむ行きてまだ見ぬ山を見むこのさびしさに君は耐ふるや
少女の私には、ほんとの人生のさびしさはまだわかりませんでした。戦争中の日本には「旅ゆく」という、おおらかな情感は想像もできませんでした。それだけになお私は、見知らぬ国への旅、さびしさの果ての磯山河をあこがれたのです。
吾木香(われもかう)すすきかるかや秋くさの
さびしききはみ

この歌を覚えたのは林芙美子さんの小説だったと思います。軍隊に入った夫から、女主人公の妻にあてた手紙に、この歌が書きつけてあったのです。私は、われもこうという草をみたいと思って、熱心に調べたことを憶えています。
白鳥はかなしからずや空の青海のあをにも染まずただよふ
多摩川の砂にたんぽぽ咲くころはわれにもおもふひとのあれかし
こういう歌を少女時代によむと、一つの歌だけで、一時間も、ぼんやり、いろいろ考えごとができるのでした。「白鳥は‥‥」の歌など、すぐれたふかい交響楽を聞いた後のように、いつまでも余韻がのこって、体のうちの小さな鐘はひびき交と、鳴りどよもし、やわらかな心の中に消えることなく、この歌が彫りつけられてゆくのでした。
牧水の恋歌には、抽象された格調高さがあります。あたらしい古典美、というような。
山を見よ山には日は照る海を見よ海に日は照るいざ唇(くち)を君
ともすれが君口無しになりたまふ海な眺めそ海にとられむ
君かりにかのわだつみに思はれて言ひょられなばいかにしたまふ
これらの恋歌は、どれだけたくさんの若者の、日記や恋文の端に書きつけられてきたことでしょう。
牧水の歌は、そこに特徴がありました。若者たちは、牧水の歌を、自分の歌のように思いなして使うのでした。どんな若者の、どんな恋にも、牧水の歌はぴったり、はまってくれました。引用する、というものではなく、若者たちが自分で作るべかりし歌、そのものが、牧水の歌でした。
かたはらに秋ぐさの花かたるらくほろびしものはなつかしきかな
古い村、古いまちを通るとき、また、人生中年に達した人が来しかたをふりかえりみるとき、私たちは自分の作りたかった歌を、牧水の歌のなからみいだしたりします。もう牧水が歌ってくれた以上、私たちはそれを口ずさむだけでよいのです。私が彼の歌を古典という所以です。牧水は、酒を愛した人でしたから、ちゃんと、こういう歌も、作ってくれました。
白玉の歯にしみとほる秋の夜の酒はしづかに飲むべかりけり
この式子(しきし)内親王のお歌は、百人一首でも人々にしたしまれていますが、何という流麗で、しかも哀婉(あいえん)切々たるしらべでしょう。
わがいのち、絶えるならいっそ絶えるがよい。生きのびていれば、この恋の苦しみに堪える力が弱ってしまおうものを。
内親王の恋のうたは、このほかにも、みな忍ぶ恋の歌ばかりです。
はかなしや枕さだめぬうたたねにほのかにかよふ夢の通ひ路
わが恋は知る人もなしせく床の涙もらすな黄楊(つげ)の小枕
内親王より百五十年ほど前の和泉式部(いずみしきぶ)は、奔放で真剣な、恋の凱歌(がいか)ともいうべき歌を高らかに歌いあげました。しかし内親王のお歌は、あくまでも抑えつけられた声にもならぬつぶやき、鬱屈(うつくつ)してむいぼれた女の重い恋のしたたりなのです。
それは、後白河帝の皇女、というご身分がらもあり、また、内親王の生きられた時代にもよりましょう。源平が血みどろの争闘を重ねていた乱世、かの、平家の打倒のさきがけとなって戦死された以仁王(もちひとおう)は、内親王の兄宮に当てられるのです。
内親王はまだほんの童女のころに、賀茂(かも)の齋院(さいいん)となられ、神に仕える清い生活を十一年ばかり送られました。齋院を辞された時はまだ二十歳前の姫宮だったと思われます。
多感な乙女のころに、内親王は動乱時代のしぶきを真っ向から浴びられました。和泉式部の生きた時代のように、官能の恋を心ゆくまで歌える開放的なよみぶりは、この時代には失われていたのです。

それに、多くは題詠――題を与えられての創作であってみれば、恋の歌といってもプロフェッショナルなテクニックによるものが多いのです。しかし、内親王のお歌には、じつにさまざまな角度から「忍ぶ恋」を擬視する、おん眼が感じられます。
思ふより見しより胸にたく恋のけふうちつけに燃ゆるとや知る
君をまづ見ず知らざりし古(いにし)への恋しきをさへ欺きつるかな
竹西寛子さんは、すぐれた式子内親王論をものされていますが、内親王に、平家の貴公子の恋人があったのではないかという想像を楽しんでいられます。
実は私もまた、そういう想像で、内親王のお歌をよむ一人なのです。平家の公達(きんたち)でなくても、心ひとつにおさめて決して明かされぬ、秘めた恋人がおありだったのではないか。もちろん、ゆたかな天分と、ふかい古典的教養を備えられた内親王には、想像だけで、修辞の技巧に支えられた恋のうたをよまれることは容易だったでしょう。
しかし、お歌には、それをつきぬけた、ある陰火が、燃えも上らず、消えもやらず、陰々滅々とくすぶりつづけています。
けし粒ほどの恋の火種を、内親王は一生お心のうちにじっと守り育てて来られた。美しく怜悧(れいり)に、才ゆたかな内親王のお心を捉えた人は、どんな人だったのでしょうか。それは決して、世に明かせない、文を交わすことも、思いをうちあけることもできない人だったのではないでしょうか。
知る人もいない恋をじっと心に抱いて、三十となり四十となり、内親王は年を重ねて来られたのではないでしょうか。忍ぶ恋が色を深め、思いを増してゆくにつれて、お歌もいよいよ傷ましく深まってゆきました。
和泉式部は、あまたの恋と情人たちとを経て、ついにひとつの真理の世界にあこがれ、「くらきよりくらき道にぞ入りぬべきはるかに照らせ山の端の月」とうたいました。
内親王はただ一つの、秘めたる恋、忍ぶ恋、明かさぬ恋をふかくきわめて、やがて、さめやらぬ煩悩に苦しむわが身、人の世を眺める眼を育てられました。
しづかなる暁ごとに見渡せばまだ深き夜の夢ぞかなしき
契る恋と忍ぶ恋,激情と鎮静の相反するふたりの女流は、期せずしておなじ境地に到達したといえるのではないでしょうか。
たいへん面白くて、読んでいるうちに、笑えてきます。
三馬は、江戸末期、一八〇〇年代のはじめに活躍した、大衆小説作家で、「浮世風呂」「浮世床」は彼の代表作です。これらは、ずいぶん、その当時の人々に愛されたものでした。
三馬は戯作の筆もとりましたが、一面、手堅い実業家でもありました。薬商を営んで化粧水などを製造し、それを自作の小説の中にも宣伝するといった、ジャーナリスティックな才能にも恵まれ、お金もうけも、決して下手ではありませんでした。
そんな三馬が書いた小説は、だから卑俗ですが、説得力があります。写実的で現実の重みがあります。
「浮世風呂」は銭湯に集まる江戸庶民の会話、「浮世床」は、床屋に集まる人々のそれを書きとめて、さながら、江戸時代のテープレコーダーを回して聞くようです。
その会話のおもしろいこと、さながら息遣いから口吻まで想像できるおかしさは、十返舎一九(じっぺんしやいっく)らのこっけい本の、作為的なおかしみと、全然、別のものです。
筋はなくて、さまざまな身分、生活環境、性格の人々を、会話でかきわけてあるだけですが、おのずから、そこに三馬の見識というか、社会を見る目の皮肉さというか、そんなものが浮き上がってくるも、たのしいところです。

「浮世風呂」三篇、「春は曙、やうやう白くなりゆく洗粉に、旧年(ふるとし)の顔を洗ふ初湯の烟(けむり)、細くたなびきたる女湯の有様、いかで見ん物をとて、松の内早仕舞ちふ札かけたる格子の下に佇(たたず)み、障子のひまよりかいま見るに、その様をかしくもあり、又、おのが身のぶざめいたるは、あさましくもありけり」女湯の中の会話を、そ――っと盗み聞きしてみましょう。
ト書に「髪の毛のうすき女房、二人にて流し合てゐる」とあります。
お川「コウコウお山さん、お前の隣ぢぁァ、夕(ゆふべ)も夫婦喧嘩があったの、久しいものさ。なぜああだらろ」
お山「思ふ中の小いさかひやらさ。どっちをどうとも云へねへはな」
お川「両方が悪いといふ内にも、商売上りの者は、癖として、やきもち深いから、夫婦喧嘩が絶えねへのさ。男のひひきをするぢゃァねへが、総体(そうてい)男といふものは、表をつとめるもんだから、ちっとづつの付き合いもありうちだァな。そこを女房も心得して居ねへぢゃァならねへ。目が明かずに悪くやかましくばかり云って見ねへな。それこそ、なほ逆らって出かけるはな。さうかと云って黙ってばかり居てもますまず、諸事、塩梅物だによ。
しかしまた、おらがかかァだの、おらが山の神だのと云って、かみさんを怖がる亭主も世間体の悪いものさ。なんぞの話ついでには、てんぐ―の女房をほめちぎるもきざな奴さ。さうかととって、むごく当たるばかりを能にして、ひどいめにあはせる亭主も、つらのにくいものなり、何でも気の合った夫婦が互の仕合せ、長い月日にゃァ、好いことばかもねへもんだから、両方で不肖しやふのさ‥‥」
このお川さんのとなりには、新婚の夫婦が住んでいるとみえ、岡焼き半分で、こきおろします。
お川「屋敷から下りたてのおかみさんに、もちたての女房だって、間がなすきがな、お縁(えん)さんのそばへよって、のろけた顔を見なナ」
お山「まだお前ひい乀たもれだものを。花嫁の間が花さ。おっつけ子小児(ここども)でもできてみな。あヽはいかねへ」
お川「ヘン、穴嫁があきれるよ。ヤレ香をかぐのお茶をくらふのと、大笠原か釆女原(うねめはら)かのお諸礼を仕候とって、風見の鳥を見るやうに、高く止まってすまァしているのも小癪(こしゃく)に障らァ」
お山「さうさ。花を活けるの琴を弾くのと、世帯もちのいらねへ事さ。飯を焚いて着物を縫って、内外の者の身じたくをして、物にすたりの出ねへやうにすりゃァ、女房の役は沢山だはな。それで気に入らざァ先さまのご無理だ」
三馬の会話の面白さは、ほんとうは落語の口述のような部分がよくわかるのですが、ここへ引用したのは、ある意味で感慨があったからです。
お川さんのいう夫婦論・男女論は、いまの世の婦人雑誌、女性週刊誌の説く夫婦論。男女論と、本質的には変わっていません。
百七十年昔の夫婦論から、まだ変化していないというのは、これは、男と女の本質論なのではないでしょうか。
そういうことをいえる三馬というひとは、卑俗に平明に書きながら、本当は、すごく世の中のことを知りぬいていたのではないかと思われます。ふかく物を見ていたのでしょう。
世間のこと、人の心、人の性格などに、どん欲な好奇心と愛情をもち、それを、しかし粉飾しないで、素朴そのままのように投げ出しました。三馬は人間の肉声が好きでした。ナマの生活が好きでした。それを面白がる自分の心のままに、筆が宙をはしって、出来上がったのが、「浮世風呂」「浮世床」なのでした。
松は日本の誇りともいうべき木です。
でも近年、美しい松を見ることは珍しくなりました。松は大気汚染に弱い木らしく、それに害虫の繫殖がひどくて、松の立ち枯れ病が全国的に蔓延しています。
あちこち旅をして、まるで紅葉しているのかと思われるような、赤茶けた枯れた松を見るほど悲しいことはありません。私は、枯れた松、色がわりして気息えんえん、といった松を見るたびに、ほとんど肉体的な苦痛さえ感じます。そしてこのごろの、山野にはびこる、芋の葉に似たツタカズラのような雑草も、高い松の梢にまで巻きつき、山肌を覆い隠しています。美しい日本の山野は、まさに荒廃寸前と叫びたい気持ちです。悲しいことです。
松をよんだ歌は「万葉集」の昔から、かず限りなくあり、歌人たちは、その葉の、冬の色かえぬめでたさや、松を待つにかける言葉のたのしさを、飽かずに歌に詠み込むのでした。
その中で、私が最も愛する松の歌、そして、最もすぐれていると信じる歌は、「万葉集」巻六の、市原王(いちはらのおおきみ)の作です。
一つ松幾余か経ぬる吹く風のおとの清きは年深みかも
なだらかで品あり、格調たかいすぐれた歌、まさに、男のひとの歌、という気のする、気概のある歌です。
この丘の、ひともとの松は、そも、幾代を経ているのか。颯々(さつさつ)と風が枝を鳴らして渡ってゆく。その松籟(しょうらい)の音がさやかに清く澄んでいるのは、長い年月を経ているためか。
作者の市原王という人は、天平の頃、東大寺の造営長官をつとめた王族ですが、代々、歌才にめぐまれた一家です。それでひとつ松の歌も、筋目ただしい秀歌、という感じがします。早春、活道(いくぢ)の岡にのぼって、ひと本の松の下に集うて、宴をしたときの歌、という詞書があります。
この歌を口ずさむと、亭々とそびえる松の巨木が目に浮かびます。がっしりと揺るがぬ幹、ふかい緑の、いきいきと、先端のするどい葉、見上げると、頂きは、気の遠くなるような高さ。その梢ごしに、はるかに遠い蒼穹(そうきゅう)――ごつごつとたくましい枝は、巨人の腕のごとく張って、たがいにさしかわし、誇りたかく幾代の風雪に堪えてきたのです。
詩人・市原王の心に、その巨(おお)きな、ひともと松は、ふかい畏敬と愛慕の念をよびおこしました。
「おお! 何という美しい木だ」
彼はその感に打たれて、叫んだことでしょう。
幹に耳をあてると、古代の風の音が聞こえるかもしれません。そんな、木なのです。
日本の木は、魂をもっています。立派な、古い木には神霊が宿ると信じられています。
私は西洋の古いまちで、巨木が町中にうっそうと茂り、その下を車が走り、人々が生活しているうらやましく思いましたが、もともと、日本と木と、西洋の木は、木と人とのかかわり方において違うような気がします。西洋の木は人馴れした木、人に愛される木、人をいこわせ、庇う木なのです。
でも日本の木は、ことに巨きな木は、人里はなれたところにあって、人に畏敬される木なのでした。精霊や神気が梢に宿っています。
木は瞑目(めいもく)したまま、深い悲しみにみちて、
〈お前は何をしてきたか‥‥〉
と人々に問います。神のような声でした。
人は、木の声に向かって頭をたれ、静かに越しかたをふり返らずにはいられませんでした。そんな木は、松こそ、ふさわしいのです。
あの枝ぶり、深い海のような葉の色。静かに口の中で、口ずさんで下さい。「ひとつ松 幾代か経ぬる 吹く風の おとの清きは 年深みかも」――ああ、清らかな松風の音が、潮ざいのように、耳に聞こえてくるはずです。
卯の刻(午前六時)に戦いははじまりました。
名にしおう激流の瀬戸。「門司・赤間・壇ノ浦はたぎッておつる潮なれば」源氏の船は潮に向かっておしおとされ、平家の船は潮に乗ってすすみ、源氏死力をつくしての戦いは、はじめ、平家に有利と見えました。
しかし午後になって潮の流れは変わり、その上、平家を見限って源氏につく船が出て来て、にわかに平家の旗和泉式部若山牧水色が悪くなりました。
平家の総大将は新中納言、知盛。平家随一の猛将です。私はこの男が好きなのです。
三十四歳の男盛り、この人を措(お)いて、平家の侍大将はないというような、勇ましいもののふでした。「平家物語」は、知盛の最期を美しく描き切っています。
知盛は決死の覚悟をきめていました。彼は今まであらん限りの力で平家の頽勢(たいせい)を支えてきたのです。今日が最後の決戦と知っています。
彼は舟の屋形に立って大音声(だいおんじょう)で武士たちに下知します。
「戦は今日ぞ限り、者ども、少しも退く心あるべからず。天竺・震旦(しんたん)にも日本我朝(にっぽんわがちょう)にも並びなき名将勇士といへども、運命つきぬれば力及ばす、されども名こそ惜しけれ。東国のもの共に弱気見ゆな。いつのために命を惜しむべき、是のみぞ思ふこと」
彼はすでに一の谷の合戦で、息子の智章(ともあき)を死なせています。まだほんの少年の息子は、彼をかばおうとして敵に討たれたのでした。その傷みを知盛は癒すすべもありません。最後の決戦に死力をつくして戦うこと、それしかないのです。
しかし源氏の船は、勢いするどく責め立て矢をいかけ、平家方はしだいに浮足立ちました。
「源平の国あらそひ、今日を限りとぞ見えたりける」源氏の兵たちは、平家の船にどんどん乗り移ってきます。源氏もまた東国そだちの荒えびす。命おしまぬ猛々しい侍たちです。平家方の水手舵取り、「射殺され、斬り殺されて、船を直すに及ばず、舟底に倒れ伏しにけり」
知盛は、形勢を見て、安徳幼帝のおわす御座船に小舟を漕ぎ寄せていきました。
「世の中、今はかうに見えて候。見ぐるしからん物どもみな海へ入れさせ給へ」

今はこれまでです。見苦しいものはみな海へ捨てなさい、と女たちにさしずして、みずからそのあたりを清めるのでした。女房たちは口々に、中納言さま、いくさはどんな様子でございますか、と聞きますと、
「めづらしきあづま男をこそ、御らんぜられ候(さうら)はんずらめ」
珍しい東国男をごらんになれるでしょう、と知盛はからからと笑うのでした。なんでこんな時にご冗談を‥‥と彼女たちは泣き声をたてて叫びます。
知盛は、こんなときこそ、冗談がいえるのでした。精神は死力をつくして戦ったあとの爽やかさに澄んでいます。
清盛の妻二位(にい)の尼君も、かねての覚悟通り、女なりとも敵の手にかかるまじと、安徳帝を抱き奉って、船端へ歩みよります。
主上ことしは八歳、「おんかたちうつくしく、あたりもてり輝くばかりなり。御髪(おんぐし)黒うゆらゆらとして、御背中すぎさせ給へり」ふしぎそうに、私をどこへつれていくの、と仰せられます。尼君は涙を抑え、幼帝の小さく美しいおん手をお合せ申して、
「浪のしたにも都のさぶらうぞ」
となぐさめ奉って、千尋(ちひろ)の海に身を投じられました。つづく建礼門院、あまたの女房たち、波の上には花を散らしたような、阿鼻叫喚のさまだったことでしょう。
平家の公達(きん)も、次々といさぎよく船から身を沈めました。平中納言教盛、修理太夫経盛(しゅうりのだいぶつねもり)、鎧の上に錨を負い、手を組んで海に入れます。
資盛、行盛、有盛らも共に「手に手をとりくんで一所に沈み給ひけり」
この中にも、総大将宗盛・清宗父子は、入水する勇気もなく、みかねて人々が海へ突き落としましたが、泳ぎが出来る上に、鎧も身にまとわず、死ぬに死ねないでいるところを源氏軍に、生け捕りせられました。
それをよそめに、華々しい武者ぶりは、知盛につづく勇将と謳われた能登守教経(のとのかみのりつね)でした。
今日を最後と、矢だねのあるほど射つくして、白柄の大長刀で薙ぎまわします。その奮闘ぶりを、知盛は余裕をもってながめつつ、使者をたてて「能登どの、いたう罪なつくり給ひそ。さりとてよき敵か」
といわせます。とるに足らぬ雑兵など討って、そう罪つくりをしなさるな、と声をかける知盛に、闊達(かつたつ)な男らしさがうかがわれます。教経は聞こえる暴れん坊若様です。〈さては大将軍に組めということか〉と刀の柄を短く持って、源氏の船にとびうつり、のりうつり、白兵戦を挑みます。めざすは九朗半官、源氏の総大将の首、しかし半官は身軽く舟を飛んで危ういところを脱し、いまはこれまでと教経は、舟につったって大音声で、われと思わん者はこの教経を生け捕りにして鎌倉へ曳け、頼朝と会うて、ひとことものいうぞ、と「おそろしなンどもをろかなり」というすさまじさ。
太刀自慢の源氏方の侍が三人、どうと教経にうちかかります。教経、一人を海に蹴り入れ、二人を両脇にかいばさんで「いざうれ、さらばおれら死途の山のともせよ」と、海へざぶんと入りました。
知盛は静かに、つぶやきます。
「見るべきほどのことは見つ」
ああ見た。滅び栄える人の世のありさま、運命の転変のおもしろさ、おもしろうてやがてあわれなさまざまを見とどけた。
平家の柱石だった清盛の死につづく一門の凋落(ちょうらく)、壇ノ浦の決戦、幼帝の最期、親しい友や肉親の死にざまを、すでに目にした、おお、女院が御髪(おんぐし)を熊手にかけて引き上げられ給うそうな。あわれ長らうべくもあらぬ命をとどめられ給うた。あれ、あそこの船へ、宗盛父子が生け捕られて救い上げられる。それもこれも、人の力の及ばぬ運命かもしれない。宗盛らしい運命かもしれぬ。それもよし。
知盛は、めのと子の家長(いえなが)をよんで、約束だぞ、共に死のう、といいます。家長、「子細にや及び候」(申すまでもございません)たがいに鎧二領を着、手を取り合って海に入りました。名を惜しむもののふたち二十余人、おくれじと手に手を取って、一所に沈みました。「平家物語」の、このあとの文章は、わけてぬきんでた名文です。
「海上には赤旗・赤じるし投げ捨て、かなぐりすてたりしなければ、竜田川の紅葉ばを嵐の吹き散らしたるがごとし。汀(みぎは)によする白浪もうす紅(ぐれなる)にぞなりにける。主(ぬし)もなきむなしき船は、汐(しほ)にひかれ風にしたがッて、いづくをさすともなくゆられてゆくこそ悲しけれ」
敗け戦の海上にただようかなしみを簡潔に叙(しる)しています。
「見るべきほどのことは見つ」――知盛は死にのぞんで、ゆくりなく、宇宙の大きな意志をかいまみたでしょうか。死も生も一如、知盛はほほえんで死んだにちがいありません。
いま、関門海峡には大きな橋が架かりました。八百年の昔、この下の海で「見るべきほどのことは見つ」とつぶやいた人の思いを秘めて、潮はとどろと渦巻いています。
冬は、小林一茶の句の思い出されるときです。
私のように暖国の関西に生まれた人間には想像もつかぬ、雪の下の人々の感情が、一茶の句には暗く烈しく渦巻いています。
一茶は、雪を風流なものと、賞で興じるのは、雲の上人のことだと嘲笑うのでした。
一茶のいう、「下々(げげ)の下国の信濃」では、
「木の葉はら乀と峰のあらしの音ばかりして淋しく、人目も草の枯れはてて、霜降月のはじめより白いものがちらちらすれば、悪いものが降る、寒いものが降ると口々にののしりて、――初雪をいまいましいというふべ哉(かな)」
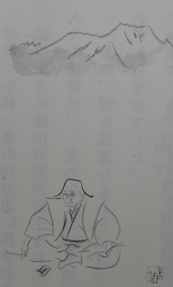
荒くきびしい自然の猛威に加え、少年時代の一茶は、まま母にいじめられて育ったと、「生ひ立の記」にかいています。異母弟が生まれてからは子守りをしていて泣くと、一茶がいじめたのではないかと責められ、
「杖のうき目にあてられること日に百度、月に八千度、一とせ三百五十九日、目のはれざる日もなかりし」
若い日の私は、一茶の不遇な少年時代に同情し、一茶がそのため、長じてやさしいおじさんとなり、「やれ打つな蠅(はえ)が手をする足をする」「痩せ蛙負けるな一茶これにあり」
などという、よわいものに哀れみの涙をそそぐ、童心詩人になったのだと、思い込んでいました。
しかし、一茶の句や伝記をよむと、中々、そんな単純なものではないのです。
一茶は少年の頃、江戸へ奉公に出されました。一七〇〇年代の終わりごろでした。辛い放浪時代のうち、いつか一茶は、俳諧師(はいかいし)としての人生を歩んでいました。故郷を追われ、後ろ盾もなく、深い学問もない彼には、この道もまた、いばらの道だったことでしょう。
夕燕我にはあすのあてはなき
梅咲くやあはれ今年も貰ひ餅
年の市何しに出たと人のいふ
春立つや四十三年人の飯
貧窮と屈辱と孤独に身をすりへらした一茶は、いつしかそんな年となっています。富裕な俳人仲間をたよっては流浪し、食つなぐ日々の辛いくらしは、彼を、気難しく傲慢で、時に卑屈な屈折した人柄に染め上げたようでした。
故郷の父を見舞ったときに、たまたま父の病いおもく、一茶はそのまま、居ついて看病をしました。それが「父の終焉日記」です。
私はそれを詠んで、一茶という人間の性格がますます底知れぬものように思えました。
その文章の、まあなんと強引で、自分本位なことでしょう。ここではまま母異母兄弟も冷酷無惨な悪人にされ、真に父のことを思う孝行者は一茶ひとり、と書かれています。とすれば「生い立ちの記」にある「杖を日に百度」というのも、かなり一茶流の誇張があるのかも知れません。
「我ときてあそべや親のない雀」も、彼らしいポーズだったかもしれません。独断的な文章や発想は、私をして一茶の人格を疑わせるに充分でした。それに、彼は父の死後十二年間も、異母弟と遺産相続で争い、ついにはむしり取るようにして、故郷の一角の地を、自分のものにしています。五十の坂をこえて若い妻を迎え、死なせたり別れたりして三度妻をとりかえ、浮世の欲望に執着するさまも、むき出しにしました。
ほんとうに一茶という男は、一筋縄では行かぬ野性的な、あらあらしい、ねじけまがった性格にみえました‥‥ところがそのむくつけき野人が、どうしてあんなに、美しい、やさしい句を、ひょいひょいと、口にのぼせるのでしょう。澄んだ詩人の目と童心がなくてどうしてこんな句がよめるでしょう。
雪とけて村いっぱいの子どもかな
うつくしや障子の穴の天の川
湯けぶりも月夜の春となりけり
これもまた疑いがいなく一茶の一面だったのです。
私にとって、人間というものの面白さ、ふしぎを教えてくれるのは、いつも一茶です。
日本人が漢詩をつくるというのは、ちょうど、英語の詩を書くのと同じで、所詮、本家の国の詩人たちに及ぶはずもありません。けれどね。本来、すぐれた資質をもち。万事につけて熱心な日本民族は、渡来した漢字文化にたちまち夢中になりました。漢文・漢詩の素養は、知識階級男子の不可欠の条件でした。そうして日本人の漢詩も大そう優れたものが作られるようになり、時には本家の中国の文人に、おほめを頂戴するほどの詩人さえ出ました。
江戸末期は、漢詩のたいそうさかんだったときで、有名な漢詩人がたくさん出ました。頼山陽(らいさんよう)はもっとも人に知られた詩人でしょう。山陽の詩句は派手で鋭く強く個性的ですが、私としては、あまり好きではありません。
――といっても、私は漢詩についてお恥ずかしいことながら深く知らないのです。起承転結の展開とか、平仄(ひょうそく)・韻脚などのきまり、絶句や律など種類が多く、むつかしい約束ごとがあり、それらに通じていればより一層味わい方も面白くなるでしょうが、私が読むのは国語まじりの読み下し、いわゆる詩吟などで唱い上げられるよみかたです。
菅茶山(かんさざん)という、江戸末期の儒学者がいます、中国風な名前ですが、これはペンネームで、備後(びんご)・福山のひとです。若い頃、京都へゆき、儒学を修め、のち郷里にかえって若者たちを教えてました。その塾の名を、「黄葉夕陽村塾(こうようせきようそんじゅく)」といいます。私は「松下村塾(しょうかそんじゅく)」という名も好きですが、この名前もすばらしいと思います。そして、若者たちに勉学される機関としては、こんな風に一人の優れた先生が私塾を開いて、真剣に学びたい意欲をもっている若者だけを教えるといのが本当ではないかと思います。

――菅茶山は一代の碩学(せきがく)でしたし、また人格の温和で謙虚なことでも知られ、彼を敬慕する生徒が多く、しまいに塾は収容しきれなくなって、とうとう藩の塾にしてもらい「簾塾(れんじゅく)」と名づけました。
彼の詩は、語句がよくこなれて、やさしい人柄と、しずかな詩人の目がかんじられます。「冬日雑詩」という詩があります。
寒鳥相追入乱松 隔渓孤寺静鳴鐘
山風俄約晩雲去 雪在西南三四峯
寒鳥 相追ウテ乱松ニ入レバ
渓ヲ隔テタル孤寺ハ静カニ鐘ヲ鳴ラス
山嵐俄(ニハ)カニ晩雲ヲ約シ去レバ
雪ハ西南ノ三四峯ニ在り
寒い澄んだ冬の日暮れの情景です。鳥たちは追ったり追われたりしつつ、ばらばらに生えている松林に入ってゆく、谷の向こう側の、ぽつんと建っている寺では静かに鐘を鳴らす。山嵐がにわかにわきおこり夕べの
雲をあつめて吹き払うと、西南の峯の三つ四つに雪がみえる‥‥風の寒さが身に感じられるような詩です。「路上」というやさしい詩もあります。
反照入楊林 沙湾晩未冥
母牛与犢児 隔水相呼応
反照ハ楊林ニ入(いりた)レバ
沙湾(ジャワン)ハ晩モ未(イマ)ダ瞑(クラ)カラズ
母牛ト犢児(トクジ)トハ
水ヲ隔テテ相呼応ス
夕日はかわやなぎの林にあかあかとさしこみ、そのため水際(みぎわ)もだあかるく照り返っている、母牛と仔牛は、川をへだてて、のどかに鳴き合っている。‥‥
漢字と漢字のつらなりは固そうにみえますが、かえり点を打ってゆっくりと味わってみますと、一語一語が珠玉のように光ってそれがふれあうたび、たまゆらのさやかな音をたてます。悲壮なもの、烈しいものが漢詩の本分のように思われますが、しずけさとやさしさのあふれる漢詩もまた、人々に愛されてきたのです。
まだ八歳のいとけない年頃に即位させられ、ほんの少年のころに、結婚させられ‥‥帝は、物心つく前から、平家一門の、政治的配慮で、その人生を人々に操られ、動かされ、強いられてきたような運命の方でした。
おん父は後白河法皇。平清盛は、義理の伯父に当たり、二大実力者の間にあって、天皇とは名ばかりの地位、そして結婚相手は、清盛の娘、徳子‥‥。
帝は仕組まれた運命のレールを、そのまま動かされて、青年となられました。
ところが、帝が、ご自分で、運命を選ばれる日がきました。それは、当時、宮中第一の美女で、ならびなき琴の名手といわれた、小督局(こごうのつぼね)と、恋におちられたからです。
この恋は清盛の怒りを買いました。わが娘の中宮徳子に、一日も早い皇子ご誕生を、と願っている清盛は、帝が、ほかの女に心をうつしていられるのに堪えられないで、小督局
を亡きものにせよ、といいつけます。
小督は心を痛めました。わが身はどうなっても帝にご迷惑がかかっては、と「ある夜内裏(だいり)をいでて、ゆくゑしらずうせ給ひぬ」
突如、恋をひき裂かれた帝は、悲しみにくれて、小督のゆくえをたずねられましたが、清盛をおそれて、お味方する者はないありさま。
八月の十日あまり、月の美しい宵です。帝は「人やある」と呼ばれます。遠くにひかえていた仲国(なかくに)が、お答えしますと、小督のゆくえを知らぬかとのお尋ねです。噂では嵯峨の奥にかくれすむそうな。探し出すことはできぬものだろうか。涙を押さえてのお尋ねです。
仲国の心は、若い薄幸な二人の恋人たちへの同情で一ぱいになりました。よろしゅうございます。私がお探しいたしましょう。このお美しい月夜、琴の妙手の小督どのは、帝のおんことを思い出しまいらせて琴をひいていられるかもしれませぬ。琴の音をたよりにあちらこちらを探してみましょう。彼はすぐさま「名月にむちをあげ、そこともしらずあこがれゆく」のでした。このあたり、まるで、大和絵をみるような「平家物語」の名文です。
「亀山のあたりちかく、松の一むらある方に、かすかに琴ぞきこえける。峯のあらしか松風か、たづぬる人の琴の音か。おぼつかなくはおもへども、駒を早めてゆく程に、片折戸したる内に、琴ぞひきすまされたる。ひかへて是をききければ、すこしもまがふべうもなき小督殿の爪音なり。楽は何ぞとききければ、夫を思うて恋ふとよむ想夫恋(そうぶれん)といふ楽なり、そればこそ、君のおんこと思ひ出まいらせて、楽こそおほけれ。此の楽をひきたまひけるやさしさよ」
みつけ出された小督は、ひそかに内裏へ迎え入れられました。禁じられ、堰(せ)かれた恋であってみれば、よりいっそうそれは二人を暗く烈しく包んだことでしょう。しかしたちまちその恋はおそろしい清盛の耳に入ってしまいました。小督は捕らえられ、尼にして放たれました。帝は憂憤やるかたなく、苦しみにやつれ、恋にやせ、ついに、おん年二十一、という短い生涯を終えられました。小督は濃い墨染の衣をまとわれたとき、花のような二十二歳だったと伝えられます。
いま小督の墓といわれるのは大堰川の渡月橋のそばと、東山清閑寺の高倉天皇の御陵の内と、二つありますが、私としては、高倉帝のそばによりそうよう埋められたと思いたい気がします――もとより御陵の内は、さしのぞくことはゆるされませんが、ひともとの杉の根元に、ひっそりと、宝篋印塔(ほうきょういんとう)が据えられているそうです――私が訪れた日は寒い冬の一日でした。
ひえびえする空気、折々こぼれる霧雨のしずく。と思うとふと雲が切れて、もみじの梢に日が当り、全山さやかに青くなりました。しいんとした高倉帝のご陵内の、すがすがしい玉垣のうちにその杉の木は立っていました。小督の塚のしるしがあるのは、あの杉の木なのでしょうか。
すでに肉体は大地に還り、いまは二人の恋と、月夜の琴の音だけが八百年ののちにも、れいろうと澄んでひびき交わしています。恋人たちのやさしいねむりを思い、私はふり返りふり返り、石段を去ったことでした。
商人・町人の金のやりくり算段、大晦日ほど大変なものはありません。昔は年に数回の節季払いでしたが、大晦日は一年の総決算、この二十四時間の峠を越さねば、あらたまの春とはならず、人々は足をそらに金の算段に走り狂います。
「けふの一日、鉄(かね)のわらじを破り、世界を韋駄天(いだてん)のかけ廻るごとく、商人は勢ひひとつの物ぞかし」
必ず掛け金をとって帰らねばと意気込む掛取り、わびごとも言いつくして果ては狂言自殺をもくろむ人々、ありそうでないものは金、裕福そうな町屋も一歩内へはいれば火の車、西鶴は大晦日を舞台に、虚々実々のかけひき、やりくりを面白おかしく描きます。面白うてやがてかなしき大晦日、金、金、金の浮き世のさまざまを、例の口早な、凄いテンポで矢継ぎ早に、西鶴はたたみかけて語るのです。
「世間胸算用」は、彼の作品中では一ばん面白いものではないかと、私は思います。
金に操られる人生を、西鶴は眺めながら、そのむごさと共におかしみ、面白さも見逃しません。ことに、貧乏長屋の大晦日の、とぼけたおかしみは無類です。
金のやりくり算段は、むしろりっぱな富家のこと、いっそ貧しい下層町人は気楽なものです。貧乏長屋六七軒、「何として年をとる事ぞと思ひしに、皆、質種の心あてあれば、少しも世を欺く風情なし」
米みそ・たきぎ・醬油・塩・あぶら、貧乏人には貸し売りするものもないので現金払いゆえ、大晦日がきてもふだん通り、「帳(掛取り帳のこと)さげて案内なしにうちへ入るものひとりもなく、誰に恐れて詫び言をするかたもなく、楽しみは貧賤(ひんせん)にありと、古人の詞(ことば)、反故(ほうぐ)にならず」
正月のことは何として埒あけるこぞと思ってみていると、みんなそれぞれ質をおく覚悟があって手廻しよくしているのが、哀れにもおかしいのです。一軒からは、古い傘一本に綿繰一つ、茶釜一つかれこれ三色で、銀一匁(もんめ)借りて「事すましける」
銀一匁は米二升五合買える程度の金でした。
その燐家では、女房のふだん帯、男のもめん頭巾、蓋なしの小重箱一組、機織の筬(おさ)、五号枡と一号枡二つ、石皿五枚、仏の道具いろいろとりあつめ、二十三色で、「一匁六分借りて年を取りける」
その東どなりには舞舞(まいまい)が住んでいました。門付芸人ですが、元日からは大黒舞に商売替えするので、面と小槌一つあれば、正月中の口過ぎはできます。それまでの商売道具の烏帽子(えぼうし)、ひたたれ、袴は「いらぬ物とて、弐匁七分の質に置て、ゆるりと年を越ける」
そのまたとなりには、小うるさい貧乏浪人が住んでいました。年久しい売食い生活、おもちゃの手内職もいまはすたれ、
「今と云ふ今、小尻(こじり)さしつまて、一夜を越すべき才覚なく、似せ梨地の長刀の鞘をひとつ」女房が質屋へ持ってきました、こんなものが何の役に立つものか、と質屋の亭主が投げ戻すと、浪人の女房、顔色をかえて「人の大事な道具を、何とてなげてそこなひけるぞ」といきりたちます。
「質にいやならば、いやですむ事なり。その上何の役に立たぬとは、爰(ここ)が聞きどころじゃ。それはわれらが親、石田自部少輔乱(じぶのしょうのらん)に、ならびなき手柄を遊ばしたる長刀なれども、男子(なんし)なき故にわたくしに譲り給はり、世に有時の嫁入に、対(つい)の鋏箱の先へ待たせたるに、役にたたぬものとは先祖の耻(はじ)。女にこそ生またれ、命はをしまぬ。相手は亭主」
ととりついてなきわめくので亭主も、閉口頓首(へいこうとんしゅ)、さまざま詫びても聞き入れず、そのうち近所の者があつまって、あの女の連れ合いの浪人は、がらがわるい。ゆすりが得意のうっとうしい男、ききつけて来ぬうちに、程よい所で手を打ちなされと仲に入り、とど、銭三百と黒米三升で、「やうやうにすましける」。女はまだ、こんな米では明日の用には立たぬというので、碓(うす)まで貸して、米を踏ませて帰しました。質屋はふんだりけったりです。西鶴はさらりとあとへ、
「扨(さて)も時世かな、この女もむかしは千二百石取たる人の息女、萬(よろず)を花車(きやしゃ)にて暮らせし身なれ共、今の貧につれて、むりなる事に人をねだるとは、身に覚て口をし。是を見るにも貧にては死なれぬものぞかし」
浪人のとなりに、一人ずみの三十七八ばかりの女、身のたしなみ目だたぬようにして、色香もすこし残っているのがいますが、正月の用意は、
「はや極月(十二月)のはじめに、万事を手廻しよく仕舞ひて、割木も二三月までのたくはへ、肴かけには二番の鰤(ぶり)一本、小鯛五枚、鱈二本、かん箸、紀伊国御器(漆塗りの食器)鍋ぶたまでさらりと新しく仕替え」というソツのなさ。まだ、そればかりではありません。世間づきあいもぬからず、「家主殿へ目ぐろ(塩漬けの魚)一本、娘御に絹緒の子雪駄(こせっだ)、内儀さまへうね足袋一足、七軒の相借屋へ、餅に牛蒡(ごぼう)一抱(わ)づつ添て、礼儀正しくとしを取ける」
西鶴は、あとへするどくつけ加えています。
「人のしらぬ渡世、何をして、内証のことはしらず」
商いをする様子でもなし、何をして生活を立てているのかしら、内輪のことはわからない。お囲いものか、ただしはもっと人に言えない商売か――けれども、この女の、手抜かりない正月支度が、手廻しがよいだけに澄ましている顔が目に見えるようで、おかしみをさそわれます。
「まことに世の中の哀れを見る事、貧家のほとりの子質屋、心弱くてはならぬ事なり。脇から見るさへ悲しき事の数々なる、年の暮れぞはならぬ事なり。脇から見るさへ悲しき事の数々なる、年の暮れにぞ有ける」
と結びながら西鶴は、貧乏人は貧乏人なりの才覚や工面を、大商人のやりくりと同じに扱い、おかしみはみな同じ、西鶴はつれなく鋭い筆致のうちに、あたたかい共感を人間の暮らしに寄せています。
因幡(いなばの)国は雪の新年を迎えました。国庁では舞い散る雪をながめながら、恒例の新年宴会がひらかれます。
国司は、都から下って来た大伴家持。
彼は、宴に招いた国や郡の役人たちに、新年を祝う歌を示しました。
新しき年の始めの初春の今日降る雪のいや重(し)け吉事(よごと)
新しく迎えた年のはじめの今日、初春のめでたきしるしの雪の降るごとく、よいことのますます、積もり重なってくれ。
大伴家持は橘奈良麻呂(たちばなのならまろ)のクーデター計画失敗の事件にまきこまれ、中央政界から遠ざけられて因幡の国に左遷されたのでした。
大伴家持は、神代以来の名門です。
「名に負ふ伴の緒」でありながら、いまは、藤原氏一族に圧迫されて、衰運に向かいつつあります。

天平の御代は、一見華やかに明るく咲き匂っているかにみえながら、その底は、血で血を洗うすさまじい政争と陰謀の世界でした。そこにあるのは、奸計(かんけい)といつわり、のろいのひとがた、たたりの恐怖、暗殺者の横行、密告裏切りの、果てしない繰り返しでした。
人はたがいに猜疑(さいぎ)しあい、にくみ、たくらみ、殺し合い、権力の座を得ようと、しのぎをけずるのです。
高潔な心の詩人、大伴家持には耐えられぬ世界であったかもしれません。
名門の誇りを抱いて、家持は、どうかしていま一度、家運を盛り返したいものと、心を砕いていたのでした。しかし、奈良の都にはすでに、清き、直き、あきらけき心は失われていたのかも知れません。
彼の悲願にもかかわらず、大伴一族は、政変のあるたび、たくみに藤原氏にはかられて、僻地へ追われ、没落してゆきます。
家持は新しい年、因幡の国庁で、この歌を口ずさみ、わが身の上と、一族の運命に思いをはせ、どんな複雑な心境でいたでしょう。
彼は、
うらうらに照れる春日に雲雀(ひばり)あがり情(こころ)悲しもひとりしおもへば
わが屋戸(やど)のいさむらたけ吹く風の音のかそけきこの夕(ゆふべ)かも
のような、心のふるえそのままのなよやかな美しい歌をよむ人であると共に、
剣太刀いよよ磨(と)ぐべしいにしへゆさやけく負ひて来にしその名ぞ
敷島の大和の国にあきらけき名に負ふ伴の緒心つとめよ
と勇ましく歌い上げて一族をさとす武人でもあったのでした。萬葉のますらおごころは彼に、まだ色濃くのこっていたのです。
国庁の庭に降る雪をみながら、また家持は二年前に七十四で死んだ、奈良麻呂の父・橘諸兄(たちばなのもろえ)のことも考えたかもしれません。諸兄一族もまた、藤原氏に圧されて滅んでいった人々です。諸兄がまだ健在で、老女帝・元正(げんしょう)に仕えていたころ、やはり雪の正月に、詔に応じてよんだ歌があります。
降る雪の白髪までに大君に仕えまつれば貴くもあるか
いかにも国家の老臣たるにふさわしい、堂々とした、荘重な、格のたかい歌です。
家持は、諸兄に愛されていました。「萬葉集」もあるいは、諸兄のアイデアによるものだったかもしれません。
しかし、家持は、因幡国庁の新年の歌を最後に、「萬葉集」巻二十を終り、また、彼自身も、それきり永久に歌わぬ歌人となってしまいます。永遠の謎を秘めたまま、「萬葉集」とあの珠玉の歌のかずかずを生んだ時代は終焉します。
デリケートで、美しい感性をもっていた詩人の家持は、あるいは、今後、詩心をしばし忘れて現実の汚濁の世界で生きようと、決意したのではないでしょうか。
家持は「今日降る雪のいやしけ、よごと」と呟き、暗い時代への憤りを胸に秘めつつも、やはり幸せへの期待を抱かずにはいられなかったのかもしれません。
このやさしい童謡を、私はどこかで聞いたことがあるような気がしてなりません。
もしかすると、それは私が生まれるずっと前、むかしむかしの遠い代の子供たちのうたごえが、耳の底に残っているからかもしれません。「徒然草」百八十一段には、鳥羽院がまだ幼くおわしたころ、雪の降る日に歌っていらしたと、讃岐典侍(さぬきのすけ)の日記にある、と書かれています。
私は、讃岐典侍といあう人の日記をよみたいものだと思いました。しかし、私が学んだころの国文科には、そのテキストはありませんでした。「讃岐典侍日記」は、源氏・枕・伊勢・蜻蛉(かげろう)といったきらびやかな星の光にけおれてひっそりと目立たぬ、地味な存在なのでした。
そしてたとえよんでも若い日の私には、この日記のもつ重い悲愁は、理解しがたかったかもしれません。中年になってめぐりあったしあわせ、という本はあるものです。
讃岐典侍は、王朝末期の堀河天皇にお仕えした女官です。堀河帝が二十九歳というお若さでお隠れになったときの、その前後のもようを、悲しみを抑えて彼女はしめやかに、するどく的確に、書きとどめています。

堀河帝は英明な方でしたが、政治の実権はおん父・白河院の手にあり、天皇とは名ばかりの不遇なご日常でした。しかしやさしく優美なお人柄で、和歌にも笛にもご堪能でいられ、人々は心から、若い帝を愛慕していました。讃岐典侍(さぬきのすけ)は帝のめのと子で、年頃も同じほど、八年ものあいだ帝に身近く仕え、その心情は、男と女の愛情に近かったでしょう。日記に現れたそれは、帝王の崩御(ほうぎょ)、というよりも、愛する一人の青年の死をめぐる悲しみと惑乱、という切実な辛さがあふれています。
嘉承二年(一一〇七年)七月、あついさかりでした。帝のご病状あらたまり、宮中は物々しい雰囲気に包まれます。加持祈禱(かじきとう)の読経の声はつなみのごとく、あたりをゆるがします。それを近くききつつ、若い帝は息苦しげに、足をうちかけ、「われわれは今日あす、死なんずる」などと仰せられる。
「きくここち、ただむせかへりて御いらへもせられず‥‥「寝いらせ給へる御顔をまもらへまゐらせて、泣くよりほかのことぞなき。いとかう、何しに馴れつかうまりけんと、くやしくおぼゆ」
どうしてまあ、こんなに親しくお仕え申したのだろう、帝に死におくれ奉るなどと悲しい目を見るくらいなら‥‥と今更のように八年ものあいだ、お傍で楽しく暮らした月日を思い出され、胸ふたがるのでした。なまじ帝の若さは、死の苦しみを増すようで、おん汗もふき出、おん手も腫れたまい、お体のやりばのない苦しみに、彼女のくびにおん手をうちかけ、喘ぎたまうのでした。抱き起せよ、臥せしめよ、との仰せに、彼女たちご看護するものは夢中でお仕えします。
「せめて苦しいおぼゆるに、かくしてこころみん、安まりやする」
と仰せられて、おん枕上の神璽(しんじ)を収めた箱を、お胸の上に置かれたりします。お胸は苦しげに、ゆらぎ、息もたえだえのごようすでした。一睡もせずお看護する彼女の耳に、明けの鐘の音が聞こえます。
ほっとして朝の光が待たれるのでした。御前をさがしって交代でとろとろと休む間もなく、たちまち使いが来て「のぼらせ給―」と呼ばれます。帝にお食事をさしあげてみようというのでした。ひとりがおうしろから支え奉り、小さな台で、ほんの形ばかりおめしうえりになる、ああなんと、お弱りになったことよ、と涙ぐまずにはいられません。
おやさしい帝は、そんなお苦しみの間にも、なぜ寝ないのか、と彼女を心配して仰せられ、また、お看病のために横に添い臥ししていますと、人が来たよと注意されて、彼女の姿をかくすように、おんひざを高くしてかばって下さるのでした。
あわただしく定められるご譲位のこと、御受戒の儀、お最期のときは一刻も早く一刻と近づきます。氷などまいり、おん汗をぬぐううち、
「いみじく苦しくこそなるなれ。われは死なんずるなりけり‥‥大神宮たすけさせ給へ。南無平等大会講明法華」ととなえられ、あまりの悲しさに讃岐典侍らは夢みるここちで「涙もせきあへず」というありさま。
「苦しうたへがたくおぼゆる、いただきおこせ」
と仰せられるのでお抱きしますと、おん腕(かいな)はもう冷やかになっていられます。こんなに暑いさなかなのに‥‥。指を水に濡らしてお口をうるおし、尊い僧正、帝の老いた乳母たち、彼女ら侍女たちは声を惜しまず、あたまから黒い煙が出るまで一心不乱に読経し、お祈りをし、仏におすがりして今は奇蹟を念じるばかり、あなやと思うままに、
「むげにおん目などかはりゆく」
ご臨終とみてとって関白や内大臣は、たちまちおん父の白河院へ使いを出し、帝のおん枕を直し、抱いて臥せしめられます。
「かかるほどに、日、はなはなとさしいでたり、日のたくるままに、御色の日頃よりも白く、はれさせ給へる御顔の清らかにて、御びんのあたりなど、御けづり髪(ぐし)したらむやうに見えて、ただ大殿ごもりたるやうにたがふことなし」
死の業苦(ごうく)からいま解放されて、仏のみもとへおもむかれた帝は、安らかにお美しく、まるで、おやすみになっていらっしゃるようでした。声をかぎりに泣き叫ぶ帝の老いた乳母たち、一緒に御召し下さいませ、とみな、変わり果てたお姿にとりすかせって泣きました。
讃岐典侍は、悲しい宮中を退出しましたが思いがけぬことに、新帝。鳥羽帝に、またお仕えすることになりました。
雪のふる朝でした。何につれても、先帝がまだおわしますような気がされて、ぼんやりしている彼女の耳に、
「ふれふれ こゆき
たンまれ こゆき
垣や木のまたに」
とあどけない幼い子のうた声がきこえてきました。おや、どこの子か、とつい思い、おおほんに、あれは帝でいらせられるかと、あわれ深い心地がされました。おん父堀河帝に五つで死に別れられた幼帝は、おん母君とも生まれてすぐ死別されており、幸うすいお身の上のいじらしさでした。はじめてお食事のお給仕にま近くお仕えしますと、走っていらしてお顔をさしのぞかれ、〈この人は誰なの〉と仰せられます。堀川院のおん乳母子(めのとご)ですよ、とそばの人が申しますと、そうかと納得されるようす、昔、おん父みかどのもとにまいられたとき、堀川院がお可愛(かわ)ゆくおぼし召されたときのことなど思い出されて讃岐典侍(さぬきのすけ)は切なくなるのでした。
幼ないみかどのもとにまいられたとは、夜おやすみになるお姿もお小さくいじらしく、お食事をまちかねて召し上がるのもおかわゆく、彼女は、ま心こめてお仕えしているうちに諒闇(りょうあん)も終り、世の中は花の衣になりました。
新帝も内裏(だいり)にお渡りになります。夜の御殿(おとど)のありさま、滝口(たきぐち)の名対面(なだいめん)、左近(さこん)の陣の夜行、みな、先帝おわしましし頃と同じでした。内裏がお珍しい幼帝は、彼女に案内させてそちこちお渡りになります。台盤所、混明地、御障子、みななつかしく、彼女は昔の知人にあう心地がして、でも、先帝だけはこの世にもうおわしまさぬのです。
幼帝をお抱きして、障子の絵をお見せしていると、夜の御殿の壁に、先帝が、あけくれ目なれて覚えようと思し召されてはりつけておかれた笛の楽譜が、まだそのままにありました。つい涙ぐまれて袖を顔におしあてていますと、どうしたの、とたずねられます。あくびが出まして、つい、と申し上げますと、知っているよ、とさかしく仰せられ、〈なにをごぞんじでいらせられますか?〉〈うん。ほの字、りの字のことを思い出していたんだね〉ほりかわ‥‥お父さまのことでしょう?‥‥とのたまうおかわいらしさ、
「あはれにさめぬるここちしてぞ、笑(ゑ)まるる」
ふと心がさわやかに晴れて、ほほえまれるのでした。
死別のくるしみ、という人生最大の苦しみを経てきた彼女の、そのときの微笑は、やさしく明るいものだったにちがいありません。
「讃岐典侍日記」は、辛く切なく、そしてやさしい物語なのです。
つづく 失われた夢
もと建礼門院(けんれいもんいん)に仕えた、右京太夫とよばれていた彼女もその一人でした。彼女の恋人、平資盛(すけもり)も、海に沈んだのです。
右京太夫は、教養ゆたかな父母の才能をうけついで、歌にも音楽の道もたけた、わかい美しい女でした。
はじめて高倉帝の中宮・建礼門院徳子の宮廷に出仕したのは十六七のころ。わかい帝と中宮を中に、世は平家のおごりの春、全盛時代でした。ときめく平家の公達や殿上人(でんじょうびと)があまたある中で、彼女は、ひとつづきです。二つ年下の資盛と恋におちました。――華やかな、宮廷ぐらしをしていても、浮ついたことはするまいと、かたく思いきめていたのに‥‥。
「おもひのほかに物思はしきことそひて、さまざま思ひみだれしころ」と、彼女はのちに、自分の歌日記「建礼門院右京太夫集」に書いています。
資盛は重盛の次男、入道相国清盛の孫になります。正妻もいる身で人目をはばからねばならぬ、物思わしい恋でしたが、彼女にも資盛にも、いちずな、真剣な恋でした。
しかし世はただらぬさわぎにまきこまれていました。高倉帝の崩御、清盛の死去をさかいに、栄華を誇った平家は、音を立てて没落していきます。
ついに寿永二年七月、平家は、幼帝・安徳天皇を奉じて都を落ちます。「寿永元暦などのころ世のさわぎは、夢ともまぼろしとも、あはれとも、なにとも、すべてすべていふべき際(きは)にもなかりしかば、よろづかいかなりしとだにおもひわかれず、中々おもひも出(い)でじとのぞみ今までもおぼゆる」
宮仕えもやめ、家に引きこもっている彼女を置いて、親しかった人々は都を落ちてゆきました。その惑乱と悲しみは、今思い出すのも辛いほどだ、と彼女は書いています。
あんなに華やかに時めいた平家の一門の人々が一転してこんな運命になろうとは‥‥。

世の人はみな、夢かうつつかと、惑いました。
今日も明日も、都を捨ててゆく人々‥‥。あの人も、この人も。
恋人の資盛も例外ではありませんでした。彼はこのとき、二十四歳、蔵人頭(くろうどのとう)という要職にあって公務が忙しい上に、世の騒がしさもあり、つねによりも人目をしのんで、あわただしく彼女と別れを惜しみました。資盛は沈痛に申しました。
〈もう生きては都へもどれないだろう。これから先は、便りもしない。だが、決してあなたをおろそかに思ってのこととは考えないでくれ。自分でそう気強く思い切らないと、未練が残って辛いのだ。死んだと聞かれたら、せめて菩提(ぼだい)を弔ってください〉
彼はさすが、嫡々の平家の大将、男らしくそう言いすてて、別れてゆきました。
それが今生の別れになりました。
平家があそこで討たれた、ここへ落ちた、と聞くたびに、右京太夫の胸は不安とかなしみに張り裂けます。
「夜明け、日の暮れ、なに事を見きくにも、かたとき思ひたゆむ事は、いかにしてか、あらむ」
どうかしてせめてもう一目、と思うこころが通じたのか、ある夜彼女は、恋人がいつもと同じ姿で、何かもの思わし気に沈んだようすでいる夢を見ました‥‥あたりには、風がひどく吹いていました。目がさめ、彼女はしばらく、胸騒ぎが静まりませんでした。もしや、あのひとの身に変事でも‥‥。それとも、ただ今の今、あのひとは、夢の通りの姿で、どこかの空で物思いに沈んでいるのかしら…‥。
なみ風のあらき騒ぎにただよひてさこそはやすき空なかるらめ
「おそろしき武士(もののふ)ども、いくらもくだる」
平家を討つ源氏の武者たちが、たくさん西へ下ります。平家敗戦の悲報は次々ともたらされました。あるいは生け捕りになった人、‥‥ついに恐れていた時がきました。寿永四年春、平家一門は、壇ノ浦に沈んだというのです。
資盛は、弟の有盛、いとこの行盛らと共に手をとって海へ入ったとききました。二十六歳の花のいのち――覚悟はしてたけれど、右京太夫は呆然として、涙さえ出ないほどでした、長いこと泣きくらし、どうかして忘れたいと思いつつ、「あやにくにおもかげは身にそひ、言(こと)の葉(は)ごとにきく心地して」悲しみは言いようもありませんでした。
資盛は、死んだと聞いたら菩提を弔ってほしいといい遺してゆきました。けれど世は平家ゆかりということさえ、憚らねばならぬ有様でした。右京太夫は悲しみに暮れる心を励まして、ひそかに志ばかりの弔いをします。彼からの古い恋文を料紙に漉(す)き直させてお経を写し、また仏のお姿を手ずからかきとどめて、尊い聖にお供養をたのんだりしました。
その紙に、なお恋人の手蹟(しゅせき)が残るのも、目もくれ魂も消える悲しさでした。長い年月に、たまり、たまったおびただしい恋文。そのとき、かのおり、あのひとはこう誓い、ああも契った、そのうれしい思いの名残りの文がらを、いま漉きかえして、尊勝陀羅尼(そんしょうだらに)、かなしいお経の文字を書こうとは。
かなしさのいとどもよほす水ぐきのあとはなかなか消えねとぞ思ふ
かばかりの思ひにたへてつれもなくなほながらふる玉の緒も憂し
平家の人々の哀れな最期も、いくつも聞きました。ことにおいたわしいのは女院――海に沈まれたのを引き上げられ、心ならずも生き長らえてご落飾、大原の里にお住まいになっていられるのを彼女はたずねます。昔の雲居(くもい)の奥ふかく華やいでおわしたお姿を知る身には、山道のけしき、御(おん)いおりの粗末なたたずまい、「夢うつつともいふかたなし」
そのかみは六十人あまりの上臈(じょうろう)女房たちにかいずかれておわしたのに、いまはお仕えする尼三四人ばかり、その人々も、いずれが誰であったか見分けられぬほど、やつれ果てているのでした。
「花のにほひ、月の光」にたぐえられた美貌の女院も、いとし子を西海に失いたまい、はらからや親に後(おく)れられた悲痛な運命に、別人のごとく面がわりしていられます。右京太夫の真心こめたおなぐさめに女院も共に新しい涙をもようされたことでしょう。
今や夢昔やゆめとまよはれていかに思へどうつっとぞなき
生きて甲斐ない命と思いつつ生きながらえてしまいました。来る年も来る年も、思い出はいよいよ鮮やかに、悲しみは深くなるばかりでした。そのうち、思いもかけぬことでしたが、たって人にすすめられて、再び宮仕えすることになりました。
世は後鳥羽上皇の御代(みよ)になっていました。昔は身分の低かった殿上人のだれかれが、今では押しも押されもせぬ上達部(かんだちめ)になっているのを見つけても、資盛が生きていたら、ああもあったろう、こうもあったろうと思われるのでした。新帝。後鳥羽天皇が、昔お仕えした、おん父みかど高倉帝によく似ておわすいのも感慨ふかいものがありました。
公の古い書類に、かの「さめやらぬ夢とおもふ人」、資盛の署名が、蔵人頭としてとどめられてあるのも、彼女を悲しませるものでした。そうして彼女は老いました。
水の泡と消えにし人の名ばかりをさがすがにとめてきくも悲しき
老いてのち、藤原定家が、新勅撰集の歌を選び集めるために、彼女のもとへ、「書きおいたものがありますか」と訪ねてくれました。そして、その折、「どちらの名にしようと思われますか」と聞かれたのも、うれしい思いやりでした。晴れの勅撰集に入れられるときの、彼女のよび名を、その昔、建礼門院にお仕えしていたときの名が、のちに後鳥羽院にお仕えしてからの名か、どちらを取りましょうかというのです。
「なをただ、へだててしまいました。はてにし昔のことの、わすれがたければ『その世のままに』など申すとて、言の葉のもし世にちらば忍ばしき昔の名こそとめまほしけれ」
そのとき、右京太夫は七十六歳でした。のちになって二十年も仕えた後鳥羽院時代のよび名より、若かりし日に、ほんの五六年呼ばれた、建礼門院右京太夫という名のほうを彼女は望んだのです。—-そして、その名は歌集に、いまもとどめられことになりました。
この右京太夫の悲しみは、先頃の戦争で愛する者を失った何十万の女たちにそのままかよいます。いま、彼女たちはその思い出を抱いてつつましく老いてゆきつつあります。
第二次大戦に出征した若者たちも、さながら資盛のように、故郷の恋人や妻にあてて、ひそかな便りを托し、万感の思いをこめて死地に赴いたのでした。
「昨夜、月光をあびて静かに眠りにはいらんとする東京を離れた。…‥今日の君の胸中を思うて、心中ひそかに哭(こく)し、君健在なれと熱き祈りをおくる。今は君の手でしるされる日記の文まで想像できるような気がする。
君、健在ならんことを。(とも子に)」
(宮崎竜夫、東大理学部人類学科学生。昭和二十年七月二十日マニラ東方四十キロの地にて戦病死。二十六歳)
「昭和十七年師走。戦況日々に激しい南の戦線に出ることとなる。‥‥目をつぶってみる。頭に浮かぶものは愛らしい子供、妻、父、母、妹等々。門出の前夜『私を未亡人にしてはいや』と言ったきみの顔が、目が、忘れられない。…‥きみの顔が浮かぶ。情熱的に黒目がちの目、きりっとした中にも愛くるしいまで引き締まった口、ふくよかな胸のあたり、きみのまぼろしが浮かんで消えない。
ああ! めめしい気持を去らねばならぬ。
後願の憂いさらになし。身体の調子も至極順調、一意待機任務の任を終え、命に依り、椰子茂る方面にでることになったこと、全く男子の本懐、御召しとあらば皇軍の一人として誓って恥じざる覚悟にいる。苦しい覚悟に。
すべて時の流れに、運命に委(まか)せ征く」
(篠崎二郎、同志社大学文学部英文科卒業。昭和十九年一月東部ニューギニアにて戦死。三十四歳)
(『きけわだつみのこえ――日本戦没学生の手記』光文社刊、より)
のこされた女たちの悲愁は、右京太夫のように、生涯消えることはありますまい。冷めやらぬ夢を抱いて老いるのが、女のロマンなのでしょうか。
幾山河
幾山河越えさり行かば寂しさのはてなむ国ぞ今日も旅ゆくこの、若山牧水の歌に、心をしびれさせなかった昔の女学生がいたでしょうか。この歌は、秋の匂いをさながらももたらすような歌でした。少女の私には、秋は、この歌と共に訪れました。
若者の心に、ぽとりとしずくをおとして、その水滴がやわらかい紙ににじむように、心をぬらしてゆく歌でした。
牧水は、昭和三年に亡くなった歌人ですが、もう古典の中に入れてもよいように思われます。そのしらべの美しさ、純粋さ。そのくせ、芯に強い線が男っぽく通っていて、いかにもゆったりと、おおらかな味わいのする歌です。
今読んでみても、その新鮮さはちっとも失せていません。そして、牧水の歌を、一つと夢中でおぼえていたころの思い出も、もろともに、レモンのように匂い立ちます。
いざ行かむ行きてまだ見ぬ山を見むこのさびしさに君は耐ふるや
少女の私には、ほんとの人生のさびしさはまだわかりませんでした。戦争中の日本には「旅ゆく」という、おおらかな情感は想像もできませんでした。それだけになお私は、見知らぬ国への旅、さびしさの果ての磯山河をあこがれたのです。
吾木香(われもかう)すすきかるかや秋くさの
さびしききはみ

この歌を覚えたのは林芙美子さんの小説だったと思います。軍隊に入った夫から、女主人公の妻にあてた手紙に、この歌が書きつけてあったのです。私は、われもこうという草をみたいと思って、熱心に調べたことを憶えています。
白鳥はかなしからずや空の青海のあをにも染まずただよふ
多摩川の砂にたんぽぽ咲くころはわれにもおもふひとのあれかし
こういう歌を少女時代によむと、一つの歌だけで、一時間も、ぼんやり、いろいろ考えごとができるのでした。「白鳥は‥‥」の歌など、すぐれたふかい交響楽を聞いた後のように、いつまでも余韻がのこって、体のうちの小さな鐘はひびき交と、鳴りどよもし、やわらかな心の中に消えることなく、この歌が彫りつけられてゆくのでした。
牧水の恋歌には、抽象された格調高さがあります。あたらしい古典美、というような。
山を見よ山には日は照る海を見よ海に日は照るいざ唇(くち)を君
ともすれが君口無しになりたまふ海な眺めそ海にとられむ
君かりにかのわだつみに思はれて言ひょられなばいかにしたまふ
これらの恋歌は、どれだけたくさんの若者の、日記や恋文の端に書きつけられてきたことでしょう。
牧水の歌は、そこに特徴がありました。若者たちは、牧水の歌を、自分の歌のように思いなして使うのでした。どんな若者の、どんな恋にも、牧水の歌はぴったり、はまってくれました。引用する、というものではなく、若者たちが自分で作るべかりし歌、そのものが、牧水の歌でした。
かたはらに秋ぐさの花かたるらくほろびしものはなつかしきかな
古い村、古いまちを通るとき、また、人生中年に達した人が来しかたをふりかえりみるとき、私たちは自分の作りたかった歌を、牧水の歌のなからみいだしたりします。もう牧水が歌ってくれた以上、私たちはそれを口ずさむだけでよいのです。私が彼の歌を古典という所以です。牧水は、酒を愛した人でしたから、ちゃんと、こういう歌も、作ってくれました。
白玉の歯にしみとほる秋の夜の酒はしづかに飲むべかりけり
忍ぶ恋
この式子(しきし)内親王のお歌は、百人一首でも人々にしたしまれていますが、何という流麗で、しかも哀婉(あいえん)切々たるしらべでしょう。
わがいのち、絶えるならいっそ絶えるがよい。生きのびていれば、この恋の苦しみに堪える力が弱ってしまおうものを。
内親王の恋のうたは、このほかにも、みな忍ぶ恋の歌ばかりです。
はかなしや枕さだめぬうたたねにほのかにかよふ夢の通ひ路
わが恋は知る人もなしせく床の涙もらすな黄楊(つげ)の小枕
内親王より百五十年ほど前の和泉式部(いずみしきぶ)は、奔放で真剣な、恋の凱歌(がいか)ともいうべき歌を高らかに歌いあげました。しかし内親王のお歌は、あくまでも抑えつけられた声にもならぬつぶやき、鬱屈(うつくつ)してむいぼれた女の重い恋のしたたりなのです。
それは、後白河帝の皇女、というご身分がらもあり、また、内親王の生きられた時代にもよりましょう。源平が血みどろの争闘を重ねていた乱世、かの、平家の打倒のさきがけとなって戦死された以仁王(もちひとおう)は、内親王の兄宮に当てられるのです。
内親王はまだほんの童女のころに、賀茂(かも)の齋院(さいいん)となられ、神に仕える清い生活を十一年ばかり送られました。齋院を辞された時はまだ二十歳前の姫宮だったと思われます。
多感な乙女のころに、内親王は動乱時代のしぶきを真っ向から浴びられました。和泉式部の生きた時代のように、官能の恋を心ゆくまで歌える開放的なよみぶりは、この時代には失われていたのです。

それに、多くは題詠――題を与えられての創作であってみれば、恋の歌といってもプロフェッショナルなテクニックによるものが多いのです。しかし、内親王のお歌には、じつにさまざまな角度から「忍ぶ恋」を擬視する、おん眼が感じられます。
思ふより見しより胸にたく恋のけふうちつけに燃ゆるとや知る
君をまづ見ず知らざりし古(いにし)への恋しきをさへ欺きつるかな
竹西寛子さんは、すぐれた式子内親王論をものされていますが、内親王に、平家の貴公子の恋人があったのではないかという想像を楽しんでいられます。
実は私もまた、そういう想像で、内親王のお歌をよむ一人なのです。平家の公達(きんたち)でなくても、心ひとつにおさめて決して明かされぬ、秘めた恋人がおありだったのではないか。もちろん、ゆたかな天分と、ふかい古典的教養を備えられた内親王には、想像だけで、修辞の技巧に支えられた恋のうたをよまれることは容易だったでしょう。
しかし、お歌には、それをつきぬけた、ある陰火が、燃えも上らず、消えもやらず、陰々滅々とくすぶりつづけています。
けし粒ほどの恋の火種を、内親王は一生お心のうちにじっと守り育てて来られた。美しく怜悧(れいり)に、才ゆたかな内親王のお心を捉えた人は、どんな人だったのでしょうか。それは決して、世に明かせない、文を交わすことも、思いをうちあけることもできない人だったのではないでしょうか。
知る人もいない恋をじっと心に抱いて、三十となり四十となり、内親王は年を重ねて来られたのではないでしょうか。忍ぶ恋が色を深め、思いを増してゆくにつれて、お歌もいよいよ傷ましく深まってゆきました。
和泉式部は、あまたの恋と情人たちとを経て、ついにひとつの真理の世界にあこがれ、「くらきよりくらき道にぞ入りぬべきはるかに照らせ山の端の月」とうたいました。
内親王はただ一つの、秘めたる恋、忍ぶ恋、明かさぬ恋をふかくきわめて、やがて、さめやらぬ煩悩に苦しむわが身、人の世を眺める眼を育てられました。
しづかなる暁ごとに見渡せばまだ深き夜の夢ぞかなしき
契る恋と忍ぶ恋,激情と鎮静の相反するふたりの女流は、期せずしておなじ境地に到達したといえるのではないでしょうか。
浮世風呂
私が何となくゆううつなときなど、ふと、とり出して読みたくなる本は、式亭三馬(しきていさんば)の、「浮世風呂」「浮世床」という、こっけい本です。たいへん面白くて、読んでいるうちに、笑えてきます。
三馬は、江戸末期、一八〇〇年代のはじめに活躍した、大衆小説作家で、「浮世風呂」「浮世床」は彼の代表作です。これらは、ずいぶん、その当時の人々に愛されたものでした。
三馬は戯作の筆もとりましたが、一面、手堅い実業家でもありました。薬商を営んで化粧水などを製造し、それを自作の小説の中にも宣伝するといった、ジャーナリスティックな才能にも恵まれ、お金もうけも、決して下手ではありませんでした。
そんな三馬が書いた小説は、だから卑俗ですが、説得力があります。写実的で現実の重みがあります。
「浮世風呂」は銭湯に集まる江戸庶民の会話、「浮世床」は、床屋に集まる人々のそれを書きとめて、さながら、江戸時代のテープレコーダーを回して聞くようです。
その会話のおもしろいこと、さながら息遣いから口吻まで想像できるおかしさは、十返舎一九(じっぺんしやいっく)らのこっけい本の、作為的なおかしみと、全然、別のものです。
筋はなくて、さまざまな身分、生活環境、性格の人々を、会話でかきわけてあるだけですが、おのずから、そこに三馬の見識というか、社会を見る目の皮肉さというか、そんなものが浮き上がってくるも、たのしいところです。

「浮世風呂」三篇、「春は曙、やうやう白くなりゆく洗粉に、旧年(ふるとし)の顔を洗ふ初湯の烟(けむり)、細くたなびきたる女湯の有様、いかで見ん物をとて、松の内早仕舞ちふ札かけたる格子の下に佇(たたず)み、障子のひまよりかいま見るに、その様をかしくもあり、又、おのが身のぶざめいたるは、あさましくもありけり」女湯の中の会話を、そ――っと盗み聞きしてみましょう。
ト書に「髪の毛のうすき女房、二人にて流し合てゐる」とあります。
お川「コウコウお山さん、お前の隣ぢぁァ、夕(ゆふべ)も夫婦喧嘩があったの、久しいものさ。なぜああだらろ」
お山「思ふ中の小いさかひやらさ。どっちをどうとも云へねへはな」
お川「両方が悪いといふ内にも、商売上りの者は、癖として、やきもち深いから、夫婦喧嘩が絶えねへのさ。男のひひきをするぢゃァねへが、総体(そうてい)男といふものは、表をつとめるもんだから、ちっとづつの付き合いもありうちだァな。そこを女房も心得して居ねへぢゃァならねへ。目が明かずに悪くやかましくばかり云って見ねへな。それこそ、なほ逆らって出かけるはな。さうかと云って黙ってばかり居てもますまず、諸事、塩梅物だによ。
しかしまた、おらがかかァだの、おらが山の神だのと云って、かみさんを怖がる亭主も世間体の悪いものさ。なんぞの話ついでには、てんぐ―の女房をほめちぎるもきざな奴さ。さうかととって、むごく当たるばかりを能にして、ひどいめにあはせる亭主も、つらのにくいものなり、何でも気の合った夫婦が互の仕合せ、長い月日にゃァ、好いことばかもねへもんだから、両方で不肖しやふのさ‥‥」
このお川さんのとなりには、新婚の夫婦が住んでいるとみえ、岡焼き半分で、こきおろします。
お川「屋敷から下りたてのおかみさんに、もちたての女房だって、間がなすきがな、お縁(えん)さんのそばへよって、のろけた顔を見なナ」
お山「まだお前ひい乀たもれだものを。花嫁の間が花さ。おっつけ子小児(ここども)でもできてみな。あヽはいかねへ」
お川「ヘン、穴嫁があきれるよ。ヤレ香をかぐのお茶をくらふのと、大笠原か釆女原(うねめはら)かのお諸礼を仕候とって、風見の鳥を見るやうに、高く止まってすまァしているのも小癪(こしゃく)に障らァ」
お山「さうさ。花を活けるの琴を弾くのと、世帯もちのいらねへ事さ。飯を焚いて着物を縫って、内外の者の身じたくをして、物にすたりの出ねへやうにすりゃァ、女房の役は沢山だはな。それで気に入らざァ先さまのご無理だ」
三馬の会話の面白さは、ほんとうは落語の口述のような部分がよくわかるのですが、ここへ引用したのは、ある意味で感慨があったからです。
お川さんのいう夫婦論・男女論は、いまの世の婦人雑誌、女性週刊誌の説く夫婦論。男女論と、本質的には変わっていません。
百七十年昔の夫婦論から、まだ変化していないというのは、これは、男と女の本質論なのではないでしょうか。
そういうことをいえる三馬というひとは、卑俗に平明に書きながら、本当は、すごく世の中のことを知りぬいていたのではないかと思われます。ふかく物を見ていたのでしょう。
世間のこと、人の心、人の性格などに、どん欲な好奇心と愛情をもち、それを、しかし粉飾しないで、素朴そのままのように投げ出しました。三馬は人間の肉声が好きでした。ナマの生活が好きでした。それを面白がる自分の心のままに、筆が宙をはしって、出来上がったのが、「浮世風呂」「浮世床」なのでした。
ひとつ松
私は日本の木の中では、殊に松が好きです。りっぱな姿の松ほど、威あって美しいものはありません。松は日本の誇りともいうべき木です。
でも近年、美しい松を見ることは珍しくなりました。松は大気汚染に弱い木らしく、それに害虫の繫殖がひどくて、松の立ち枯れ病が全国的に蔓延しています。
あちこち旅をして、まるで紅葉しているのかと思われるような、赤茶けた枯れた松を見るほど悲しいことはありません。私は、枯れた松、色がわりして気息えんえん、といった松を見るたびに、ほとんど肉体的な苦痛さえ感じます。そしてこのごろの、山野にはびこる、芋の葉に似たツタカズラのような雑草も、高い松の梢にまで巻きつき、山肌を覆い隠しています。美しい日本の山野は、まさに荒廃寸前と叫びたい気持ちです。悲しいことです。
松をよんだ歌は「万葉集」の昔から、かず限りなくあり、歌人たちは、その葉の、冬の色かえぬめでたさや、松を待つにかける言葉のたのしさを、飽かずに歌に詠み込むのでした。
その中で、私が最も愛する松の歌、そして、最もすぐれていると信じる歌は、「万葉集」巻六の、市原王(いちはらのおおきみ)の作です。
一つ松幾余か経ぬる吹く風のおとの清きは年深みかも
なだらかで品あり、格調たかいすぐれた歌、まさに、男のひとの歌、という気のする、気概のある歌です。
この丘の、ひともとの松は、そも、幾代を経ているのか。颯々(さつさつ)と風が枝を鳴らして渡ってゆく。その松籟(しょうらい)の音がさやかに清く澄んでいるのは、長い年月を経ているためか。
作者の市原王という人は、天平の頃、東大寺の造営長官をつとめた王族ですが、代々、歌才にめぐまれた一家です。それでひとつ松の歌も、筋目ただしい秀歌、という感じがします。早春、活道(いくぢ)の岡にのぼって、ひと本の松の下に集うて、宴をしたときの歌、という詞書があります。
この歌を口ずさむと、亭々とそびえる松の巨木が目に浮かびます。がっしりと揺るがぬ幹、ふかい緑の、いきいきと、先端のするどい葉、見上げると、頂きは、気の遠くなるような高さ。その梢ごしに、はるかに遠い蒼穹(そうきゅう)――ごつごつとたくましい枝は、巨人の腕のごとく張って、たがいにさしかわし、誇りたかく幾代の風雪に堪えてきたのです。
詩人・市原王の心に、その巨(おお)きな、ひともと松は、ふかい畏敬と愛慕の念をよびおこしました。
「おお! 何という美しい木だ」
彼はその感に打たれて、叫んだことでしょう。
幹に耳をあてると、古代の風の音が聞こえるかもしれません。そんな、木なのです。
日本の木は、魂をもっています。立派な、古い木には神霊が宿ると信じられています。
私は西洋の古いまちで、巨木が町中にうっそうと茂り、その下を車が走り、人々が生活しているうらやましく思いましたが、もともと、日本と木と、西洋の木は、木と人とのかかわり方において違うような気がします。西洋の木は人馴れした木、人に愛される木、人をいこわせ、庇う木なのです。
でも日本の木は、ことに巨きな木は、人里はなれたところにあって、人に畏敬される木なのでした。精霊や神気が梢に宿っています。
木は瞑目(めいもく)したまま、深い悲しみにみちて、
〈お前は何をしてきたか‥‥〉
と人々に問います。神のような声でした。
人は、木の声に向かって頭をたれ、静かに越しかたをふり返らずにはいられませんでした。そんな木は、松こそ、ふさわしいのです。
あの枝ぶり、深い海のような葉の色。静かに口の中で、口ずさんで下さい。「ひとつ松 幾代か経ぬる 吹く風の おとの清きは 年深みかも」――ああ、清らかな松風の音が、潮ざいのように、耳に聞こえてくるはずです。
知盛(とももり)最期
元暦二年(一一八五年)三月二十四日。卯の刻(午前六時)に戦いははじまりました。
名にしおう激流の瀬戸。「門司・赤間・壇ノ浦はたぎッておつる潮なれば」源氏の船は潮に向かっておしおとされ、平家の船は潮に乗ってすすみ、源氏死力をつくしての戦いは、はじめ、平家に有利と見えました。
しかし午後になって潮の流れは変わり、その上、平家を見限って源氏につく船が出て来て、にわかに平家の旗和泉式部若山牧水色が悪くなりました。
平家の総大将は新中納言、知盛。平家随一の猛将です。私はこの男が好きなのです。
三十四歳の男盛り、この人を措(お)いて、平家の侍大将はないというような、勇ましいもののふでした。「平家物語」は、知盛の最期を美しく描き切っています。
知盛は決死の覚悟をきめていました。彼は今まであらん限りの力で平家の頽勢(たいせい)を支えてきたのです。今日が最後の決戦と知っています。
彼は舟の屋形に立って大音声(だいおんじょう)で武士たちに下知します。
「戦は今日ぞ限り、者ども、少しも退く心あるべからず。天竺・震旦(しんたん)にも日本我朝(にっぽんわがちょう)にも並びなき名将勇士といへども、運命つきぬれば力及ばす、されども名こそ惜しけれ。東国のもの共に弱気見ゆな。いつのために命を惜しむべき、是のみぞ思ふこと」
彼はすでに一の谷の合戦で、息子の智章(ともあき)を死なせています。まだほんの少年の息子は、彼をかばおうとして敵に討たれたのでした。その傷みを知盛は癒すすべもありません。最後の決戦に死力をつくして戦うこと、それしかないのです。
しかし源氏の船は、勢いするどく責め立て矢をいかけ、平家方はしだいに浮足立ちました。
「源平の国あらそひ、今日を限りとぞ見えたりける」源氏の兵たちは、平家の船にどんどん乗り移ってきます。源氏もまた東国そだちの荒えびす。命おしまぬ猛々しい侍たちです。平家方の水手舵取り、「射殺され、斬り殺されて、船を直すに及ばず、舟底に倒れ伏しにけり」
知盛は、形勢を見て、安徳幼帝のおわす御座船に小舟を漕ぎ寄せていきました。
「世の中、今はかうに見えて候。見ぐるしからん物どもみな海へ入れさせ給へ」

今はこれまでです。見苦しいものはみな海へ捨てなさい、と女たちにさしずして、みずからそのあたりを清めるのでした。女房たちは口々に、中納言さま、いくさはどんな様子でございますか、と聞きますと、
「めづらしきあづま男をこそ、御らんぜられ候(さうら)はんずらめ」
珍しい東国男をごらんになれるでしょう、と知盛はからからと笑うのでした。なんでこんな時にご冗談を‥‥と彼女たちは泣き声をたてて叫びます。
知盛は、こんなときこそ、冗談がいえるのでした。精神は死力をつくして戦ったあとの爽やかさに澄んでいます。
清盛の妻二位(にい)の尼君も、かねての覚悟通り、女なりとも敵の手にかかるまじと、安徳帝を抱き奉って、船端へ歩みよります。
主上ことしは八歳、「おんかたちうつくしく、あたりもてり輝くばかりなり。御髪(おんぐし)黒うゆらゆらとして、御背中すぎさせ給へり」ふしぎそうに、私をどこへつれていくの、と仰せられます。尼君は涙を抑え、幼帝の小さく美しいおん手をお合せ申して、
「浪のしたにも都のさぶらうぞ」
となぐさめ奉って、千尋(ちひろ)の海に身を投じられました。つづく建礼門院、あまたの女房たち、波の上には花を散らしたような、阿鼻叫喚のさまだったことでしょう。
平家の公達(きん)も、次々といさぎよく船から身を沈めました。平中納言教盛、修理太夫経盛(しゅうりのだいぶつねもり)、鎧の上に錨を負い、手を組んで海に入れます。
資盛、行盛、有盛らも共に「手に手をとりくんで一所に沈み給ひけり」
この中にも、総大将宗盛・清宗父子は、入水する勇気もなく、みかねて人々が海へ突き落としましたが、泳ぎが出来る上に、鎧も身にまとわず、死ぬに死ねないでいるところを源氏軍に、生け捕りせられました。
それをよそめに、華々しい武者ぶりは、知盛につづく勇将と謳われた能登守教経(のとのかみのりつね)でした。
今日を最後と、矢だねのあるほど射つくして、白柄の大長刀で薙ぎまわします。その奮闘ぶりを、知盛は余裕をもってながめつつ、使者をたてて「能登どの、いたう罪なつくり給ひそ。さりとてよき敵か」
といわせます。とるに足らぬ雑兵など討って、そう罪つくりをしなさるな、と声をかける知盛に、闊達(かつたつ)な男らしさがうかがわれます。教経は聞こえる暴れん坊若様です。〈さては大将軍に組めということか〉と刀の柄を短く持って、源氏の船にとびうつり、のりうつり、白兵戦を挑みます。めざすは九朗半官、源氏の総大将の首、しかし半官は身軽く舟を飛んで危ういところを脱し、いまはこれまでと教経は、舟につったって大音声で、われと思わん者はこの教経を生け捕りにして鎌倉へ曳け、頼朝と会うて、ひとことものいうぞ、と「おそろしなンどもをろかなり」というすさまじさ。
太刀自慢の源氏方の侍が三人、どうと教経にうちかかります。教経、一人を海に蹴り入れ、二人を両脇にかいばさんで「いざうれ、さらばおれら死途の山のともせよ」と、海へざぶんと入りました。
知盛は静かに、つぶやきます。
「見るべきほどのことは見つ」
ああ見た。滅び栄える人の世のありさま、運命の転変のおもしろさ、おもしろうてやがてあわれなさまざまを見とどけた。
平家の柱石だった清盛の死につづく一門の凋落(ちょうらく)、壇ノ浦の決戦、幼帝の最期、親しい友や肉親の死にざまを、すでに目にした、おお、女院が御髪(おんぐし)を熊手にかけて引き上げられ給うそうな。あわれ長らうべくもあらぬ命をとどめられ給うた。あれ、あそこの船へ、宗盛父子が生け捕られて救い上げられる。それもこれも、人の力の及ばぬ運命かもしれない。宗盛らしい運命かもしれぬ。それもよし。
知盛は、めのと子の家長(いえなが)をよんで、約束だぞ、共に死のう、といいます。家長、「子細にや及び候」(申すまでもございません)たがいに鎧二領を着、手を取り合って海に入りました。名を惜しむもののふたち二十余人、おくれじと手に手を取って、一所に沈みました。「平家物語」の、このあとの文章は、わけてぬきんでた名文です。
「海上には赤旗・赤じるし投げ捨て、かなぐりすてたりしなければ、竜田川の紅葉ばを嵐の吹き散らしたるがごとし。汀(みぎは)によする白浪もうす紅(ぐれなる)にぞなりにける。主(ぬし)もなきむなしき船は、汐(しほ)にひかれ風にしたがッて、いづくをさすともなくゆられてゆくこそ悲しけれ」
敗け戦の海上にただようかなしみを簡潔に叙(しる)しています。
「見るべきほどのことは見つ」――知盛は死にのぞんで、ゆくりなく、宇宙の大きな意志をかいまみたでしょうか。死も生も一如、知盛はほほえんで死んだにちがいありません。
いま、関門海峡には大きな橋が架かりました。八百年の昔、この下の海で「見るべきほどのことは見つ」とつぶやいた人の思いを秘めて、潮はとどろと渦巻いています。
雪ちるや
雪ちるやおどけも言へぬ信濃(しなの)空冬は、小林一茶の句の思い出されるときです。
私のように暖国の関西に生まれた人間には想像もつかぬ、雪の下の人々の感情が、一茶の句には暗く烈しく渦巻いています。
一茶は、雪を風流なものと、賞で興じるのは、雲の上人のことだと嘲笑うのでした。
一茶のいう、「下々(げげ)の下国の信濃」では、
「木の葉はら乀と峰のあらしの音ばかりして淋しく、人目も草の枯れはてて、霜降月のはじめより白いものがちらちらすれば、悪いものが降る、寒いものが降ると口々にののしりて、――初雪をいまいましいというふべ哉(かな)」
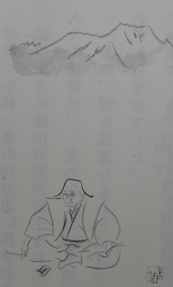
荒くきびしい自然の猛威に加え、少年時代の一茶は、まま母にいじめられて育ったと、「生ひ立の記」にかいています。異母弟が生まれてからは子守りをしていて泣くと、一茶がいじめたのではないかと責められ、
「杖のうき目にあてられること日に百度、月に八千度、一とせ三百五十九日、目のはれざる日もなかりし」
若い日の私は、一茶の不遇な少年時代に同情し、一茶がそのため、長じてやさしいおじさんとなり、「やれ打つな蠅(はえ)が手をする足をする」「痩せ蛙負けるな一茶これにあり」
などという、よわいものに哀れみの涙をそそぐ、童心詩人になったのだと、思い込んでいました。
しかし、一茶の句や伝記をよむと、中々、そんな単純なものではないのです。
一茶は少年の頃、江戸へ奉公に出されました。一七〇〇年代の終わりごろでした。辛い放浪時代のうち、いつか一茶は、俳諧師(はいかいし)としての人生を歩んでいました。故郷を追われ、後ろ盾もなく、深い学問もない彼には、この道もまた、いばらの道だったことでしょう。
夕燕我にはあすのあてはなき
梅咲くやあはれ今年も貰ひ餅
年の市何しに出たと人のいふ
春立つや四十三年人の飯
貧窮と屈辱と孤独に身をすりへらした一茶は、いつしかそんな年となっています。富裕な俳人仲間をたよっては流浪し、食つなぐ日々の辛いくらしは、彼を、気難しく傲慢で、時に卑屈な屈折した人柄に染め上げたようでした。
故郷の父を見舞ったときに、たまたま父の病いおもく、一茶はそのまま、居ついて看病をしました。それが「父の終焉日記」です。
私はそれを詠んで、一茶という人間の性格がますます底知れぬものように思えました。
その文章の、まあなんと強引で、自分本位なことでしょう。ここではまま母異母兄弟も冷酷無惨な悪人にされ、真に父のことを思う孝行者は一茶ひとり、と書かれています。とすれば「生い立ちの記」にある「杖を日に百度」というのも、かなり一茶流の誇張があるのかも知れません。
「我ときてあそべや親のない雀」も、彼らしいポーズだったかもしれません。独断的な文章や発想は、私をして一茶の人格を疑わせるに充分でした。それに、彼は父の死後十二年間も、異母弟と遺産相続で争い、ついにはむしり取るようにして、故郷の一角の地を、自分のものにしています。五十の坂をこえて若い妻を迎え、死なせたり別れたりして三度妻をとりかえ、浮世の欲望に執着するさまも、むき出しにしました。
ほんとうに一茶という男は、一筋縄では行かぬ野性的な、あらあらしい、ねじけまがった性格にみえました‥‥ところがそのむくつけき野人が、どうしてあんなに、美しい、やさしい句を、ひょいひょいと、口にのぼせるのでしょう。澄んだ詩人の目と童心がなくてどうしてこんな句がよめるでしょう。
雪とけて村いっぱいの子どもかな
うつくしや障子の穴の天の川
湯けぶりも月夜の春となりけり
これもまた疑いがいなく一茶の一面だったのです。
私にとって、人間というものの面白さ、ふしぎを教えてくれるのは、いつも一茶です。
黄葉夕陽村塾
私は漢詩のもつ、あのきりッとした硬質のリズム感と、そこにくりひろげられる、清澄なイメージの世界が大好きです。日本人が漢詩をつくるというのは、ちょうど、英語の詩を書くのと同じで、所詮、本家の国の詩人たちに及ぶはずもありません。けれどね。本来、すぐれた資質をもち。万事につけて熱心な日本民族は、渡来した漢字文化にたちまち夢中になりました。漢文・漢詩の素養は、知識階級男子の不可欠の条件でした。そうして日本人の漢詩も大そう優れたものが作られるようになり、時には本家の中国の文人に、おほめを頂戴するほどの詩人さえ出ました。
江戸末期は、漢詩のたいそうさかんだったときで、有名な漢詩人がたくさん出ました。頼山陽(らいさんよう)はもっとも人に知られた詩人でしょう。山陽の詩句は派手で鋭く強く個性的ですが、私としては、あまり好きではありません。
――といっても、私は漢詩についてお恥ずかしいことながら深く知らないのです。起承転結の展開とか、平仄(ひょうそく)・韻脚などのきまり、絶句や律など種類が多く、むつかしい約束ごとがあり、それらに通じていればより一層味わい方も面白くなるでしょうが、私が読むのは国語まじりの読み下し、いわゆる詩吟などで唱い上げられるよみかたです。
菅茶山(かんさざん)という、江戸末期の儒学者がいます、中国風な名前ですが、これはペンネームで、備後(びんご)・福山のひとです。若い頃、京都へゆき、儒学を修め、のち郷里にかえって若者たちを教えてました。その塾の名を、「黄葉夕陽村塾(こうようせきようそんじゅく)」といいます。私は「松下村塾(しょうかそんじゅく)」という名も好きですが、この名前もすばらしいと思います。そして、若者たちに勉学される機関としては、こんな風に一人の優れた先生が私塾を開いて、真剣に学びたい意欲をもっている若者だけを教えるといのが本当ではないかと思います。

――菅茶山は一代の碩学(せきがく)でしたし、また人格の温和で謙虚なことでも知られ、彼を敬慕する生徒が多く、しまいに塾は収容しきれなくなって、とうとう藩の塾にしてもらい「簾塾(れんじゅく)」と名づけました。
彼の詩は、語句がよくこなれて、やさしい人柄と、しずかな詩人の目がかんじられます。「冬日雑詩」という詩があります。
寒鳥相追入乱松 隔渓孤寺静鳴鐘
山風俄約晩雲去 雪在西南三四峯
寒鳥 相追ウテ乱松ニ入レバ
渓ヲ隔テタル孤寺ハ静カニ鐘ヲ鳴ラス
山嵐俄(ニハ)カニ晩雲ヲ約シ去レバ
雪ハ西南ノ三四峯ニ在り
寒い澄んだ冬の日暮れの情景です。鳥たちは追ったり追われたりしつつ、ばらばらに生えている松林に入ってゆく、谷の向こう側の、ぽつんと建っている寺では静かに鐘を鳴らす。山嵐がにわかにわきおこり夕べの
雲をあつめて吹き払うと、西南の峯の三つ四つに雪がみえる‥‥風の寒さが身に感じられるような詩です。「路上」というやさしい詩もあります。
反照入楊林 沙湾晩未冥
母牛与犢児 隔水相呼応
反照ハ楊林ニ入(いりた)レバ
沙湾(ジャワン)ハ晩モ未(イマ)ダ瞑(クラ)カラズ
母牛ト犢児(トクジ)トハ
水ヲ隔テテ相呼応ス
夕日はかわやなぎの林にあかあかとさしこみ、そのため水際(みぎわ)もだあかるく照り返っている、母牛と仔牛は、川をへだてて、のどかに鳴き合っている。‥‥
漢字と漢字のつらなりは固そうにみえますが、かえり点を打ってゆっくりと味わってみますと、一語一語が珠玉のように光ってそれがふれあうたび、たまゆらのさやかな音をたてます。悲壮なもの、烈しいものが漢詩の本分のように思われますが、しずけさとやさしさのあふれる漢詩もまた、人々に愛されてきたのです。
峯のあらし
高倉天皇という帝は、「平家物語」によれば「むげに幼主のときより性を柔和にうけさせ給へり」、やさしいお気立ての方でした。まだ八歳のいとけない年頃に即位させられ、ほんの少年のころに、結婚させられ‥‥帝は、物心つく前から、平家一門の、政治的配慮で、その人生を人々に操られ、動かされ、強いられてきたような運命の方でした。
おん父は後白河法皇。平清盛は、義理の伯父に当たり、二大実力者の間にあって、天皇とは名ばかりの地位、そして結婚相手は、清盛の娘、徳子‥‥。
帝は仕組まれた運命のレールを、そのまま動かされて、青年となられました。
ところが、帝が、ご自分で、運命を選ばれる日がきました。それは、当時、宮中第一の美女で、ならびなき琴の名手といわれた、小督局(こごうのつぼね)と、恋におちられたからです。
この恋は清盛の怒りを買いました。わが娘の中宮徳子に、一日も早い皇子ご誕生を、と願っている清盛は、帝が、ほかの女に心をうつしていられるのに堪えられないで、小督局
を亡きものにせよ、といいつけます。
小督は心を痛めました。わが身はどうなっても帝にご迷惑がかかっては、と「ある夜内裏(だいり)をいでて、ゆくゑしらずうせ給ひぬ」
突如、恋をひき裂かれた帝は、悲しみにくれて、小督のゆくえをたずねられましたが、清盛をおそれて、お味方する者はないありさま。
八月の十日あまり、月の美しい宵です。帝は「人やある」と呼ばれます。遠くにひかえていた仲国(なかくに)が、お答えしますと、小督のゆくえを知らぬかとのお尋ねです。噂では嵯峨の奥にかくれすむそうな。探し出すことはできぬものだろうか。涙を押さえてのお尋ねです。
仲国の心は、若い薄幸な二人の恋人たちへの同情で一ぱいになりました。よろしゅうございます。私がお探しいたしましょう。このお美しい月夜、琴の妙手の小督どのは、帝のおんことを思い出しまいらせて琴をひいていられるかもしれませぬ。琴の音をたよりにあちらこちらを探してみましょう。彼はすぐさま「名月にむちをあげ、そこともしらずあこがれゆく」のでした。このあたり、まるで、大和絵をみるような「平家物語」の名文です。
「亀山のあたりちかく、松の一むらある方に、かすかに琴ぞきこえける。峯のあらしか松風か、たづぬる人の琴の音か。おぼつかなくはおもへども、駒を早めてゆく程に、片折戸したる内に、琴ぞひきすまされたる。ひかへて是をききければ、すこしもまがふべうもなき小督殿の爪音なり。楽は何ぞとききければ、夫を思うて恋ふとよむ想夫恋(そうぶれん)といふ楽なり、そればこそ、君のおんこと思ひ出まいらせて、楽こそおほけれ。此の楽をひきたまひけるやさしさよ」
みつけ出された小督は、ひそかに内裏へ迎え入れられました。禁じられ、堰(せ)かれた恋であってみれば、よりいっそうそれは二人を暗く烈しく包んだことでしょう。しかしたちまちその恋はおそろしい清盛の耳に入ってしまいました。小督は捕らえられ、尼にして放たれました。帝は憂憤やるかたなく、苦しみにやつれ、恋にやせ、ついに、おん年二十一、という短い生涯を終えられました。小督は濃い墨染の衣をまとわれたとき、花のような二十二歳だったと伝えられます。
いま小督の墓といわれるのは大堰川の渡月橋のそばと、東山清閑寺の高倉天皇の御陵の内と、二つありますが、私としては、高倉帝のそばによりそうよう埋められたと思いたい気がします――もとより御陵の内は、さしのぞくことはゆるされませんが、ひともとの杉の根元に、ひっそりと、宝篋印塔(ほうきょういんとう)が据えられているそうです――私が訪れた日は寒い冬の一日でした。
ひえびえする空気、折々こぼれる霧雨のしずく。と思うとふと雲が切れて、もみじの梢に日が当り、全山さやかに青くなりました。しいんとした高倉帝のご陵内の、すがすがしい玉垣のうちにその杉の木は立っていました。小督の塚のしるしがあるのは、あの杉の木なのでしょうか。
すでに肉体は大地に還り、いまは二人の恋と、月夜の琴の音だけが八百年ののちにも、れいろうと澄んでひびき交わしています。恋人たちのやさしいねむりを思い、私はふり返りふり返り、石段を去ったことでした。
世間胸算用(せけんむなざんよう)
西鶴(さいかく)は大晦日をテーマにした世間胸算用という小説集を書いています。商人・町人の金のやりくり算段、大晦日ほど大変なものはありません。昔は年に数回の節季払いでしたが、大晦日は一年の総決算、この二十四時間の峠を越さねば、あらたまの春とはならず、人々は足をそらに金の算段に走り狂います。
「けふの一日、鉄(かね)のわらじを破り、世界を韋駄天(いだてん)のかけ廻るごとく、商人は勢ひひとつの物ぞかし」
必ず掛け金をとって帰らねばと意気込む掛取り、わびごとも言いつくして果ては狂言自殺をもくろむ人々、ありそうでないものは金、裕福そうな町屋も一歩内へはいれば火の車、西鶴は大晦日を舞台に、虚々実々のかけひき、やりくりを面白おかしく描きます。面白うてやがてかなしき大晦日、金、金、金の浮き世のさまざまを、例の口早な、凄いテンポで矢継ぎ早に、西鶴はたたみかけて語るのです。
「世間胸算用」は、彼の作品中では一ばん面白いものではないかと、私は思います。
金に操られる人生を、西鶴は眺めながら、そのむごさと共におかしみ、面白さも見逃しません。ことに、貧乏長屋の大晦日の、とぼけたおかしみは無類です。
金のやりくり算段は、むしろりっぱな富家のこと、いっそ貧しい下層町人は気楽なものです。貧乏長屋六七軒、「何として年をとる事ぞと思ひしに、皆、質種の心あてあれば、少しも世を欺く風情なし」
米みそ・たきぎ・醬油・塩・あぶら、貧乏人には貸し売りするものもないので現金払いゆえ、大晦日がきてもふだん通り、「帳(掛取り帳のこと)さげて案内なしにうちへ入るものひとりもなく、誰に恐れて詫び言をするかたもなく、楽しみは貧賤(ひんせん)にありと、古人の詞(ことば)、反故(ほうぐ)にならず」
正月のことは何として埒あけるこぞと思ってみていると、みんなそれぞれ質をおく覚悟があって手廻しよくしているのが、哀れにもおかしいのです。一軒からは、古い傘一本に綿繰一つ、茶釜一つかれこれ三色で、銀一匁(もんめ)借りて「事すましける」
銀一匁は米二升五合買える程度の金でした。
その燐家では、女房のふだん帯、男のもめん頭巾、蓋なしの小重箱一組、機織の筬(おさ)、五号枡と一号枡二つ、石皿五枚、仏の道具いろいろとりあつめ、二十三色で、「一匁六分借りて年を取りける」
その東どなりには舞舞(まいまい)が住んでいました。門付芸人ですが、元日からは大黒舞に商売替えするので、面と小槌一つあれば、正月中の口過ぎはできます。それまでの商売道具の烏帽子(えぼうし)、ひたたれ、袴は「いらぬ物とて、弐匁七分の質に置て、ゆるりと年を越ける」
そのまたとなりには、小うるさい貧乏浪人が住んでいました。年久しい売食い生活、おもちゃの手内職もいまはすたれ、
「今と云ふ今、小尻(こじり)さしつまて、一夜を越すべき才覚なく、似せ梨地の長刀の鞘をひとつ」女房が質屋へ持ってきました、こんなものが何の役に立つものか、と質屋の亭主が投げ戻すと、浪人の女房、顔色をかえて「人の大事な道具を、何とてなげてそこなひけるぞ」といきりたちます。
「質にいやならば、いやですむ事なり。その上何の役に立たぬとは、爰(ここ)が聞きどころじゃ。それはわれらが親、石田自部少輔乱(じぶのしょうのらん)に、ならびなき手柄を遊ばしたる長刀なれども、男子(なんし)なき故にわたくしに譲り給はり、世に有時の嫁入に、対(つい)の鋏箱の先へ待たせたるに、役にたたぬものとは先祖の耻(はじ)。女にこそ生またれ、命はをしまぬ。相手は亭主」
ととりついてなきわめくので亭主も、閉口頓首(へいこうとんしゅ)、さまざま詫びても聞き入れず、そのうち近所の者があつまって、あの女の連れ合いの浪人は、がらがわるい。ゆすりが得意のうっとうしい男、ききつけて来ぬうちに、程よい所で手を打ちなされと仲に入り、とど、銭三百と黒米三升で、「やうやうにすましける」。女はまだ、こんな米では明日の用には立たぬというので、碓(うす)まで貸して、米を踏ませて帰しました。質屋はふんだりけったりです。西鶴はさらりとあとへ、
「扨(さて)も時世かな、この女もむかしは千二百石取たる人の息女、萬(よろず)を花車(きやしゃ)にて暮らせし身なれ共、今の貧につれて、むりなる事に人をねだるとは、身に覚て口をし。是を見るにも貧にては死なれぬものぞかし」
浪人のとなりに、一人ずみの三十七八ばかりの女、身のたしなみ目だたぬようにして、色香もすこし残っているのがいますが、正月の用意は、
「はや極月(十二月)のはじめに、万事を手廻しよく仕舞ひて、割木も二三月までのたくはへ、肴かけには二番の鰤(ぶり)一本、小鯛五枚、鱈二本、かん箸、紀伊国御器(漆塗りの食器)鍋ぶたまでさらりと新しく仕替え」というソツのなさ。まだ、そればかりではありません。世間づきあいもぬからず、「家主殿へ目ぐろ(塩漬けの魚)一本、娘御に絹緒の子雪駄(こせっだ)、内儀さまへうね足袋一足、七軒の相借屋へ、餅に牛蒡(ごぼう)一抱(わ)づつ添て、礼儀正しくとしを取ける」
西鶴は、あとへするどくつけ加えています。
「人のしらぬ渡世、何をして、内証のことはしらず」
商いをする様子でもなし、何をして生活を立てているのかしら、内輪のことはわからない。お囲いものか、ただしはもっと人に言えない商売か――けれども、この女の、手抜かりない正月支度が、手廻しがよいだけに澄ましている顔が目に見えるようで、おかしみをさそわれます。
「まことに世の中の哀れを見る事、貧家のほとりの子質屋、心弱くてはならぬ事なり。脇から見るさへ悲しき事の数々なる、年の暮れぞはならぬ事なり。脇から見るさへ悲しき事の数々なる、年の暮れにぞ有ける」
と結びながら西鶴は、貧乏人は貧乏人なりの才覚や工面を、大商人のやりくりと同じに扱い、おかしみはみな同じ、西鶴はつれなく鋭い筆致のうちに、あたたかい共感を人間の暮らしに寄せています。
国庁の雪
天平宝字三年(七五九年)正月一日。因幡(いなばの)国は雪の新年を迎えました。国庁では舞い散る雪をながめながら、恒例の新年宴会がひらかれます。
国司は、都から下って来た大伴家持。
彼は、宴に招いた国や郡の役人たちに、新年を祝う歌を示しました。
新しき年の始めの初春の今日降る雪のいや重(し)け吉事(よごと)
新しく迎えた年のはじめの今日、初春のめでたきしるしの雪の降るごとく、よいことのますます、積もり重なってくれ。
大伴家持は橘奈良麻呂(たちばなのならまろ)のクーデター計画失敗の事件にまきこまれ、中央政界から遠ざけられて因幡の国に左遷されたのでした。
大伴家持は、神代以来の名門です。
「名に負ふ伴の緒」でありながら、いまは、藤原氏一族に圧迫されて、衰運に向かいつつあります。

天平の御代は、一見華やかに明るく咲き匂っているかにみえながら、その底は、血で血を洗うすさまじい政争と陰謀の世界でした。そこにあるのは、奸計(かんけい)といつわり、のろいのひとがた、たたりの恐怖、暗殺者の横行、密告裏切りの、果てしない繰り返しでした。
人はたがいに猜疑(さいぎ)しあい、にくみ、たくらみ、殺し合い、権力の座を得ようと、しのぎをけずるのです。
高潔な心の詩人、大伴家持には耐えられぬ世界であったかもしれません。
名門の誇りを抱いて、家持は、どうかしていま一度、家運を盛り返したいものと、心を砕いていたのでした。しかし、奈良の都にはすでに、清き、直き、あきらけき心は失われていたのかも知れません。
彼の悲願にもかかわらず、大伴一族は、政変のあるたび、たくみに藤原氏にはかられて、僻地へ追われ、没落してゆきます。
家持は新しい年、因幡の国庁で、この歌を口ずさみ、わが身の上と、一族の運命に思いをはせ、どんな複雑な心境でいたでしょう。
彼は、
うらうらに照れる春日に雲雀(ひばり)あがり情(こころ)悲しもひとりしおもへば
わが屋戸(やど)のいさむらたけ吹く風の音のかそけきこの夕(ゆふべ)かも
のような、心のふるえそのままのなよやかな美しい歌をよむ人であると共に、
剣太刀いよよ磨(と)ぐべしいにしへゆさやけく負ひて来にしその名ぞ
敷島の大和の国にあきらけき名に負ふ伴の緒心つとめよ
と勇ましく歌い上げて一族をさとす武人でもあったのでした。萬葉のますらおごころは彼に、まだ色濃くのこっていたのです。
国庁の庭に降る雪をみながら、また家持は二年前に七十四で死んだ、奈良麻呂の父・橘諸兄(たちばなのもろえ)のことも考えたかもしれません。諸兄一族もまた、藤原氏に圧されて滅んでいった人々です。諸兄がまだ健在で、老女帝・元正(げんしょう)に仕えていたころ、やはり雪の正月に、詔に応じてよんだ歌があります。
降る雪の白髪までに大君に仕えまつれば貴くもあるか
いかにも国家の老臣たるにふさわしい、堂々とした、荘重な、格のたかい歌です。
家持は、諸兄に愛されていました。「萬葉集」もあるいは、諸兄のアイデアによるものだったかもしれません。
しかし、家持は、因幡国庁の新年の歌を最後に、「萬葉集」巻二十を終り、また、彼自身も、それきり永久に歌わぬ歌人となってしまいます。永遠の謎を秘めたまま、「萬葉集」とあの珠玉の歌のかずかずを生んだ時代は終焉します。
デリケートで、美しい感性をもっていた詩人の家持は、あるいは、今後、詩心をしばし忘れて現実の汚濁の世界で生きようと、決意したのではないでしょうか。
家持は「今日降る雪のいやしけ、よごと」と呟き、暗い時代への憤りを胸に秘めつつも、やはり幸せへの期待を抱かずにはいられなかったのかもしれません。
ふれふれこゆき
「ふれふれこゆき たんばのこゆき」このやさしい童謡を、私はどこかで聞いたことがあるような気がしてなりません。
もしかすると、それは私が生まれるずっと前、むかしむかしの遠い代の子供たちのうたごえが、耳の底に残っているからかもしれません。「徒然草」百八十一段には、鳥羽院がまだ幼くおわしたころ、雪の降る日に歌っていらしたと、讃岐典侍(さぬきのすけ)の日記にある、と書かれています。
私は、讃岐典侍といあう人の日記をよみたいものだと思いました。しかし、私が学んだころの国文科には、そのテキストはありませんでした。「讃岐典侍日記」は、源氏・枕・伊勢・蜻蛉(かげろう)といったきらびやかな星の光にけおれてひっそりと目立たぬ、地味な存在なのでした。
そしてたとえよんでも若い日の私には、この日記のもつ重い悲愁は、理解しがたかったかもしれません。中年になってめぐりあったしあわせ、という本はあるものです。
讃岐典侍は、王朝末期の堀河天皇にお仕えした女官です。堀河帝が二十九歳というお若さでお隠れになったときの、その前後のもようを、悲しみを抑えて彼女はしめやかに、するどく的確に、書きとどめています。

堀河帝は英明な方でしたが、政治の実権はおん父・白河院の手にあり、天皇とは名ばかりの不遇なご日常でした。しかしやさしく優美なお人柄で、和歌にも笛にもご堪能でいられ、人々は心から、若い帝を愛慕していました。讃岐典侍(さぬきのすけ)は帝のめのと子で、年頃も同じほど、八年ものあいだ帝に身近く仕え、その心情は、男と女の愛情に近かったでしょう。日記に現れたそれは、帝王の崩御(ほうぎょ)、というよりも、愛する一人の青年の死をめぐる悲しみと惑乱、という切実な辛さがあふれています。
嘉承二年(一一〇七年)七月、あついさかりでした。帝のご病状あらたまり、宮中は物々しい雰囲気に包まれます。加持祈禱(かじきとう)の読経の声はつなみのごとく、あたりをゆるがします。それを近くききつつ、若い帝は息苦しげに、足をうちかけ、「われわれは今日あす、死なんずる」などと仰せられる。
「きくここち、ただむせかへりて御いらへもせられず‥‥「寝いらせ給へる御顔をまもらへまゐらせて、泣くよりほかのことぞなき。いとかう、何しに馴れつかうまりけんと、くやしくおぼゆ」
どうしてまあ、こんなに親しくお仕え申したのだろう、帝に死におくれ奉るなどと悲しい目を見るくらいなら‥‥と今更のように八年ものあいだ、お傍で楽しく暮らした月日を思い出され、胸ふたがるのでした。なまじ帝の若さは、死の苦しみを増すようで、おん汗もふき出、おん手も腫れたまい、お体のやりばのない苦しみに、彼女のくびにおん手をうちかけ、喘ぎたまうのでした。抱き起せよ、臥せしめよ、との仰せに、彼女たちご看護するものは夢中でお仕えします。
「せめて苦しいおぼゆるに、かくしてこころみん、安まりやする」
と仰せられて、おん枕上の神璽(しんじ)を収めた箱を、お胸の上に置かれたりします。お胸は苦しげに、ゆらぎ、息もたえだえのごようすでした。一睡もせずお看護する彼女の耳に、明けの鐘の音が聞こえます。
ほっとして朝の光が待たれるのでした。御前をさがしって交代でとろとろと休む間もなく、たちまち使いが来て「のぼらせ給―」と呼ばれます。帝にお食事をさしあげてみようというのでした。ひとりがおうしろから支え奉り、小さな台で、ほんの形ばかりおめしうえりになる、ああなんと、お弱りになったことよ、と涙ぐまずにはいられません。
おやさしい帝は、そんなお苦しみの間にも、なぜ寝ないのか、と彼女を心配して仰せられ、また、お看病のために横に添い臥ししていますと、人が来たよと注意されて、彼女の姿をかくすように、おんひざを高くしてかばって下さるのでした。
あわただしく定められるご譲位のこと、御受戒の儀、お最期のときは一刻も早く一刻と近づきます。氷などまいり、おん汗をぬぐううち、
「いみじく苦しくこそなるなれ。われは死なんずるなりけり‥‥大神宮たすけさせ給へ。南無平等大会講明法華」ととなえられ、あまりの悲しさに讃岐典侍らは夢みるここちで「涙もせきあへず」というありさま。
「苦しうたへがたくおぼゆる、いただきおこせ」
と仰せられるのでお抱きしますと、おん腕(かいな)はもう冷やかになっていられます。こんなに暑いさなかなのに‥‥。指を水に濡らしてお口をうるおし、尊い僧正、帝の老いた乳母たち、彼女ら侍女たちは声を惜しまず、あたまから黒い煙が出るまで一心不乱に読経し、お祈りをし、仏におすがりして今は奇蹟を念じるばかり、あなやと思うままに、
「むげにおん目などかはりゆく」
ご臨終とみてとって関白や内大臣は、たちまちおん父の白河院へ使いを出し、帝のおん枕を直し、抱いて臥せしめられます。
「かかるほどに、日、はなはなとさしいでたり、日のたくるままに、御色の日頃よりも白く、はれさせ給へる御顔の清らかにて、御びんのあたりなど、御けづり髪(ぐし)したらむやうに見えて、ただ大殿ごもりたるやうにたがふことなし」
死の業苦(ごうく)からいま解放されて、仏のみもとへおもむかれた帝は、安らかにお美しく、まるで、おやすみになっていらっしゃるようでした。声をかぎりに泣き叫ぶ帝の老いた乳母たち、一緒に御召し下さいませ、とみな、変わり果てたお姿にとりすかせって泣きました。
讃岐典侍は、悲しい宮中を退出しましたが思いがけぬことに、新帝。鳥羽帝に、またお仕えすることになりました。
雪のふる朝でした。何につれても、先帝がまだおわしますような気がされて、ぼんやりしている彼女の耳に、
「ふれふれ こゆき
たンまれ こゆき
垣や木のまたに」
とあどけない幼い子のうた声がきこえてきました。おや、どこの子か、とつい思い、おおほんに、あれは帝でいらせられるかと、あわれ深い心地がされました。おん父堀河帝に五つで死に別れられた幼帝は、おん母君とも生まれてすぐ死別されており、幸うすいお身の上のいじらしさでした。はじめてお食事のお給仕にま近くお仕えしますと、走っていらしてお顔をさしのぞかれ、〈この人は誰なの〉と仰せられます。堀川院のおん乳母子(めのとご)ですよ、とそばの人が申しますと、そうかと納得されるようす、昔、おん父みかどのもとにまいられたとき、堀川院がお可愛(かわ)ゆくおぼし召されたときのことなど思い出されて讃岐典侍(さぬきのすけ)は切なくなるのでした。
幼ないみかどのもとにまいられたとは、夜おやすみになるお姿もお小さくいじらしく、お食事をまちかねて召し上がるのもおかわゆく、彼女は、ま心こめてお仕えしているうちに諒闇(りょうあん)も終り、世の中は花の衣になりました。
新帝も内裏(だいり)にお渡りになります。夜の御殿(おとど)のありさま、滝口(たきぐち)の名対面(なだいめん)、左近(さこん)の陣の夜行、みな、先帝おわしましし頃と同じでした。内裏がお珍しい幼帝は、彼女に案内させてそちこちお渡りになります。台盤所、混明地、御障子、みななつかしく、彼女は昔の知人にあう心地がして、でも、先帝だけはこの世にもうおわしまさぬのです。
幼帝をお抱きして、障子の絵をお見せしていると、夜の御殿の壁に、先帝が、あけくれ目なれて覚えようと思し召されてはりつけておかれた笛の楽譜が、まだそのままにありました。つい涙ぐまれて袖を顔におしあてていますと、どうしたの、とたずねられます。あくびが出まして、つい、と申し上げますと、知っているよ、とさかしく仰せられ、〈なにをごぞんじでいらせられますか?〉〈うん。ほの字、りの字のことを思い出していたんだね〉ほりかわ‥‥お父さまのことでしょう?‥‥とのたまうおかわいらしさ、
「あはれにさめぬるここちしてぞ、笑(ゑ)まるる」
ふと心がさわやかに晴れて、ほほえまれるのでした。
死別のくるしみ、という人生最大の苦しみを経てきた彼女の、そのときの微笑は、やさしく明るいものだったにちがいありません。
「讃岐典侍日記」は、辛く切なく、そしてやさしい物語なのです。
つづく 失われた夢