上古の神々たちの大らかな哄笑(こうしょう)、怒り喜び悲しみの、くもりない明らけき心は、すでに失われました。人智が開けるに従い、あやしい心のくまや、かげりが生まれます。神の国から下界へ下りた人間たちは醜く争い。妬み傷つけあうのです。
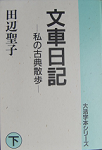 田辺聖子著
田辺聖子著
文車日記(ふぐるまにっき) 下巻
――私の古典散歩――
大君のみ盾
崇峻(すしゆん)天皇の二年(五八九年)七月、河内の国、志紀・渋川の野(今の八尾・東大阪)には、烈しい戦いがくりひろげられていました。
かねてから排仏が崇仏かをめぐって、すさまじい政争を繰り返していた。物部(もののべ)・蘇我(そが)の二大豪族が、ついにそれぞれの総力を結集して、一代決戦の火ぶたを切り落としたのです。
戦塵(せんじん)はもうもうと天に連なり、軍兵の雄たけび、矢のうなりは野に満ちました。「日本書紀」はこの辺りから、ようやく現実的な体臭を持ち、文章に迫力を増します。‥‥ヤマトの国に、やっと肉体・肉声をもった人間たちが跳梁跋扈(ちょうりょうばっこ)しはじめたのです。
上古の神々たちの大らかな哄笑(こうしょう)、怒り喜び悲しみの、くもりない明らけき心は、すでに失われました。人智が開けるに従い、あやしい心のくまや、かげりが生まれます。神の国から下界へ下りた人間たちは醜く争い。妬み傷つけあうのです。陰謀・戦争。奸計(かんけい)。暗闘。物欲はとめどなくあふれ、社会は複雑怪奇なすがたを帯びてゆきます。
旧来の勢力の頂点にたつ古い名門貴族。物部と、外来文化と新興勢力の代表者、蘇我。この決戦は、蘇我の勝利におわりました。神代の昔から勇名をうたわれた物部のもののふたちも、蘇我の政治力や物量作戦にはかないませんでした。首長の守屋(もりや)は殺され、軍は大敗、その屍(しかばね)は恵我(えか)川原を埋めつくしました。
物部守屋の従者に、捕鳥部(ととりべ)の萬(よろず)という勇士がいました。彼はただ一騎で和泉(いずみ)の国へ落ち、物部の旧領地で兵をあつめて最後の一戦を交えようとしました。
しかし萬に従う兵士もすでになく、硬骨の彼は、こうなったら一人で最後まで戦い抜こうと決心したのです。愛する妻に別れを告げ、ひとりで山にこもった萬を、数百の精兵が、ひしひしととりかこみます。
勝てば官軍、勝ちに傲(おご)った蘇我氏はたちまち、天皇軍となったのです。天皇の軍から見た萬は、すなわち逆臣にほかなりませんでした。「すみやかに族(やから)を滅すべし。な怠りそ」という朝命が発せられたのです。
「衣裳幣(きものや)れ垢(あか)つき、形色憔悴(かほかし)けて、弓を持ち剣を帯(は)きて独り自から出で来たり」
たった人の萬は、ちえをめぐらせて、さんざんに敵兵を悩まします。竹藪にかくれて、縄を竹につけてひっぱり、おのがいるように欺いて、そこへ群がりよせて敵兵を片っ端から射殺し、「一つとして中(あた)らざること無し」
萬は飛鳥のようにここと思えばまたかしこと逃げて戦いました。しかしついに膝を射抜かれて倒れ、倒れた萬に矢は雨のように降ってきます。彼はそれを払いながら、絶叫しました。――おれは、天皇(すめらみこと)の盾として今まで戦ってきたのだ。守屋の大連(おおむらじ)さまが、すめらみことのためだとご命令になったから、おれは戦ったのだ。それをどうして、おれが、すめらみことの軍に追われ、殺されなくてはならないのだ。
たのむ、そのわけを聞かせてくれ、誰か来て、そのわけを話してくれ、すめらみことのために戦ったおれが、すめらみことのために討たれなければならぬ理由を話してくれ‥‥。
「萬は天皇(すめらみこと)の盾(たて)として、其の勇を効(あらば)さむとすれども、推問(と)ひたまはず、翻(かへ)りて此の窮(きはまり)に、逼追(せ)められることを致しつ。共に語るべき者(ひと)来れ。願はくは殺し虜(とら)ふることの際(わきだめ)を聞かむ」
という萬の悲痛な絶叫に耳をかすものはありませんでした。兵士は折り重なって殺到しました。萬はそれでもなお三十何人を殺しついにわが弓を折り、剣を曲げて河中に投じ、みずから短剣で首を刺して死にました。
萬の死骸として八つ切り刻まれ、八つの国で串刺しして、さらされました。その屍を雨に濡らしたといいます。
昭和十一年二月二十六日の朝まだき。大雪をついて決起した陸軍青年将校たちの掲げた旗には「尊皇討奸」とありました。しかし彼らは謀反者として直ちに処刑されました。「天皇陛下万歳」と叫びつつ、天皇陛下の軍に銃殺された彼らは、萬の末裔(まつえい)たちだったのです。殺される理由を「語るべきひと来れ」という、混乱にみちた彼らの号泣に、答えてやる人はなかったのです。
あやゐがさ
君が愛せし
綾藺傘(あやゐがさ意=いぐさ作りの傘=」)
落ちにけり 落ちにけり
加茂川に 川中に
それを求むと 尋ねと せしほどに
明けにけり 明けにけり
さらさら さけの 秋の夜は
古い古い、民謡です。
「梁塵秘抄(りょうじんひしょう)という、八百年ほど昔の歌の本にのっています。歌といっても、萬葉・古今といったみやびやかな敷島(しきしま)の道ではなくて、当時の民衆が愛誦(あいしょう)した、今様(いまよう)という流行歌の、歌詞をあつめたものなのです。
だからこの歌もきっと、ふしをつけて歌ったり、舞ったりしたものでしょう。
綾藺傘(あやゐがさ)は、藺草を編んでつくった笠で、武者たちが狩や旅のときに用いた、スポーツ用ともいうべき笠。戦いの兜(かぶと)や、女用のなまめかしい市女笠(いちめがさ)とちがって、綾藺傘は瀟洒(しょうしゃ)な風趣をもたらします。
私は「梁塵秘抄」の中でこの歌がいちばん好きです。何という軽やかでリズミカルな、美しい歌でしょう。
下巻十七ページ写真
清らかな若殿ばらの、愛用の笠が風に吹かれて、はらりと賀茂川に。
やはれ、かしこぞ、流るるは、と連れの人々はわらわらと水辺に下り、笑いさざめく。
賀茂の川水はその頃、空よりも清澄に冷たかったことでしょう。
さらさらやけ、ということばの清々しさ。川の水も秋の夜も。

この歌に似たものに、芥川龍之介の「相聞(そうもん)」と題する詩があります。
これもさわやかにかろく美しく、私の好きな作品です。
風にまひたるすげ笠の
なにかは路に落ちざらん。
わが名はいかで惜しむべき。
惜しむは君が名のみとよ。
こんな歌をひろめたのは、諸国を流浪する傀儡子(くぐつ)たち(人形使いのジプシー的芸能集団)や巫女(みこ)、琵琶(びわ)法師、遊女、白拍子(しらびょうし)たちでした。賀茂川の水辺をゆく若殿ばらの一行の中にはきっと、裾をからげて白い素足を川水にひたす、陽気な遊女もいたでしょう。
我を頼めて来ぬ男
角(つの)三つ生ひたる鬼になれ
さて 人にうとまれよ
霜 雪 あられふる 水田の鳥となれ
さて 足冷たかれ
池の浮草と なりねかし
と揺りかう揺り ゆられて歩け
あんなにかたく契りをこめ、あてにさせておきながら通ってこなくなった憎らしい男。
あんな奴、角が三つも生えた鬼になって人にきらわれるがいいわ。
霜や雪やあられの降る冷たい水田の鳥となって立ちつくし、足が冷えればいいんだわ。それとも池の浮草か、あっちへゆれ、こっちへゆれ、さまよい歩けばいいのよ――。
天真爛漫に毒づいてすます。名もない民衆の心々の喜び悲しみは誰からともなくわき上る歌声になり、人々に愛せられ、歌いひろめられてゆきました。
舞へ舞へ 蝸牛(かたつぶり)
舞はぬものならば
馬の子や牛の子に蹴(くゑ)させてん
踏みわらせてん
まことに美しく舞うたらば
華の園まで遊ばせん
美少女の巫女たちが声をそろえて歌う舞う、この世ながらの浄土のような華やかさ、そしてその低音部に、呻吟(しんぎん)
する如きべつの歌声が、たえずひびきわたります。――
遊びをせんとや生まけん
たはぶれせんとや生れけん
遊ぶ子供の声聞けば
我が身さへこそゆるがるれ
仏は常に在(いま)せども
現(うつつ)ならぞあはれなる
人の音せぬ 暁に
ほのかに夢に見えたまふ
あかつきの仏、というところが、儚い憧れを象徴するようで、私の好きな歌です。
百日百夜(ももかももよ)は独り寝と 人の夜夫(よづま)は何(なじ)せうに
欲しからず
宵より夜半(よなか)まではよけれども 暁鶏なけば床さびし
我が子は十余りなりならん
巫(かうなぎ)してこそ歩(あり)くなれ
田子の浦に汐(しほ)踏むと いかに海女人集うらん
正(まさ)しとて 問ひみ問はずみ嬲(なぶ)るらん いとほしや
我が子が二十(はたち)になりぬらん 博打(ばくち)してこそ歩くなれ
国々の博党(ばくと)に さすがに子なれば憎か無し
負かいたまふな 王子の住吉(すみよし) 西の宮
このごろ都に流行るもの 柳黛(りゆうたい) 髪々 似而非鬘(ゑせかづら) しほゆき近江(あふみ)女 女冠者(くわざ) 長刀(なぎなた)持たぬ尼ぞ無き
女の盛りなるは 十四五六歳廿三四とか 三十四五にし成りぬれば紅葉(もみじ)の下葉に異(こと)ならず
これらの歌を編集して、「梁塵秘抄」と名づけられたのは、ほかならぬ、後白河合院でした。
源平が血みどろの死闘を繰り返しているあいだ、たえず権謀術策の中に生きてきた人。――清盛。義仲。義経。頼朝。あまたの人間の盛衰を見つつ、みずから時代の暗黒の巨魁(きょかい)であった王者。院が民衆の歌を憑(つ)かれたように好まれたのは、六十年の波乱にみちたご生涯を通して、生きること、歌うことの何たるか、そのはかなさ、と同時に、その永遠のいのちを非凡なお眼に見ぬかれたからでしょうか。
男の出発
天平八年(七三六年)夏六月。
難波の港から友綱を解いて、まさに出航銭とする大船がありました。
勅命を奉じて万里の波濤(はとう)をつき新羅(しらぎ)へおもむく、遺新羅大使、阿倍継麿(あべのつぎまろ)の一行です。
慣例によれば、一行が新羅から帰朝するのは秋のはずでした。
「萬葉集」巻十五の前半は、この使節一行の出発時の贈答歌や、旅程中歌で占められています。
結果としてこの旅は惨澹(さんたん)たる苦難にみちたものになりました。台風の強い風波に弄(もてあそ)ばれて航路の予定は大幅におくれ、しかも大使自身、九州地方で猖獗(しょうけつ)を極めていた疫病にかかり、対馬で歿(ぼつ)し、副使は旅先で病臥(びょうが)、しかも旅の目的たる対新羅折衝にも、政治的に何の成果も上らなかったという、いわば、男の仕事のむなしさを表象したような旅でした。大使・副使を欠いた一行がようやく奈良の都へ帰り着いたのは、翌天平九年正月も末のことだといいます。
もとより、出発する際の使臣一行は、神ならぬ身の、そんな将来の運命を予知するはずはありません。しかし、彼らがその妻と交した贈答歌は、ゆえ知らぬ不安と憂慮と、ただならぬ情愛にみちています。あるいは、苦難の旅の予兆が、胸をかすめることもあったのでしょうか。これをたとえば、防人(さきもり)たちの、りりしい男のいさみ立ちのような歌――「大君のみことかしこみ磯に触り海原わたる父母をおきて」や、「あめつちの神を祈りて征箭貫(さつやぬ)き築紫(ちくし)の島をさして行くわれは」などとくらべると、ことのほか、うら悲しいムードがあふれています。
武庫(むこ)の浦の入江の渚鳥(すどり)はぐくもる君を離れて恋に死すべし
私の一ばん好きな歌です。武庫川は私の長年すみなれた所でもありますので、ことさらゆかしい気がします。兵庫県西宮市の海のあたりをいったのでしょうか。ある使い人の妻の歌です。武庫の浦の入江の、洲にいる鳥が大きな羽を拡げて暖かく子を抱くように、あたしはあなたの愛情につつまれて生きています。いまそのあなたに離れるなんて‥‥あたしはきっと恋しくてこがれ死にしてしまいますわ。

「君を離れて恋に死ぬべし」という高く張った歌の調子が、女心のいちずな思いを強くひびかせます。夫であり、恋人である男は、それに対して、「大船に妹(いも)乗るものにあらませば羽ぐくみもちて行かましものを」
私の乗る大船に妻のお前も乗っていいものなら、羽でくるむようにして連れてゆくものを。これは官船。
しかも男のおおやけの仕事に、女は連れてゆけないのだ。
更にひとりの妻は歌います。
君がゆく海辺の宿に霧立たば吾(あ)が立ち嘆く息と知りませ
あなたのゆく先の、海辺の宿に霧が立ったら、あたしのめ息と思いになってね。
それにこたえて男は、「秋さらば相見むものを何しかも霧に立つべく嘆きしまさむ」――秋になればまたあえるのじゃないか、どうしてためいきが霧に立つほど嘆くのか。
そうなだめながら男は、雲煙万里の旅程を思って、妻恋にうしろ髪ひかれる思いがします。――「潮待つとありける船を知らずしてくやしく妹(いも)を別れきにけり」
船は大潮を待って出航をたゆとうている。しまった、こんな時間があるのなら、もっとゆっくり妻と別れを惜しんできたものを。
古代の船旅は決死の勇を必要としたでしょう。しかし男はそれでも、男の仕事として出てゆきます。いかにうしろ髪ひかれようと、宿命の出発をします。男は出発し、女は見送ります。私はこの一連の贈答歌は、男と女のありようの象徴のように思えます。そして事実、この旅で幾人かの男は、ついにヤマトの土地を再び踏むことなく異郷で果てたのでした。
白き鳥の歌
私たちが民族的英雄として言いつぎ、語りついできた人たちの中で、ヤマトタケルノミコトほど、愛された青年はいないでしょう。
この英雄は、たくさんの人間のイメージが複合してつくられた伝説上の人物、ということになっていますが、「古事記」あるいは「日本書紀」をよむとき、おのずから目の前に立つおもかげは、これはもう、実在の青年王子にほかなりません。実在と伝説のあいだをこの青年王子はなつかしくはるばると飛翔(ひしょう)し、私たちに、永遠の夢とロマンをかたりかけるのです。
ヤマトタケルは、傾行(けいこう)天皇の王子でした。天皇の命令をうけて、西の国のクマ
ソという荒ぶる賊たちを討ちにいったのは、まだほんの少年のときでした。彼は女装して
クマソに近づき、剣で刺しました。それをはじめとして西に東に、戦塵(せんじん)にまみれ
て天皇のために戦います。そのヤマトタケルに天皇は更に次々と討伐を命じ、彼は叔母の
ヤマトヒメに向かって、
〈天皇は私に死ねと思われているのでしょうか、西の征伐に帰ったと思うとこんどは東へ
向かえと仰せられるのです。私に死ねよといわれるのだと思われます〉
と訴えて泣くのでした。多感な青年、ヤマトタケルは、父王の愛うすいのではないかと
疑って、それを訴えずにはいられないのです。そして訴える相手は、やはり、「永遠に女
性的なるもの」、ここでは、やさしく彼を慰めてくれる、叔母なのでした。ヤマトヒメは、
草薙(くさなぎ)の太刀と、袋を彼に与え〈危急のことあればこれをあけなさい〉といいました。
ヤマトタケルが賊軍にかこまれ火をつけられて一命危ういとき、その太刀で草を払い、
袋の中の火打石で、あべこべに賊軍を焼き払って虎口を脱した話は有名です。ヤマトタケ
ルはまた、愛妻オトタチバナヒメの献身によって危機をのがれます。ヒメは海の荒波を鎮
めるため、己が身を捨てて海神の怒りを和らげるのですが、その別れのとき、
さしねさし相模の小野(おぬ)にもゆる火の火中(ほなか)に立ちて問ひし君はも
とうたって海に身を投じました。七日たって。ヒメの櫛が海辺に流れ着き、ヤマトタケ
ルは涙ながらにその櫛を納めて墓を作りました。
ヤマトタケルの漂泊と戦いは更につづけられます。白鹿に化けた坂の神、白猪に姿をかえた山の神、氷雨(ひさめ)はヤマトタケルを打ち、脚を弱らせ、若き英雄は、これでもかこれでもかと、悩ませられます。
ヤマトタケルはなお、故郷へかえりつくことはできません。
美女、ミヤスヒメとの恋をとげることもできないのです。故郷を目前にしながら、ヤマトタケルは、ついに倒れます。そのとき、口をついて出るのは、望郷の歌です。
倭(やまと)は国のまほろば たたなづく青垣 山ごもれる 倭しうるはし
命の全(また)けむ人は、たたみこも 平群(へぐり)の山の 熊白檮(くまかし)が葉を、
髻華(うず)に挿せ その子
ヤマトはいい国だ。青々とした山々にかこまれてうるわしい国だ。
命つつがなく、無事にかえった人は、平群の山の、クマガシの葉を髪にさして、人の世の楽しく長からんことを祈れ。
命あるものよ。私の分まで生きてくれ。
ヤマトタケルは死にました。彼の妃や子供たちはそのあとを慕い、蔓草(つるくさ)のようにはいまつわって泣き叫ぶのでした。
「是(ここ)に、八尋(やひろ)白千鳥になりて、天(あめ)に翔(かけ)りて浜に向きてとびいでましき」ヤマトタケルの死霊は白い鳥となって去るのです。死霊が白い鳥になる伝説は世界各地にあって、奄美大島の民謡にもあります。
船ぬそとどもに白鳥ぬ鳴ちゅり 白鳥やあらぬ をなり神がなし
白き鳥になったヤマトタケルは、何千年の昔から人々のあこがれが擬縮した、美しい夢だったのです。妻を恋い望郷に涙し流浪する人々の心の歌だったのです。
蟲(むし)めづる姫君
蝶を愛する人は多いのですが、毛虫を愛する人は珍しいでしょう。
「堤中納言物語」という、王朝末期の小説集の中に、「蟲めづる姫君」という、たいへん面白いお話があります。
この「堤中納言物語」という本についてはまだよくわからない点が多いのです。モダンでしゃれた、軽妙な短編小説が十ばかり集められていまして、中味にふさわしく、そのタイトルもそれぞれ「花桜をる少将」だの「ほどほどの懸想(けそう)」だの「貝あはせ」だの「このついで」「逢坂(あふさか)越えぬ権中納言」だのと魅力的ですが、作者はそれぞれがちがうらしく、またそのアンソロジーをなぜ「堤中納言物語」と名づけたか、一切は謎に包まれています。
私はことに「蟲めづる姫君」が好きです。
ある中納言の姫君は、たいへん風変わりな方でした。虫がたいへんお好きで、ことに、
「かはむし(毛虫のこと)の心深きさましたるこそ、心にくけれ」
毛虫がおもむき深くておもしろいわ、とてのひらにのせ、じっと見守ったりなさいます。
若い侍女は気味わるいやら恐ろしいやら、逃げ惑ってしまうので、姫は、腕白ざかりの少年たちを召し使われて、それらに、けらを、いなご麿(まろ) ひき麿などと名づけ、さまざま恐ろしげな虫どもを捕り集められて虫箱に飼い、いうなら、生態観察に講じられていました。
おまけに、「人はすべて、つくろふところあるはわろし」とおっしゃって、一切、お化粧もなさいません。
そのころの高貴な女性はみな眉を抜いて、やさしい描き眉を点じ、お歯黒をして、おちょぼ口、おしろいを塗り、香をたきしめ、というのが身だしなみの常識なのに、「眉さらに抜き給はず、歯黒めさらにうるさし、きたなしとて、つけ給はず、いと白らかに笑みつつ、この虫どもを朝夕(あしたゆふべ)に愛し給ふ」
少年たちを相手に「あららかに踏みて」庭に下り立ち、木の幹の毛虫を集められるというありさま。
両親の困惑と嘆きはひと通りではありません。世間の聞こえも悪いですよ、とたしなめられるのへ、姫は平然として、
「よろずのことどもをたづねて、末を見ればこそ、事は故あれ。いと幼なきことなり。かはむしの蝶とはなるなり」

何につけても結果と原因を探求してこそ、面白いものですわ。それをむやみと忌みきらうのは幼稚なことですわ。毛虫が蝶になるのよ、ほら、ごらん遊ばせ。などと「そのさまのなり出づるを取り出でて見せ給へり」
さすがの両親も言い返すすべもなく、呆れてしまわれるばかりでした。
その噂を聞いた若い貴公子たちが面白がって、こっそりとお邸へ姫をのぞきに来ます。そうしてびっくりしました。むくつけき毛虫を好みたまうにしては、これはまた何と、「あざやかに気高く」世にも美しい姫君だったのです。ああそれで、世間なみなお化粧をしていられたら、どんなに美しく、より愛らしかろうものを、と青年たちは残念がります、
殿方ばらがかいまみていられますよ、と侍女たちははらはらして姫の不用意をたしめますが、姫は、べつに恥ずかしくないわよ、と気にも留められません。
「人は夢幻のやうなる世に誰か止まりて悪しきことをも見、よきをも見思ふべき」
この、儚い夢まぼろしみたいな世に、誰がいつまでも生きていて、いいことだ、悪いことだとあげつらうものですか。――どうせ、この世はいっときのことよ。…‥若い姫にしては達観していて、明快で合理的で、当時としては驚くべくユニークな個性です。それゆえにこそ、この一篇は男性の手になるものだろうというのが、大方の研究家の通説ですが、しかしこの姫は、これほど風変わりでありながら、とても可愛らしい性格に描かれています。
毛虫が好きなくせに蛇は怖がったり、たいへんユーモラスで愛すべきヒロインなのです。それは、女の手になったからではないかと私は思うものです。もしかしたら、ある女性の自画像なのではないでしょうか。彼女は愛をこめて「蟲めづる姫君」を描きました。女性は本質的にはナルシストなのです。
ませの白菊
橘成季(たちばななりすえ)が「古今著聞集(ここんちょもんじゅう)」を書き上げたのは十三世紀なかば――正確にいうと、建長六年(一二五四年)秋のことでした。
成季という人については、まだよくわかっていませんが、あまり身分高いお公卿(くげ)さんではなかったようです。
しかし京の朝廷に仕え、貴族の末としてのプライドを守って生きてきた彼にしてみれば、鎌倉幕府が朝廷を圧して、いまをときめく武士の世の中になったことに対して、さまざまな感慨を抱かずにはいられませんでした。
今はおどろおどろしい武者ばらが跳梁跋扈(ちょうりょうばっこ)し、馬のいななき、ひづめのとどき、何かというと矢のうなり、太刀のひかり、あらあらしい力の行われる世でした。力あるものが正義なのでした。
あの華やかにもやさしい物のあわれの世界――詩歌、管絃(かんげん)の風流、恋とロマンの夢は、跡形もなく消え失せようとしています。
まさしく、それは王朝貴族文化の落日でした。成季は、失われてゆく「人間のやさしみ」「風雅有情のあはれ」を、書きとどめ託思いました。それが、王朝文化の臨終に立ち合った人間の、なすべき仕事のような気がしたのです。
「これ、そこはとななきすずろ事なれども、いにしーより、よき事もあしき事も、しるしわき侍(はべ)らずは、誰か古きをしたふ情けを残し侍るべき」
成季は、あとがきにそう書いています。彼は、人に見聞きし、あるいは本を読んだ、たくさんの、そういうやさしいお話をあつめて「古今著聞集」と名付けました。
そのなかの私の愛する一つのお話。
刑部卿(ぎょうぶきょう)の敦兼(あつかね)という人は、たいへんな醜男(ぶおとこ)でした。「みめのよに憎さげなる人なりけり」とあります。その北の方はまた、たいへんな美女でした。
あるとき、北の方は宮中の五節(ごせち)という、祭礼舞楽の一大ページェントを参観し、たくさんの参会者の貴顕紳士をはじめて見ました。
どの貴公子も、どの公卿も、かがやくように美しく、りっぱな殿方ばかりに思われました。
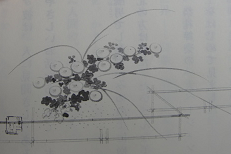
深窓の姫として生い立ち、親のいうままに、敦兼を、むこに迎えた北の方は、男性というものはみな、こういうものだと思っていたのです。でも、はじめて現実の男性たちをかいまみて、世間知らずの彼女は、びっくりしたのです。帰宅してからは、もう、みにくい夫を見るのもいやでした。
目も見合わせず、ものもいわず、つんと、そっぽを向いているので、夫の敦兼は、たいへんいぶかしく思いました。
どうしたのだろう、とふしぎでしたが、北の方のほうは、ますますいとわしくなって、同じ邸ながら、離れたところへ別に移ってしまいました。
ある日、夫の敦兼は宮中へ出仕して、夜おそく帰邸しました。すると居間には灯りもともしてありません。装束をぬいでも、たたんでくれる侍女もいません。彼女らもみな、北の方の意をうけて、主人の世話さえしなくなったのです。
敦兼は仕方なく、廊下の車寄せのところでひとり考えに沈んでいました。今も彼は、北の方の言葉のはしばし、侍女の耳打ちなどから、うすうす事情を悟っていたのです。
「月の光風の音、物ごとの身にしみわたりて、人のうらめしさも、とりそへておぼえけるままに」彼は篳篥(ひちりき)を吹き、歌いました。
ませの内なる白菊も
うつろふみるこそあはれなれ
われらがかよひてみし人も
かししつつこそ離(か)れにしか
垣根の内の白菊も色香うつり枯れてしまうように、あんなに愛し合っていたと思ったわれられの仲も、こうやってはなればなれになるか‥‥。その歌は北の方の耳にも入りました。
北の方は、がくぜんと現実に引き戻されました。男の愛情というものは、目に見えず手にもつかめない、無形の大きなものだと悟ったのです。彼女はすぐ、心をとり直し、そののちは前よりも「仲ひらめでたく」生涯をちぎりました。成季が「優(ゆう)なる北の方の心なるべし」と、妻の女心をほめているのも、おもむきふかいことです。
あ――ら わが君
ふるい落語に、大阪でいう「延陽伯(えんようはく)」、東京で「たらちね」というのがあります。
私は、この中に出てくるお嫁さんの延陽伯こと、お鶴さんが好きなのです。
やもめの「喜(き)ィさん」の家に、美人がおこし入れ(もおかしい、ボロ長屋ですが)してきます。
お嫁さんを迎える喜ィさんの支度が、また、たいへんすてきで、私は、こんな婚礼(結婚ではなく)にとてもあこがれをおぼえます。
やもめですから、何も道具はありません。仲人さんの注意で、形ばかりの祝言の支度を、花婿の喜ィさんが大慌てでするのですが、それがごく素朴で簡便、
「かんてき(七輪)に火ィいこして茶ァわかして酸い酒の一ぱいも買うて、何でもええから、あたまとしっぽついた魚買うて」
この時分のふつうの町人たちの結婚支度は、式亭三馬(しきていさんば)の「浮世床」にもありますが、まずざっとこんな具合でした。
「仲人が葛籠(つづら)を背負って、左の手にお歯黒壺を提げて、右の手に酒を一升瓶提げて来たは。イヤまた恥をいはねえぢゃァ理が聞こえねえ。ソコデ、おれは商ひから帰って、今に大方、花嫁が来るだらろと思ふから、豆腐を小半丁買って来て、かつお節をかいてる所へお輿入れよ。それから仲人が指図して、すぐに花嫁が茶釜の下へたきつける、仲人が味噌を摺る。ソコデ、仲人の懐から出した三枚の鯣(スルメ)を焼いて、三々九度よ。ナントどうだ‥‥」
待ちながら、喜ィさんは、あれこれと、花嫁が来てからの生活を想像します。
そこのところが、この上なく聞いていて、楽しくおかしい。喜ィさんの大ぶりな茶碗と花嫁の、「薄手の可愛らしい」茶碗がならぶさま。お茶づけを二人してかきこむ。チンチロリンのガーサガサ、ポーリポリの、バーリバリ‥‥という、お馴染みの所など、聞いていて、喜ィさんの弾みと期待がこちらにも伝わってくるような、たのしい場面です。
喜ィさんは、結婚生活、男と女の二人して営む新しい人生に、とても夢と期待をもっています。やもめの喜ィさんにとっては、女房(よめはん)、嬶(かか)というのは、永遠の女性、ベアトリーチェでもあるのです。
だから、夫婦ゲンカの想像すら、喜ィさんにとっては、手の舞い、足踏む所知らず、という、わくわくするような夢なのです。
ところが、やってきたお嫁さんは、高貴な家に奉公していた人で、言葉がちんぷんかんぷんで、無学な喜ィさんにはちっともわからない。そこが、この落語のおかしみで、ねらいどころなのですけれど、このお嫁さんも、わざとそういう言葉を使って、無学な新郎を煙にまいているのではないところが、よけい、おかしみをそそります。
このお嫁さんは、精一杯敬語を使って、みずからも、手鍋ひとつ下げて長屋にやってきた新生活への希望を表現しているわけです。
喜ィさんの方は、お公卿さんの言葉は使えません。双方、外国人同士のようなあんばい、名を聞かれて有名なセリフを、嫁さんは答えます。
「わらわ、父はもと京都の産にして、姓は安藤、名は啓蔵。字(あざな)を五光と申せしが、わが母三十三歳の折、ある夜、丹頂を夢み、わらわをはらみしがゆえに、たらちねの胎内を出でし頃は、鶴女(つるじよ)鶴女と申せしが、これは幼名、成長ののちこれ改め、延陽伯と申すなり」
どこからどこまでが名なのか、喜ィさんは困りはてます。翌朝はそれでも、延陽伯のお鶴さんは亭主より早く起き、
「あーら、わが君」
とよびかけて、朝食をつくってすすめますが、葱(ねぎ)を一束、買うのにも、「こりゃ、門前に市(いち)をなす賤(しず)のおのこ。おのこやおのこ」と呼びかけて、八百屋まで、あっけにとられてしまう。
でも、お鶴さんとしては、一生けんめいなのです。
お鶴さんは、「酸い酒と小魚」で、偕老同穴(かいろうどうけつ)をちぎった亭主に、生涯をかけて、ついていくつもりでいます。むつかしい言いまわしや、いささかのよみ書き、学問は、亭主の喜ィさんよりは堪能かもしれませんが、お鶴さんは、そんなことは気にもとめていません。彼女の考えることは、祝言の翌朝、喜ィさんより早くとびおきて、「白米のありかはいずくなりや」と聞き、ねぎ一わ買うにも「わが君の御意に召すや召さぬや、伺うあいだ、しばらく門前に控えておじゃ」と喜ィさんを大切にすることだけです。お鶴さんの結婚こそ、最もやさしく美しく、プリミティブな強い結びつきのような気がします。
浅茅(あさじ)が宿
わが国の古典文学の中で、いちばん美しく、いちばん悲しい”愛の物語”は、と問われれば、私はためらわず、上田秋成の「浅茅が宿」を推すでしょう。
この短編小説を読んだあとのふかい感動は、すぐれた長編の大河小説「源氏物語」五十四帖にも比敵します。
上田秋成は、享保十九年(一七三四年)に大阪で生まれ、七十六歳で、京都で死んだ文学者です。その出目は定かではないのですが、早くに富裕な商家に養われ、自由に学問・文芸に遊ぶことのできる少・青年時代を過ごしたことは、秋成にとって、たいへん、幸せでした。その才能を大いにのばせたからです。
彼は気難しく、偏屈な人のように、伝えられていますが、それは、心があまりにもデリケートで、生一本だったからではないでしょうか。彼の小説を読むと、至純な心の主人公たちが美しく描かれていて、作者そのひとと重なります。あまりにも頭がよく、俊敏明察の人であった秋成は、世間の大方の人の多欲、通俗、蒙昧(もうまい)に堪えられなかったのでしょう。
「浅茅が宿」は「雨月物語」という短編集の中に収められている一篇です。彼の三十なかば、脂ののり切ったころの作品です。
もとの話は中国の「剪燈新話(せんとうしんわ)」にあるお話ですが、秋成は、日本の室町時代の話に作りかえ、美しい雅文調の小説に仕立てました。
下総(しもふさ)の国に、勝四郎という男がありました。京へいって商いをして家をお輿し、身を立てようと志し、妻の宮木に、しばしの別れを告げます。

宮木は美しい「人の目とむるばかりのかたちに、心ばへも愚かなら」ぬ女でしたが、夫が他国へゆくのを心細がり、「あしたに夕べに忘れ給はで、はやく帰りたまへ。命だにとは思ふものの、あすを頼まれぬ世のことわりは、たけきみ心にもあはれみ給へ」ながらに夫を送り出します。もちろん勝四郎も秋風立つまでには帰るつもりでした。
しかし、世は戦国時代の幕明け、諸国動乱のころでした。関東はたちまち、戦に巻き込まれました。里の女わらべは散り散りににげまどい、宮木もとほうにくれます。
夫は秋をまて、といった。だからそのころまでは、と頼みにして心ぼそく暮らしていましたが、そのうち婢女(はしため)も去り、たくわえもつき、年もくれました。
そのころ、夫の勝四郎も、京の戦乱にまきこまれていたのです。戦火は、相愛の夫の妻をへだててしまいました。勝四郎は、旅の途中、病に伏し、あるいは放浪し、「七とせがほど夢のごとくに」すごしてしまいました。
「古さとに捨てし人の消息をだに知らで、忘れ草おひぬる野辺に長々しき年月をすごしけるは、まことなきおのが心なりける物を」勝四郎はどんなことをしても故郷に妻を探そうと決心し、やっとのことで帰りつきます。日は早や西に沈み、「雨雲はおちかかるばかるばかりに暗」かったのですが、ようようたずねあてたわが家に、幽鬼のようにやせおとろえた妻はいました。
勝四郎は別れてからの辛苦を涙ながらに語れば、妻もまた、七年の長いあいだ、みさおをたててまちつづけた心を語り、「今は長き恨みもはればれとなりぬることのうれしく侍(はべ)り」と泣きつつ、ともに再会のよろこびに夜のふけるのも忘れました。
勝四郎はふと目を覚ました。こはいかに、荒れはてたむぐらの庭に、朽ちたあばらや、傍らに臥した妻の姿はなく、塚だけが残っています。卒塔婆(そとば)の文字も消えがちに「さりともと思ふ心にはかられて、世にもけふまでいける命か」ゆうべの妻は、妻の霊だったのです。相逢うたましいが、冥界(めいかい)から風にのってやってきたのでした。
勝四郎は塚の上をつかんで泣き伏します。
秋成は、至純の愛は、たえず、死とうら表に貼り合わせになっていることを、いいたかったのだと、私には思えます。人間至高の愛は、死との調合しなければ、完成しないのだと、理想家の秋成は夢見ていたのでしょう。
浮きあぶらの国
「古事記」という本ほど、私たちをふしぎな、ゆめごこちに誘うものはありません。
中世の本はすこし読み慣れてくると、その文体の感覚が、現代とあんまり変わっていないような気がされます。谷崎潤一郎の作品などに、私はことに「源氏物語」のもつ口吻(こうふん)そのままを感じとります。
それゆえ、王朝小説は、私には、ちかしい気がするのです。
でも、「古事記」の文体は、まあ、どう言えばいいでしょう。
難解ではないのですが、なんとなく肌になじまぬ晦渋(かいじゅう)さ、神秘で、おそろしく、妖しく、呪術(じゅじゅつ)的で、まるで冥界から落とされた死者のたよりのような、ふしぎな匂いがたちこめています。
たとえば、比喩(ひゆ)の、自由自在な発想のたのしい斬新さ。美しい女を表現するのに、その白い腕(かいな)は大根にたとえられました。すらりとした背は戦士の盾に、白くそろえたきれいな歯は椎や菱の実に、ういういしい少女や新妻は若草に、そして悄然(しょうぜん)とひとり泣く女の姿は、山のひともとススキに。
ちょうど、小さな子供たちがときおり、思いがけぬことを言って、大人をビックリさせるような、そういう、手の切れそうな素朴で新鮮な文章に、たくさん出会います。
私の好きな部分は、上巻の冒頭です。
「天地(あめつち)のはじめて発(ひら)けし時、高天(たかま)の原に成れる神の名は、天之御中主神(あめのみなかぬしのかみ)‥‥」
という、そのひとつづきです。
日本の国のはじまりから、ページはひらかれます、「あめつちのはじめてひらけしとき」という荘重な文章は、まさに、民族がはじめて生まれ、その国が神の手でつくられてゆく一大叙事詩の冒頭にふさわしい重みと、しかもさわやかさが感じられます。アメノミナカヌシノ神というのも、いかにも天の中心、宇宙をつかさどる主宰神たるに相応しい、厳粛な、おん名です。この神の次に高御産巣日神(たかみむびのかみ)、神産巣日神(かみむすびのかみ)の神々が生まれられ、「此の三柱の神は、みな独り神と成りまして、身を隠したまひき」独り神たちはまだ天上界の漠々たる世界にいられて、地上へは降りたまわぬのでした。
「次に国稚(わか)く、浮きし脂の如くして、久羅下(くらげ)なすただよへるとき、葦牙(あしかび)のごとく萌(も)え騰(あが)るものによりて成れる神の名は、宇摩志阿斯訶備比古遅神(うましあしかびひこぢのかみ)、次に、天之常立神(あめのとこたちのかみ)」

国はまだ、水に浮んだ脂のように、また、水母(くらげ)のように漂っていました。天も地もいまだ分かれず、混沌としていました。そのとき生々たる気が、かすかにたちのぼり、葦の芽のように、芽がふき出たのです。あらたな神の誕生でした。
しかし、この神々も、まだ天上界にとどまっていられました。やがて、雲が生まれ、野が出来、野には泥や砂も生まれました。そして最後に、やっと、男神と女神が出来たのです。
天界の神々は、男女の神、伊邪那岐(いざなぎ)、伊邪那美(いざなみ)に、「このただよへる国を修め理(つく)り、固め成せ」と命じられます。天の沼矛(ぬぼこ)を下さいました。
「故(かれ)、二柱の神、天の浮橋に立たしてその沼矛を指し下ろしてかきたまへば、塩こをろこをろに、かきならして引き上げたまふとき、その矛の末(さき)よりしたたりおつる塩、累(かさ)なり積もりて島と成りき。是れおのごろ島なり」
二神は、日本神話のアダムとイブなのです。天の浮橋は、天界から地上へむすぶ、虹だったのでしょうか。二神のかきまわす矛さきから、滴る雫が、きらきら光ってこりかたまる、美しいイメージが浮かびます。二神はその島に降り、やがて、新婚の八尋殿(やひろどの)をたてて、日本の島々を次々と生んでゆきます。これが国生みの神話なのです。
浮きあぶら、水母の如き国が、こうして固まって天界と地上に分たれました。葦の芽のように人間たちは神々の末から分れ、ふえました。古代の人々の敬虔(けいけん)でしかも誇りにみちた国生みの言い伝えにそむかず、日本は、天地生成のときから美しい風光にめぐまれた国なのです。美しい神話の国なのです。
おさん
「うたひの本は近衛流、野郎帽子はわかむらさき」ときまっていますが、そのように、「悪所ぐるひの身のはては、かくなりゆくと定まりし‥‥」
天満に店を張る紙屋治兵衛は。妻子ある身でありながら、曾根崎の遊女、小春におぼれ、はてはお定まりの、店もかたむき、親類に意見され、妻子も離別されようという運命におち入りました。
それでも治兵衛は、小春を思い切れません。小春もまた、そういう悪所の女でありながら、純情でやさしく、美しく、心から治兵衛を愛しています。
それゆえ、彼女は治兵衛の妻のおさんから、どうぞ夫と手を切ってほしい、このままでは二人は心中するばかり、「女の相身たがひごと、切られぬところを思ひ切り、夫の命をたのむたのむ」と書きくどいた手紙をもらい、衝撃を受けます。そうして心ならずも、恋しい治兵衛に愛想尽かしをするのでした。
治兵衛はうつうつとこたつに蒲団をかぶっています。「まだ曾根崎を忘れずかと」おさんは呆れながら引きのけると、治兵衛は泣いているのでした。おさんは思わず、かきくどきます。
「あんまりぢゃ治兵衛殿。それほど名残惜しくば誓紙書かぬがよいわいの。をととしの十月中のゐの子に、こたつあけた祝儀とて、まあこれここで枕ならべてこのかた、女房のふところには鬼が住むか蛇が住むか、二年といふもの巣守にして」ようやく、夫婦らしく家へ戻って来てくれたかと思えば、もう小春を思うて泣いている。

「ほんとにむごいつれない、さほど心残らば泣かんしゃんせ、泣かしゃんせ、その涙がしじみ川へ流れて、小春の汲んで飲みゃろうぞ、エ、曲もないうらめしや」と膝にだきついてかきくどきます。
近松門左衛門の書いた「心中天の網島」というお芝居に出る女房のおさんは、貞女、と昔からいわれていたタイプですが、門左衛門は、おさんに熱い血と心を与えました。おさんは、身も世もなく、夫の愛人の小春を嫉妬しているのです。身を投げてとりみだし、物狂おしいまで、夫を責めるのでした。型通りの貞女ではないのです。
治兵衛は弁解します。ちがう、これは悔し涙なのだ、あの心変わした売女など、もう何の恋しいことがあろうか、あの小春を、憎らしいべつの男がうけ出すらしい、さぞおれのことを金につまったあげくの果てと、大阪中に笑うていいふれるであろう、問屋中のつきあいにも男が廃る、それが口惜しい、と無念の涙をこぼすのでした。
おおさんははっとします。
「いとしや小春は死にゃるぞや」
治兵衛は嘲笑い、「ハテサテなんぼ利発でもさすが町の女房ぢゃの。あの不(ぶ)心中者
なんの死なう。灸するゑ薬のんで命の養生するわいの」
「いやさうではない、わしが一生言ふまいとは思へども、かくしつつんでむざむざ殺すその罪もおそろしく大事のことを打ち明ける」
とおさんは手紙で小春をくどいたことを治兵衛にうちあけ、
「ア、 悲しいこの人を殺しては、女同志の義理立たぬ。まづこなさん早ういて、どうぞ殺
して下さるな」
と夫にすがりつき、泣き沈みます。
おさんは商用にとりのけてあった金を出し、さらに箪笥から衣類をすべてとり出して、
「わたしや子供は何着いでも男は世間が大事」
小春を受けだして男の意地を見せて下さんせ、と治兵衛にすすめます。
おさんは、自分の立場など考えられないのでした。あんなに夫を愛していた小春が、夫を思いきり、ほかの男と添うというのは、小春が死ぬ決心でいるからにちがいない。小春の命をとりとめなくては‥‥。
また、夫が、社会の場で、問屋仲間のつきあいで、金に困って、惚れた女を人に取られて恥かかされてはならぬ、と、夫の立場でばかり考えます。もし小春が夫に受け出されたら自分は「子供のうばか、ままたきか、隠居なりともしませう」と泣くばかり、治兵衛は妻のやさしい心根に返す言葉もありません。
「あまりに冥加(みょうが)おそろしい、この治兵衛には、親の罰天の罰、仏神の罰はあたらずとも女房の罰」があたると心で拝みつつ、それでも、治兵衛は、小春と心中しなければならぬ成りゆきでした。おさんのような美しい心の女房をもちながら、やはり死なねばならなかった治兵衛に、作者は人間のふかい業をかいまみせてくれます。それにしても、おさんは貞女ではなく、「日本のマリア」、観音さまのような女です。
誇りたかき男
王朝の貴族といえば、柔媚(じゅうび)軟弱の人、という印象が浮かびます。
また事実、藤原道長の全盛時代の貴族たちはそうでした。彼らは、天下第一の権力者、道長の前に摺伏(しょうふく)し、彼の意を迎えるのにけんめいでした。
ところがその中でただ一人、道長を恐れずにも堂々と対等に渡り合った、気骨ある男がいました、
それは、かの「薄幸の皇后」定子(ていし)の宮の弟にあたる、権中納言(ごんちゅうなごん)、藤原隆家卿です。
私には、この隆家が、とても男らしくて魅力があるのです。
この時代のことを書いた、歴史物語「大鏡」は、権力の座をめぐって争う高級貴族たちの性格を一人一人、じつに巧みに書き分け、凡百の小説の及ばぬ、すぐれた面白さをもっています。
隆家は若い時から、やんちゃ若様、あばれん坊公達(きんたち)、といわれた青年でした。兄の伊周(これちか)は、それに反し、おだやかで心優しく、優柔不断な貴公子だったようです。この兄弟の人生スタートは、かがやかしい、恵まれたものでした。
父の、中(なか)の関白・道隆は天下第一の人として世に君臨し、兄弟は若くして高位高官にすすみました。姉の定子皇后は、一条帝のおんおぼえもめでたく、のちには第一皇子敦康親王さえ、御生誕になったのです。ゆくゆくは次代の帝、そうなれば、伊周・隆家兄弟は、皇室の外戚(がいせき)・天皇のおん叔父として権力をふるえる、それが一家の政治的青写真でした。
思いのほかの事態が出来(しゅったい)しました。父の道隆が死に、そのあとの権力の座を当然、長男の伊周がおそう所を、父の弟、道長にさらわれたのです。道長はこの日を、虎視眈々と待っていたのです。伊周兄弟は忽(たちま)ち権力の座から蹴落とされてしまいました。
あまつさえ、頼みにする定子皇后は世を去られ、新しい皇后は、道長の娘、彰子(しょうこ)でした。どこまで道長は運がつよいのか、彰子中宮には、つづけて皇子が二人も生まれたのです。
兄の伊周は、気のよわい男らしく、皇子誕生の喜びにわく道長邸へ、のめのめと、お祝いに出かけたりしています。
隆家は、さぞ、そんな兄を、歯ぎしりして悔しがったことでしょう。
伊周は、道長にあえば、いつも貫禄負けして、おじけづき、他愛ない勝負ごとにさえ、わざと負けたりする人でした。

しかし隆家は、決して政敵に弱味を見せないのです。
それは三条帝の大嘗会(だいじょうえ)の御禊(ごけい「ご即位ののち、新穀で以て天皇が神々を祭られ、そのためのみそぎをされる儀式」)の日でした。
隆家はことさら、きらびやかに装いおい立てて出仕したのです。
三条帝のご即位は、大きな意味がありました。というのは、ご即位と同時に、皇太子が定められるからです。それは道長一派の策動によって、彼の外孫・敦成親王ときまりました。伊周・隆家兄弟は、これで、皇室の外戚として政権を握るチャンスは、永遠に失われたのです。そういう折の、儀式の日でした。
「人の、この際(きは)は、さりともくづほれ給ひなむと思ひたりし所を、違(たが)へむと思(おぼ)したりしなンめり」
人々が、この際、いくら隆家卿だといっても、打撃をうけてしょんぼりせずにはいるまいと、予想している、それを覆してやろうという意気込ごみだつたのだろう。――「大鏡」の作者は「さやうなる所のおはしまししなり」――そんな、意地っ張りな所のおありになる方だった、と隆家のことを、「男の好意」ともいうべき口吻(こうふん)で書いています。
慣習では、節会(せちえ)や行幸(みゆき)の供奉(ぐぶ)には掻練(かいねり)がさね(紅(くれない)の、裾長く引き衣)は着けないことになっているのに、それを着こみ、その下に、
「単衣(ひとえ)青くて着けさせ給へれば紅葉襲(もみぢがさね)にてぞ見えける。表(うへ)の御袴(はかま)、竜胆(りんどう)の二重織物にて、いとめでたく、けうらにこそ、きらめかせ給へりしか」
人目をそばだてるような美々しき盛装をして、意気軒昂(けんこう)、隆家の心の中には、(負けるものか)という負けじ魂が烈々と燃えているのでした。
「いみじう魂(たましひ)おはすぞ、世ノ人に思はれ給へりし」
そういう隆家を、政敵の道長も、一目おかずにはいられませんでした。道長邸での遊宴には、「かやうの事に権中納言(隆家のこと)のなきこそ、なほさうざうしけれ」――どうもやっぱり、宴会には隆家がいないと、物足りなくて淋しいよ、といって、わざわざ使いをやって招くのでした。一座に酒が廻って人々が乱れ、衣の紐を解いてくつろいでいるときに、隆家はやってきました。隆家には気遣いされるとみえ、酔った人々もあわてて居ずまいを正したりしています。
主の道長は声をかけました。
「とく御紐とかせ給へ。事破れ侍(はべ)りぬべし」
ともかく早いこと、お召物の紐を解いておくつろぎ下さい、座の興が冷めてしまいます、と促すのですが、隆家がためらっていますと、
「公信卿、後より、『解き奉らむ』とて寄り給ふに、中納言殿、御気色悪(みけしきあ)しくなりて、『隆家は不運なることこそあれ、そこたちにかやうにせらるべき身にもあらず』と荒らかにのたまふに、人々の御気色変り給へる‥‥」
座の一人、公信卿が、隆家のうしろへ廻って、お解きしましょう、と近寄りました。そのなれなれしい態度には、悪気はないのですが、隆家のプライドを刺激しました。政争に破れた不遇の身ではあるけれども、志まで枉(ま)げて、政敵の下風には立たないぞ、という気概が隆家にはあったのです。招きに応じて宴に臨んだのは、対等の意気込みだったのでした。
それなのに、あるじに追従する如き、相客のなれなれしさが隆家には腹に据えかねたのでしょう。〈私は不運な身だが、そこもとたちに、こんな扱いをされる身ではない〉と荒々しくいい放ちます。人々は驚き酔いも醒めてしまいました。天下第一の権力者の前で居直って一喝するような男は、はじめてでした。ただごとではすむまいと一座の顔色も変わりました。だが、さすがに道長は老獪(ろうかい)な政治家です。一座の空気を収拾する気力も度量も充分でした。
「入道殿(道長のこと)うち笑はせ給ひて、『今日はかやうの戯(たはぶ)れごと侍(はべ)らでありなむ。道長とき奉らむ』とて寄らせ給ひて、はらはらととき奉らせ給ふに、『これらこそあるべきことよ』とて、御気色直りて、さしおかれつる盃取りて給ひて、数多度(あまたび)召し、常よりも乱れ遊ばせ給ひける様など、あらまほしくおはしましけり」
道長は明るく笑い、〈今日のところは、そういうご冗談はなしにいたしましょう、ささ、みなもくつろいで居る所ですぞ。中納言どの、御召物の紐は私がお解きしましょう〉と、気軽に寄って、はらはらと解きます。
〈や、こういうことなら、べつに否やはありませんな〉と隆家は機嫌を直し、前に据えられた盃をとり、何献もかたむけ、ふだんよりも酩酊して歓をつくしました。
「大鏡」の作者は、――男らしく、好もしい態度だった――とほめています。「殿もいみじうもてはやし聞こえさせ給ひけり」道長も非常に心を使って接待したのでした。
そんな隆家でしたから、不遇の時代も世に重く思われ、訪問客は絶えないほどでした。
目を患ったのは三十代半ば、その治療をかねて赴任した九州で、隆家はさらに大きな事件にあいました。刀夷(とい「今の沿海州辺の国」)の賊の来襲です。
「筑紫にはかねての用意もなく、大弐どの(隆家の官命)弓矢の本末をも知り給はねば、いかがと思しけれど、やまと心かしこくおはする人にて」九州中の武士はむろん、太宰府の文官まで総動員して戦い、刀夷の賊をうち破ることができました。隆家は早速、京の朝廷へ、戦功ある将兵の名を奏上し、朝廷はそれによって褒賞を与えました。更に賊の捕虜になっていた住民を連れた帰った新羅(しらぎ)の使いには、黄金三百両を与えてねぎらうなど、彼の政治的手腕は抜群のものでした。
「まつりごとよくし給ふとて、筑紫の人さながら従ひ申したりけり」
「大鏡」の作者は、道長も、隆家をみとめ、その人物を愛していたのだというふうにほのめかせています。それはそのまま、作者の、隆家に対する好意なのでしょう。
隆家は悲運にくじけず、誇りをもって生き抜きました。定子皇后が、薄命ながら背の君のみかどの愛を一身にうけて亡くなられたのを、女の命の華とすると、弟の隆家も、逆境にあって意地をたて通し、男の華を咲かせたといえるでしょう。
黄泉比良坂(よもつひらさか)
男と女の愛のかたちについて、日本神話はゆたかな示唆と暗示をふくんだ、おもしろいお話を持っています。
「古事記」によれば、最初の男神。女神のイザナギ・イザナミは、あたまの国を生み終えたあと、死で以て、相愛の仲を引き裂かれました。イザナミは、火の神を生んだために焼け死んだのです。
イザナギは、愛する妻の枕辺にはらばい、足元にはらばって泣きました。そして妻が地下の死者の国へおもむいたあともあきらめきれず、そのあとを追ってゆきました。
この形の神話は、世界のさまざまの国にあります。ギリシャ神話の「詩人オルフェウスとその妻エウリデケ」の物語もそうです。オルフェウスは死せる妻をもとめて冥界に下り、妙(たえ)なしらべの歌でよみの王の心をうごかし、ついに妻を連れ戻すことを許されます。しかし地上へでるまで妻を振り向かないという条件がついていました。二人はあと先になって黙々と、死者の国を去りました。あと一歩で地上というとき、夫はうれしさのあまり、思わず妻を振り向きました。たちまちエウリデケは連れされました。〈あなた、さようなら‥‥〉という声を残して‥‥。
シュメール神話にも「女神イシュタルと、若き夫、タンムズ」の物語があります。こちらは女神が、死んだ夫を追って冥界に下り、さまざまな試練にうちかって、ついに首尾よく、よみの女王からタンムズを取り返します。二人が地上へ戻ると春は再びよみがえり、穀物はみのり花咲いたという、枯死復活の美しい物語です。
では日本神話のイザナギ・イザナミたちはどうしたでしょうか。
イザナギは死者の国へ下り、妻にあって、かきくどきます。〈お前と作った国はまだ出来上っていないじゃないか、かえってきておくれ〉
イザナミは困って申しました。
「悔しきかも、速(と)く来ずて。吾(あ)は黄泉戸喫(よもつへぐひ)しつ」
残念ね、というより、むしろ、恨めしいわ、もっと早くいらとして下さらなくて、というようなふかい嘆きの意味でしょうか。よもつへぐいは、黄泉の国で煮たきしたたべものをたべることです。これをたべるとうつし身の人間にはもう戻れないのでした。イザナミは、でもむろん愛する夫と共に地上へかえりたいと願います。〈冥界の神々に相談してみますから、そのあいだ、ごらんにならないでね――〉

長い時間がたちました、イザナギは待ちきれませんでした。昔も今も、男は女に、ちょっと待っていて、と言われるとかえってせっかちになります。彼は髪にさした櫛の歯を一本かいてそれに火をともし、闇の中をさぐると、そこには妻が横たわっていましたが、これは何ということ、あの美しいイザナミの体は腐って「うみ沸き、うじたかり」恐ろしい雷神がうずくまっていたのです。
イザナギは仰天して逃げました。彼は愛も忘れ。恋の記憶も投げ捨てて、ひたすら走り去りました。イザナミは怒り狂いました。「吾(あれ)に恥見せつ」昔も今も、しばしば女のプライドは、恋にうちかちます。彼女は愛が燃えるような憎しみに変化するのをおぼえました。すぐさま彼女は黄泉の国の悪霊たちに命じてイザナギを追わせます。
イザナギは必死に逃げ、ついに冥界と地上の国とのさかいの、黄泉比良坂にたどりつき、千人がかりでやっと動かせるような大岩をまん中に据えて、追手を防ぎました。自身追いかけて来たイザナミは悔しげに、〈こんなことをなさるのなら、あなたの国の人民を一日に千人殺しますよ〉と叫びます。イザナギはこれに答えて、〈よろしい、それなら私を一日に千五百人生まれさせよう!〉
相愛の恋人たちは、いまは恐怖と嫌悪と憎しみに身をふるわせ、はげしい応酬をつづけるのでした。
愛と憎しみは双面神であることを、この日本神話は鮮やかに解き明かして見せてくれます。イザナギ・イザナミは、それぞれ男と女の原型なのです。神は、彼と彼女の鋳型から、私たち、男や女を造りたもうたのです。
つづく さめやらぬ夢