「蜻蛉(かげろふ)日記」はいかにも女のすなる書きもの、という気がします。なぜなら、女は、男と女との愛憎関係にしか、本質的な関心をもたないのではないかと思えるからです。
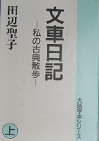 田辺聖子著
田辺聖子著
魅惑の男
これは、千年の昔に生きた人の人妻が、その夫との長年の夫婦生活の相剋(そうこく)を、綿々とつづった、日記風物語ですが、ほんとに男女関係のエッセンスのような、おもしろい本です。文章は、「源氏物語」より古雅で難解ですが、文学的質度のたかさからいうと、源氏より上かもしれません。
作者の名は右大将・藤原道綱の母、とあるだけで、呼び名はいまも分かりません。かりにかげろふと名づけましょう。
夫の名はわかっています。藤原兼家(かねいえ)、のちに関白にまでなった人ですが、辣腕(らつわん)の政治家で、おのが野望をとげるためには兄弟、一門をも仮借なく葬り去るほどのすさまじい男です。
「蜻蛉日記」をよむたのしみは、また、この男を知る楽しみでもあるのです。じつをいいますと、私は、「蜻蛉日記」にあらわれた兼家という男に、すっかり魅惑されているのです。
強引でずうずうしく、大胆奔放で、色好みで、しかもやさしく、たのもしい所もあるといった‥‥端倪(たんげい)すべすらざる、したたかものなのです。
この当時、男は重婚を許されています。妻たちはそれぞれの親の家で、夫の訪れをまつだけです。子供が生まれれば、妻の手元で育てられます。夫は自分の家にはどの妻もおかず、気の向くままに、何人もの妻の家に出かけます。

妻の地位には格差はありませんが、そこは人間、おのずから愛情の深浅によって親疎ができます。
かげろふは美女で、有名な歌人でもある、つまり才媛(さいえん)でしたが、結局は、この時代の女のつねの、嫉妬に身をやく運命から逃れませんでした。
兼家は他の女の元にいくときも、平気で彼女の邸の前を前駆(さき)に警蹕(けいひつ)させ、供を従え、牛車(ぎっしゃ)で悠々とすぎてゆきます。邸の下男たちが「中門おしひらきてひざまづきて居るに、むべもなくひきすぎぬ」という仕打ちなど、平気でする男です。
だから、たまに夫が来るとかげろふはありったけの怨み言います。果ては「岩木のごとして明かしつれば」夫も怒って帰ってしまう、そうかと思うと時には侍女の目も恥ずかしいほど、戯れたり、あるいは妻が怨みごとをいうあいだ、眠ったふりをしたりする、ずるい男です。また時には雨の日に来たりして、さすがに堅い妻の心もとけるのですが、明日も来るからね、という夫の言葉を信じて待つうちに、半月、ひと月、たよりもないという、‥‥そうです、律儀で誠実な女とっては、地獄の苦しみともいうべき夫婦生活なのでした。
兼家が急病で倒れ、ほかの女の邸へかつぎこまれた時がありました。彼は使者を出して、夜半こっそり、かげろふをよびよせます。
かげろふは本邸の夫人に遠慮がありましたが、兼家がかさねて、車までよこして促しますので、出かけました。
暗い縁にかげろふは佇んで探しておりますと、〈ここにいるのが見えないか〉と夫が手をとって導き入れてくれました。
そうして、いろいろのことを夫婦らしく語り合い、兼家はやはり、一ばん愛しているのはお前だったと病の床で告白するのです。まだ魚など食べていないのだが、お前今夜来るので一緒に食べようと思って待っていた、と、病後はじめての食事の箸を、かげろふと共にとります。
なんという可愛い男のセリフでしょう。積年の閨怨(けいえん)も雪のように溶け、かげろふは男にひしと心がよりそうのでした。
と、思うふと、病が癒(い)えるが早いから、色ごのみの兼家はもう新しい愛人を作ったりするのです。
かげろふは嫉妬の苦しみに負け、寺へ入って尼になろうと決心しました。それを力づくで連れ戻したのは、やっぱり、夫の兼家なのでした。西山の寺にこもり、どんな人のいさめや忠告にも耳をかさず、出家をかたくなに念じていたかげろふのもとに、兼家はまっすぐ、やってきます。散ったものを取り片付け、袋に入れ、車に積ませ、仕切りをとりはらい、〈さあ、仏においとまごいをしろ〉と冗談をいって、かげろふの手をとり、笑いながらむりやり車に押し込むのでした。彼は彼なりのやりかたで、かげろふを愛していたのです。
かげろふは中年になり、ようやくに、嫉妬や妄執(もうしゅう)の業苦から、いささかときはなたれて、夫やわが身を見るようになりました。思いがけなく兼家がたずねてくれた夜のあけ方‥‥。
「雨いとのどかにふるなり。格子などあげつれど、れいのやうに心あわただしからぬは、雨のするなめり」
いつもは朝になるとあわただしく帰る兼家が、けさはゆっくりしている。それは私への情愛からではない、きっと雨のせいだろう――かげろふはそんな風に考える女になっていますが、しかし、その彼女の眼からみても、中年に達した夫の男ぶりは水際立ったものでした。
共の男たちは来たか、などといいつつ夫は起き出して、なよらかな直衣(のうし)、よきほど柔らかな練絹(ねりきぬ)の袿(うちぎ)を下に着こみ、帯をなかば垂れつつゆるやかにしめて歩いてきます。侍女たちが、朝餉(あさげ)はいかが遊ばしますか、とお伺いをたてますと、いつも食わないのだから、べつにいい、と、きげんのいいようすも、おのずから威と気品がそなわり、美しい男なのです。
「太刀を」
といいますと、息子がとって膝まずいて捧げるのでした。のどかに縁をあるいて庭を見やり、――庭を雑然とさせてしまったなあ、――などといいます。やがて車がさしよせられ、夫はゆっくり乗り込みます。中門から出た車の、前駆(さき)をおう声も、かげろふをなつかしく、たのもしく、慕わしい心地にさそうのでした。
このとき兼家四十四歳、大納言という高官に加えて大将に進み、自信と威厳にあふれて男の魅力をあますなくそなえています。でも、そんな魅力的な夫の訪れもごく、たまのことでした。
「そののち、夢の通ひ路たえて、年くれはてぬ」
夫の訪れはいよいよ、間遠(まどお)になり、たよりも通り一ぺんのものになりました。ただ息子の道綱のみ、父と母の邸をゆき来してわずかに消息をもたらし、縁をつないでいます。
いまは道綱も青年となり、公達(きんだち)の一人として世に出る年頃でした。かげろふは、息子の将来にのぞみをつないで生きています。
でも来しかたをふりかえったとき、はたして私の一生は何だったのかとかげろふは自問せずにはいられませんでした。秋冬、物思いにくれてはかなくすぎました。そしていつも、餓(かつ)えていました。兼家への恋が満たされないことが、彼女の心を飢えさせていたのです。かげろふは長い苦しみの半生をかえりみつつ、筆をとってかきつづけます。
「…ふりける雪、三四寸ばかりたまりていまもふる。簾(すだれ)をまきあげてながむれは、『あな寒(さむ)』といふこゑ、ここかしこにきこゆ。風さへはやし。世の中、いとあれなり…」
夫を憎みながら愛し、愛しつつ憎み、そのくせ、かげろふは夫に恋していたのです。
妻に恋されるほど、兼家は魅力ある男なのでした。
しかし私は、彼女は石女(うまずめ)ではなかったか、あるいは子供を産んでも、手許から放してしまって、子供縁のうすい女ではなかったかと思っています。
なぜなら、彼女のエッセイ集「枕草子」の中にある、子供の描写はすばらしいからです。光り輝いているからです!
イギリスの女流作家、キャサリン・マンスフィールドも病身で子供を持たなかった女(ひと)でした。彼女の子供の描写もまた、じつに生彩を帯びています。
私は、現実に子供を持てば、こうまで愛らしさを端的に描写できないのではないかといつも思います。
「枕草子」の名高いくだり、「うつくしきもの(愛らしいもの)」の幼い子供の可愛らしさはどうでしょう。
「二つ三つばかりなるちごの、急ぎて這(は)ひくる道にいと小さき塵(ちり)のありけるを、目ざとにみつけて、いとをかしげなる指(および)にとらへて、大人などにみせたる、いとうつくし」
またおかっぱあたまの童女が、目の上までかかった髪を、あたまをかしげてふり払って物を見ている愛くるしさ。美しい赤ちゃんをちょっと抱いて遊ばせてあやしているうちに、とりついて寝入ってしまうその愛らしさ。
彼女は赤ん坊や幼な子のやわらかな肌、愛らしい笑顔、声を、物ぐるおしいまで、飽かずに賞(め)で、慈しみます。
「こころときめきするもの。ちご遊びする所の前、わたる」
「つれづれなぐさむもの。三つ四つのちごの、ものをかしういふ」
その片言も、そのしぐさも、彼女にとってつきぬ愛執と、新鮮な好奇心をかきたてるものでした。
その愛情や執着、好奇心は、「ちご」たちが自分のものでないから、なのです。
自分で子供を持つ人は、決して、こういう第三者的な好奇心をもちますまい。清少納言の、愛情にあふれた観察は、いきいきしていればいるほど。ヒトの子供をみる女の目なのです。
「いみじう白く肥えたるちごの二つばかりなるが、二藍(ふたあゐ「染めの色」)のうすものなど、衣長(きぬなが)にてたすき結ひたるがはひ出たるも、また、短きが袖がちなる着てありくも、みなうつくし」
「八つ、九つ、十ばかりなどの男児の、声は幼なげにて書(ふみ)読みたる、いとうつくし」
棒切れや弓みたいなものを持って遊んでいる小さい男の子も、たいそう可愛い。
「車などとどめて、いだき入れて見まほしくこそあれ」
その愛情には、自分が自由にできない、この愛らしいせつない生きものへの憧憬・羨望の影が、煙のように立ち込めています。
だから清少納言は、子供のいやらしさ、にくらしさも鋭く指摘します。
「にくきもの。物聞かむと思ふほどに、泣くちご」
「見苦しきもの、例ならぬ人の前に、子負ひて出て来たる」
調子づくもの、母親に連れられて遊びに来、他人の部屋の大事なものをさがし出してとりちらかす子供。それを母親もまた制止もしないで、だめよ、などとにこにこしているだけ。こんなのは親まで憎らしい。
憎しげなちごを、親からみると可愛いのか、片言をまねしているなど笑止だ。
これということもない人が、子供をたくさん作っているのも、わずらわしい。
その直截(ちょくせつ)な辛辣(しんらつ)さ。この口ぶりはもう、まるで男性のものです。
あの、母になった女たちがもつ、子供に対してとめどなくのめりこんでゆくようなあいまいさ、「これこそ我が骨の骨、肉の肉なれ」というからみつくような一体感のもつ妖気(ようき)は、彼女の文章にはありません。「枕草子」は颯爽(さっそう)たる、石女の文学だったのです。
ことに時代小説の女の子の名前が美しく私は好きでした。「天兵童子」に出てくる少女は千尋(ちひろ)だったかと思います。千葉省三氏の
「陸奥(むつ)の嵐」は狭霧(さぎり)でした。吉川英治氏の「左近右近」には笹枝という少女が登場します。これも武家娘らしい、きりッとした名前です。
汀(みぎわ)は「大陸の若鷹」でしたか? 渚、桔梗、露路、彼女たちはみんな、きれいな名前を与えられて、心も姿もうつくしいのです。ことに「咲椰子(さくやこ)という名前は、大好きでした。ずっとあとになってそれは「古事記」の「木花咲椰姫(このはなさくやひめ)」からとられたとわかりました。古事記にも美しい女名前がたくさんありますが、それらはたいてい悲劇のヒロインです。求婚者である大王を拒み、その弟に恋してしまった女鳥(めどり)の姫、兄と愛しあって罪におちた衣通(そとおり)の姫。この姫は、あまり美しいので
「其の身の光、衣(そ)より通り出づれば」衣通姫といわれたのでした。神秘でロマンティックな名です。
ところで、小説の主人公に千尋や狭霧といったきれいな名前が付けられるようになったのはいつからだろうと思っていましたが、これは江戸時代の小説からの系統ではないかと考えました。馬琴(ばきん)の読本にも、あるいは種彦の「偐紫田舎源氏(にせむらさきいなかげんじ)にもあります。
老女には、岩根とか、杉生(すぎばえ)とか、適当な名前をつけられてあります。若い美女には、白縫(しらぬい)、真鶴(まなづる)、花桐、稲船、小百合、紅(くれない)、葛樹(かつらぎ)、朝霧…‥その名さえゆかしく思われます。
秋成の、恐ろしい悲しい、また美しい物語の中にも真名子(まなこ)や、宮木、などといういい名が用いられています。
「萬葉集」にみえる女の名は実名でしょうが、安見児(やすみこ)、手古奈(てこな)、小鹿など、土の匂いがして素朴でいい名です。
けれども、やはり一ばん美しいのは「源氏物語」の巻名でしょう。
昔の大奥女中たちは源氏からとった名で呼ばれることが多かったのです。蓬生(よもぎゅう)、浮船、といったお女中がいました。
桐壺、帚木(ははきぎ)、空蝉(うつせみ)、夕顔、若紫、花宴(はなのえん)‥‥と巻々の名をひろいよみしてゆくだけで心ときめきした女学生のころがしのばれます。艶(えん)に華やかな王朝絵巻が極彩色でくりひろげられていくようで、ふと、西条八十氏が源氏をうたわれた一節が思い出されるのです。
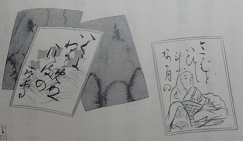
生者必滅、会者定離(えしゃじょうり)
かなしい恋の 花ふぶき‥‥
少し前まで宝塚歌劇の生徒さんたちは、百人一首からとった名前をつけていました。天津(あまつ)乙女さん、雲野かよ子さんなど、すてきな名です。富士野高嶺さん、有馬稲子さん、霧立のぼるさん、蘆野(あしの)もろやさんなど、ほんとうにうまくつけた、いい名だと思われます。
あるとき、若い美しいお嬢さんが、かなもじを紅色に散らし書きして染めた着物を、身にまとっていられるのをみました。それは、「あけぼの」「くれなゐ」という字でした。――まさに、あけぼのもくれないも、若い娘の美しさ、清らかさをあらわす、こよない言葉に思われました。
それで私もまた、そんな美しい言葉をちらし書きして染めた着物を着てみたいと空想しました。おぼろよ、かげろふ、あぢさゐ、あはゆき、はるさめ、なのはな、うぐひす‥‥口ずさむだけで、美しさに酩酊(めいてい)するような言葉がたくさんあります。もし私が時代小説を書くときは、ヒロインたちに字も発音もイメージも美しい、こんな名を与えたいなと思います。
もしかしたら、日本の女が美しかったのは、日本語が美しいかったせいではないでしょうか。日本の若いお嬢さんに、美しい言葉をたくさん知ってほしい気がします。
珠は、神秘な魔力をもち、人々の運命を左右することさえ、しました。
三種の神器の中に「ヤサカニの勾玉(まがたま)」があるのは周知のことですが、神代の昔、尊い神が珠を嚙んで、「吹き棄つる気吹(いぶき)の狭霧(さぎり)に」たくさんの神々をお生みなった、という神話も美しいものです。
大和の橿原(かしはら)神宮の外苑(がいえん)にある大和歴史館には、出土品の勾玉がいくつか展観されています。――私は、古墳の出土品の珠に、ふかく執着しているのです。
勾玉には、ガラス、瑪瑙(めのう)、ヒスイ、石、動物の牙などがあります。
陳列ケースの中にひっそりとただ一顆(か)、おさまっていた小さな勾玉は、ことにも忘れがたいものでした。それは鉛ガラスの、重そうな、女の拇指くらいの勾玉でした。煙のような色、というか、石油色というか、(私は夢色、と呼びたい気がしました。
古代の夢をそのまま、まどろみつづけているような色なのです)灰色ともうすい墨色ともつかぬ、不透明な玉のいろ、それはどんな男、どんな女の肌にあたためられ、その手に慈しまれてきたのでしょうか。千数百年の眠りから醒めて日の光にさらされた珠の色というのは、これはもうガラスではなくて宝玉なのでした。
晴瑯玕(せいろうかん)の管玉(くだたま)というのも見ました。これは古代の玉を趣味であつめていられるTさんという方に見せて頂いたものです。これも誰とも知れぬ古墳から出て、何十年となく人の手から手へ渡ったものらしく、不透明な碧(みどり)いろが、人の心をさそいこむようなとろりした深いもの、この玉はきっと、衣通姫のような美女のうなじにかけられ、その死に際しては愛するものの手で石棺へ入れられたのかもしれません。
あるいはまた、仁徳天皇の御代に記されている、メドリの姫のものか。謀反の罪に問われた。メドリの姫のハヤブサワケの王子は、天皇の追手に殺されました。皇后・ヤタノヒメはメドリの姫の妹ぎみでした。姉の身の上を悲しんで、姫のもたれる珠を奪わないようにと天皇に願われました。天皇はあらかじめ、兵士たちに「皇女のもたる足玉手玉をな取りそ」と命令されたのです。
そののち、宮中の宴会で、人々がむれ集まったとき、皇后は、一人の女の腕輪に目をとめ、あっと叫ばれました。それは、薄幸な、メドリの姫のもちものでした。早速、彼女は捕らえられ糾明されました。その女は、追手の将軍の妻だったのです。
将軍が死んだ姫から「膚(はだ)もあたたけきに剥(は)ぎもちきて、すなはちおのが妻に与へつる」ことがわかり、死罪となるところを、たくさんのタカラモノを差し出して許されました‥‥。
珠に対する物欲と愛執から騒動のおきた話は、安泰天皇のくだりにも載っています。珠は、人々の判断や理性を狂わせる神秘な力を持っていたのでしょう。
山幸(やまさち)、海幸(うみさち)で有名な、ホオリノミコトは、海神の娘、豊玉姫と結婚しました。姫はお子を生まれるとき〈私は人間の身ではありませんから、本来の姿に変じて出産します。どうか、ごらん遊ばさないで〉といわれました。

しかしそう制されると却(かえ)ってミコトは好奇心をかきたてられ、産屋をのぞかれました。すると大蛇が「はひもこよ」っていたのです。姫は怒って故郷の海に帰ってしまわれました。しかし、「恋しき心にしのびずて」歌をよこされるのでした。
赤玉は緒さへ光れど白玉の君がよそひと貴くありけり
髪はみづら、白い衣に金の太刀、珠をつらぬいてうなじにかけた高貴な古代の男の姿が、この歌をよむと、ほうふつと浮かびます。古い勾玉はそんな女のためにいきも吸い込んでするのです。
「高直はつと捕へ、さらに許さん様子もなくじりり乀とつめよせて『命惜しくば助けてやらん、その代わりには下帷子(かたびら)もはぎとって肌をあらはし恥かかせてくれんず』と水原(みはら「女の名」)が寝巻の帯をとき、ぬがせんとなしければ、ぬがじとこなたは争いて、引きあふ中に縫糸の、絶えもやしつらん、かの帯に、ほころび切れてほろほろと、うちよりこぼるる数通の密書‥‥」
あわや、際どい場面が展開するかと思いきや、必ず、しかつめらしい密書や短剣が出て来て、おかしくなるのです。この文章など、江戸小説の一つの典型みたいです。
しかし、お家騒動や政治的陰謀の骨組みをつくり、つまり大義名分をあきらかにし、君臣・親子の義理・道徳をタテマエにしなければ、恋愛や、まして日かげのひそかな乱倫・邪恋などテーマにできない時代でした。小説や戯曲の作家はそのからくりをよく心得ていました。
そして読者や観客も、そのからくりを知って、タテマエとホンネの巧妙に交錯する世界を楽しんだのでしょう。
「摂州合邦辻(せっしゅうがっぽうつじ)」という浄瑠璃(じょうるり)があります。ずつと昔、文楽で「合邦内の段」を見たことがありますが、若い私は、筋立ての不自然、不合理についていけない思いがしました。若さというものは、不合理に対して過酷なものです。
しかしいま人生中歳にして、台本を読み返してみますと、このタテマエとホンネのからくりがよくわかります。
河内国(かわちのくに)の城主、高安家の若くて美しい奥方、玉手御前は、先妻の子・俊徳丸(しゅんとくまる)に恋して、応じられないのに嫉妬し、毒を盛って業病(ごうびょう)の身にしてしまいます。しかしそれは実は、お家騒動を企む悪人から、義理の子・俊徳丸を守る彼女の苦衷(くちゅう)から出た計略で、いつわりの恋をしかけて世の人の目を欺き、俊徳丸を無事、悪人の手から逃れさせるためでした。その証拠には、俊徳丸の業病を医(い)やすには自分の生肝(いきぎも)の血を飲めば効くと、みずから刃を胸に立て、身を以(もつ)て、おのが潔白と義理をあきらかにする、というのが大方の筋です。
しかし、玉手御前が、自分より一つ二つ下の、美しい凛々(りり)しい若殿・俊徳丸にしかける恋の、「いつわり」というにはなんと切なく、もの狂おしいことでしょうか。

それは、タテマエのうちに、蛇(くちなわ)の舌のようにちろちろと仄(ほの)見えるホンネなのです。観客はそのホンネの物すさまじい嵐にまきこまれ、目もくらむここちがして、しばしタテマエを忘れます。
「俊徳様のおん事は、寝た間も忘れず恋ひこがれ、思ひ余ってうちつけに、いふても親子の道を立て、つれない返事かたい程、なほいやまさる恋の淵(ふち)。いっそ沈まばどこまでもと跡を慕うてかちはだし。あしの浦々難波潟(なにはがた)、身をつくしたる心根を、ふびんと思うてともどもに‥‥」
おどろき怒る父、悲しむ母。俊徳丸の怒りと嘆き。
「ヘェ、情けない母上様。‥‥親子の中々に、恋の色のとかほどまで、慕ひ給うは御身ばかりか。宿業深き俊徳に、まだまだ罪を重ねよとか。‥‥道をも恥をも知りたまへ」「涙とともに恨み」む俊徳丸、けれども玉手御前はきき入れません。
「恋路の闇に迷ふた我身。道も法も、聞く耳もたぬ。モウ此の上は俊徳さまいづくへなりとも連れのいて、恋の一念通さで置こふか、邪魔しやつたら蹴殺す」
と、俊徳丸の手をとって引き立て、
「ア、ラ、けがらはし」
とふり切る青年をはなれじやじと追い廻し、俊徳丸のいいなずけの浅香姫が、
「エ、あんまりでござんすわいな」
とささえるのを、「ふみのけ、蹴のけ、怒る目元は薄紅梅、逆立つ髪は青柳の、姿も乱るる嫉妬の乱行‥‥」
とうてい成らぬ恋になのでした。玉手は義理の名分にかくれてホンネの恋をここで明かしてしまったのです。
先妻の子との悲恋、というテーマはラシーヌの悲劇「フェードル」にも扱われています。清らかな心の王子イポリットを、義理の母のフェードル王妃は愛してしまいます。邪恋をみずから恥じ、戒めながらも、あらがいがたい運命の力に引きずり込まれ、王妃・フェードルは破滅します。しかし日本のフェードル・玉手御前の恋は、もっと戦慄的な魅惑を感じさせます。それは義理、忠義のためというタテマエにかくれた、甘美で恐ろしいホンネだからこそ、その不倫のドラマが、人々の心に二百年もの間、共感されつづけてきたのでしょう。
江戸時代には(旧暦)四月一日、十月一日をもって春夏の衣を更(か)えました。いまは四季、かわらぬ風俗ですが、町中いっせいに、衣がぬぎかえられる季節は、ほんとうに、季あらたまるという感じだったでしょう。珠には初夏、風かおえる日、町にははろやかな春着、夏着のあふれるうれしさ。
「人は春服をととのへて高き丘にのぼり、春風春水一時に来るというた」うのです。
ほととぎす。花たちばな。一年で一ばん美しいとき。
蕪村は、この美しい季節に、御手討ちの夫婦」を配したのでした。
私は、この句をことさら秀句とも思いませんが、でも、たいへん好きなのです。
蕪村の句には、たのしいフィクションが多いのです。彼は歴史絵巻風な、物語の一シーンのような句をたくさん作りました。
鳥羽殿へ五六騎いそぐ野分かな
指貫(さしぬ)を足でぬぐ夜やおぼろ月
私は、これらの句から、物語をあれこれ作りつつ、一句また一句とよむたびに、本を一冊読んだような、豊醇(ほうじゅん)な酩酊を与えられます。蕪村の句は、さながら一篇の小説と同じ重みに感じられたりするのです。
御手討の夫婦も、たぶん蕪村の想像でしょう。現実のことではありますまい。
武家方では恋愛は、きついご法度(はっと)です。もし露顕すれば、不義者として成敗されてしまいます。でも、若侍と、可憐なお腰元は、(勘平とお軽のような)いつとなく、恋し合ってしまいました。お家を乱す不義者と、あたまの固い三太夫は声をあららかに詰(なじ)ろうとしますが、やさしい奥方は、かげになり、日向になってかばわれたかもしれません。
〈殿に申し上げます〉と白髪あたまをふりたてて青筋立てている三太夫を、奥方はまあまあ、と抑えて、〈わたくしに任せておきや〉などといわれる。殿様のごきげんのおよろしき時など見計らって、そっと心配りして、よしなにとりなされたことでしょう。怒りっぽい殿さまのことですから、持ってゆき方によっては、どんな大事になったかもしれません。でも怒りっぽいだけに根は単純で善人なので、奥方のとりなしで、〈よきにはからえ〉とおうようにいわれたでしょう。
奥方はそっとお腰元と若侍を、しるべのもとへ落してやったり、身の立つようにはからい、新生活のはなむけを下さったかもしれません。
とび立つ思いのお腰元と、若侍。本来なら二人重ねて御手討ちになっても文句のないところなのに。希望にみちてお邸を出ます。
晴れて二人の人生がはじまります。町は初夏、さわやかな衣更えの季節と同じく、二人もまた、生まれ変わったような人生の第一歩なのです。
「更衣」には、たくさんの句があります。でも有名な「越後屋の絹裂く音や更衣」(其角「きかく」)などよりもやっぱり、私は「御手討の夫婦」と更衣のさわやかな季節のとり合せを、ことに面白く蕪村らしいと思います。
そういえば、「野分」の句も、べつに何が上についてもよいわけです。しかし、「鳥羽殿」ときたとき、これはやはり「野分」という語と、「鳥羽殿へ五六騎いそぐ」という状景とはぬきさしならぬものと感じられます。「おぼろ月」も指貫でなければならない的確さがあります。
蕪村は不義者、いたずらものたちにあたたかい共感をよせ、祝福しています。更衣という、さわやかで美しい季題に配するには、絶対、御手討ちになるべかりし恋人たちでなければならないのでした。
「沙石集」は「古昔物語」と同じように、庶民生活のさまざまのエピソードを集めています。私は、「沙石集」から、よく小説の材料を仰ぐことがあります。ただ、無住はそのつもりで書いたのでしょうが、終わりは必ず、仏道談義、信心のすすめ、で結ばれているところが特徴です。そして、無住の見識はすべて、すぐれて味わい深く、彼がなみなみならぬ「人生の達人」だったことを思わせます。それに、一つ一つの話の面白さは無類で、読んで楽しいのです。文章も、男らしく硬質で、簡潔です。
私の好きなお話は、巻九「君ニ忠アリテ栄(さかえ)タル事」というのです。
ある年、世間でふしぎなことがはやりました。くじで相手をきめて互いに贈り物をすると、不慮の災難(無住は、横災(おうさい)、ということばを使っています)をまぬがれるという迷信です。身分高きもいやしきも、このくじに夢中になりました。
あるお公卿(くげ)さまのお邸でも、くじ引きがあったのですが、当主の殿のお相手を引きあてたのは、なんと、一ばん貧しい、殿にお目通りもかなわぬような身分の侍だったのです。
「不運ノ至リ」と彼は思い、周囲もそう、うわさしました。
男は悄然(しょうぜん)と家に帰り、妻にいいました。
〈長いことお世話になった、死なばともに、と誓いあった夫婦の仲だけれど、もうおしまいだよ。私は出家して世を捨てるつもりだ〉
妻は驚いて問い返します。なぜ、そのようなことを‥‥。この妻も、ささやかな商いをして世をわたる「貧シキ女人」なのです。
男はわけを話します。互いのくじの相手には、それ相当の贈り物をすべきなのです。これが同輩なら適当にごまかせるのですが、殿が相手では、どうしようもありません。見苦しいものでは恥をかき、人に笑われるだけ、りっぱなものを用意しようとすれば資力がない。この上は、あとをくらまし、夜逃げをするのみだ、というのです。
妻はすぐ、答えました。
〈何をいうの、あんた、このあばら家と土地を売ったら何とか金はできますよ、同じ出奔するなら、ちゃんと殿さまへ失礼のないようにりっぱな引き出物を差し上げ出ればいいじゃないの〉
夫は妻の優しいことばをきいて心苦しさがまさります。
〈今まで貧乏で、お前にいい思いの一つもさせることができなかった、それなのにこの上、おれのためにお前まで流浪させるなんて心苦しいよ〉
妻はさえぎって、原文によれば、「先世ノ契リアレバコソ、妻夫(メヲト)トモナリテ、今日マデ志カハラズテ、スゴシラメ。栄ヘバ同ジク栄ヘ、惑ハバ共ニコソ惑ハメ」
妻は、当然のような顔つきで、更に言いつぐのでした。
〈あんたが出家するというんなら、あたしも共に尼さんになりますよ〉
そして彼女は、強く、こう言い放つのです。
「コレホドノアリガヒモナキ世間ハ、惑フトモ歎クニモタラズ」――こんな、生きてる甲斐(かい)もない世の中は、行き場に困ったり歎(なげ)いたりするほどのこともありませんよ。
夫は妻に励まされ、家土地を売ってその金で金銀の細工物をつくり、当日、殿に献上しました。貧しい彼が何を持ってくるかと、目引き袖引きしていた人々は、あっと驚いたのです。殿も感嘆され、その返しの引き出物に土地を賜わり、その男は以後、あべこべに大いに富み栄えた、という話です。無住は、「妻ノ志コソマメヤカニ哀れニ覚ユレ」といっています。
私はこの妻の、したたかな人生観を示す言葉を、愛するものです。彼女のうちには、人生で一番大切なものと、そうでないものとの違いがハッキリしています。彼女が即座に夫との愛を選んだとき、「コレホドノアリガヒモナキ世間」と吐き捨てるようにいえたのは、無学な貧しい彼女が、その違いだけは知っていたからなのです。
定子皇后は、一条天皇より四歳お年上であられました。少年少女のころに結婚された一条帝と定子皇后は、非常におん仲むつまじく、帝には、あまた后がおありでしたが、どんな女人も、帝から定子皇后への愛を奪うことはできなかったのです。
それがどんなに大きな価値のあることだったかは、この時代の歴史を少し読めばわかります。定子皇后は、たよりにする父の中(なか)の関白・藤原道隆に死別し、兄の伊周(これちか)・隆家(たかいえ)らは叔父の道長のために政治的に失脚させられ、孤立無援のお立場でした。しかも道長はわが娘・彰子(しょうし)を一条帝の中宮に立て、陰に陽に定子皇后を圧迫していたのです。
でも皇后は、清少納言の記述によれば不遇の時代もいつも変わらずお人柄のけだかく、やさしく、なつかしい方でいらっしゃいました。才気かんぱつの清少納言がすこしひびきのにぶい男――たとえば大進生昌(だいじんなりまさ)らを揶揄(やゆ)したりしているのを聞かれると、
「あはれ、かれをはしたなういひけんこそ、いとほしけれ」(まあ、かれをはしたなういひけんこそ、手ひどくいいこめたりして、かわいそうではありませんか)
「例の人のやうに、これな、かくな、いひ笑ひそ。いと勤厚(きんこう)なるものを」
(ふつうの人のように、あの人をいろいろからかったり笑ったりしないでおきなさい。まじめで、りちぎな人なのですよ)ととりなされるのです。
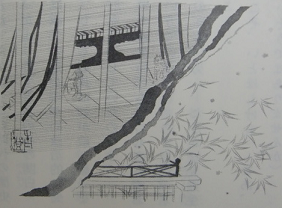
「いとほしがらせ給ふもをかし」
と、清少納言はいっています。生昌がやってくると皇后は、
「また、なでふこといひて、笑われんとならん」(また、どんなことをいって、皆に笑われようとするのかしら)
などと、気の毒がられたりします。生昌は、鈍いけれども純真な男らしく、自分はやり込められながらいつも清少納言の才気に関心しています。「すこし申し上げることがございます」とわざわざ呼び出すので清少納言が出てみると、
〈私の兄も、あなたをほめておりました。いつか、適当な折にお目にかかって、ゆっくりお話をうけたまわりたい、と申しておりました〉
ということで、べつに何のことでもなく、清少納言ほどの才気ある女が、生昌の兄に褒められたとてどういう気もないのでした。それで清少納言たちの嘲笑をまた買うのです。それを皇后はまたたしなめられて、
「おのが心地にかしことと思う人のほめたる、うれしと思ふと、告げ聞かするにらん」(自分の心に一ばん賢いと思っている兄が、あなたを褒めたので、そのことを聞かせたらさぞ嬉しく思うだろうと思って、わざわざ知らせにきたのですよ)ととりなされるのでした。
「のたまはする御(み)けしきもいとめでたし」
と、清少納言は感じ入っています。
清少納言の勝気さを示すエピソードとしてよく知られている「雪山」事件。長徳四年の十二月十日、大雪が降りました。雪の山を御所の庭に作り、いつまであるかしらと、皇后のおことばでそれぞれ、十日、二十日すぎとお答えしたのです。途中、雨ふりがあったり、いろいろハプニングがおきましたが、まさかと人々は思ううち、とうとう雪の山はだいぶ小さくなりながら年を越しました。清少納言の得意はいうまでもありません。
十五日には盆に盛って皇后の御前に献上し、人々の鼻を明かせてやろうと、手に汗にぎる心地で、十五日を待つのでした。雪の山はまだ円座くらいに残っています。十五日未明、暗いうちに下男に取りにやらせると、こはいかに、なくなっていたのです。皇后のお心づかいなのでした。あまりにもあざとく勝ち負けをあらわにして、人々に清少納言がにくまれても、と思いになって、侍たちにいって取り捨てるようはからわれたのです。
「いま、かくいひあらはしつれば、おなじごと勝ちたるなり」(いま、こうやってほんとのことをいった上は、あなたが勝ったも同じでしょう)
と人々の前でなぐさめられるのです。
こういう練れたおやさしいお人柄を帝がお愛しにならぬはずはありませんでした。皇后はわずか二十五歳でなくなられたのですが、一条帝に最後まで熱愛されたその短い生涯は、決して薄幸ではなかったと、円地文子氏も「なまみこ物語」で讃(たた)えていられます。
「萬葉集」巻十三にある雑歌(ぞうか)で、長歌の反歌ですが、作者はわかりません。
天にある月や日のように私が思っている君が、日に日に老いてゆかれるのはたいへん残念だ――というような意味でしょうか。
私は、この歌をはじめて見たときから、ふしぎな歌だと思いました。萬葉人の心は現代人にはわかりにくいニュアンスがあるのかもしれないのですが、「日にけに老ゆらく惜しも」というからには、自分も老いているのです。でも、自分の老いのことは作者の念頭にはないのです。この反歌の前の長歌は、こういうのです。
「天橋(あまはし)も、長くもがも 高山も 高くもがも 月読(つくよみ)の 持てる変若水(をちみづ)い取り来て 君に奉りて 変若(をち)得しむもの」
これは、現代では、「天にのぼるハシゴも長くあれ、高い山もいや高くあってほしい、そのハシゴや高山のようにいついつまでも、若くあってほしい、月の神のもっていられる若返りの水をとってきてわが君に奉って若返らせたいものを」というような意味でしょう。
作者は、わが老いを棚に上げて、ひたすら、自分の尊しと思う相手のことを考えています。
相手はだれでしょう。
私は、異性でなく、同性のような気がします。長いこと、ま心こめて仕え、身を粉にしてつくし、その献身ぶりには、仰ぎみるも眩しいというような、愛慕と渇仰(かつごう)と、それに一抹の、性愛的な気分もあります。
たぶん相手は身分の高い人なのでしょう。歌から見ると、その決して巧みとはいえない、ゴツゴツした修辞や発想から、男性のような気がします。
これは草ふかい田舎から連れてこられた男、土の匂いのする男が、長いこと都の貴人の一人に仕えてきて、掌中の珠のように大事に思い、生涯の忠誠を誓い、おそらく愛情のすべてをかたむけてきた相手に対する思いでありましょう。
その相手と自分との間をつなぐ感情の交流は、同等のものではありません。下から上へ、一方通行のものらしく思われます。
266ぺーじ写真
この男にとって、その君は、唯一絶対のものなのです。高貴な血といい、けだかい心といい、美貌といい、身分といい、‥‥そういう神か人かというような、見るもまばゆい、賛嘆(さんたん)の対象が、やはりこの世に生きる人間の常として、老いてゆくということを、目のあたり見た。男にとっては、深き嘆きであると共に、愕然と世の無常を悟る契機であったのでしょう。
でも、むろん無常感というような、屈折した心理は、この素朴で、原始的な男には無縁のものです。
男は、折々、痴呆(ちほう)のように、宝の「わが君」をぬすみ見たりしています。すこし面(おも)がわりされたのではないか。すこし、このごろはお疲れになることが多くなったのではないか。
昔は、こんなことはなかった。強くてたくましくて、もっと美しくていられたような気がするが。
そういう男自身、ほんとうは老いてきています。でも自分自身のことは気づかないのです。
共に老いてきたなあ、という感慨などは、数ならぬわが身の、男の心をかすめることさえないのです。男の生涯の夢もロマンも、すべて、月・日のごとく輝かしい「わが君」にあるのです。
そういう素朴な男が考えられることは、伝説の「若返り水」だけです。自分が飲むことは夢にも思わず、わが君に捧げることばかり考えています。献身者のエロティシズムのほのみえる、私が「ふしぎなうた」という所以(ゆえん)です。
若年のころより、中年、老年になるに従って、ますます面白く、そして解釈もちがってくるからです。たとえば第三段階の、
「よろずにいみじくとも、色好まざらん男は、いとさうざうしく(殺風景、不風流なこと)玉のさかづきの当(そこ)なき心地ぞすき」
どんなにりっぱな男でも、恋のあわれを解しない男は、玉の盃の底なきようなものだ――この文章に秘められた含蓄は、おとなの人間にして、はじめて味わえる面白さです。
作者の吉田兼光(けんこう)がこれを書いたのは、四十台の後半でした。彼の生きた十三世紀の末は、鎌倉幕府崩壊の直前という動乱時代でした。彼は早くに世をすて、いわば傍観者として世を見、人を見、恋を見、彼一流の見識をつくりあげました。
彼の恋愛美学は、恋に迷い、恋にやつれつつも、恋に溺れず、女にも見くびられたりしない、そういうのが、男として恋する人として「あらまほしかるべきわざなれ」というものです。
かねて私は、第百五段の、男と女の、忍び会いをさらりと描いた美しいスケッチが好きでした。
「北の屋かげに消え残りたる雪の、いたう凍りたるに、さし寄せたる車の轅(ながえ)も、霜いたくきらめきて、有明の月さやかなれども、くまなくはあらぬに、人離れなる御堂の廊に、なみなみにあらずとみゆる男、女と長押(なげし)に尻かけて、物語するさまこそ、何事にかあらん、尽きすまじけれ。

かぶし、かたちなど、いとよしと見えて、えもいはぬ匂いひの、さとかをりたるこそ、をかしけれ。けはひなど、はづれはづれ聞えたるも、ゆかし」
いてつく有明の月。人けのない御堂の廊に、普通の身分でないような男――いずれ名ある貴公子でしょう――が、美しい女と、長押に腰をかけて何事か、いつまでも尽きない話をしている。女のあたまの格好、顔立ちなど、いかにも美しく、たきしめた香の匂い立つのも風情がある。ひそひそという話し声のはしばしが耳に入るのも、心をそそられ、思わずきき耳をたてたくなる‥‥兼好は、そんな「恋の情趣」を愛した男でした。
彼の見識によれば、恋はそばから見て、「何事にかあらん‥‥ゆかし」と心そそられるようなものであるべきであり、女はそのために添景人物だったのです。
だから、現実の女は、これは彼からみると、「人我(にんが)の相ふかく、貪欲甚だしく、物のことわりを知らず」言葉もたくみに「苦しからぬ事をも問ふ時は言わず。用意あるかと見れば、また、浅ましき事まで、問はず語りに言ひだす。ふかくたばかり飾れる事は、男の知恵にもまさりたるかと思へば、その事、あとより顕(あら)はるるをしらず」というおろかさ、彼はこともなげに「女の性(さが)は、みなひがめり」と断定します。さればとて「もし賢女あらば、それも物うとく、すさまじかりなん」
女について点の辛い彼が、全文でただ一ヶ所、ほめています。ある男が、久しく訪れない女のことを「いかばかり恨むらん」と思いやって、弁解の言葉もなく気になっているときに女の方から「仕丁(じちょう)やある、ひとり」と言ってよこしたのです。仕丁は人夫、何か女の家でとりこみごとがあったので人手が要ったのでしょう、仕丁がありますか、一人貸して、と言ってよこした。「ありがたくうれしけれ。さる心ざましたる人ぞよき」――そんな、あっさりした気立ての女が、とても好もしい、というのです。
しかし、中年女の私は、いま「徒然草」を読み返してみて、そういうあっさりした女は疑問だと思いました。もしかして男の反応を予期してそういってよこしたのかもしれない。「いかばり恨むらん」と思っている男の心を察して、さりげなく、きっかけを作っているのです。
だとすればすばらしく賢い、女臭い女、女の中の女なのです。そして女なら、誰でもこのくらいの恋の駆け引きには、長けています。――兼好は、ほんとうの女、ほんとうの恋を知らなかったのではないでしょうか。恋人たちを鑑賞し、「恋のあはれ」についての評論家ではありましたが、「恋する男」ではなかったような気がします。
「源氏物語」の数あるヒロインの中でも、ことに「夕顔」の君は、あえかな美女です。弱い内気なやさしい性格の、なよなよと心もとなく、男の庇護本能をそそらずにはいられないような美女なのでした。
それはさながら、夏の夕、垣根などにまつわるツル草に、ひっそりと咲く夕顔の花の象徴のようでもありました。
光の君は五条わたりの下町へ、身をやつして乳母の病気を見舞いにゆき、はからずも、燐家に隠れ住んでいる「夕顔」を見染めます。
私はこのくだりがことに思い出がふかいのです。
私は終戦の前年の昭和十九年に、旧制女子専門学校の国文科に入学したのでした。あるとき洗面所にいきますと、美しい上級生が数人やってきて試験の話でもあるのか、源氏の「夕顔」の巻について話し合っていました。と、中のひとりが、きれいな声で口ずさみました。
うちわたす 遠方人(をちかたびと)にもの申す
そのそこに白く咲けるは 何の花ぞも
そのとき、どんな話を彼女たちが交わしていたか、具体的にはおぼえがありません。けれどその古歌は、なぜか、れいろうと澄んだ声とともにいつまでも私の心にしみました。いまでも時にふれ、耳の底に甦ってきます。それから、毎日の国文科の授業が心の底から好きで楽しかったことも。
――それは、入学して五カ月ばかり先には、もう学徒動員で、学校を離れて航空機の部分品をつくる工場へやらされることが、わかっていたからでもありました。ペンを持つ手で旋盤を扱うことを強いられたとき、短い間の学校の授業は、一瞬一瞬をぬすむような、強い喜びでした。あんなに学ぶことへの緊張と熱愛がたまったことは、生涯で二度とないでしょう。それは男子学生が、ペンに銃を持ち換えて戦場におもむくことを義務づけられた、それまでの数か月間、勉強や学問に感じた執着と同じ類のものだったでしょう。
そんなときに聞いたので、よけい印象的だったのでしょうか。
「源氏物語」では、光の君は「うちわたす遠方人」と口ずさみ、〈花折ってまいれ〉と随身(お付き武官)にいいつけます。するとその家から少女が出て来て、白い扇を差し出し、これに乗せてお目にかけて下さいましと随身にいいました。移り香もゆかしいその扇には「心あてにそれかとぞ見る白露の光そーたる夕顔の花」という歌が、みやびやかかな手で書かれてあり、光の君の好きごころをはげしくかきたてたのでした。
こうして「夕顔の君」は光の君の愛人になりますが、物の化にとりつかれてははかなく身をまかせてしまいます。夕顔の花の印象のような、というゆえんです。
室町時代の小唄にも、「五条わたりを車が通る 誰(た)そと夕顔の花車」というのがあります。
「夕顔」といえば、「源氏物語」を思い浮かべるのが、古典教養の決まりのようになりました。けれども「源氏」にかぎらず、夕顔のテーマは、女のものらしく思われます。私の好きなのは、
夕顔やなごのはだの見ゆるとき
という、加賀の千代女の句です。夏の夕、下町の卑し気な庶民の住まいに夕顔がほの白く浮かんでいる。夏は行水のあとであるのか、ふと肌をすこしくつろげて、すず風をいれている。ちらりとみえた女の白い肌が、うく闇の中に夕顔の花と見間違うばかり浮き上がる。そんな美しい女っぽい句です。
千代女には、「朝顔につるべ取られてもらひ水」という有名な句がありますが、私は夕顔の句の方が、艶な花やぎがあって美しく思われます。
それにしても、「うちわたすをちかたびと‥‥」と澄んだ声で私の耳と心を洗ってくれたことでしょうか。あれからもう、三十年たちました。
朝光は当時、たいへん人気のある、人々の愛された貴公子でした。堀川関白の次男で兄をこえて父に寵愛(ちょうあい)され、若くして高位高官にすすみ、その美貌、優雅なものごし、端正な心映えを、世にうたわれた青年貴族でした。
彼には早く結婚した美しい北の方(妻)がありました。北の方は重明親王の姫君という高貴な身分に加え、二人の間には可愛い子供たちさえ生まれていました。
身分といい、年恰好といい、容姿といい、まことに一対のお雛様のような似合いの夫婦だったのです。
それを朝光はうちすて、心変わりしてしまいました。そして新たに作った恋人は、枇杷(びわ)大納言・延光(のぶみつ)卿の未亡人、年のころなら四十すぎ、朝光の親のような人で、この人の娘すら、朝光より年上でした。
「大鏡」という本には、「色黒くい額には花がたうちきて(シワのあること)髪ちぢけたるぞはしける」とあります。
片や、花の如き青年貴公子。
片や、老いた醜婦。
このとりあわせは世間の好奇心を刺戟(しげき)し、にわかに同情は、朝光のもと北の方に集まり、朝光は指弾のまとになりました。
「大鏡」には世俗の解釈をそのままに、朝光が金にころんだのだ、と断言しています。
延光卿の未亡人は金持でした。朝光を自分のもとへ通わせるようになると、「女房三十人ばかり、裳(も)・唐衣(からぎぬ)きさせて」何ともいえぬほど美しくよそおわせ、並べて出迎えました。
「めでたくしたてて、かしづき聞こゆる事限りなし」と「大鏡」にあります。朝光が帰ってくると冬は炭火をふんだんに埋めて伏籠(ふせかご)に着換えをかぶせてあたため、薬もさまざま用意し、畳の上敷に綿を入れ、やすむときは侍女三四人が火のしで床をあたたかにのし撫でるという世話ぶり。「あまりなる御用意なりしかし」と「大鏡」は、揶揄(やゆ)しています。
そして本人の未亡人は、黄ばんだ絹の綿入れの衣など着て、白い袴をはき、化粧げもなく、自分の容貌を知ってそんな身なりをしてらしたのだろう、「誠にやその御装束こそかたちにあひて見えけれ」と「大鏡」は辛辣に未亡人をこき下ろしています。
「大鏡」には、朝光がこの未亡人を選んだことを、「徳につき給へるとぞ世人申しし」
お金を持っている方に傾いたのだと世人はいった、とありますが、果たしてそうでしょうか? 「大鏡」はその筆致からして男性のものした本だと思われますが、私には「大鏡」の解釈は、いかにも男性的粗放さがあるように思われてなりません。
男性的思考の単純さ、独断があるように思えてなりません。
与謝野晶子も、指摘していますが、朝光という人は、本来、富裕な貴族なのです。彼は父の遺産を受け継ぎ、更に、彼を愛した異母姉の、円融院中宮・皇女の遺産も、相続しています。金ばかりでは、なかったのではありませんか。
世間の人は、おそらく、四十すぎの初老の女と(当時では初老に近かったのです)二十七八の青年が恋し合うことなど、有り得ないとさかしらにきめているのです。でも、朝光とこの婦人との間に、どんな恋が芽生えていたのか、二人のほかには誰も知らぬことなのです。
「栄花物語」はさすが女の筆なので、この間の消息を伝えています。
「かの枇杷の北の方いみじう、賢うものしたまふ人なり」それにくらべ、もとの妻は「ちごのやうにおはなしければ」とあります。あまりに子供っぽい妻にくらべ、未亡人の聡明さは朝光の心を捉えて離さなかったのかもしれません。朝光はこの人に、女の真の美しさを見たのかも知れません。
朝光は生涯ついに、「親のような」年上の妻と添い遂げました。千年の昔の話です。
「住吉物語。埋れ木。月待つ女。梅壺の大将。松の枝(え)。こま野。ものうらやみの中将。交野の少将。とほ君。せりかは。しらら。あさうづ。みづからくゆる。かばねたづぬる宮」‥‥なんという、心をそそる題でしょう。
でもかなしいことに、これら、さまざまの物語は、当時の人に愛読されつつも、いつとなし散り散りになり、やがてわすれられ、消えてゆきました。
あるいは「源氏」という強い輝きをもった美しい星の前に、光を失ったというのでしょうか。また、「源氏」という巨大な本流にそれぞれの小川は、まきこまれ、合流したというべきかもしれません。
その中で「源氏」に吸収消化されぬ、異質の個性をもった物語だけが、千年の風雪に堪えて生き残りました。「伊勢」「竹取」「宇津保(うつぼ)」「落窪(おちくぼ)」などです。
私はこの、「落窪物語」がとても好きなのです。
これはいかにも男性の筆になると思われる、(作者も書かれた時期もわかりません)
大まかで粗っぽいタッチ、しかも構成がきちんとしていて、いきいきとマンガ風な人物、たいへんよくできた楽しい通俗小説なのです。
「落窪」は昔から、まま子いじめの物語、で通っていて、まま母・まま子への大衆の同情関心が、この小説を生きのこらせたのだという人もありますが、それだけではないでしょう。

ある中納言の亡くなった妻の忘れ形見の姫はまま母の北の方に冷遇されて、離れの、一段低くなった間におしこめられ落窪の君とよばれて、憂くつらい日を送っていました。北の方の産んだ姫たちは花やかにしずかれ幸福な結婚もしているというのに、落窪の君はたべものもなく、着物もなく、ひもじい寒い思いをし、異腹の姫の婿のため、お針女の仕事に追いまくられるという暮らしでした。
でもこのシンデレラに、王子さまが現れました。左近の少将というすばらしい貴公子です。少将は姫の逆境に同情し、また、その美しさやさしさ聡明さに魅せられ、ひそかな恋人として通います。少将の従者、帯刃(たちはき)と姫の侍女、あこぎの二人が、それぞれのあるじのため、心をくだいて恋をとりもつおもしろさ。
北の方は姫に恋人がいると知って、夫の中納言にあしざまに告げ口し、姫はとうとう一室に錠をおろして閉じ込められてしまいます。その上、北の方は好色な老人の典薬助(てんやくのすけ)をやって姫を襲わせます。あやうし、落窪の君! もう猶予はなりません。
少将は帯刀とあこぎの手引きで、北の方らの留守を幸い、姫を救いにのりこむ。錠があかないので男二人の力で戸を打ち壊し、姫を抱いて車に乗せ、首尾よく邸につれ帰りました。北の方らが帰宅して大騒ぎ、北の方は誰の仕業とも分からないので怒り狂います。
読んでいて思わずハラハラして手に汗をにぎり、北の方がしてやられたところでは快哉を叫んだりする、ほんとうにページをくるのももどかしい面白い部分です。
さて、このあと少将は、存分に北の方に復讐します。そして姫は、少将の出世につれ、いよいよ幸福なくらしを送ります。
作者は庶民の願望に充分にこたえて、その栄華の物質的幸福を力こめて詳述するのですが、それよりも女性読者をひきつけるのは少将の純愛です。少将は大臣の姫の婿にと懇望されたのをふり切って、財産も親の後ろ盾もない、みなし子の姫をただ一人の妻として貞潔を誓うのでした。これはいかにも通俗小説の典型でしょう。善玉悪玉入り乱れ、美しい聡明なやさしいヒロインが運命に翻弄される、純愛あり謀計あり、復讐ありの面白いよみものです。でも、大衆の共感と喝采(かっさい)は、まさに少将と姫の純愛にあったのです。永遠に古く、永遠に新しいテーマだったから、千年の風雪に堪えたのです。
やさしいサムライ
「花の都の室町に、花を飾りし一構へ、花の御所とて時めきつ、あさひの登るいきほひに。文字も縁ある東山‥‥」
このやさしげな、平明な書き出しではじまる小説「偐紫田舎源氏(にせむらさきいなかげんじ)」が文政十二年(一八二九年)はじめて刊行されたとき、満天下の女性たちは熱狂して迎えました。以後、天保十三年(一八四二年)に、お上のお咎めをうけてその版木を没収されるまで、十数年のあいだ、ロングセラーをつづけたのです。
作者の柳亭種彦(りゅうていたねひこ)は、「源氏物語」を巧みに翻案(ほんあん)して、上品な通俗小説とでもいうべき、新しい面白い味わいを作り上げました。
舞台を室町時代の足利将軍家にうつし、主人公は足利光氏(みつうじ)に、桐壺は花桐に、藤壺は藤の方に、葵の上は二葉の前に、名を変え趣向をこらし、こまやかでデリケートな構成です。しかも登場人物の生活感情は全く現代風で、美男の若殿をめぐる、美女群の確執、陰謀、恋のさやあて、純愛、嫉妬、‥‥それらはどれほどその頃の女心をかきたてたことでしょう。
江戸城大奥の女中たちも、自分たちがモデルのように熱狂し、この小説は大当たりでした。着物の柄から、芝居、錦絵、生人形にまで「田舎源氏」はもてはやされ、種彦の名文はあがりました。
光氏が義理の母、藤の方をくどく文句のやさしいしおらしさ。
「水より清い御身をば、わたくし故に濁らせます。此の世ばかりか前世から、結びおいたる悪縁と、思へばいとど悲しきを‥‥」と手をとれば義母の藤の方も「道にそむくはそなたのため、命捨てるはかねての覚悟‥‥」
この柔媚(じゅうび)な小説をかいた種彦は、本名を高島彦四郎知久という、小身ながら、れっきとしたご直参の旗本でした。でも四角張って生きるのを好まぬ、武士らしからぬやさ男なのです。本所生まれの下谷育ち、江戸末期の燗熟した文化の露を吸って、いっぱいひらいた大輪の花のような才能にめぐまれながら、その出身は、両刀たばさむ身分なのでした。
種彦は教養も文才もありますが、武芸の心得はありません。銭湯へいって、田舎者の勤番侍が、お湯をうめていると、
〈江戸っ子はあつ湯を好むものだ〉
といって侍たちに水舟へ投げ込まれたりします。荒っぽい田舎侍にどうしてかないましょう、種彦はあやまって、勘弁してもらいました。
また、朋輩(ほうばい)の侍と話していて役者の路考(ろこう)を〈路考さん〉とさんづけで呼び、朋輩の侍の怒りを買ったりします。〈武士たるものが、役者づれの卑しい河原者(かわらもの)をさんづけするとは何ごとぞ。何という性根の腐った奴。そこへ直れ!〉と槍をしごかれ、種彦は慌てふためいて逃げまどい、縁の下にかけこんで息を殺して隠れたりしました。
彼は切ったはったの暴力が大きらいな、心優しい、おだやかな知識人、趣味人なのでした。そして私はこんな男が大好きなのです。
やがて「天保の改革」と呼ばれる弾圧の嵐が吹きすさびました。老中・水野忠邦(ただくに)は人心を引き締めようと、春本、人情本のたぐいの売買を禁じたのです。戯作者(げさくしゃ)たちはどんどん処罰され、その版木は没収されました。種彦は武士ですので処罰は家名断絶、食禄おめし上げの形になります。封建の世の武士として家名の断絶は最低の不忠不幸です。種彦は、自決をえらびました。それなら本人病死という名目で、家名は残されるのです。
ちるものに定まる秋の柳哉(かな)
それが種彦の辞世でした。侍のきらいな種彦が最後は最も侍らしく死ぬことを強いられたのは哀れでした。杉本宛子氏の好短篇「偐紫楼の秋」(朝日新聞社刊「瑪瑙(めのう)の鳩」に収録)には、「やさしい侍」種彦のおもかげがほうふつとしています。
それにしても道徳倫理で文学を律しようとする官憲の場違いな弾圧は、今も昔も少しも変わりません。私は野坂昭如氏が起訴された「四畳半襖の下張」事件をあわせて思わずにはいられないのです。
1996年12月20日 上巻 田辺聖子 著
つづく 文車日記(ふぐるまにっき) 下巻
――私の古典散歩――
大君のみ盾
作者の名は右大将・藤原道綱の母、とあるだけで、呼び名はいまも分かりません。かりにかげろふと名づけましょう。
夫の名はわかっています。藤原兼家(かねいえ)、のちに関白にまでなった人ですが、辣腕(らつわん)の政治家で、おのが野望をとげるためには兄弟、一門をも仮借なく葬り去るほどのすさまじい男です。
「蜻蛉日記」をよむたのしみは、また、この男を知る楽しみでもあるのです。じつをいいますと、私は、「蜻蛉日記」にあらわれた兼家という男に、すっかり魅惑されているのです。
強引でずうずうしく、大胆奔放で、色好みで、しかもやさしく、たのもしい所もあるといった‥‥端倪(たんげい)すべすらざる、したたかものなのです。
この当時、男は重婚を許されています。妻たちはそれぞれの親の家で、夫の訪れをまつだけです。子供が生まれれば、妻の手元で育てられます。夫は自分の家にはどの妻もおかず、気の向くままに、何人もの妻の家に出かけます。

妻の地位には格差はありませんが、そこは人間、おのずから愛情の深浅によって親疎ができます。
かげろふは美女で、有名な歌人でもある、つまり才媛(さいえん)でしたが、結局は、この時代の女のつねの、嫉妬に身をやく運命から逃れませんでした。
兼家は他の女の元にいくときも、平気で彼女の邸の前を前駆(さき)に警蹕(けいひつ)させ、供を従え、牛車(ぎっしゃ)で悠々とすぎてゆきます。邸の下男たちが「中門おしひらきてひざまづきて居るに、むべもなくひきすぎぬ」という仕打ちなど、平気でする男です。
だから、たまに夫が来るとかげろふはありったけの怨み言います。果ては「岩木のごとして明かしつれば」夫も怒って帰ってしまう、そうかと思うと時には侍女の目も恥ずかしいほど、戯れたり、あるいは妻が怨みごとをいうあいだ、眠ったふりをしたりする、ずるい男です。また時には雨の日に来たりして、さすがに堅い妻の心もとけるのですが、明日も来るからね、という夫の言葉を信じて待つうちに、半月、ひと月、たよりもないという、‥‥そうです、律儀で誠実な女とっては、地獄の苦しみともいうべき夫婦生活なのでした。
兼家が急病で倒れ、ほかの女の邸へかつぎこまれた時がありました。彼は使者を出して、夜半こっそり、かげろふをよびよせます。
かげろふは本邸の夫人に遠慮がありましたが、兼家がかさねて、車までよこして促しますので、出かけました。
暗い縁にかげろふは佇んで探しておりますと、〈ここにいるのが見えないか〉と夫が手をとって導き入れてくれました。
そうして、いろいろのことを夫婦らしく語り合い、兼家はやはり、一ばん愛しているのはお前だったと病の床で告白するのです。まだ魚など食べていないのだが、お前今夜来るので一緒に食べようと思って待っていた、と、病後はじめての食事の箸を、かげろふと共にとります。
なんという可愛い男のセリフでしょう。積年の閨怨(けいえん)も雪のように溶け、かげろふは男にひしと心がよりそうのでした。
と、思うふと、病が癒(い)えるが早いから、色ごのみの兼家はもう新しい愛人を作ったりするのです。
かげろふは嫉妬の苦しみに負け、寺へ入って尼になろうと決心しました。それを力づくで連れ戻したのは、やっぱり、夫の兼家なのでした。西山の寺にこもり、どんな人のいさめや忠告にも耳をかさず、出家をかたくなに念じていたかげろふのもとに、兼家はまっすぐ、やってきます。散ったものを取り片付け、袋に入れ、車に積ませ、仕切りをとりはらい、〈さあ、仏においとまごいをしろ〉と冗談をいって、かげろふの手をとり、笑いながらむりやり車に押し込むのでした。彼は彼なりのやりかたで、かげろふを愛していたのです。
かげろふは中年になり、ようやくに、嫉妬や妄執(もうしゅう)の業苦から、いささかときはなたれて、夫やわが身を見るようになりました。思いがけなく兼家がたずねてくれた夜のあけ方‥‥。
「雨いとのどかにふるなり。格子などあげつれど、れいのやうに心あわただしからぬは、雨のするなめり」
いつもは朝になるとあわただしく帰る兼家が、けさはゆっくりしている。それは私への情愛からではない、きっと雨のせいだろう――かげろふはそんな風に考える女になっていますが、しかし、その彼女の眼からみても、中年に達した夫の男ぶりは水際立ったものでした。
共の男たちは来たか、などといいつつ夫は起き出して、なよらかな直衣(のうし)、よきほど柔らかな練絹(ねりきぬ)の袿(うちぎ)を下に着こみ、帯をなかば垂れつつゆるやかにしめて歩いてきます。侍女たちが、朝餉(あさげ)はいかが遊ばしますか、とお伺いをたてますと、いつも食わないのだから、べつにいい、と、きげんのいいようすも、おのずから威と気品がそなわり、美しい男なのです。
「太刀を」
といいますと、息子がとって膝まずいて捧げるのでした。のどかに縁をあるいて庭を見やり、――庭を雑然とさせてしまったなあ、――などといいます。やがて車がさしよせられ、夫はゆっくり乗り込みます。中門から出た車の、前駆(さき)をおう声も、かげろふをなつかしく、たのもしく、慕わしい心地にさそうのでした。
このとき兼家四十四歳、大納言という高官に加えて大将に進み、自信と威厳にあふれて男の魅力をあますなくそなえています。でも、そんな魅力的な夫の訪れもごく、たまのことでした。
「そののち、夢の通ひ路たえて、年くれはてぬ」
夫の訪れはいよいよ、間遠(まどお)になり、たよりも通り一ぺんのものになりました。ただ息子の道綱のみ、父と母の邸をゆき来してわずかに消息をもたらし、縁をつないでいます。
いまは道綱も青年となり、公達(きんだち)の一人として世に出る年頃でした。かげろふは、息子の将来にのぞみをつないで生きています。
でも来しかたをふりかえったとき、はたして私の一生は何だったのかとかげろふは自問せずにはいられませんでした。秋冬、物思いにくれてはかなくすぎました。そしていつも、餓(かつ)えていました。兼家への恋が満たされないことが、彼女の心を飢えさせていたのです。かげろふは長い苦しみの半生をかえりみつつ、筆をとってかきつづけます。
「…ふりける雪、三四寸ばかりたまりていまもふる。簾(すだれ)をまきあげてながむれは、『あな寒(さむ)』といふこゑ、ここかしこにきこゆ。風さへはやし。世の中、いとあれなり…」
夫を憎みながら愛し、愛しつつ憎み、そのくせ、かげろふは夫に恋していたのです。
妻に恋されるほど、兼家は魅力ある男なのでした。
うまずめ
「枕草子」の作者、清少納言という女性は、こんにちの研究では、結婚して、一子をあげたのではないかと推定されています。しかし私は、彼女は石女(うまずめ)ではなかったか、あるいは子供を産んでも、手許から放してしまって、子供縁のうすい女ではなかったかと思っています。
なぜなら、彼女のエッセイ集「枕草子」の中にある、子供の描写はすばらしいからです。光り輝いているからです!
イギリスの女流作家、キャサリン・マンスフィールドも病身で子供を持たなかった女(ひと)でした。彼女の子供の描写もまた、じつに生彩を帯びています。
私は、現実に子供を持てば、こうまで愛らしさを端的に描写できないのではないかといつも思います。
「枕草子」の名高いくだり、「うつくしきもの(愛らしいもの)」の幼い子供の可愛らしさはどうでしょう。
「二つ三つばかりなるちごの、急ぎて這(は)ひくる道にいと小さき塵(ちり)のありけるを、目ざとにみつけて、いとをかしげなる指(および)にとらへて、大人などにみせたる、いとうつくし」
またおかっぱあたまの童女が、目の上までかかった髪を、あたまをかしげてふり払って物を見ている愛くるしさ。美しい赤ちゃんをちょっと抱いて遊ばせてあやしているうちに、とりついて寝入ってしまうその愛らしさ。
彼女は赤ん坊や幼な子のやわらかな肌、愛らしい笑顔、声を、物ぐるおしいまで、飽かずに賞(め)で、慈しみます。
「こころときめきするもの。ちご遊びする所の前、わたる」
「つれづれなぐさむもの。三つ四つのちごの、ものをかしういふ」
その片言も、そのしぐさも、彼女にとってつきぬ愛執と、新鮮な好奇心をかきたてるものでした。
その愛情や執着、好奇心は、「ちご」たちが自分のものでないから、なのです。
自分で子供を持つ人は、決して、こういう第三者的な好奇心をもちますまい。清少納言の、愛情にあふれた観察は、いきいきしていればいるほど。ヒトの子供をみる女の目なのです。
「いみじう白く肥えたるちごの二つばかりなるが、二藍(ふたあゐ「染めの色」)のうすものなど、衣長(きぬなが)にてたすき結ひたるがはひ出たるも、また、短きが袖がちなる着てありくも、みなうつくし」
「八つ、九つ、十ばかりなどの男児の、声は幼なげにて書(ふみ)読みたる、いとうつくし」
棒切れや弓みたいなものを持って遊んでいる小さい男の子も、たいそう可愛い。
「車などとどめて、いだき入れて見まほしくこそあれ」
その愛情には、自分が自由にできない、この愛らしいせつない生きものへの憧憬・羨望の影が、煙のように立ち込めています。
だから清少納言は、子供のいやらしさ、にくらしさも鋭く指摘します。
「にくきもの。物聞かむと思ふほどに、泣くちご」
「見苦しきもの、例ならぬ人の前に、子負ひて出て来たる」
調子づくもの、母親に連れられて遊びに来、他人の部屋の大事なものをさがし出してとりちらかす子供。それを母親もまた制止もしないで、だめよ、などとにこにこしているだけ。こんなのは親まで憎らしい。
憎しげなちごを、親からみると可愛いのか、片言をまねしているなど笑止だ。
これということもない人が、子供をたくさん作っているのも、わずらわしい。
その直截(ちょくせつ)な辛辣(しんらつ)さ。この口ぶりはもう、まるで男性のものです。
あの、母になった女たちがもつ、子供に対してとめどなくのめりこんでゆくようなあいまいさ、「これこそ我が骨の骨、肉の肉なれ」というからみつくような一体感のもつ妖気(ようき)は、彼女の文章にはありません。「枕草子」は颯爽(さっそう)たる、石女の文学だったのです。
あけぼの・くれなゐ
子供の頃に愛読した少年少女小説の、主人公の名前にはとてもいいのがありました。吉川英治氏の、「天兵童子(てんぺいどうじ)」なぞ、字もひびきもいいのです。ことに時代小説の女の子の名前が美しく私は好きでした。「天兵童子」に出てくる少女は千尋(ちひろ)だったかと思います。千葉省三氏の
「陸奥(むつ)の嵐」は狭霧(さぎり)でした。吉川英治氏の「左近右近」には笹枝という少女が登場します。これも武家娘らしい、きりッとした名前です。
汀(みぎわ)は「大陸の若鷹」でしたか? 渚、桔梗、露路、彼女たちはみんな、きれいな名前を与えられて、心も姿もうつくしいのです。ことに「咲椰子(さくやこ)という名前は、大好きでした。ずっとあとになってそれは「古事記」の「木花咲椰姫(このはなさくやひめ)」からとられたとわかりました。古事記にも美しい女名前がたくさんありますが、それらはたいてい悲劇のヒロインです。求婚者である大王を拒み、その弟に恋してしまった女鳥(めどり)の姫、兄と愛しあって罪におちた衣通(そとおり)の姫。この姫は、あまり美しいので
「其の身の光、衣(そ)より通り出づれば」衣通姫といわれたのでした。神秘でロマンティックな名です。
ところで、小説の主人公に千尋や狭霧といったきれいな名前が付けられるようになったのはいつからだろうと思っていましたが、これは江戸時代の小説からの系統ではないかと考えました。馬琴(ばきん)の読本にも、あるいは種彦の「偐紫田舎源氏(にせむらさきいなかげんじ)にもあります。
老女には、岩根とか、杉生(すぎばえ)とか、適当な名前をつけられてあります。若い美女には、白縫(しらぬい)、真鶴(まなづる)、花桐、稲船、小百合、紅(くれない)、葛樹(かつらぎ)、朝霧…‥その名さえゆかしく思われます。
秋成の、恐ろしい悲しい、また美しい物語の中にも真名子(まなこ)や、宮木、などといういい名が用いられています。
「萬葉集」にみえる女の名は実名でしょうが、安見児(やすみこ)、手古奈(てこな)、小鹿など、土の匂いがして素朴でいい名です。
けれども、やはり一ばん美しいのは「源氏物語」の巻名でしょう。
昔の大奥女中たちは源氏からとった名で呼ばれることが多かったのです。蓬生(よもぎゅう)、浮船、といったお女中がいました。
桐壺、帚木(ははきぎ)、空蝉(うつせみ)、夕顔、若紫、花宴(はなのえん)‥‥と巻々の名をひろいよみしてゆくだけで心ときめきした女学生のころがしのばれます。艶(えん)に華やかな王朝絵巻が極彩色でくりひろげられていくようで、ふと、西条八十氏が源氏をうたわれた一節が思い出されるのです。
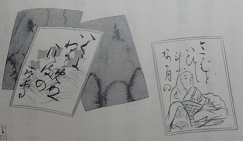
生者必滅、会者定離(えしゃじょうり)
かなしい恋の 花ふぶき‥‥
少し前まで宝塚歌劇の生徒さんたちは、百人一首からとった名前をつけていました。天津(あまつ)乙女さん、雲野かよ子さんなど、すてきな名です。富士野高嶺さん、有馬稲子さん、霧立のぼるさん、蘆野(あしの)もろやさんなど、ほんとうにうまくつけた、いい名だと思われます。
あるとき、若い美しいお嬢さんが、かなもじを紅色に散らし書きして染めた着物を、身にまとっていられるのをみました。それは、「あけぼの」「くれなゐ」という字でした。――まさに、あけぼのもくれないも、若い娘の美しさ、清らかさをあらわす、こよない言葉に思われました。
それで私もまた、そんな美しい言葉をちらし書きして染めた着物を着てみたいと空想しました。おぼろよ、かげろふ、あぢさゐ、あはゆき、はるさめ、なのはな、うぐひす‥‥口ずさむだけで、美しさに酩酊(めいてい)するような言葉がたくさんあります。もし私が時代小説を書くときは、ヒロインたちに字も発音もイメージも美しい、こんな名を与えたいなと思います。
もしかしたら、日本の女が美しかったのは、日本語が美しいかったせいではないでしょうか。日本の若いお嬢さんに、美しい言葉をたくさん知ってほしい気がします。
赤珠は‥‥
「古事記」や「日本書紀」を詠んでいますと、古代の人たちが珠玉に対してもつ、ふかいあこがれと賛嘆がよくわかります。古代の人たちは、美しい珠に対して呪術(じゅじゅつ)的な信仰さえ、抱いていました。珠は、神秘な魔力をもち、人々の運命を左右することさえ、しました。
三種の神器の中に「ヤサカニの勾玉(まがたま)」があるのは周知のことですが、神代の昔、尊い神が珠を嚙んで、「吹き棄つる気吹(いぶき)の狭霧(さぎり)に」たくさんの神々をお生みなった、という神話も美しいものです。
大和の橿原(かしはら)神宮の外苑(がいえん)にある大和歴史館には、出土品の勾玉がいくつか展観されています。――私は、古墳の出土品の珠に、ふかく執着しているのです。
勾玉には、ガラス、瑪瑙(めのう)、ヒスイ、石、動物の牙などがあります。
陳列ケースの中にひっそりとただ一顆(か)、おさまっていた小さな勾玉は、ことにも忘れがたいものでした。それは鉛ガラスの、重そうな、女の拇指くらいの勾玉でした。煙のような色、というか、石油色というか、(私は夢色、と呼びたい気がしました。
古代の夢をそのまま、まどろみつづけているような色なのです)灰色ともうすい墨色ともつかぬ、不透明な玉のいろ、それはどんな男、どんな女の肌にあたためられ、その手に慈しまれてきたのでしょうか。千数百年の眠りから醒めて日の光にさらされた珠の色というのは、これはもうガラスではなくて宝玉なのでした。
晴瑯玕(せいろうかん)の管玉(くだたま)というのも見ました。これは古代の玉を趣味であつめていられるTさんという方に見せて頂いたものです。これも誰とも知れぬ古墳から出て、何十年となく人の手から手へ渡ったものらしく、不透明な碧(みどり)いろが、人の心をさそいこむようなとろりした深いもの、この玉はきっと、衣通姫のような美女のうなじにかけられ、その死に際しては愛するものの手で石棺へ入れられたのかもしれません。
あるいはまた、仁徳天皇の御代に記されている、メドリの姫のものか。謀反の罪に問われた。メドリの姫のハヤブサワケの王子は、天皇の追手に殺されました。皇后・ヤタノヒメはメドリの姫の妹ぎみでした。姉の身の上を悲しんで、姫のもたれる珠を奪わないようにと天皇に願われました。天皇はあらかじめ、兵士たちに「皇女のもたる足玉手玉をな取りそ」と命令されたのです。
そののち、宮中の宴会で、人々がむれ集まったとき、皇后は、一人の女の腕輪に目をとめ、あっと叫ばれました。それは、薄幸な、メドリの姫のもちものでした。早速、彼女は捕らえられ糾明されました。その女は、追手の将軍の妻だったのです。
将軍が死んだ姫から「膚(はだ)もあたたけきに剥(は)ぎもちきて、すなはちおのが妻に与へつる」ことがわかり、死罪となるところを、たくさんのタカラモノを差し出して許されました‥‥。
珠に対する物欲と愛執から騒動のおきた話は、安泰天皇のくだりにも載っています。珠は、人々の判断や理性を狂わせる神秘な力を持っていたのでしょう。
山幸(やまさち)、海幸(うみさち)で有名な、ホオリノミコトは、海神の娘、豊玉姫と結婚しました。姫はお子を生まれるとき〈私は人間の身ではありませんから、本来の姿に変じて出産します。どうか、ごらん遊ばさないで〉といわれました。

しかしそう制されると却(かえ)ってミコトは好奇心をかきたてられ、産屋をのぞかれました。すると大蛇が「はひもこよ」っていたのです。姫は怒って故郷の海に帰ってしまわれました。しかし、「恋しき心にしのびずて」歌をよこされるのでした。
赤玉は緒さへ光れど白玉の君がよそひと貴くありけり
髪はみづら、白い衣に金の太刀、珠をつらぬいてうなじにかけた高貴な古代の男の姿が、この歌をよむと、ほうふつと浮かびます。古い勾玉はそんな女のためにいきも吸い込んでするのです。
玉手の恋
江戸時代の小説をよんでいて、私がつい、おかしくなって笑うのは、いわゆるこっけい本ではなく、むしろ、普通のよみもの、当時の流行小説「偐紫田舎源氏(にせむらさきいなかげんじ)」のある部分などです。「高直はつと捕へ、さらに許さん様子もなくじりり乀とつめよせて『命惜しくば助けてやらん、その代わりには下帷子(かたびら)もはぎとって肌をあらはし恥かかせてくれんず』と水原(みはら「女の名」)が寝巻の帯をとき、ぬがせんとなしければ、ぬがじとこなたは争いて、引きあふ中に縫糸の、絶えもやしつらん、かの帯に、ほころび切れてほろほろと、うちよりこぼるる数通の密書‥‥」
あわや、際どい場面が展開するかと思いきや、必ず、しかつめらしい密書や短剣が出て来て、おかしくなるのです。この文章など、江戸小説の一つの典型みたいです。
しかし、お家騒動や政治的陰謀の骨組みをつくり、つまり大義名分をあきらかにし、君臣・親子の義理・道徳をタテマエにしなければ、恋愛や、まして日かげのひそかな乱倫・邪恋などテーマにできない時代でした。小説や戯曲の作家はそのからくりをよく心得ていました。
そして読者や観客も、そのからくりを知って、タテマエとホンネの巧妙に交錯する世界を楽しんだのでしょう。
「摂州合邦辻(せっしゅうがっぽうつじ)」という浄瑠璃(じょうるり)があります。ずつと昔、文楽で「合邦内の段」を見たことがありますが、若い私は、筋立ての不自然、不合理についていけない思いがしました。若さというものは、不合理に対して過酷なものです。
しかしいま人生中歳にして、台本を読み返してみますと、このタテマエとホンネのからくりがよくわかります。
河内国(かわちのくに)の城主、高安家の若くて美しい奥方、玉手御前は、先妻の子・俊徳丸(しゅんとくまる)に恋して、応じられないのに嫉妬し、毒を盛って業病(ごうびょう)の身にしてしまいます。しかしそれは実は、お家騒動を企む悪人から、義理の子・俊徳丸を守る彼女の苦衷(くちゅう)から出た計略で、いつわりの恋をしかけて世の人の目を欺き、俊徳丸を無事、悪人の手から逃れさせるためでした。その証拠には、俊徳丸の業病を医(い)やすには自分の生肝(いきぎも)の血を飲めば効くと、みずから刃を胸に立て、身を以(もつ)て、おのが潔白と義理をあきらかにする、というのが大方の筋です。
しかし、玉手御前が、自分より一つ二つ下の、美しい凛々(りり)しい若殿・俊徳丸にしかける恋の、「いつわり」というにはなんと切なく、もの狂おしいことでしょうか。

それは、タテマエのうちに、蛇(くちなわ)の舌のようにちろちろと仄(ほの)見えるホンネなのです。観客はそのホンネの物すさまじい嵐にまきこまれ、目もくらむここちがして、しばしタテマエを忘れます。
「俊徳様のおん事は、寝た間も忘れず恋ひこがれ、思ひ余ってうちつけに、いふても親子の道を立て、つれない返事かたい程、なほいやまさる恋の淵(ふち)。いっそ沈まばどこまでもと跡を慕うてかちはだし。あしの浦々難波潟(なにはがた)、身をつくしたる心根を、ふびんと思うてともどもに‥‥」
おどろき怒る父、悲しむ母。俊徳丸の怒りと嘆き。
「ヘェ、情けない母上様。‥‥親子の中々に、恋の色のとかほどまで、慕ひ給うは御身ばかりか。宿業深き俊徳に、まだまだ罪を重ねよとか。‥‥道をも恥をも知りたまへ」「涙とともに恨み」む俊徳丸、けれども玉手御前はきき入れません。
「恋路の闇に迷ふた我身。道も法も、聞く耳もたぬ。モウ此の上は俊徳さまいづくへなりとも連れのいて、恋の一念通さで置こふか、邪魔しやつたら蹴殺す」
と、俊徳丸の手をとって引き立て、
「ア、ラ、けがらはし」
とふり切る青年をはなれじやじと追い廻し、俊徳丸のいいなずけの浅香姫が、
「エ、あんまりでござんすわいな」
とささえるのを、「ふみのけ、蹴のけ、怒る目元は薄紅梅、逆立つ髪は青柳の、姿も乱るる嫉妬の乱行‥‥」
とうてい成らぬ恋になのでした。玉手は義理の名分にかくれてホンネの恋をここで明かしてしまったのです。
先妻の子との悲恋、というテーマはラシーヌの悲劇「フェードル」にも扱われています。清らかな心の王子イポリットを、義理の母のフェードル王妃は愛してしまいます。邪恋をみずから恥じ、戒めながらも、あらがいがたい運命の力に引きずり込まれ、王妃・フェードルは破滅します。しかし日本のフェードル・玉手御前の恋は、もっと戦慄的な魅惑を感じさせます。それは義理、忠義のためというタテマエにかくれた、甘美で恐ろしいホンネだからこそ、その不倫のドラマが、人々の心に二百年もの間、共感されつづけてきたのでしょう。
ころもがへ
御手討の夫婦なりしを更衣(ころもがえ) 蕪村(ぶそん)江戸時代には(旧暦)四月一日、十月一日をもって春夏の衣を更(か)えました。いまは四季、かわらぬ風俗ですが、町中いっせいに、衣がぬぎかえられる季節は、ほんとうに、季あらたまるという感じだったでしょう。珠には初夏、風かおえる日、町にははろやかな春着、夏着のあふれるうれしさ。
「人は春服をととのへて高き丘にのぼり、春風春水一時に来るというた」うのです。
ほととぎす。花たちばな。一年で一ばん美しいとき。
蕪村は、この美しい季節に、御手討ちの夫婦」を配したのでした。
私は、この句をことさら秀句とも思いませんが、でも、たいへん好きなのです。
蕪村の句には、たのしいフィクションが多いのです。彼は歴史絵巻風な、物語の一シーンのような句をたくさん作りました。
鳥羽殿へ五六騎いそぐ野分かな
指貫(さしぬ)を足でぬぐ夜やおぼろ月
私は、これらの句から、物語をあれこれ作りつつ、一句また一句とよむたびに、本を一冊読んだような、豊醇(ほうじゅん)な酩酊を与えられます。蕪村の句は、さながら一篇の小説と同じ重みに感じられたりするのです。
御手討の夫婦も、たぶん蕪村の想像でしょう。現実のことではありますまい。
武家方では恋愛は、きついご法度(はっと)です。もし露顕すれば、不義者として成敗されてしまいます。でも、若侍と、可憐なお腰元は、(勘平とお軽のような)いつとなく、恋し合ってしまいました。お家を乱す不義者と、あたまの固い三太夫は声をあららかに詰(なじ)ろうとしますが、やさしい奥方は、かげになり、日向になってかばわれたかもしれません。
〈殿に申し上げます〉と白髪あたまをふりたてて青筋立てている三太夫を、奥方はまあまあ、と抑えて、〈わたくしに任せておきや〉などといわれる。殿様のごきげんのおよろしき時など見計らって、そっと心配りして、よしなにとりなされたことでしょう。怒りっぽい殿さまのことですから、持ってゆき方によっては、どんな大事になったかもしれません。でも怒りっぽいだけに根は単純で善人なので、奥方のとりなしで、〈よきにはからえ〉とおうようにいわれたでしょう。
奥方はそっとお腰元と若侍を、しるべのもとへ落してやったり、身の立つようにはからい、新生活のはなむけを下さったかもしれません。
とび立つ思いのお腰元と、若侍。本来なら二人重ねて御手討ちになっても文句のないところなのに。希望にみちてお邸を出ます。
晴れて二人の人生がはじまります。町は初夏、さわやかな衣更えの季節と同じく、二人もまた、生まれ変わったような人生の第一歩なのです。
「更衣」には、たくさんの句があります。でも有名な「越後屋の絹裂く音や更衣」(其角「きかく」)などよりもやっぱり、私は「御手討の夫婦」と更衣のさわやかな季節のとり合せを、ことに面白く蕪村らしいと思います。
そういえば、「野分」の句も、べつに何が上についてもよいわけです。しかし、「鳥羽殿」ときたとき、これはやはり「野分」という語と、「鳥羽殿へ五六騎いそぐ」という状景とはぬきさしならぬものと感じられます。「おぼろ月」も指貫でなければならない的確さがあります。
蕪村は不義者、いたずらものたちにあたたかい共感をよせ、祝福しています。更衣という、さわやかで美しい季題に配するには、絶対、御手討ちになるべかりし恋人たちでなければならないのでした。
ありがひもなき世間
無住(むじゅう)というお坊さんが十三世紀の終わりごろいました。彼は名僧とうたわれた人ですが、生来、話好き、酒好きの、垢抜けた坊さんでした。六十ちかくになって、それまで見聞きしたさまざまのことを書きとめたくなって、「沙石集(しゃせきしゅう)」という本を書きました。書き出したのは、弘安二年(一二七九年)ごろ、つまり蒙古来襲の二年前で、しだいに物情騒然としてきたころです。「沙石集」は「古昔物語」と同じように、庶民生活のさまざまのエピソードを集めています。私は、「沙石集」から、よく小説の材料を仰ぐことがあります。ただ、無住はそのつもりで書いたのでしょうが、終わりは必ず、仏道談義、信心のすすめ、で結ばれているところが特徴です。そして、無住の見識はすべて、すぐれて味わい深く、彼がなみなみならぬ「人生の達人」だったことを思わせます。それに、一つ一つの話の面白さは無類で、読んで楽しいのです。文章も、男らしく硬質で、簡潔です。
私の好きなお話は、巻九「君ニ忠アリテ栄(さかえ)タル事」というのです。
ある年、世間でふしぎなことがはやりました。くじで相手をきめて互いに贈り物をすると、不慮の災難(無住は、横災(おうさい)、ということばを使っています)をまぬがれるという迷信です。身分高きもいやしきも、このくじに夢中になりました。
あるお公卿(くげ)さまのお邸でも、くじ引きがあったのですが、当主の殿のお相手を引きあてたのは、なんと、一ばん貧しい、殿にお目通りもかなわぬような身分の侍だったのです。
「不運ノ至リ」と彼は思い、周囲もそう、うわさしました。
男は悄然(しょうぜん)と家に帰り、妻にいいました。
〈長いことお世話になった、死なばともに、と誓いあった夫婦の仲だけれど、もうおしまいだよ。私は出家して世を捨てるつもりだ〉
妻は驚いて問い返します。なぜ、そのようなことを‥‥。この妻も、ささやかな商いをして世をわたる「貧シキ女人」なのです。
男はわけを話します。互いのくじの相手には、それ相当の贈り物をすべきなのです。これが同輩なら適当にごまかせるのですが、殿が相手では、どうしようもありません。見苦しいものでは恥をかき、人に笑われるだけ、りっぱなものを用意しようとすれば資力がない。この上は、あとをくらまし、夜逃げをするのみだ、というのです。
妻はすぐ、答えました。
〈何をいうの、あんた、このあばら家と土地を売ったら何とか金はできますよ、同じ出奔するなら、ちゃんと殿さまへ失礼のないようにりっぱな引き出物を差し上げ出ればいいじゃないの〉
夫は妻の優しいことばをきいて心苦しさがまさります。
〈今まで貧乏で、お前にいい思いの一つもさせることができなかった、それなのにこの上、おれのためにお前まで流浪させるなんて心苦しいよ〉
妻はさえぎって、原文によれば、「先世ノ契リアレバコソ、妻夫(メヲト)トモナリテ、今日マデ志カハラズテ、スゴシラメ。栄ヘバ同ジク栄ヘ、惑ハバ共ニコソ惑ハメ」
妻は、当然のような顔つきで、更に言いつぐのでした。
〈あんたが出家するというんなら、あたしも共に尼さんになりますよ〉
そして彼女は、強く、こう言い放つのです。
「コレホドノアリガヒモナキ世間ハ、惑フトモ歎クニモタラズ」――こんな、生きてる甲斐(かい)もない世の中は、行き場に困ったり歎(なげ)いたりするほどのこともありませんよ。
夫は妻に励まされ、家土地を売ってその金で金銀の細工物をつくり、当日、殿に献上しました。貧しい彼が何を持ってくるかと、目引き袖引きしていた人々は、あっと驚いたのです。殿も感嘆され、その返しの引き出物に土地を賜わり、その男は以後、あべこべに大いに富み栄えた、という話です。無住は、「妻ノ志コソマメヤカニ哀れニ覚ユレ」といっています。
私はこの妻の、したたかな人生観を示す言葉を、愛するものです。彼女のうちには、人生で一番大切なものと、そうでないものとの違いがハッキリしています。彼女が即座に夫との愛を選んだとき、「コレホドノアリガヒモナキ世間」と吐き捨てるようにいえたのは、無学な貧しい彼女が、その違いだけは知っていたからなのです。
薄幸の皇后
「枕草子」には、一条天皇(在位九八六年――一〇一一年)の皇后・定子(ていし)の、後宮サロンのありさまが活写されていますが、作者・清少納言が、ことに心を尽くしてうたいあげているのは、定子皇后のめでたさです。定子皇后は、一条天皇より四歳お年上であられました。少年少女のころに結婚された一条帝と定子皇后は、非常におん仲むつまじく、帝には、あまた后がおありでしたが、どんな女人も、帝から定子皇后への愛を奪うことはできなかったのです。
それがどんなに大きな価値のあることだったかは、この時代の歴史を少し読めばわかります。定子皇后は、たよりにする父の中(なか)の関白・藤原道隆に死別し、兄の伊周(これちか)・隆家(たかいえ)らは叔父の道長のために政治的に失脚させられ、孤立無援のお立場でした。しかも道長はわが娘・彰子(しょうし)を一条帝の中宮に立て、陰に陽に定子皇后を圧迫していたのです。
でも皇后は、清少納言の記述によれば不遇の時代もいつも変わらずお人柄のけだかく、やさしく、なつかしい方でいらっしゃいました。才気かんぱつの清少納言がすこしひびきのにぶい男――たとえば大進生昌(だいじんなりまさ)らを揶揄(やゆ)したりしているのを聞かれると、
「あはれ、かれをはしたなういひけんこそ、いとほしけれ」(まあ、かれをはしたなういひけんこそ、手ひどくいいこめたりして、かわいそうではありませんか)
「例の人のやうに、これな、かくな、いひ笑ひそ。いと勤厚(きんこう)なるものを」
(ふつうの人のように、あの人をいろいろからかったり笑ったりしないでおきなさい。まじめで、りちぎな人なのですよ)ととりなされるのです。
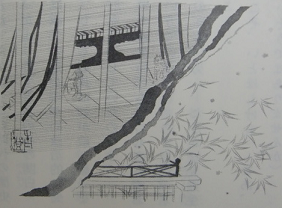
「いとほしがらせ給ふもをかし」
と、清少納言はいっています。生昌がやってくると皇后は、
「また、なでふこといひて、笑われんとならん」(また、どんなことをいって、皆に笑われようとするのかしら)
などと、気の毒がられたりします。生昌は、鈍いけれども純真な男らしく、自分はやり込められながらいつも清少納言の才気に関心しています。「すこし申し上げることがございます」とわざわざ呼び出すので清少納言が出てみると、
〈私の兄も、あなたをほめておりました。いつか、適当な折にお目にかかって、ゆっくりお話をうけたまわりたい、と申しておりました〉
ということで、べつに何のことでもなく、清少納言ほどの才気ある女が、生昌の兄に褒められたとてどういう気もないのでした。それで清少納言たちの嘲笑をまた買うのです。それを皇后はまたたしなめられて、
「おのが心地にかしことと思う人のほめたる、うれしと思ふと、告げ聞かするにらん」(自分の心に一ばん賢いと思っている兄が、あなたを褒めたので、そのことを聞かせたらさぞ嬉しく思うだろうと思って、わざわざ知らせにきたのですよ)ととりなされるのでした。
「のたまはする御(み)けしきもいとめでたし」
と、清少納言は感じ入っています。
清少納言の勝気さを示すエピソードとしてよく知られている「雪山」事件。長徳四年の十二月十日、大雪が降りました。雪の山を御所の庭に作り、いつまであるかしらと、皇后のおことばでそれぞれ、十日、二十日すぎとお答えしたのです。途中、雨ふりがあったり、いろいろハプニングがおきましたが、まさかと人々は思ううち、とうとう雪の山はだいぶ小さくなりながら年を越しました。清少納言の得意はいうまでもありません。
十五日には盆に盛って皇后の御前に献上し、人々の鼻を明かせてやろうと、手に汗にぎる心地で、十五日を待つのでした。雪の山はまだ円座くらいに残っています。十五日未明、暗いうちに下男に取りにやらせると、こはいかに、なくなっていたのです。皇后のお心づかいなのでした。あまりにもあざとく勝ち負けをあらわにして、人々に清少納言がにくまれても、と思いになって、侍たちにいって取り捨てるようはからわれたのです。
「いま、かくいひあらはしつれば、おなじごと勝ちたるなり」(いま、こうやってほんとのことをいった上は、あなたが勝ったも同じでしょう)
と人々の前でなぐさめられるのです。
こういう練れたおやさしいお人柄を帝がお愛しにならぬはずはありませんでした。皇后はわずか二十五歳でなくなられたのですが、一条帝に最後まで熱愛されたその短い生涯は、決して薄幸ではなかったと、円地文子氏も「なまみこ物語」で讃(たた)えていられます。
老いゆく君
天(あめ)なるや月日の如くわが思(も)へる君が日にけに老ゆらく惜しも「萬葉集」巻十三にある雑歌(ぞうか)で、長歌の反歌ですが、作者はわかりません。
天にある月や日のように私が思っている君が、日に日に老いてゆかれるのはたいへん残念だ――というような意味でしょうか。
私は、この歌をはじめて見たときから、ふしぎな歌だと思いました。萬葉人の心は現代人にはわかりにくいニュアンスがあるのかもしれないのですが、「日にけに老ゆらく惜しも」というからには、自分も老いているのです。でも、自分の老いのことは作者の念頭にはないのです。この反歌の前の長歌は、こういうのです。
「天橋(あまはし)も、長くもがも 高山も 高くもがも 月読(つくよみ)の 持てる変若水(をちみづ)い取り来て 君に奉りて 変若(をち)得しむもの」
これは、現代では、「天にのぼるハシゴも長くあれ、高い山もいや高くあってほしい、そのハシゴや高山のようにいついつまでも、若くあってほしい、月の神のもっていられる若返りの水をとってきてわが君に奉って若返らせたいものを」というような意味でしょう。
作者は、わが老いを棚に上げて、ひたすら、自分の尊しと思う相手のことを考えています。
相手はだれでしょう。
私は、異性でなく、同性のような気がします。長いこと、ま心こめて仕え、身を粉にしてつくし、その献身ぶりには、仰ぎみるも眩しいというような、愛慕と渇仰(かつごう)と、それに一抹の、性愛的な気分もあります。
たぶん相手は身分の高い人なのでしょう。歌から見ると、その決して巧みとはいえない、ゴツゴツした修辞や発想から、男性のような気がします。
これは草ふかい田舎から連れてこられた男、土の匂いのする男が、長いこと都の貴人の一人に仕えてきて、掌中の珠のように大事に思い、生涯の忠誠を誓い、おそらく愛情のすべてをかたむけてきた相手に対する思いでありましょう。
その相手と自分との間をつなぐ感情の交流は、同等のものではありません。下から上へ、一方通行のものらしく思われます。
266ぺーじ写真
この男にとって、その君は、唯一絶対のものなのです。高貴な血といい、けだかい心といい、美貌といい、身分といい、‥‥そういう神か人かというような、見るもまばゆい、賛嘆(さんたん)の対象が、やはりこの世に生きる人間の常として、老いてゆくということを、目のあたり見た。男にとっては、深き嘆きであると共に、愕然と世の無常を悟る契機であったのでしょう。
でも、むろん無常感というような、屈折した心理は、この素朴で、原始的な男には無縁のものです。
男は、折々、痴呆(ちほう)のように、宝の「わが君」をぬすみ見たりしています。すこし面(おも)がわりされたのではないか。すこし、このごろはお疲れになることが多くなったのではないか。
昔は、こんなことはなかった。強くてたくましくて、もっと美しくていられたような気がするが。
そういう男自身、ほんとうは老いてきています。でも自分自身のことは気づかないのです。
共に老いてきたなあ、という感慨などは、数ならぬわが身の、男の心をかすめることさえないのです。男の生涯の夢もロマンも、すべて、月・日のごとく輝かしい「わが君」にあるのです。
そういう素朴な男が考えられることは、伝説の「若返り水」だけです。自分が飲むことは夢にも思わず、わが君に捧げることばかり考えています。献身者のエロティシズムのほのみえる、私が「ふしぎなうた」という所以(ゆえん)です。
恋のあはれ
「徒然草(つれづれぐさ)」は、学生の教科書や試験問題によく用いられるので、つい、初歩的な国語テキストのように思われがちですが、本当は、おとなのよむエッセー集です。若年のころより、中年、老年になるに従って、ますます面白く、そして解釈もちがってくるからです。たとえば第三段階の、
「よろずにいみじくとも、色好まざらん男は、いとさうざうしく(殺風景、不風流なこと)玉のさかづきの当(そこ)なき心地ぞすき」
どんなにりっぱな男でも、恋のあわれを解しない男は、玉の盃の底なきようなものだ――この文章に秘められた含蓄は、おとなの人間にして、はじめて味わえる面白さです。
作者の吉田兼光(けんこう)がこれを書いたのは、四十台の後半でした。彼の生きた十三世紀の末は、鎌倉幕府崩壊の直前という動乱時代でした。彼は早くに世をすて、いわば傍観者として世を見、人を見、恋を見、彼一流の見識をつくりあげました。
彼の恋愛美学は、恋に迷い、恋にやつれつつも、恋に溺れず、女にも見くびられたりしない、そういうのが、男として恋する人として「あらまほしかるべきわざなれ」というものです。
かねて私は、第百五段の、男と女の、忍び会いをさらりと描いた美しいスケッチが好きでした。
「北の屋かげに消え残りたる雪の、いたう凍りたるに、さし寄せたる車の轅(ながえ)も、霜いたくきらめきて、有明の月さやかなれども、くまなくはあらぬに、人離れなる御堂の廊に、なみなみにあらずとみゆる男、女と長押(なげし)に尻かけて、物語するさまこそ、何事にかあらん、尽きすまじけれ。

かぶし、かたちなど、いとよしと見えて、えもいはぬ匂いひの、さとかをりたるこそ、をかしけれ。けはひなど、はづれはづれ聞えたるも、ゆかし」
いてつく有明の月。人けのない御堂の廊に、普通の身分でないような男――いずれ名ある貴公子でしょう――が、美しい女と、長押に腰をかけて何事か、いつまでも尽きない話をしている。女のあたまの格好、顔立ちなど、いかにも美しく、たきしめた香の匂い立つのも風情がある。ひそひそという話し声のはしばしが耳に入るのも、心をそそられ、思わずきき耳をたてたくなる‥‥兼好は、そんな「恋の情趣」を愛した男でした。
彼の見識によれば、恋はそばから見て、「何事にかあらん‥‥ゆかし」と心そそられるようなものであるべきであり、女はそのために添景人物だったのです。
だから、現実の女は、これは彼からみると、「人我(にんが)の相ふかく、貪欲甚だしく、物のことわりを知らず」言葉もたくみに「苦しからぬ事をも問ふ時は言わず。用意あるかと見れば、また、浅ましき事まで、問はず語りに言ひだす。ふかくたばかり飾れる事は、男の知恵にもまさりたるかと思へば、その事、あとより顕(あら)はるるをしらず」というおろかさ、彼はこともなげに「女の性(さが)は、みなひがめり」と断定します。さればとて「もし賢女あらば、それも物うとく、すさまじかりなん」
女について点の辛い彼が、全文でただ一ヶ所、ほめています。ある男が、久しく訪れない女のことを「いかばかり恨むらん」と思いやって、弁解の言葉もなく気になっているときに女の方から「仕丁(じちょう)やある、ひとり」と言ってよこしたのです。仕丁は人夫、何か女の家でとりこみごとがあったので人手が要ったのでしょう、仕丁がありますか、一人貸して、と言ってよこした。「ありがたくうれしけれ。さる心ざましたる人ぞよき」――そんな、あっさりした気立ての女が、とても好もしい、というのです。
しかし、中年女の私は、いま「徒然草」を読み返してみて、そういうあっさりした女は疑問だと思いました。もしかして男の反応を予期してそういってよこしたのかもしれない。「いかばり恨むらん」と思っている男の心を察して、さりげなく、きっかけを作っているのです。
だとすればすばらしく賢い、女臭い女、女の中の女なのです。そして女なら、誰でもこのくらいの恋の駆け引きには、長けています。――兼好は、ほんとうの女、ほんとうの恋を知らなかったのではないでしょうか。恋人たちを鑑賞し、「恋のあはれ」についての評論家ではありましたが、「恋する男」ではなかったような気がします。
夕顔
夕顔の花の咲く季節になりました。「源氏物語」の数あるヒロインの中でも、ことに「夕顔」の君は、あえかな美女です。弱い内気なやさしい性格の、なよなよと心もとなく、男の庇護本能をそそらずにはいられないような美女なのでした。
それはさながら、夏の夕、垣根などにまつわるツル草に、ひっそりと咲く夕顔の花の象徴のようでもありました。
光の君は五条わたりの下町へ、身をやつして乳母の病気を見舞いにゆき、はからずも、燐家に隠れ住んでいる「夕顔」を見染めます。
私はこのくだりがことに思い出がふかいのです。
私は終戦の前年の昭和十九年に、旧制女子専門学校の国文科に入学したのでした。あるとき洗面所にいきますと、美しい上級生が数人やってきて試験の話でもあるのか、源氏の「夕顔」の巻について話し合っていました。と、中のひとりが、きれいな声で口ずさみました。
うちわたす 遠方人(をちかたびと)にもの申す
そのそこに白く咲けるは 何の花ぞも
そのとき、どんな話を彼女たちが交わしていたか、具体的にはおぼえがありません。けれどその古歌は、なぜか、れいろうと澄んだ声とともにいつまでも私の心にしみました。いまでも時にふれ、耳の底に甦ってきます。それから、毎日の国文科の授業が心の底から好きで楽しかったことも。
――それは、入学して五カ月ばかり先には、もう学徒動員で、学校を離れて航空機の部分品をつくる工場へやらされることが、わかっていたからでもありました。ペンを持つ手で旋盤を扱うことを強いられたとき、短い間の学校の授業は、一瞬一瞬をぬすむような、強い喜びでした。あんなに学ぶことへの緊張と熱愛がたまったことは、生涯で二度とないでしょう。それは男子学生が、ペンに銃を持ち換えて戦場におもむくことを義務づけられた、それまでの数か月間、勉強や学問に感じた執着と同じ類のものだったでしょう。
そんなときに聞いたので、よけい印象的だったのでしょうか。
「源氏物語」では、光の君は「うちわたす遠方人」と口ずさみ、〈花折ってまいれ〉と随身(お付き武官)にいいつけます。するとその家から少女が出て来て、白い扇を差し出し、これに乗せてお目にかけて下さいましと随身にいいました。移り香もゆかしいその扇には「心あてにそれかとぞ見る白露の光そーたる夕顔の花」という歌が、みやびやかかな手で書かれてあり、光の君の好きごころをはげしくかきたてたのでした。
こうして「夕顔の君」は光の君の愛人になりますが、物の化にとりつかれてははかなく身をまかせてしまいます。夕顔の花の印象のような、というゆえんです。
室町時代の小唄にも、「五条わたりを車が通る 誰(た)そと夕顔の花車」というのがあります。
「夕顔」といえば、「源氏物語」を思い浮かべるのが、古典教養の決まりのようになりました。けれども「源氏」にかぎらず、夕顔のテーマは、女のものらしく思われます。私の好きなのは、
夕顔やなごのはだの見ゆるとき
という、加賀の千代女の句です。夏の夕、下町の卑し気な庶民の住まいに夕顔がほの白く浮かんでいる。夏は行水のあとであるのか、ふと肌をすこしくつろげて、すず風をいれている。ちらりとみえた女の白い肌が、うく闇の中に夕顔の花と見間違うばかり浮き上がる。そんな美しい女っぽい句です。
千代女には、「朝顔につるべ取られてもらひ水」という有名な句がありますが、私は夕顔の句の方が、艶な花やぎがあって美しく思われます。
それにしても、「うちわたすをちかたびと‥‥」と澄んだ声で私の耳と心を洗ってくれたことでしょうか。あれからもう、三十年たちました。
朝光(あさてる)の恋
閑院(かんいん)の大将、藤原朝光卿の、新しい恋人を知って、世間はあっと驚きました。あまりにも、その取り合わせが、思いがけなかったからです。朝光は当時、たいへん人気のある、人々の愛された貴公子でした。堀川関白の次男で兄をこえて父に寵愛(ちょうあい)され、若くして高位高官にすすみ、その美貌、優雅なものごし、端正な心映えを、世にうたわれた青年貴族でした。
彼には早く結婚した美しい北の方(妻)がありました。北の方は重明親王の姫君という高貴な身分に加え、二人の間には可愛い子供たちさえ生まれていました。
身分といい、年恰好といい、容姿といい、まことに一対のお雛様のような似合いの夫婦だったのです。
それを朝光はうちすて、心変わりしてしまいました。そして新たに作った恋人は、枇杷(びわ)大納言・延光(のぶみつ)卿の未亡人、年のころなら四十すぎ、朝光の親のような人で、この人の娘すら、朝光より年上でした。
「大鏡」という本には、「色黒くい額には花がたうちきて(シワのあること)髪ちぢけたるぞはしける」とあります。
片や、花の如き青年貴公子。
片や、老いた醜婦。
このとりあわせは世間の好奇心を刺戟(しげき)し、にわかに同情は、朝光のもと北の方に集まり、朝光は指弾のまとになりました。
「大鏡」には世俗の解釈をそのままに、朝光が金にころんだのだ、と断言しています。
延光卿の未亡人は金持でした。朝光を自分のもとへ通わせるようになると、「女房三十人ばかり、裳(も)・唐衣(からぎぬ)きさせて」何ともいえぬほど美しくよそおわせ、並べて出迎えました。
「めでたくしたてて、かしづき聞こゆる事限りなし」と「大鏡」にあります。朝光が帰ってくると冬は炭火をふんだんに埋めて伏籠(ふせかご)に着換えをかぶせてあたため、薬もさまざま用意し、畳の上敷に綿を入れ、やすむときは侍女三四人が火のしで床をあたたかにのし撫でるという世話ぶり。「あまりなる御用意なりしかし」と「大鏡」は、揶揄(やゆ)しています。
そして本人の未亡人は、黄ばんだ絹の綿入れの衣など着て、白い袴をはき、化粧げもなく、自分の容貌を知ってそんな身なりをしてらしたのだろう、「誠にやその御装束こそかたちにあひて見えけれ」と「大鏡」は辛辣に未亡人をこき下ろしています。
「大鏡」には、朝光がこの未亡人を選んだことを、「徳につき給へるとぞ世人申しし」
お金を持っている方に傾いたのだと世人はいった、とありますが、果たしてそうでしょうか? 「大鏡」はその筆致からして男性のものした本だと思われますが、私には「大鏡」の解釈は、いかにも男性的粗放さがあるように思われてなりません。
男性的思考の単純さ、独断があるように思えてなりません。
与謝野晶子も、指摘していますが、朝光という人は、本来、富裕な貴族なのです。彼は父の遺産を受け継ぎ、更に、彼を愛した異母姉の、円融院中宮・皇女の遺産も、相続しています。金ばかりでは、なかったのではありませんか。
世間の人は、おそらく、四十すぎの初老の女と(当時では初老に近かったのです)二十七八の青年が恋し合うことなど、有り得ないとさかしらにきめているのです。でも、朝光とこの婦人との間に、どんな恋が芽生えていたのか、二人のほかには誰も知らぬことなのです。
「栄花物語」はさすが女の筆なので、この間の消息を伝えています。
「かの枇杷の北の方いみじう、賢うものしたまふ人なり」それにくらべ、もとの妻は「ちごのやうにおはなしければ」とあります。あまりに子供っぽい妻にくらべ、未亡人の聡明さは朝光の心を捉えて離さなかったのかもしれません。朝光はこの人に、女の真の美しさを見たのかも知れません。
朝光は生涯ついに、「親のような」年上の妻と添い遂げました。千年の昔の話です。
おちくぼ
「源氏物語」が書かれる前後、世間にはたくさんの物語が流布していました。「枕草子」や「更級日記」を見ると、見慣れないタイトルがいっぱい並んでいます。「住吉物語。埋れ木。月待つ女。梅壺の大将。松の枝(え)。こま野。ものうらやみの中将。交野の少将。とほ君。せりかは。しらら。あさうづ。みづからくゆる。かばねたづぬる宮」‥‥なんという、心をそそる題でしょう。
でもかなしいことに、これら、さまざまの物語は、当時の人に愛読されつつも、いつとなし散り散りになり、やがてわすれられ、消えてゆきました。
あるいは「源氏」という強い輝きをもった美しい星の前に、光を失ったというのでしょうか。また、「源氏」という巨大な本流にそれぞれの小川は、まきこまれ、合流したというべきかもしれません。
その中で「源氏」に吸収消化されぬ、異質の個性をもった物語だけが、千年の風雪に堪えて生き残りました。「伊勢」「竹取」「宇津保(うつぼ)」「落窪(おちくぼ)」などです。
私はこの、「落窪物語」がとても好きなのです。
これはいかにも男性の筆になると思われる、(作者も書かれた時期もわかりません)
大まかで粗っぽいタッチ、しかも構成がきちんとしていて、いきいきとマンガ風な人物、たいへんよくできた楽しい通俗小説なのです。
「落窪」は昔から、まま子いじめの物語、で通っていて、まま母・まま子への大衆の同情関心が、この小説を生きのこらせたのだという人もありますが、それだけではないでしょう。

ある中納言の亡くなった妻の忘れ形見の姫はまま母の北の方に冷遇されて、離れの、一段低くなった間におしこめられ落窪の君とよばれて、憂くつらい日を送っていました。北の方の産んだ姫たちは花やかにしずかれ幸福な結婚もしているというのに、落窪の君はたべものもなく、着物もなく、ひもじい寒い思いをし、異腹の姫の婿のため、お針女の仕事に追いまくられるという暮らしでした。
でもこのシンデレラに、王子さまが現れました。左近の少将というすばらしい貴公子です。少将は姫の逆境に同情し、また、その美しさやさしさ聡明さに魅せられ、ひそかな恋人として通います。少将の従者、帯刃(たちはき)と姫の侍女、あこぎの二人が、それぞれのあるじのため、心をくだいて恋をとりもつおもしろさ。
北の方は姫に恋人がいると知って、夫の中納言にあしざまに告げ口し、姫はとうとう一室に錠をおろして閉じ込められてしまいます。その上、北の方は好色な老人の典薬助(てんやくのすけ)をやって姫を襲わせます。あやうし、落窪の君! もう猶予はなりません。
少将は帯刀とあこぎの手引きで、北の方らの留守を幸い、姫を救いにのりこむ。錠があかないので男二人の力で戸を打ち壊し、姫を抱いて車に乗せ、首尾よく邸につれ帰りました。北の方らが帰宅して大騒ぎ、北の方は誰の仕業とも分からないので怒り狂います。
読んでいて思わずハラハラして手に汗をにぎり、北の方がしてやられたところでは快哉を叫んだりする、ほんとうにページをくるのももどかしい面白い部分です。
さて、このあと少将は、存分に北の方に復讐します。そして姫は、少将の出世につれ、いよいよ幸福なくらしを送ります。
作者は庶民の願望に充分にこたえて、その栄華の物質的幸福を力こめて詳述するのですが、それよりも女性読者をひきつけるのは少将の純愛です。少将は大臣の姫の婿にと懇望されたのをふり切って、財産も親の後ろ盾もない、みなし子の姫をただ一人の妻として貞潔を誓うのでした。これはいかにも通俗小説の典型でしょう。善玉悪玉入り乱れ、美しい聡明なやさしいヒロインが運命に翻弄される、純愛あり謀計あり、復讐ありの面白いよみものです。でも、大衆の共感と喝采(かっさい)は、まさに少将と姫の純愛にあったのです。永遠に古く、永遠に新しいテーマだったから、千年の風雪に堪えたのです。
やさしいサムライ
「花の都の室町に、花を飾りし一構へ、花の御所とて時めきつ、あさひの登るいきほひに。文字も縁ある東山‥‥」
このやさしげな、平明な書き出しではじまる小説「偐紫田舎源氏(にせむらさきいなかげんじ)」が文政十二年(一八二九年)はじめて刊行されたとき、満天下の女性たちは熱狂して迎えました。以後、天保十三年(一八四二年)に、お上のお咎めをうけてその版木を没収されるまで、十数年のあいだ、ロングセラーをつづけたのです。
作者の柳亭種彦(りゅうていたねひこ)は、「源氏物語」を巧みに翻案(ほんあん)して、上品な通俗小説とでもいうべき、新しい面白い味わいを作り上げました。
舞台を室町時代の足利将軍家にうつし、主人公は足利光氏(みつうじ)に、桐壺は花桐に、藤壺は藤の方に、葵の上は二葉の前に、名を変え趣向をこらし、こまやかでデリケートな構成です。しかも登場人物の生活感情は全く現代風で、美男の若殿をめぐる、美女群の確執、陰謀、恋のさやあて、純愛、嫉妬、‥‥それらはどれほどその頃の女心をかきたてたことでしょう。
江戸城大奥の女中たちも、自分たちがモデルのように熱狂し、この小説は大当たりでした。着物の柄から、芝居、錦絵、生人形にまで「田舎源氏」はもてはやされ、種彦の名文はあがりました。
光氏が義理の母、藤の方をくどく文句のやさしいしおらしさ。
「水より清い御身をば、わたくし故に濁らせます。此の世ばかりか前世から、結びおいたる悪縁と、思へばいとど悲しきを‥‥」と手をとれば義母の藤の方も「道にそむくはそなたのため、命捨てるはかねての覚悟‥‥」
この柔媚(じゅうび)な小説をかいた種彦は、本名を高島彦四郎知久という、小身ながら、れっきとしたご直参の旗本でした。でも四角張って生きるのを好まぬ、武士らしからぬやさ男なのです。本所生まれの下谷育ち、江戸末期の燗熟した文化の露を吸って、いっぱいひらいた大輪の花のような才能にめぐまれながら、その出身は、両刀たばさむ身分なのでした。
種彦は教養も文才もありますが、武芸の心得はありません。銭湯へいって、田舎者の勤番侍が、お湯をうめていると、
〈江戸っ子はあつ湯を好むものだ〉
といって侍たちに水舟へ投げ込まれたりします。荒っぽい田舎侍にどうしてかないましょう、種彦はあやまって、勘弁してもらいました。
また、朋輩(ほうばい)の侍と話していて役者の路考(ろこう)を〈路考さん〉とさんづけで呼び、朋輩の侍の怒りを買ったりします。〈武士たるものが、役者づれの卑しい河原者(かわらもの)をさんづけするとは何ごとぞ。何という性根の腐った奴。そこへ直れ!〉と槍をしごかれ、種彦は慌てふためいて逃げまどい、縁の下にかけこんで息を殺して隠れたりしました。
彼は切ったはったの暴力が大きらいな、心優しい、おだやかな知識人、趣味人なのでした。そして私はこんな男が大好きなのです。
やがて「天保の改革」と呼ばれる弾圧の嵐が吹きすさびました。老中・水野忠邦(ただくに)は人心を引き締めようと、春本、人情本のたぐいの売買を禁じたのです。戯作者(げさくしゃ)たちはどんどん処罰され、その版木は没収されました。種彦は武士ですので処罰は家名断絶、食禄おめし上げの形になります。封建の世の武士として家名の断絶は最低の不忠不幸です。種彦は、自決をえらびました。それなら本人病死という名目で、家名は残されるのです。
ちるものに定まる秋の柳哉(かな)
それが種彦の辞世でした。侍のきらいな種彦が最後は最も侍らしく死ぬことを強いられたのは哀れでした。杉本宛子氏の好短篇「偐紫楼の秋」(朝日新聞社刊「瑪瑙(めのう)の鳩」に収録)には、「やさしい侍」種彦のおもかげがほうふつとしています。
それにしても道徳倫理で文学を律しようとする官憲の場違いな弾圧は、今も昔も少しも変わりません。私は野坂昭如氏が起訴された「四畳半襖の下張」事件をあわせて思わずにはいられないのです。
1996年12月20日 上巻 田辺聖子 著
つづく 文車日記(ふぐるまにっき) 下巻
――私の古典散歩――
大君のみ盾