仁徳天皇の皇后、磐之媛は、古来から日本では嫉妬ぶかい悪妻の代表とされ、幾世紀もの間、彼女は、女の悪徳の権化のように貶められてきました。
しかし、どうしたふしぎか、「萬葉集」に採録されている彼女の四首の歌は、みなすばらしく美しい、いい歌なのです。
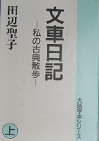 田辺聖子著
田辺聖子著
わが愛の磐之媛
わが愛の磐之媛(いわのひめ)
君が行き日長くなりぬ山たづね迎へか行かむ待ちにか待たむかくばかり恋ひつつあらずは高山の磐根(いはね)し枕(ま)きて死なましものを
ありつつも君をば待たむうち靡(なび)くわが黒髪に霜の置くまでに
秋の田の穂の上に霧らふ朝がすみ何方(いづへ)の方にわが恋やまむ
(あなたがいらっしてから、もう長くなりました。山をわけ入って迎えにまいりましょうか、それともこのままお待ちしましょうか‥‥ああ、こんなに苦しい恋をするくらいなら、山の岩根を枕に死んだ方がましでございます。あなた‥‥いえいえ、苦しみながらも、あなたが再びあたくしの手に戻られる日をお待ちしましょう。あたしの黒髪が白くなるまでも‥‥。秋の田の穂の上を流れる白い霞が、いずことなく消えてゆくように、あたくしのこの恋心も、いっそ消えてしまえばいいのに‥‥消え去りやらぬ、忘れ去りやらぬ、このわが心が、われとわれながら悔しく、悔しく、悲しゅうございます‥‥)
なんという美しい相聞(そうもん)でしょう。
おそらく、古代歌謡を通して第一級のうたです。しらべの優婉(ゆうえん)、詩句の美しさ。何よりも、この歌には切ないまでのリアリティがあります。女の吐息が聞こえるばかりの、なまなましく官能的な、それでいて清韻(せいいん)匂うばかりのしらべです。
この歌は、磐之媛が詠んだ、というのではありますまい。古い伝誦歌(でんしょうか)を磐之媛に仮託したものでしょう。
「君が行き日(け)長くなりぬ…」
のうたなどは、元来、死者の魂乞(たまご)いの歌だといわれています。折口信夫(しのぶ)の「死者の書」にあるように、招魂のため山奥へはいり、「こうこう」と呼ばうときの祭祀(さいし)歌かもしれませんし、のちの軽大郎女(かるのおおいらつめ)の歌もよく似ているので、こんな類似の民謡は、いくつもあったのかも知れません。
何にせよ、こんな美しい歌が、どうして所業醜く、心卑しい嫉妬深い磐之媛の作と伝えられてきたのでしょう。それがふしぎです。
もし、誰かの作と伝えるならば、私は仁徳がのちに皇后とした八田皇女(やたのひめこ)か、それとも女鳥皇女(めどりのひろみこ)、またのちの世の衣通姫(そとおりひめ)の作にでも擬すべきです。美しい歌は、あえかな美姫佳人(びきかじん)の口から洩れるにふさわしい。しかし古代の人々は、磐之媛の作、と伝えてきました。私はそこに、何か深い意味を見る思いがします。
歴史学者によれば、「記・紀」の編纂(へんさん)された八世紀は、すでに妻の貞節や婦徳が要求され出しており、その点、嫉妬ぶかい悪妻の磐之媛は、皇后たるにふさわしくないので、美しい伝誦歌(でんしょうか)を磐之媛の作に仮託して、イメージを改めるように作為した、とのことです、また、直木幸次郎氏は更に、藤原一族が孝明皇后冊立(さくりつ)の際、臣下から上がった皇后の先例として、磐之媛をあげましたが、その磐之媛が古来から悪妻という烙印を押されているのは困るので、政治的意図から、美しい相聞歌を磐之媛の作と擬した、というふうなことをのべていられます。まことにそうであろうという解釈で、頷けます。
けれども、磐之媛は背の君と別れてのちも「葉広(はびろ) 五(ゆ)百箇真椿(つまつばき) 其(し)が花の 広がり坐(いま)すは 大君ろかも」となつかしさに堪えず恋うる心を歌いました。この古拙な、直截(ちょくせつ)な歌いぶりはいかにも磐之媛のイメージにふさわしく、そうすると、あるいは「秋の田の…」の美しい相聞歌も、あんがい本当に磐之媛の作と伝誦されてきたのかも知れません。その矛盾がとけないまま「萬葉集」にものせられてきたのかもしれません。
磐之媛は葛城一族の姫でした。五世紀の時代は、大王と豪族はひとしい勢威をもっています。ことに葛城氏の勢力には怖るべきものでありました。一族の向背が大王家の運命を左右するくらいです。(私はこの時代のイメージとしては天皇でなく大王だと思います。)とくに葛城氏は五世紀大王家の外戚(がいせき)として栄え、威を振っています。
応神、履中(りちゅう)、反正(はんせい)、允恭(いんぎょう)、雄略、歴代大王の母はみな葛城氏、さらにいえば飯豊(いいとよ)王、顕宗(けんそう)、仁賢(にんけん)、清寧(せいねい)、みなは母葛城氏の出目、飯豊王にいたっては一種の巫女(みこ)的存在で、大王家と葛城氏との信仰的な関係の接点に立っていたのではないか、という学者もあります。
――なぜなら、葛城は魔霊のこもる特異な山界として怖れられていたからです。
一言主神(ひとことぬしかみ)という霊妙な畏怖(いふ)すべき魔神がひそんでいる山です。山人、土蜘蛛(つちぐも)、いずれも勇猛で不可解な、あやしい集団であったでしょう。葛城氏はそれをてなずけ、この地方に根を下ろし、更にはのちに対外的な政治上のポストにあったために、巨富を蓄積しました。
磐之媛の父、葛城襲津彦(そつひこ)は、「百済(くだら)記」という外書にも記載されている、四世紀末の実在の人物です。代々襲津彦の名を名乗ったのではないかと思いますが、磐之媛の父たる襲津彦は対朝鮮半島との外交に当たった将軍です。もしかしたら磐之媛は、大王家より豪奢(ごうしゃ)な生活環境に育ったかもしれません。
葛城の一族はたえず海外と接触し、侵攻し講和し、おびただしい武器、新知識、舶来の奢侈(しゃし)品、異族の美姫たちをたずさえて帰ったことでしょう、葛城一族の豪宕(ごうとう)な城郭には、ヤマトの文化圏とは異なった、より高度な、そしてエキゾチックな雰囲気があったでしょう。
そして襲津彦が新羅(しらぎ)の美女を納(い)れた、と史書にある以上、想像を逞しくすれば、磐之媛はハーフだったのかもしれない。あのスケールの大きな、古代に悪名たかき「うわなりねたみ」も、どうやら日本人ばなれした感じがなくもありません。
日本人ばなれしているはきっとその美貌も、だったでしょう。美しくて、しかも葛城一族の娘として驕慢(きょうまん)に育ち、打てば響く才気に加え、烈しく剽悍(ひょうかん)な彼女の性質は、この一族特有のものでありました。
いちずで烈しくて誇り高い、若き日の美しい磐之媛は、おそらく、臣下の出目、などというけちくさいコンプレックスは持たなかったとおもわれます。それに、彼女が仁徳と結婚したのは、仁徳がまだ一王子であった頃です。
葛城一族
仁徳には兄の大山守命(おおやまもりのみこと)、父王が愛して皇太子とした菟道稚郎子(うじのわきいらつこ)という王位継承者たちが、ゆく手をはばんでいました。
それゆえ、磐之媛と、彼女の一族の尽力がなければ、仁徳大王は出現しなかったでしょう。
記・紀によれば、大山守と稚郎子が争い、大山守が死また稚郎子も自殺します。儒教風潤色が多いとはいえ、ある政治的策謀の臭いもします。仁徳は直接でなくとも、兄弟を殺しをしたのです。血で血を洗う争乱、火花の出るような謀略と策術が横行したにちがいない。
――王位は、最も沈着に、知性と勇気に富んだ者の手におちた。仁徳はついに邪魔者を蹴りおとして王位についたと思われます。その背後には葛城一族の力があったからこそです。
磐之媛(いわのひめ)は大后(おおきさき)と呼ばれました。二人は夫と妻、又は大王と大后というより、もはや悪事の共犯者、同志でした。二人は相扶(た)けて王位にのぼりました。いわば糟糠(そうこう)の妻です。
磐之媛は仁徳を愛していました。ほかの女が近づくと足音もあららかに地団駄ふむので官女も部屋に出入りできぬほどです。一方、仁徳のほうは好色多淫な父の応神大王の血を享(う)けて、オオサザキと呼ばれ青年の頃から、名だたる魚色漢でした。吉備(きび)の美女、黒比売(くろひめ)をせっかく呼び寄せたのに、美女は大后の嫉妬におそれて逃げ帰ってしまう。大王は、あとを追って吉備までいくとう執心ぶりです。
もっともこれも葛城一族と吉備一族との政治抗争と軋轢(あつれき)が投影している説話かもしれません。
さて大王仁徳は、中年に至って、はじめて、青年のような恋をしました。八田皇女です。
今までの女は仁徳のたわむれ心でした。しかし今度はちがいます。仁徳はその心を傾けて、若く美しい姫を愛しはじめたのです。八田皇女は中年男の心を捉える清らかな現(うつ)そ身の美しさと、気高い、精神の美しさを備えた佳人でした。
仁徳のように、思慮分別もあり、大いなる威厳、権力を持ち、海外にまでその武勇を怖れられている、鉄の如く強い王者の心を、このかよわい手弱女(たおやめ)は、瞬時にとろかしてしまったのです。
そうです。中年の恋です。それはしばしば、若者の恋より純粋で猛烈なのです。いかに彼が八田皇女を愛したかは、のちに、彼女を大后にしたから、子ができないのを悲しむ歌が残っているほどです。
仁徳は八田皇女を、ぜひ妃にしたい、と思いました。磐之媛をはばかって、彼女のほかには一人しか妃がいないのです。それはずっと昔の青年時代、父王から賜った美女で、そればかりは磐之媛も干渉できない存在だったからです。
仁徳は磐之媛に相談しようと思いました。彼は他の大王がしたように、むりやりに王者の強権で女を囲ったりしませんでした。彼は妻の承諾をとりつけようと涙ぐましい努力をします。それが有名な仁徳と磐之媛の問答集です。仁徳は歌います。
〈弓の弦に予備がいるように、お前のいないときに八田皇女と逢ってもいいだろうか〉
磐之媛は決然と拒否します。
〈着物こそ二重かさねて着るのもよいけれど、夜の床を並べようとなさるなんて、あなたは何とおそろしい方でしょう。私たちの愛のあいだに、ほかの人の影を立たせるなんて〉
〈難波の並び浜のように、二人を並べようとて八田皇女はあるのだよ。わるいと思うけど、私は八田を忘れられなくなってしまった。いとしいお前は右に、可愛い八田を左に、並べてみたいのが私の本心なのだ。どうかそういわず、二人仲よく暮らしておくれ。これは、むりな相談だとわかっているのだが〉
〈わかっていて、そんなことをおっしゃるのですか? 夏のカイコが繭(まゆ)を二重につくるように、二人の女をおそばにおくなんて、まあ、何ていやなことでしょう〉
〈あなたはそういうが、二人いればまた何かと面白い人生も見られるというものだよ。朝妻のヒカの坂を泣き泣きゆくのも二人連れならいい、というコトワザがあるではないか〉
〈私はいやです〉
大后は峻拒(しゅんきょ)して口をつぐみました。
私たちからみると、このときの仁徳はとても魅力的です。ぶこつに誠実に、妻をくどいています。すばらしくやさしく、男らしく、私は仁徳という英雄が大好きです。
彼は単なる漁色漢ではなくて、ほんとうに愛することを知っている。すぐれた男に思えます。磐之媛の承諾なくしては彼は八田をお召しよせることもしなかったのです。なんという誠実で、しかも不器用な愛でしょう。これでみても彼がいかに磐之媛を心の底から愛していたか、わかります、
何十年を共に生き、共に辛酸に堪え、共通の敵と闘い抜いてきた、恋人であり同志である磐之媛。四人の子供を共有し、何十年の思い出を分かちあい、手をたずさえて共に老いてきた、妻であり旧友である磐之媛。仁徳は磐之媛を愛していました。ふかくふかく、愛していました。
しかし、八田皇女への慕情も、どうしても断ち切ることができないのです。仁徳は大后の不在中、八田皇女をとうとう宮殿へ連れてきてしまいました。大后は旅先でそれを聞き、憤怒と屈辱にわれを忘れてしまいました。
磐之媛の愛の強い独占的な愛でした。仁徳はそれに悩まされながらも、彼はまた個性の強い男性です。磐之媛にまきこまれてしまうタイプの男ではありません。結局、自分の我を通さずにはいられない。強い個性と個性がぶつかりあい、火花を散らす壮烈な性格ドラマとしてみれば、ここから先の物語はたいそう興味がある部分なのです。
二人の間にすでに愛がなければ、この出来事の終末はあっさりと割り切れたでしょう。しかし仁徳にも磐之媛にも愛は消えずにあるのです。ましてや磐之媛の愛は憎悪に裏打ちされ、愛と憎しみが縄のようにないあわされた、複雑な感情なのです。
より深く愛する能力を神から与えられた、この火のように烈しい女は、より深く男を憎み、嫉妬に身を焼く性質にうまれついていました。
磐之媛の苦渋にみちた煩悩の放浪がはじまります。もはや男の心が、自分の身の上ばかりにないと知った彼女はいさぎよく身を引きます。プライドの高い彼女は、二人妻の屈辱に堪えられなかったのです。
彼女はつねに最高の、最善の、状態を要求する、人生の美食家でした。完全な勝利を手に入れなければおさまらない、王者のプライド――それ故に孤独な魂――をもった女、生まれながらにしてトップクラスの坐りつづけたい、タイプの人間でした。
どうしていまさら帰れましょう。愛しくも憎い男のそばへ。どうして二人妻として並びたつことができましょう。ただ一人の女、として愛されてきた身が。
彼女には皇太子はじめ三人の若い王子もあります。宮廷での彼女の勢力は、いま、八田皇女があとから入ったとて、なんの影響もあるはずありません。仁徳はそれに、切に、彼女の帰還を乞うているのです。でも彼女は一蹴しました。彼女の誇りは、われとわが身を愛の奴隷に貶めることはできなかったのです。
山背(やましろ)川をさかのぼり、美しい大木をみては愛する男の姿になぞらえ、男から離れれば離れるほど、忘れることができない。それでいて夫の使いに会いもせず追い返してしまう。
この苦しい矛盾、相せめぎあう複雑な女心のみだれ。そうです、彼女の恋は、女王の恋でした。ただ愛されればいいと願う、つましい、しおらしいただの一人の女と、常に絶対の愛を手に入れなければ納得しない、誇りたかい女王とが、磐之媛の一身に同居していたのです。
恋に痩(や)せ、苦悩にやつれた磐之媛が奈羅(なら)山を越えた時、はるか故郷の葛城がみえました。磐之媛の頬に涙が流れました。
たのしかった少女の頃。私はいつも女の中で一番幸福な人生に恵まれたと信じ続けてきた。そして仁徳は、私が生涯の愛を傾けるにふさわしい、すぐれた男だった。あの人とはじめて結ばれた日を、私はまだ覚えている。葛城の私の父の城に、あの人は私を妻問いに来た。十七と十五の若くて美しい盛りの私たちだった。あの乙女の頃の私は、この幸福が永遠につづくものと思っていた。
四人の子をもうけ、何十年の生涯を共に生きて来たというのに、いまあの人は私のほかの女に心を奪われている。夫と妻とのきずなというのは、それほど脆いものなのか。
磐之媛はたえず、自己中心的な思考の外から出られませんでした。そいう女性だったのです。それだけに、仁徳に対する思いは純粋で強烈でした。
ああこの現在の苦しみにくらぶれば、いかばかり乙女の日の輝かしいく、楽しかったことか。――「我が見が欲し国は、葛城高宮 我家のあたり」歌のしらべは嗚咽(おえつ)にみちています。
磐之媛の生涯の苦悩をこの一ときに凝縮したかと思われるような、辛い現在なのです。
そういうとき想起されるのは、やはりわがふるさと、わが少女の日のころだったのです。
彼女は筒城(つづき)の宮にいて、再び還ろうとしませんでした。仁徳は使者では心もとなく、ついにみずから筒城の宮まで、いかめしく仰々しい供奉(ぐぶ)をととのえて迎えにきます。
仁徳はどうしても彼女を失うには耐えられないのです。いかにも八田皇女を愛しているものの、でも、息子を四人も生ませた、古妻の磐之媛への情愛は別です。そして磐之媛あればこそ、八田を得てたのしいのも、男ごころの不思議でしょうか。仁徳の人生に、磐之媛は欠けてはならない要素だったのです。仁徳は歌をもって妻にいいやりました。
〈あなたがやかましくいうものだから、とうとう私が迎えに来たのだよ。ねえ、いつまでも強情はらずに、すんなり、一緒に帰っておくれ、おねがいだ〉
仁徳の口調には必死の情をおしかくした、なだめる調子があります。ごきげんとり、下手に出、なんというやさしでしょう。
しかし磐之媛はうべないません。断固として初志をひるがえしません。軟化するいろもみせぬ妻に対して、こんどは仁徳は、べつの方法で試みます。
「つぎねふ 山背女(やましろめ)の 木鍬(こくは)持ち 打ちし大根(おおね) 根白(ねじろ)の 白椀(しろただむき) 纏(ま)かずけばこそ 知らずとも言はめ」
やさしい愛の歌です。山背女が木の鍬で打ち起こす大根のような、その真っ白い雲みたいなお前の腕を、私はまいて寝たではないか。もしそんなことがないというなら、そのようにつれない仕打ちをしてもよかろう。でも私たちの仲の、二人きりのひめごとはよもやお前だとて知らぬ、忘れたとはいうまい。
仁徳は彼女の官能の共有の記憶に訴えようとしています。
磐之媛は、黙然して聞いていました。しかし彼女の口からはついに、
〈だは思い直して共にかえります〉
という言葉は出ませんでした。
彼女は決意を眉宇(びう)にひらめかせ、きっぱりと、こう言い切ります。
「陛下(きみ)、八田皇女を納(めしい)れて妃(みめ)としたまふ。其れ皇女に副(そ)ひて后(きさき)たらまく欲(ほ)りせじ」
なんという気強くもりりしい、しかも見ようによっては可愛げのない、頑固な女でしょう。古来から日本では、女は素直でなよらかなのがよい、とされてきました。
しかし磐之媛はそういう男性本位の女性観を一蹴したのです。女にも強烈な自我があること、それを貫き通す強さをもっていることを、示したのです。
誰が、二千年の日本歴史の中で、こんな強い言葉を男に投げつけることができた女がいたでしょう。そして、仁徳はきっと、そういう女を愛したと思えるのです。すぐれた男である仁徳は生きた人形のような女より、磐之媛のような個性のある、手ごたえのある女を好んだでしょう。仁徳は志のある人間が好きだったにちがいありません。
彼はやむなく、車駕(しやが)を返しました。
「天皇、是に、皇后の大きさに忿(いか)りたまふことを恨みたまふ」のですが、
「而(しかう)して猶(なお)し恋(しの)び思ほすこと有(ま)します」仁徳は妻を忘れることは、できませんでした。
こうして二人は互いに強く求めあい、烈しく愛しい合いながら、ついにそのまま、別居してしまいます。そして磐之媛は、さびしく筒城の宮で生涯を終えます。
しかし死ぬまでの数年間、彼女は何を考えたでしょうか。私はその時期に彼女のほんとうの愛がはじまったと思うのです。愛が深まり、醇化(じゅんか)したことに彼女は気付きます。別れることによって愛を完(まっと)うさせたのです。あの絶唱は、きっとこの時代の彼女の気持を託してあるのです。
秋の田の穂の上(へ)に霧(き)らふ朝がすみ何方(いずへ)の方(かた)にわが恋やまむ
あの美しい歌は、彼女のもにくい嫉妬とうらおもて一体になっていたからこそ、あのように美しいのです。あのように血を吐く切実な思いを千年ののちまで伝え、人々の心をゆすぶるのです。磐之媛こそ、女の中の女なのではありますまいか。
仁徳は子のない八田皇女をあわれみ、彼女の名を記念するため御名代(みなしろ)を残しました。いま矢田という地名は、その名残りなのでしょうか。でも磐之媛の名はもっと残ります。なぜならそれは時代や国境を越え、人々の胸にいつまでもあつく燃え、人々の涙をしぼるからです。
そしてこの美しい歌が、なぜみにくい嫉妬ぶかい女の磐之媛の作と擬せられたか、という謎は、まさにそれゆえにこそ、解けるのです。
さよう、人々は千何百年前かの間、このうわなりねたみの烈しい、荒ぶる女神を、女の典型として愛し、共感、感動してきたのです。
古代の名もなき女たちは、磐之媛の物語にいくばかり泣き、共鳴し、慰められてきたことでしよう。
人々は、知っていました。女の嫉妬のもののあわれを。それはみにくいものでも悪業でもありません。女のごくしぜんな、天与の特性です。理性とのバランスがとれている人と崩れる人とがあるだけです。
私には、磐之媛という女は、たとえば持統女帝などという女より好きです。持統も日本女性に珍しい理知的な女で、史上有数の謀略政治家でした。持統の夫の天武天皇には七人の后、十数人の子女がありました。持統はその中で大らかに身を処し、しかも稀有(けう)な謀略で以(もつ)て、夫の死後、夫の愛した大津皇子を殺し、政敵を追い払って、わが子の草壁皇子の地位を安泰にしたのです。
私は、夫の天武天皇と一つのみささぎに眠っている持統女帝のことを時々思います。
彼女が死んで、夫がさきに待つ、根の堅洲国(かたすくに)におもむいたとき、天武はどう言って迎えたでしょう。天武と持統はほんとうに心から相抱いて再会を喜んだでしょうか?
一つのみささぎに葬られていても、そのへんは複雑です。
それにくらべ、私は那羅山のみささぎに眠る磐之媛と、石津原のみささぎに眠る仁徳の魂は、しっかりとよりそい手をとりあって共に白鳥となって去ったのではないかと思えるのです。
磐之媛の死霊は、白鳥となって月明の夜、故郷さして飛び立ちます。今はすでに、愛恋のもの狂おしさから解き放され、無心の清らかな姿となって…‥。いつの日か、私自身も、女の愛や迷妄(めいもう)や嫉妬や狂恋の煩悩から解き放され、至純至高の世界へとびたてるときがくるでありましょうか。磐之媛こそ、私の中にいる女でもあるのです。「わが愛の」というタイトルをつけてないではいられない所以(ゆえん)なのです。
船 と 琴
「古事記」には、ふしぎな、おもしろい、夢ものがたり、おとなの童話のようなはなしが、いっぱい、みちています。勇壮な武人の手柄話、美しい王子と姫の悲恋。全く、おとなのお伽噺の宝庫です。私が大好きなのは、「枯野(からの)」と名付けられた、船の話です。
仁徳天皇の御代に、免寸河(何と読むのか今もってわかりません)の西に一本の高い樹がありました。
「其の樹の影、旦日(あさひ)に当たれば淡道(あはぢ)島におよび、夕日にあたれば高安山を越えき。故(かれ)、この樹を切りて、船を作りしに、甚倢(いとはや)く行く船なりき。時にその船を号(なづ)けて枯野と謂(い)ひき。故、この船を以ちて、旦夕(あさゆふ)、淡道島の寒泉(しみづ)を酌みて、大御水献(おほみもひたてまつ)りき、玆(こ)の船、破(や)れ壊(こぼ)れて塩を焼き、その焼け遺(のこ)りし木を取りて琴に作りしに、その音、七里(ななさと)に響(とよ)みき」
朝日が当たれば影は淡路島に及び、夕日の影は河内の高安山に及んだというから、天を突く巨木だったのでしょう。大和の古い森や社(やしろ)をたずねると、時にしめ縄をめぐらした巨木に出会います。梢(こずえ)をあおぐと気も遠くなる高さ。――それを伐って官船にしたら、おそろしく、舟足が早かった。
朝夕、この船で、天皇のめしあがる水を、淡路島まで汲みにいったのです。すずやかで、冷たい水だったのでしょうか。
朽ちて、もはや用いられなくなったとき、天皇は考えられました。長らく官船として働いてくれた功績に報いるため、その名を後に残したい。
「枯野」を薪として、塩を焼くことになりました。すると五百籠もの塩が焼けました。それは、諸国に下賜されました。
しかしどうしても、焼けない芯が残りました。天皇はふしぎがられて、それで琴を作られましたら、さやさやと音はすずしく鳴りわたり、七つの里にまでひびきわたりました。
ふしぎな、さびしいお伽話です。
「枯野」は傷ましい運命に堪え抜く、誇りあるいきものの姿のような気がします。
さらには、青い海の上を、鳥のように奔(はし)る木の刳(く)り船。
天に達するかと思われる孤独な巨木。
幾日も、幾晩も、燃え続ける、薪の山。
どうしても燃えない、焼えない、焼けのこりの芯は、巨木の魂だったのかもしれません。
琴の音は美しかったのは、それが、「枯野」の魂だったからかもしれないと、私には思えます。

琴を弾(だん)じている埴輪(はにわ)がありますが、あの琴は、もしかした「枯野」なのではなかろうか、と想像します。なお、想像を楽しめば――。
その琴の音に、大王は、海辺の高殿で耳を傾けていられる。目の前には、月光にひかる、茅渟(ちぬ)の海が広がっています。
大王は孤独です。王者の資格は、孤独に堪え得る強さをもつこと、ですから――。
大王は老いておられます。
オオサキノミコト、とよばれた若い頃から、大王はひたすら、戦いつづけて来られました。同族たちと血と血を洗う争闘のあげく、大王の位を手に入れ、ほしいままに国を領有(うしは)いてこれた。権力も財宝も美女もいまの大王のお手にはあふれています。
しかも、老いて孤独の思いは去りません。
石津原のみささぎも、すでに出来上がり、大王の永遠の眠りは用意されているというのに――。
大王のお胸には、そのかみ、大王の思い人の姫を奪って大王の怒りに触れ、姫もろともに殺された、弟王子のことがあったかもしれません。今にして思えば、恋のうちに死んだ若くて美しい王子と姫は、幸福な生涯だったのではあるまいか。
大王のお耳にはまだ琴の音が聞こえています。孤独に巨木「枯野」の魂が哭(な)くような‥‥。
女の児(こ)
「土左日記」の文章は、古風で典雅で、大らかな味わいがあって、私の好きな文章です。それに全編に、何ともいえない、美しい悲哀のようなものがあふれ、それが、この日記に、気品ある透明感を与えています。地方官である紀貫之(きのつらゆき)は、任地の土佐で、可愛ざかりの女児を失いました。「京へかへるに、をんな児のなきのみぞ悲しび恋ふる」
任はてて承平四年( 九三四)貫之は帰京することになりましたが、その子の面影は忘れられません。
いとし子を埋めた土佐を去るとき、彼や彼の妻は、文字通り、うしろ髪ひかれる思いだったのでしょう。
その心やりに、貫之は筆をとり、亡児をしのびながら、海路の道中を日記にしたためます。
一行の中には、任地でできた幼な子を抱いている人もあります。
「京より下りしときに、みなひと、子供なかりき。倒れりし国にてぞ、子生める者どもありあへる」それが、貫之の場合は反対に、京でできた子をつれて、土佐に下ったのに、その子はついに、その国でみまかったのです。悲しみは深まるばかりでした。
天候にはばまれ、海賊襲来の情報に怯えて、一行の船旅し遅々とすすみません。船がとまる浜には美しい貝や石が打ち寄せられてありました。
寄する浪打ちもよせなんわが恋ふる
ひとわすれ貝おりて拾はん
忘れ貝というのはどんな貝なのか、拾うと恋しい人を忘れることができるという貝なのでした。父と母は沖の波に忘れ貝をうちよせておくれ、と呼びかけます。忘れる間もなく、死んだ子を恋う心の苦しさに。
「をんな児のためには、親をさなくなりぬべし」
死んだ子は、真珠のように美しかったものを。「死し子、顔よかりき」と思うのは人情でしょうけれど、とりわけ、美しい女の児であったのがいじらしい、と親は思いつづけます。
失った女の児なので、その愛借や慟哭(どうこく)は、なお陰影をもたらすような気がされます。
おそらく、それが男の子であったらなれば、すこし、この作品のニュアンスもちがってきたでしょう。――
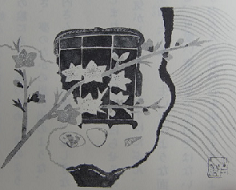
たとえば、矢内六郎さんの絵にある、
美しいかわいい子供たちが、つねに、姉と、小さな弟であるように。
…兄と妹とでは、きっと矢内さんの絵にある、あのためいきのような美しい悲哀、あまい追憶のたのしさ、夢のなかの思い出のような、ふかい味わいは出ないでしょう。矢内さんの絵の女の児は、ふしぎなちからを秘めています。
「土左日記」の中で、惜しまれ、悲しまれ、父母の涙をしぼらせるのも、「女の児」ではなくは、ならない気がします。その子はたぶん、十歳くらいまでの、髪をかぶろに切り揃え、美しく生い立つような面影が、もう幼い目鼻立ちにほのみえる、かわいい童女だったのではないでしようか。やさしく素直に、まわりの大人たちの心を明るくするような。
ボンタン実る樹のしたにむねるべし
ボンタン思へば涙は流る
ボンタン遠い鹿児島で死にました
ボンタン九つ
ひとみは真珠
ボンタン萬人に可愛がられ
いろはにほへ らりるれろ
ああ らりるれろ
可愛いその手も遠いところへ
天のははびとたづね行かれた
あなたのぢさん
あなたたづねて すずめのお宿
ふぢこ来ませんか
ふぢこ居りませんか
(或る少女の死まで)
私の大好きな室生犀星(むろうさいせい)の「悼詩」です。女の児というのは、時により、神秘な魔力を秘め、ふしぎな情感をもたらします。東北伝説の「お座敷ぼッこ」というのも、可愛い童女の姿で、誰もいない部屋に、ぽつんと一人坐っていたりするそうです‥‥貫之は、四五年るすにした荒れたわが家へたどりつきます。
「この家にて生まれしをんな児のもろともに帰らねば、いかがは悲しき」
天のははびとを尋ねて去ったわが子への悲しみが美しく結晶し、「土左日記」はふしぎな明るさをたたえて終わります。
船 唄
「土左日記」にある別の一面、ふしぎな明るさ、ユーモアは、作者の、舟旅の感輿からきています。ことに、作者が今まで知らぬ、かこ(舟人)、かじ取りのたたずまい。荒々しい船頭らのありさま、いうことすること、うたう唄。
上流階級であった国司の一行としては、こんなに身近に庶民の日常に触れたことがなかったでしょう。中でも歌人である作者としては、彼らのうたう歌声に、耳を傾けずにはいられませんでした。
彼らは舟仕事をしながら、哀愁こめてうたいます。
なほこそ国のかたはみやらるれ わが父母 ありとし思へば
情けも知らぬげな、むくつけき海の男たちが無心にうたう歌は、はるばると海の上にひびきわたり、人々の旅愁をかき立てたことでしょう。
土佐の国府を出て、海岸づたいに北上し、鳴門海峡から紀淡海峡をわたり、和泉の灘から淀川を遡って桂川に入り、京へつくというのが土佐海路のコースですが、千年の昔ゆえ、二ヶ月ちかくかかる大航海です。
「山も海もみな暮れ、夜ふけて、西ひんがしも見えずして天気(てけ)のこと、かじ取りの心に任せつ。男(をのこ)もならはぬは、いとも心細し。まして女は舟底にかしらを突き当てて、音(ね)をのみぞ泣く」
ならわぬ舟旅に、みんなは悲しみ苦しんでいるのに、船頭、水夫たちは平気で、
「舟唄うたひて、何とも思へらず」
その歌がまた、のんびりした、野趣萬溢(まんいつ)のたのしいフォークソングなのです。おそらく、そのころの民衆のはやり唄だったのでしょう。

春の野にてぞ、音をば泣く。
若すすきに、手を切る切る、摘んだる菜を
親や、まぼるらん
姑(しゅうとめ)や、食ふらん、かへらや
よんべのうなゐもがな、銭(ぜに)乞はん、
そらごとをして、おぎりのりわざをして
銭も持てず、おのれだにこず
春の野で声をあげて泣くよ、ススキの葉で手を切りながら摘んだ若菜を、今ごろは、親がむしゃむしゃとむさぼり食っていることだろう、それとも姑が食っているのか。ゆうべの可愛い子ちゃんがまた来ないかな、あの金をもらわなきゃ。うそをついて掛買いをして、金も持って来ず、自分の顔をみせもしない。――かへらや、というのは、ハヤシ言葉といわれています。
「これらを人の笑ふをききて、海は荒るれども、心はすこしなぎぬ」
ほんとにこの歌には間抜けたユーモアがあって、これにメロディーや拍子がついて唄われれば、つい吹きだすおかしさがあったでしょう。
荒くれ男たちの何の教養もない無心な人々ながら、それだけに、いう言葉がふと、おもしろいのです。
「黒鳥のもとに、白き浪をよす」
などとつぶやく言葉さえ、何か身にしむ風趣として、都びとの耳にはとまります。
ことおかしいことがありました。ある日、〈舟を早く出せ、天気がよいのに〉といいますと、かじ取りはかしこまって叫びました。
「み船より、仰せたぶなり、朝きたの いでこぬ先に 綱手はや引け」
一行はそれを聞いて「あやしく歌めきても言ひつるかな」と興じ入ります。「この言葉の歌のやうなるは、かぢ取りのおのづからの言葉なり」
船頭がいつも使っている言葉を指図すると自然にみそひと文字の歌になっていたのです。「朝きた」は、朝、はげしく吹く北風のことです。私はこの下りを読むといつも、以前ラジオで聞いた愉快な天気予報を思い出します。
「明日(みょうにち)は北東の風うす曇り 天気しだいによくなる見込み」
とまり、「土左日記」にあるこんなユーモアに、私は作者、紀貫之の男らしさ大らかさを発見して、貫之が好きなのです。
ロマンのページ
これ一冊あれば、決して退屈しない本、というのがあります。私には、「今昔物語」です。この本はあまりにも膨大、浩瀚(こうかん)なもので、たいていの人は、むつかしい名前の羅列された、仏教説話集、天竺(てんじく)、震旦(しんたん)の部を、とばしてしまいます。実は、私も、そうです。そうして、「本朝」の「世俗」なんてタイトルのところを読むのです。このお話集を、「日本のアラビアンナイト」といわれたのは、小島政二郎氏ですが、一つ一つのお話は短いけれど、奥行きがあって、アラビアンナイトよりも多彩で変化にみちています。
この本をよむと、平安末期というのは、乱世蒙昧(もうまい)なりに、決して無気力・退廃の時代ではなかったよです。この中に出てくる主人公たち、天皇・皇后、大臣・武士・僧侶から、乞食・遊女、ひさぎめ(行商人のおばさん)、猟師に盗人に至るまで、みんなイキイキと、正直に、闊達(かったつ)に生きています。
盗み、人殺し、放火、思い立つと矢もたてもたまらず、欲望のままに悪業(あくごう)を犯すかと思うと、酷烈な乱世に生きながら、仏の教えを守って慈悲の心を失わない男や女、それらが笑ったり、泣いたりしながら、縦横無尽に活躍します。全編、「今ハ昔」からはじまり、「トナム語り伝へタルトヤ」で終わります。
ところが、中に、ごくまれに、「未完」のお話があります。人の手から手へ写すあいだに、紙がちぎれ、やがて散佚(さんいつ)したのでしょう。
また、そういう、「以下欠」となっているお話に限って、あとがとても知りたいのです。
たとえば――巻三十「大和ノ国ノ人、人ノ娘ヲ得タルコト、第六」というおはなし。
今は昔、ある身分の高い貴族がありました。妻のほかに、ひそかに愛人を持っていましたが、折も折とて双方いちどに懐妊し、どちらも女の子ができました。夫はよん所なく妻に打ち明けました。妻はやさしい心の女でした。〈じゃここへ引き取って一緒に育てましょうよ〉といい、

「此ノ継子(ままこ)ヲニクシトモ思ハデ、我ガ子ニモ劣ラズ思ヒテスグシケルニ」姫君につけられた乳母の方は、その子が同じように大事にされるのが憎くてならないのです。乳母はひそかに腹心の下女をよび、
「イカナラム所ニモ落システテ、犬食ハセテヨ」
と愛人の生んだ赤ちゃんを渡します。下女がとっとと、赤ん坊を抱いて道をゆく途中、美々しく勢揃いした、あるお金持ちの一行にゆきあいました。そのお金持ちの夫婦は、子供のいないのを悲しんで観音さまに子を授けて頂くよう、お詣りに来たのですが、卑し気な下女が美しい赤ちゃんを抱いているのを見咎め、いろいろ聞きただします。どうせ捨てろと命じられた子供なので、下女は喜んで、夫婦に与えました。
「ヒトヘニ観音ノ御助ケ」
と、夫婦はとび立つばかり喜び、抱いて帰って大切に育てました。
――さて、親の家では大騒ぎして失われた赤ちゃんの行方をたずねましたが、消息はしれぬまま、残された姫君を一層、大切に育てました。姫君は美しく成長し、これまた似合いの、美しい公達(きんだち)と結婚しました。しかし楽しい結婚生活も束の間、姫君はふとした病いがもとではかなく世を去ります。
青年の悲嘆は見る目もいたわしいほど、彼は、もっぱら神ほとけにお詣りして亡きひとをしのんでいました。
ある日、ふと、路上で会った、あえかな姫君。なんとその面影は、恋しい泣き姫に生き写しの美女ではありませんか。彼は「目モクレ、ムネモサワギテ」必死にあとをつけますが、はぐれてしまいます。夢中で探し求めること幾日か、ついにある大きな邸の門から出てくる少女が、かの日、姫君のお供についていた子供だったことを発見します‥‥
残念! ここでページはちぎれ、そのあとは永久に未完です。印刷された本にはみな、非情に「以下欠」となっています。ああ、でも、このページからは、かぐわしいロマンの風が吹いています。私はあれこれと結末を作りつつ、これこそ「物語のいできはじめのおや」ではないかと、うっとりするのです。
恋の奴(やっこ)
天武天皇の子女たち――十人の皇子、七人の皇女にはそれぞれ魅力があってつきぬ興味を覚えさせられますが、その中でも私は、但馬皇女(たじまのひめみこ)という人がすきなのです。この皇女の事蹟(じせき)は何ひとつわかりません。たとえばあの美しい愛の歌、愛弟・大津皇子(おおつのみこ)とのあいだの情感を愛と哀しみをこめて歌った大伯皇女(おおくにのひめみこ)ほどには知られていない人です。
ただ、天武天皇の皇女、としてその名をとどめているにすぎないのです。
けれども、「萬葉集」にある、彼女の数首の歌が、彼女の生涯のアウトラインと、愛のすべてを示唆しています。それは史書の千行にもまして、千三百年のちに生きている私たちに彼女のいのちを感じさせるのです。重くたしかな手ごたえで、その実在感をもたらすのです。
皇女の母君は、藤原鎌足の娘で、氷上娘(ひかみのいらめ)といいました。氷上娘は若くして身まかったので、皇女はまだ、いとけない少女の頃に母を失った、さびしい生い立ちでした。
しかし、幸い、世は平穏な、華やかな時代に入っていました。たぶん壬申の乱は、皇女が生まれたか生まれぬかの頃に終わっていたのでしょう。物心ついた皇女が見た父帝、天武の宮廷、飛鳥浄御原(あすかのきょみはら)の宮は、活気にあふれ、華やかに栄えていました。世は平らぎ、民草(たみくさ)はふえ、英明の君主のもとに、倭(やまと)の国原にはさかんな発展途上のエネルギーがみちみちていたのです。
けれども、母の亡い皇女は、この華やかな宮廷のかげでひっそりと咲く、人に知られぬ小さな花でした。のちに持統女帝となった皇后の権力も強かったのでしょう。一見華やかでありながら、裏には策謀と暗闘のうずまく宮廷でした。母君の庇護と愛を持たない皇女は、みたされない思いを抱きながら、政争の圏外でひそやかに乙女となっていったことでしょう。
天武十三年、天皇はついに崩御、間髪をいれず、疾風のごときクーデターを敢行して皇后は、わが所生の皇太子・草壁(くさかべ)の宿敵、大津皇子を斃(たお)し、皇位継承権を自分の手に確実におさめます。彼女は即位して持統女帝となり、愛児・草壁を摂政にしました。大津皇子の実姉、大伯皇女が、伊勢の斎宮(いつきのみや)を解任されて都へ還ってきたのはそのころです。彼女を迎えたのは、非命に斃れた愛弟・大津を葬った二上山の塚でした。大伯は涙ながらに歌います。
神風(かむかぜ)の伊勢の国にも在らましを何しか来けむ君もあらなくに
人々はこの歌を聞いてみな泣きました。大津皇子は才気あふれたけだかい心の皇子でしたから、世の人々に深く愛されていたのです。
しかし、女帝が、大津を殺してまで守った草壁皇子は三年ののち、わずか二十八歳の若さで、はかなく世を去ってしまいます。運命のふしぎさ、このあたりが、はるかのちの世に読む歴史の面白さです。
誰が、かがやく日並皇子(草壁皇子)の早世を予知し得たのでしょうか。持統女帝にとっては足元の崩れるような衝撃だったにちがいありません。しかし彼女は心を取り直し、生来の剛毅(ごうき)な気性と、父帝・天智ゆずりの冷徹犀利(さいり)な判断力で、からくも立ち直ります。いま女帝は、ここで挫折してはならないのです。
こんどは、草壁皇子の遺児、軽皇子(かるのみや)に位をゆずるまでは持ちこたえねばなりません。彼女は、夫・天武の皇子たちのうち、最年長の高市皇子(たけちのみこ)を太政(だいじょう)大臣に任じ、あたらしい国家の体裁をととのえ、再出発をはかろうとします。
ときに高市皇子は三十七、八歳、おそらく四十近かったのではないでしょうか。
その彼が、宮廷の片隅で、ひそかに花開いた、年わかい佳人を見染、恋におち、やがて妃に迎えました。まだ十七、八の皇女、それが但馬皇女だったのです。
高市は天武天皇の長子でした。壬申(じんしん)の乱のときには十九歳の颯爽(さっそう)たる青年皇子、他の皇子はまだ幼なくてたのむに足りず、父・天武はいかに高市をたよりにしたことでしょう。
高市もまた、父の期待にこたえ、その片腕として一方の将として、目ざましく奮闘し、近江軍を花々しくうち破って、ついに壬申の乱を勝利に導きました。彼は父譲りの慎重で果敢な性質をもつ、すぐれた武人だったのです。
けれど、それほどの大功ある彼も、乱平定後は、ひっそくして世を過ごしました。長子とはいえ、生母の生まれの卑しい彼は、当時の慣習上、皇太子にはなれないのです。自分よりはるか年少の草壁や大津の下風に甘んじて隠忍していなければならなかったのです。
しかし何が幸せするのかわからぬもので、却ってそのことが、彼をして生を完(まっと)とせしめるのに好都合となりました。おそらく彼が大津ほど、人目をそばだてる才気と、高い地位身分をもっていれば、持統女帝に危険視されたでしょうし、大津同様の悲運に見舞われたかもしれません。
もしかしたら、高市はすべてそれらを見抜き、じっと手を拱(こまぬ)いて、世の推移をみつめつづけていたのかもしれません。彼が壬申の乱後、史書の表面に出てこないということは、つまり彼は、いかに、生きのびる才能に恵まれていたということかも知れない。無能で鈍感だから隠遁(いんとん)していたのではなく、世を見、人を見、自分を知悉(ちしつ)していて黙していたのではあるまいか。
やがて時期がめぐりって来ました。大津が斃(たお)され、草壁も死に、持統女帝は幼い孫皇子をかかえた自分を補佐(ほさ)してくれる人として高市をねんごろに迎えたのです。
年を加え、敦厚(とんこう)にして慎重な高市の人となりは、大政大臣として女帝の都、藤原宮の宮廷に重い地位を保ち、世をしずめ、国の固めとなるべき人だったに違いありません。
但馬皇女からみた夫・高市は、まさにその通り、重々しく完成した、一つの歴史そのもののような存在だったでしょう。皇女は高市の愛を、どのようにして受けとめたのでしょうか。あまりにも完成され、あまりにも立派すぎる、荘重な年上の夫は、皇女にとって父に代わるべき保護者のような印象だったのかもしれません。高市の愛は、皇女にはほとんど理解しがたい、当惑にちかいものだったかもしれないのです。
高市は二人の愛の色合の違いを、きっと看破していたことでしょう。このぶこつな武人は、一面、秘めたやさしさと、なみなみならぬ聡明な、鋭敏な知性をもっているのです。けっして武辺一辺倒の男性ではないのです。
彼は若い美しい妃を、情熱を傾けて愛しました。私は中年の人生に激情などおとずれるはずはないと確信している、さかしらな人々を悲しく思います。それから、人生中歳にして道をふみ迷う人を嘲(あざ)ける、世のさかしらな風潮をも心浅いことに思うものです。
高市の熱情はきっと、若者の恋よりも強く純粋で、いちずに燃えたことでしょう。
ただ、若者の恋とちがう点は、烈しく燃えながらも、状況を判断する理性の目がくもっていないことです。高市は恋の為に盲目になる年齢でも、性格でもありませんでした。この物静かが凛呼(りんこ)とした中年男は、自分の皇女に対する思いと、皇女が自分に対する思いとは、別のものだと知っていました。
しかし、その理性や判断が何の役に立ちましょう? それはよけい、高市を苦しめ、絶望させるだけでした。
絶望し、思い直し、高市はそれでも彼なりのやり方で妃を愛しつづけてゆくほかありません。
皇女はまだ稚(おさな)いといっていいほどわかく、世をも人をも知りませんでした。彼女の男といえば、年たけた夫の高市しか知らないわけです。高市の胸に抱かれるとき、さながら父の懐に育まれるような安らぎがあって、無心な童女のように、寄りすがったのです。それは、女の、男に対する愛ではありませんでした。
高市の言葉は神託のように皇女は重々しく聞え、高市の意志は神意のように、あらがいがたい力にみちて皇女を圧倒しました。ほんとうは、やさしさの極みである愛のいろんな動作すら、皇女にはある種の運命のような感じで受け入れるのでした。皇女は幸福でもなく、不幸でもなく、ただ、無智だったのです。
恋の何たるかも知らず、男と女の愛の何たるかも知らなかったのです。高市はどんなにか、それを知らせたいと思ったことでしょう。
皇女が真に人間らしい恋をおぼえること、そしてその対象が夫の高市であってくれることを、どんなにか願わしく思ったことでしょう。しかし皇女の心は深く眠っていて、かたいつぼみは開くようにもみえませんでした。高市は――彼らしく慎重に、焦らずに、忍耐づよく待ちました。皇女が身も心も花ひらき、高市とのあいだの、男と女の恋に目ざめ、あたらしい次元の愛の世界へ二人で手をとってはいってゆける、そのよろこびの日を。
しかしそれは、忍耐のいる楽しみであるとともに、薄氷をふむような愛の生活でした。高市はおとなの経験で、皇女ぐらいの年ごろのあやういときめきを知っていました。わかい女の心はつねにたゆたい、流れ、一刻し一刻とうつり変わってゆきます――果然、悲劇は起きました。高市の危惧(きぐ)は適中したのです。
いつ、どうしてかは、つまびらかではありません。恋に理由や原因があり得ましょうか。但馬皇女は、穂積皇子(ほずみのみこ)という青年に恋してしまったのです。
穂積皇子も天武天皇の皇子ですが、壬申の乱を知らぬ世代、つまり戦無派という点では但馬皇女と同じなのです。戦争を知らない子供たちだったのです。
但馬皇女は、はじめて恋を知りました。――あの、恋人の一つのしぐさ、一ことの言葉にがっかりしたり有頂天になったりし、恋人の姿がちられと見えたら心が熱くなり目が眩む、ほとんど苦しいとさえいえる歓喜、目ざとくなり、あたまはとぎすまされ、恋人の動きばかりに心は敏感にふるえ、昼も夜も、面影がまなかいからはなれず‥‥、そういう恋のくるしみ、恋の喜びを知ってしまったのです。
そして穂積皇子のよろこびも、皇女に負けぬ烈しいものでした。自分があの人を愛していることをあの人は知ったばかりか、あの人も自分を愛していると、ひそかにことづけてよこした。自分と同じようにあの人も恋しているといった。あの佳(よ)き人の美しい唇からもれる言葉は、まさしく自分を愛していると誓った。若い穂積は狂うような恋のよろこびに目がくらんで、自分が如何に重大な人生の危機に立っているか、わからないのです。
権勢ならびなき廟堂(びょうどう)の第一人者の高市が、若い妃を掌中の珠のように慈しんでいることは、誰も知らぬ者もないのです。その人をひそかに盗む、という恐ろしい所業。もしことが発覚したら、穂積の生涯は破滅してしまうでしょう。自分ばかりでなく、愛するこの女人をも破滅の道ずれにしてしまうのです。
それでも青年は引き返すことは出来ません。若い恋人たちはついに、人目を忍んで愛の一夜をもつのです。
秋の田の穂向の寄れること寄りに君に寄りなな事痛(こちた)かりも
有名な但馬皇女の歌です。(秋の田の穂波が、風になびいてそろって同じ向きによるように、わたくしもひたすら、あなたに寄りすがっていることにきめたわ。どんなに世間のうわさがひどかろうとも、私の心は変わらないわ)
白々と明るんでゆく夜明けの窓をみながら、皇女は男の指に自分の指を絡ませて誓うのです。皇女のいろどり美しい領巾(ひれ)や、青年の佩刀(はいとう)が散乱している床の上で、恋人たちは、絶望感に裏打ちされたような辛い、はげしい愛を交わしました。
若さは不器用な、つたないものです。彼らは恋を包み隠すにはあまりに正直すぎ、純真すぎました。二人はたちまちにして、世の指弾と非難の嵐に包まれました。
もはや穂積は、責められるような人の目と、そしてまた監視を破って、皇女に会いにゆくことは困難です。
皇女のほうはもとよりのことでした。恋人たちは隔てられて、なお心を焦がし、身悶えし、身も世もあらず恋に狂います。それは皇女に大胆な勇気を与えました。
人言を繁み言痛(こちた)み己(おの)が世にいまだ渡らぬ朝川渡る
(世間のうわさがかしましいので、わたしは生まれてまだ一度も経験していないような、朝の川を渡ることができました)
朝川渡る、はいろいろに考えられますが、文字通りうけとめると、いっそう切実です。穂積は無鉄砲な恋人が、いかに可愛いく、いじらしかったことか。
このトリスタンとイゾルデは、やはりその仲を割(さ)かずにはいられませんでした。たぶん謀略によるのでしょう、穂積皇子は、近江に追われました。
後(おく)れ居て恋ひつつあらずは追ひ及(し)かむ道の隈回(くまみ)に標結(しめゆ)へわが夫(せ)
(ああ穂積。あなたのあとへひとり残されて恋いこがれて苦しむよりは、わたくしもあなたのあとを追ってゆきたいわ。どうか道のまがりかどに、めじるしの道しるべをつけておいてちょうだい)
皇女は苦しんでいました。生まれてはじめての恋、最初で最後の恋でした。はじめて男を愛するというのはどういうことか、男と女のあいだの恋の何たるかを知ったのです。恋人と会えぬこと、道ならぬ恋の何たるかを知ったのです。皇女は、夫・高市の望まなかったいきさつを経て、おとなに成長していたのでした。
皇女の苦しみを、夫の高市皇子も複雑な苦しみで以て察することができました。高市は心のこまやかな、デリケートな男でした。蕪雑(ぶざつ)なだけの中年男ではないのです。
彼には、若い日の烈しい恋の思い出もありました。ずっと昔、青年の日、彼は十市皇女という女人を恋したことがありました。十市は有名な額田女王(ぬかたのおおきみ)と天武天皇のあいだにできた皇女で、大友皇子(おおとものみこ)の妃でした。壬申の乱では、夫と父がたがいに敵対すね皮肉な運命に遭遇しました。夫が父のために敗れ、自決したあと、十市もいくばくもして自殺しました。
高市はその薄幸な佳人を愛していたのです。しかも、人知れず――。
そんな記憶のある彼には、充分、若い二人の恋に同情がもてました。
彼は穂積の盲目的な、無思慮な行動も、皇女の無鉄砲な、はらはらするような苦しみも、理解できるのです。高市は無体に二人の仲を裂き、穂積に報復を加える気にはなれないのです。
かといって、二人を許すには、高市の身分が重くて、世人の注視をあつめすぎてしまいました。それに、彼はやはり、但馬皇女を愛して未練があり、手離す気にはなれないのでした。
高市は苦しみました。この抜け出しようのない煩悩地獄。三人が三人とも苦しんで、何ひとつ、その苦しみが解決への力とならないのです。年齢(とし)たけた高市が、やはり事態を収拾する、いちばんの責任者だったのでしょうが、また高市の苦しみは一ばん底深かったのです。
(それにしても――)
と高市は思わずにはいられない、太い吐息とともに。
(穂積といい、但馬といい、何という若い世代だろう。あの壬申の乱さえ知らない世代なのだ。自分にとっては、つい昨日のことのようだのに‥‥天に連なる戦塵(せんじん)。ひるがえる味方の赤旗。兵士の歓声。槍。矛(ほこ)。剣のひらめき。とどろく馬のひづめ…自分は力いっぱい戦った。
十九だった、命を賭け、青春を賭けた。おれの青春はあそこで使い果たした。そしてやっと得た勝利、父は皇位をふみ、民草は歓喜して迎えた。ああ、命の一滴まであのとき傾け尽くした…それからいろんな運命を見た。非命に斃(たお)れた皇子も重臣もたくさん見た。しかしおれは戦って、ここまでやって来た。槍や矛をもたぬ、暗黙のうちの政争や駆け引きは、実戦よりもっと辛いものだった。おそろしい苦闘の歴史だった。そしておれは生き延びた)
その長い歴史。重く厚く、にがい人生。その値打ちを知り、それを尊重し、共感してくれる力は、若い但馬皇女にはあるまい。高市はおとなの分別で、それを知っていました。
彼は皇女を責める気持ちはありませんでしたが、人生の厚みを理解してもらえぬことが、このすぐれた武人政治家である高市を苦しめました。
苦しみ、なやみながら、しかし事は急転直下、意外な方向で、ピリオドを打たれてしまいます。
高市は急死したのです。朝野(ちょうや)の深い嘆きのうちに、四十三歳で、太政大臣・高市皇子は急逝(きゅうせい)したのです。
高市が亡きいまは、かえって皇女は穂積と会いがたくなります。
戦無派の子供たちだった皇女と穂積皇子の上にも、おとなの社会の憂愁のベールがおちて来て、うれい多い、影ふかい人生になってしまいます。
もはや二人を遮るものはないのに、目に見えぬ垣根は高くなりました。恋慕の情はいやまさりつつも、かえって会うのにためらいがあり、心を焦がすのみならぬ人生になりました。
そのうち、やがてほどなく、皇女も病いを得て、その母に似て若くして世を去ってしまいます。穂積ひとり、生き残ったのです。
(ああ、こんなに若いのに、おれはもう、百歳になったほども年をとった気がする!)
穂積は悲鳴に近い思いで、絶叫したことでしょう。
(但馬よ、わが思いびとよ。おまえは、おれの生涯をそっくり、夜見の国へ持ち去ってしまったのだ!)
自分の人生は、あとは余生ではないかと、彼は思いました。どうやって生きていったらいいのかわからない、彼はそう思いました。彼の悲しみの歌が「萬葉集」にのせられています。冬の雪の降る日、はるかに皇女の墓をみやって悲傷流涕(りゅうてい)して作った、とあります。
降る雪は多(あは)にな降りそ吉隠(よなばり)の猪養(ゐかひ)の岡の寒からまくに
(よき人のむねる猪養の岡が寒かろうではないか、雪よ、降りつもるか、かのよき人の墓の上に)
穂積皇子の歌はみな近代的で美しい、一級の芸術作品です。「今朝の朝明(あさけ)、雁(かり)が音(ね)ききつ春日山 黄葉(もみじ)にけらし、わが情(こころ)いたし」など、私は好きです。穂積はもののあわれを知る、すぐれた青年だったと見えます。
ところで、穂積は、どんな中年男(おとな)になったのでしょうか。
われわれとしては、この薄幸な恋を経験した青年の、以後の人生が知りたいと思うのです。
穂積もまた、最後には政界の表面に浮き上がって、政治家として活躍しますが、そのことよりも、彼の人生の内面です。面白いところで、彼の名を発見するのです。
彼は大伴坂上郎女(おおとものさかのいらつめ)を愛した。とあります。たぶん高市が但馬を愛したほどの年齢のひらきがあったでしょう。壮年の穂積は、年若く才気煥発(かんぱつ)な女流歌人の郎女(いらつめ)を、どんなふうに愛したのでしょうか。私が思うに、郎女はおそらく、但馬のような世間知らずのおぼこな女人ではなく、充分、恋の味も知り、最初から男と女として対等の愛を交わすことが出来る、男と太刀打ちできる成熟した女として、穂積の前に現れただろうと思われます。
郎女は打てば響くような女でした。そして男の値打ちをかなり見分け、知ることのできる女で、穂積を愛したのも彼女の心からのことと思われます。穂積はそんな郎女に満足し、愛を注いだでしょう。
ある折に、ふと穂積は、昔の恋に口をすべらせます。
〈ああ、そのお話は、わたくしも噂だけ聞いたことがありましてよ〉
と郎女は、いくばかの嫉妬をおぼえつつ、夫であり恋人である穂積を見守ります。
〈まだ、わたしがほんの子供のころだったけれど――どうか、くわしくお聞かせてくださいましな、そのかたは、どういう方でいらしたの?〉
郎女は、かるい嫉(ねた)ましさと、かすかな憎しみを、昔、男の心を占めて死んでしまった女人に感じていたのです。しかし、穂積の話をきくうちに、妬みも憎しみも、大きな感動にまきこまれて消えてしまいました。それほど皇女ののこした歌は、真率で純粋で、人の心を揺さぶるのです。郎女もまた、それを汲みとり得るほど、心のゆたかな人間だからでした。
穂積は酔っていました。彼はしばし、昔の恋の思い出に心をとられているのでしょうか。
家にありし櫃(ひつ)に鏁(かぎ)さしをさめてし恋の奴(やっこ)のつかみかかりて
穂積は酔うといつもこの歌をうたいました。家の内にふかくカギをかけて櫃にしまいこんでおいた恋の奴が、つかみかかってきた。ユーモラスなうたいぶりの中に、自嘲的な悲痛が漂っています。恋の奴とは、いかにも、怪しい魔力を示唆するようで面白く、真実味のあるコトバです。
(あなた。あなたのまなかいに終生立ってはなれないのは、あの皇女さまの面影なのですね。あなたは、あのときの狂ったような愛執を、ご自分で制御することがおできになれなかったような恋慕を、〈恋の奴〉とお呼びになったのね?)
坂上郎女は、酔い伏した男をいたわるように手をのべつつ、心でそう問いかけていました。わかく美しい郎女は、穂積がかって愛した貴婦人の但馬と同じほどの年ごろだったけれども、郎女のほうがぐんと、情理(わけ)しりでした。彼女は恋人の昔の恋をやさしく抱擁し、思いやるほどの恋の手練れでもあったのです。
彼女は穂積皇子の歿後(ぼつご)、いろんな男と恋の遍歴をかさねました。しかし個性ゆたかで自我のある彼女は、どんな男のときのそれでも決してかりそめの、ゆきずりの恋ではなくて、ただ一人の女として、妻として、相手の男に愛されたのです。
何年かのち、(それは天平勝宝(てんぴょうしょうほう)のある年でしょうか?)彼女は、兄の大伴旅人の息子で、かつ、自分の愛娘の婿でもある、一人の青年に、昔がたりをしていました。穂積と、但馬の、わかい二人の悲恋も話しました。
〈ああ、それを萬葉集に採録しなければ〉
と男は目を輝かせていいました。
〈そういう歌を、私がさがし求めていたのです。拙(つたな)くとも真率な、人間の歌を。その歌は千年、いや二千年ののちまでも、人々の心を打ちますよ〉
男の名は、大伴家持(おおとものやかもち)といいました。
庭たづみ
今朝は雨が降っています。私の家は下町なので、庭はありませんが、窓を開けると、家と家のあわいの、細い路地に水たまりができて、はかない春の青草、ハコベやヨモギなどの根が、水に漬かっているのがみえます。
ひとつは「古事記」の中のおはなし。オオサザキノミコト(仁徳天皇)のお妃、イワノヒメ(磐之媛)の伝説です。
大后(おきさき)は、背の君の大王の愛が、もう一人の女人、ヤタという王女にもそそがれたと知って「いたく恨み怒りまして」山城の国に去ってしまわれた。大王は、嫉妬ぶかい妻に対してどこまでも心ひろくやさしく、帰ってわしいと呼びかけられます。手をかえ品を変えて妻の翻意(ほんい)をうながし、われわれの愛はまだ消えていないと訴えられます。
そのことづてを命ぜられたのは、クチコノオミ(口子ノ臣)という若者でした。大后の前にひざまずいて申し上げるとき、「いたく雨がふりき」。大后はお怒りがとけず、彼が前戸に伏していると後戸へ避けられ、彼が後戸へ廻ると前戸へおかくれになるのです。クチコノオミは必死でおあとについて、大王のお言葉を伝えようとして、
「庭中に跪(ひざまず)きし時、水潦(にはたづみ)腰に至りき。その臣、紅(あか)き紐著(ひもつ)けし青摺(あをず)りの絹をきたり」それゆえ、
「水潦紅き紐にふれて、青みな紅き色に変わき」
クチコノオミの妹が、たまたま、大后のそばに仕えておりました。妹は、兄が庭にたづみの中に伏して、青い衣もあかく染まるまでぬれそぼつ姿に、涙ぐまずにはいられませんでした。その姿のものすさまじさと、大后の妬心(としん)のただにらぬ烈しさ、物狂おしさとはよく対照をなして、色あざやかな名画のような、印象的なシーンです。
もう一つは、皇極天皇四年六月、戊申(つちのえさるのひ――十二月)「日本書紀」巻二十四に伝える、一大クーデターの日です。
この日は雨が降っていました。三韓の調(みつき)をたてまつる日といつわって、専横の蘇我入鹿(そがのいるか)を殺そうという陰謀が、入念に水ももらさずはりめぐらされています。入鹿が参内してきました。まず入り口でたばかって、彼の腰の刀をとりあげてしまいます。陰謀の首魁(しゅかい)、中大兄皇子(なかのおおえみこ)は間髪を入れず、宮廷の門を閉ざし、入鹿の手兵が入れないように固めてしまいます。中大兄自身、槍をとって殿中にかくれ、一味の鎌子連(かまこのむらじ)は弓矢をとって守ります。暗殺者たちは刀を抜いてすきを窺っています。
入鹿はまだ、自分の運命を知りません。天皇の玉座近くにいて、表文を読んでいる倉山田麻呂(くらやまだまろ)が、声ふるえ、手足わななくのを、何事か、と咎めたりします。
倉山田麻呂もまた一味だったのです。入鹿をもし、暗殺しそこねたらと思うと、冷汗が身を伝います。
豪胆な中大兄は、ついに自分が口火を切りました。刀をひらめかせて躍り出て、入鹿に斬りつけ、それにはげまされて、暗殺者たちが殺致しました。
入鹿は殺されました。クーデターは成功したのです。
「是(こ)の日、雨ふりて潦水庭(いさらみづおほば)に溢(いは)めり。席障子(むしむろしとみ)を以て、鞍作が屍(かばね)に覆(おほ)ふ」
鞍作は入鹿の名です。
庭たづみは、入鹿の血によって。朱(あけ)に染まりました。権勢ならびなき入鹿、甘橿(あまかし)の岡に宮殿をたてて天下をほしいままにした大豪族の、あまりにも凄愴(せいそう)・無惨な死でした。
庭たづみは、私には、風流というよりも、むしろ、悲惨で、非情な情趣をさそう気がします。入鹿の死体にふりそそぐ雨と、それを浸した庭たづみは、いまも、世界のあちこちをつめたく、ぬらすのです。
さくらの歌
さくらが咲きました。
さくらの歌は、やはり私たちには「萬葉集」よりも、「古今集」「新古今集」のものが好きです。たとえば、
見渡せば春日の野辺にかすみ立ち咲き匂へるは桜花かも
(萬葉集)
というのよりは、
みよしの高ねの桜ちりにけり嵐もしろき春のあけぼの
(新古今集)
の方がすきです。桜は、素朴に歌われるよりは、一種の様式美をもって表現された方がにつかわしいのです。
みよしのの歌の方は、「最勝四天王院のしやうじに、吉野山かきたる所」という詞書(ことばがき)が、歌の前についていて、障子に描かれた吉野山の絵にそえられた歌、ということがわかります。
まるで、イラストレーションの一部のように美しい歌ではありませんか。私は春、花便りがきかれはじめると、ふっと、くちびるにこのなだらかなしらべの美しい歌がのぼるのです。このあいだ、神戸の護国神社の桜を見に行きましたら、風に吹かれてふぶく花びらで、あたりは白くつつまれ、夢幻のような美しさ、「嵐もしろき春のあけぼの」というのは、字でかいた絵のようです。
この作者は、後鳥羽上皇なのです。あの多芸多趣味、ありあまる才気の君、一世にかくれもなきすぐれた歌人、そして、承久の変で政治的に失脚して、隠岐島に流された悲劇の帝王でもあるのです。上皇の歌は、どれも珠玉のように美しく、「ほのぼのと春こそ空に来にけらし天のかぐ山かすみたなびく」(新古今集春歌)というのも、私は好きです。私は、ちいさなガラス細工の動物や、花や蝶の指輪や、陶器の人形といった、こまごました美しい、あるいは可愛らしいものを集めるのが好きなのですが、それらのコレックションと同じように、こんな美しい歌を、心の中に一つ、二つ、とためてゆくのが、大好きなのです。
むかしの歌集には、ことば書き、というのがあります。「和泉式部日記」や「建礼門院左京大夫集」は、ことば書きがそのまま、小説風になったりしていますが、「どんな場合によんだ」あるいは、「こういう歌で返しをした」などと作歌成立の事情ともいうべき、「前説」がことば書きです。この、ことば書きと、歌とがいかにもぴったりしていると思うのは、「古今集」にある、紀貫之の歌です。
歌たてまつれと仰せられし時に、よみたてまつれる 貫之
桜花さきにけらしもあしびきの山のかひよりみゆる白雲
山峡に白くかすむは、雲かさくらか。このことば書きのおうようさ、上品さ、何の作為もないままに、つくろわぬ気高さが、すらりと出、またそれに呼応して、歌の姿も品たかいものがあります。典雅、というのは、こんなことば書きと歌のことをいうのでしょうか。両々釣り合い、補い合っているような美しさで、私はこの歌は、ことば書きと共に味わうものだと思ったり、します。
西行も美しい桜の歌を残しました。「吉野山やがて出でじと思ふ身も花散りなばなと人や待つらむ」などは私の好きなコレックションの中へ加えていますが、西行は武者の出なので、その勁(つよ)さが私には近づきにくいときがあります。それで恥ずかしいな、と思いながら、告白しますが、ほんとに好きなのは、絵本の絵のような歌です。
山里の春の夕暮れきてみれば入相(いりあい)の鐘に花ぞ散りける
(能因法師)
絵のような桜は、絵のように歌われるのがふさわしいのかもしれません。
つづく 魅惑の男「蜻蛉(かげろふ)日記」