このごろの少年少女に、すぐれた古典の名文の一節を暗記させないのは何故でしょうか。私には受験勉強などよりもずっと大事なことに思えるのですが。
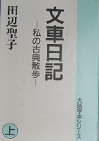 田辺聖子著
田辺聖子著
文車日記|―私の古典散歩―上巻 田辺聖子
ゆく河の流れ
昔の学生たちは「方丈記」や「平家物語」の冒頭の一章など、まる暗記させられたものでした。リズム感のある名文なので、若者はすぐおぼえてしまいます、みずみずしい若いあたまに刻み付けられた記憶は、一生消えません。そのうち二十代、三十代、四十代と生きるにつれて、その文章の意味を、年ごとに深く汲みとるようになります。訳も分からず暗記していたものがたえず新しい意味をもって生き返り、その生涯の血肉となります。古典というものはそういうものです。
「ゆく河の流れは絶えずして、しかも、もとの水にあらず。淀みにうかぶうたかたは、かつ消えかつ結びて、久しくとどまりたる例(ため)しなし。世の中にある人と栖(すみか)と、また、かくのごとし」‥‥
旧制高等女学校のひるさがりの教室、少女の澄んだ声で朗読されていた「方丈記」‥‥きのうのことのように、わたしの耳もとにありありとよみ返ります。なんと流麗で、しかも、ものさびしい味をたたえた名文でしょう。
「朝(あした)に死に、夕(ゆふべ)に生きるならひ、ただ水の泡にぞ似たりける。知らず、生れ死ぬる人、いづかたより来たりて、いづかたへ去る。また知らず、仮の宿り、誰が為(ため)にか心を悩まし、何によりか目を喜ばしむる。その、あるじと栖(すみか)と、無常を争うさま、いはばあさがほの露(つゆ)に異ならず」
「方丈記」の作者、鴨長明(かものちょうめい)が生きていた時代は、日本歴史の中でも最も激しい動乱の時代でした。源平の争乱、平家の没落。鎌倉幕府の出現。
花の京都は荒れに荒れ、公卿(くぎょう)たちは零落してゆきました。それに加えてひまなくおこる天変地異。大火、大地震、飢饉(ききん)、悪疫の流行、つむじ風‥‥恐ろしい時代でした。
若い長明の、澄んだ眼と心に、この世の地獄ともいうべき酸鼻(さんび)のかずかずが焼き付けられていきました。
大火に吹き立てられて逃げ惑う人々。燃え落ちる大邸宅。
安元三年四月廿八日(一一七七年)風の激しく吹く夜、都は大火に焼かれ、はては朱雀門(すざくもん)・大極殿(だいごくでん)・民部省などに移って一夜に焦土となりました。
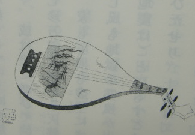
「吹き迷ふ風に、とかく移りゆくほどに、扇をひろげたる如く末広になりぬ。遠き家は煙に咽(むせ)び、近きあたりはひたすら焔(ほのお)を地に吹きつけたり、空には灰を吹き立てたれば、火の光に映じて、あまねく紅なる中に、風に堪へず、吹ききられたる焔。飛ぶが如くして一二町を越えつつ移りゆく。その中の人、現(うつ)し心あらむや。或は煙に咽びて倒れ伏し、或は焔にまぐれてたちまちに死ぬ‥‥七珍万宝さながら灰燼(かいじん)となりにき」
家も垣根も虚空(こくう)にまきあげてしまう治承四年(一一八〇年)のつむじ風も地獄の業風かと思われましたが、元暦(げんりゃく)二年(一一八五年)の大地震はことにもすごく、「山はくづれて河を埋(うづ)み、海は傾きて陸地をひたせり。土裂けて水湧き出で、巖(いわほ)割れて谷にまろび入る」
飢饉が襲うと、力ない庶民はばたばたと倒れました。これも悲惨なことでした。
「築地(ついひぢ)のつら、道のほとりに、飢ゑ死ぬるもののたぐひ、数も知らず、取り捨つるわざも知らねば、くさき香(か)、世界にみちみちて、変りゆくかたちありさま、目も当てられぬこと多かり」
長明は世におごり、富を誇ることの空(むな)しさを見てしまいました。無常と、世の転変と、人の存在の儚さは、彼に、「どうやって人間は生きるべきか」を探究させました。
五十になった彼は出家して、京の郊外の日野山に一丈(三メートルあまり)四方の小さな庵(いおり)を作ってこもりました。「方丈記」というタイトルは、ここから出ています。
彼は、この侘しい山奥の一人暮らしを愛しました。蕨(わらび)の穂を敷き詰めて寝床とし、仏に仕え、念仏し、木の実を拾って飢えをしのぎ、月の明るい夜は琵琶(びわ)を弾いてみずからをなぐさめました。
しかし「方丈記」の真骨頂は、さきの冒頭の名文と、そして沈うつな最後の一章だと、私には思われます。
この中世最高の知識人の一人である長明、死を目前に控えた、老長明の知性は、みずからの、隠遁(いんとん)者ポーズの虚飾をするどく見破らずにはいられませんでした。
「仏の教へ給ふおもむきは、事にふれて執心なかれとなり、今、草庵を愛するも、とがとす。閑寂に著(ぢやく)するもさはりなるべし」
方丈の小庵を愛するのも「要なきたのしみ」だったと彼は言い捨てます。そのとき、長明の目には、美しい西空の夕映えが浄土のように映っていたことでしょう。
額田女王(ぬかたのおおきみ)の恋
「萬葉集」を飾る、美しい星の一つ――額田大王という女性の生涯は、謎にみています。女帝・斉明は、偉大な息子を二人ももちました。不世出ともいうべき帝王たち――天智・天武の両帝でした。ともに才分に恵まれ、すぐれた意志力と鋭敏な時代感覚をもつ、偉大な王者たちでした。
この非凡な男たちの双方から愛された女人は、なお、非凡といわねばならなりますまい。それが額田女王です。
でも彼女の名は、両帝の后妃の名には記されていません。その生まれ年も没年も、出目もさだかではありません。そして私にとって、もっとも大きい謎は、この美しい才女は、二人の男の、どっちを愛したのだろうかということです。
額田がはじめて大海人皇子(おおあまのみこ)にあったのは、まだごく若い少女のころでした。そのころ、額田の姉の鏡王女(かがみのおおきみ)は、中大兄皇子(なかのおおえのみこ)という恋人をもっていました。中大兄はのちの天智帝、大海人はのちの天武帝です。
中大兄は皇太子という地位にありましたが、多端な政務のあいまに、難波(なにわ)の都から、姉妹の邸のある大和(やまと)へ通ってきていました。
額田はあるとき、中大兄に従ってきた大海人をひとめ見て心を奪われました。彼女は中大兄の、するどいきびしい雰囲気よりも、大海人の、あたたかな、人を誘い込むような微笑みや、おだやかで寛容な人柄にひかれました。
〈あたしは、あなたの思いびとになりたいの。もうきめたわ、大海人皇子さま〉
大胆で素直な少女の言葉に、大海人は目をみはりました。彼は中大兄よりずっと若く、十八九になったばかりの若々しい青年でした。
〈思いびとよりは、妃として妻問(つまど)いにこよう。あなたのお父上、鏡王に〉
と青年皇子は顔を赤らめつついいました。
〈いいえ。あたしは並の女ではありません。神をお祀(まつ)りするお役目があるの。お妃にはなれないの。でもわたしは自由なの。恋をしてもいいの。思うがまま生きよ、とおっしゃったわ。人を恋しても許す、と〉
美しいさかしい姫の唇からもれる言葉の奔放な強さに、大海人皇子はたじたじするばかりでした。
〈誰が、そういったの? かわいい姫〉
〈神が。あたしには神の意志がわかるの〉
姫は汚れをしらぬ澄んだ瞳を大海人に向けました。そのときから、大海人は神秘な恋におちてしまったのです。
〈おお、いとしい私のお巫女(みこ)さん、額田よ〉
青年はやにわに少女を抱き上げて、自分の乗ってきた馬に乗せました。
〈なんという人だ。なんという人だろう。あなたは‥‥好きだ、好きだ、よし、このままどこかへ連れていってしまおう!〉
青年・大海人皇子は、今までこんなに驚倒したことも見せられたこともありませんでした。この少女はなんと一語一語、人の心を揺さぶるようなことをいうのか。

〈ええ、いいわ、夜見の国へ連れていかれたって平気だわ!〉
青年の一鞭で、馬は天馬のごとく野を駆けました。丘を越え、森をかすめ、二人は若い神々のように炎の息を吐いて疾駆してゆきました。たちまち姫の黒髪はとけ、うしろへ長くなびきます。山々は新緑にきらめき、夏の光はめくるめくばかりでした。
額田はつぼすみれや、紫草の咲き乱れる花野で馬から下ろされ、青年の手でやさしく花のしとねに横たえられました。
夢のように過ぎた青春の日々の、なんと迅(はや)かったことか。
大海人とはやさしく大らかな男でした。額田は男の安らかな愛になれ、二人の間には、十一皇女(といちのひめみこ)と呼ばれる愛らしい娘さえ生まれました。
けれども彼らの愛を引き裂いたのは、年月ばかりでなく、時勢のうつり変わり、都の政変のせいでした。
七世紀は疾風怒濤の時代です。中大兄が政権を握ると、革新の嵐は日本中を吹きまくりました。中大兄は弟の大海人とちがって、冷徹で非情の政治家でした。彼はロボットにすぎない孝徳天皇を廃し、その皇子を断罪し、邪魔者や障害物を片はしから追放し、処刑し、窮死させ、大化の改新の理想政治を実現する目的のためには、手段を選びませんでした。
中大兄の両手は、幾人の血に汚れているかもしれません。しかし中大兄は、そんなことを顧慮する男ではありません。それより彼には処理すべき政治問題が山積しているのです。
新都の造営、蝦夷(えぞ)の討伐、朝鮮半島との外交折衝‥‥中大兄は、一身に、新興日本の運命を背負って立っている男なんでした。そして彼のよき協力者で、有能な補佐官は、弟の大海人でした。いずれも、男でした。彼は額田に直接に迫りました。
〈額田。おれはお前が気に入った。欲しい。欲しいものは奪うのがおれのやりかただ。お前を大海人から奪う。おれを愛せよ〉
〈あたくしは自由です。太子よ。――あなたも大海人も、あたくしをつなぎとめることはおできになれませんよ‥‥けれど、ほんとうをいえば〉
額田はほほえみました。
彼女も、昔の幼い姫ではなかったのです。男盛りになり、ほしいままに国の運命を切り開いてゆく鉄の意志をもった、堂々たる王者、中大兄に魅力をおぼえていました。
〈太子よ。あたくしもあなたが気に入りました。あなたをえらんだのは、あたくしです〉
額田は、中大兄を愛人にもちました。彼女は、そういうやりかたで愛を示す女でした。
斉明女帝が崩御し、中大兄は即位して天智帝となりました。初夏のある日、蒲生野(がもうの)で、大きな遊猟がもようされました。大海人皇子は以下、諸臣が従いました。額田は、この宴の席で、大海人を見て、興をそそられ、歌います。
あかねさす紫野ゆき標野(しめね)ゆき野守(ぬもり)はミズ君が袖ふる
紫草の咲く野をゆき、御料地の野を、あなたはずんずんいっておしまいになって――ずいぶん、人もなげなおふるまいを遊ばすのですね、袖なんかお振りになって合図なさったりて、野守がないでしょうか。
大海人皇子はすぐさま返しました。
紫の匂へる妹(いも)を憎くあらば人妻ゆゑにわれ恋ひめやも
紫草のように美しいあなたを、もし憎かろうならば、人妻なのにどうして私が恋しく思うものか。
人々はどよめき、このやりとりを喝采(かっさい)しました。
これは秘めて忍び交わした恋歌ではありませんでした。大海人もすでに四十すぎの男盛り、額田も、三十五六にはなっていたでしょう。ゆったりした中年の男女が、諧謔(かいぎゃく)をこめ、したしみにあふれて投げ交した座興の歌でした。
雲一つない初夏の青空のもと、酒に酔い、手拍子に浮かれ、人々はくりかえし、この相聞(そうもん)を興がって、歌いはやしたかもしれません。仕止められた獣の血の匂い、肉の焼ける芳しい煙、どよめきと歓声のうちに、人々はこの歌を口ずさみ交わしたことでしょう。
みんなが、昔は大海人と額田が恋人同士であったことを知っており、だからこそ、一そう興をそそられたかもしれません。古代の恋はオープンでしたから。
けれども私には、座興的に歌い交わしたらくみえる歌に、中年の男と女の、図太い、したたかな、恋の未練を感じます。厚顔な、傍若無人な口調の中に、ふっと美しい、はにかんだ恋の記憶をさぐりあてます。片方が手馴れて呼びかけると、片方が巧みにうけとめるその呼吸に、昔、愛を交わしあった男と女のみもつ、大っぴらな狎(な)れ合いが出て、豪快な感じさえあります。
たぶん、大海人と額田は、たがいにほほえんで見交わしたことでしょう。もう十なん年の昔。あのめくるめく夏の光、暑い陽射し、紫草とつぼすみれの野‥‥初恋のある日を、どちらも忘れてはいない。時はうつり、世はかわって、二人の運命は、はなれてしまったけれども。
額田は手をさしのべ、大海人はそれをとって馬にひきあげました。
額田の領巾(ひれ)は、あの乙女の日のように駆け出した馬の上で、旗のごとく、なびくのでした。
額田女王の歿年はつまびらかではありませんが、しかし彼女はその後も、天智帝の恋人でした。
君待つとわが恋ひ居ればわが宿のすだれ動かし秋の風吹く
これは天智を恋い待つ思いの歌、ということです。私は額田の晩年の歌、
いにしへに恋ふらむ鳥は時鳥(ほととぎす)けだしや鳴きしわが恋ふるごと
を、ことに興ふかく思うものです。天智・天武のうち、彼女はそのどちらを愛したのでしょうか。おそらく優劣きわめたがい二人の英雄を同じウエイトで愛したのではありますまいか。額田はそれができる女でした。みずからの意志で男を愛したと声高くいえる、最初の女人でした。
むかしはものを
あひみてののちの心にくらぶればむかしはものを思はざりけり権中納言敦忠(ごんちゅうなごんあつただ)
百人一首の歌の中では、私の好きなものの一つだす。
平明なことば、なだらかなしらべ、一読して意味がすらりとわかります。「あう」というのは、昔の語意では男女のあいだの直接的な恋愛行為を指します。
恋の夜を体験したあとは、いろんな物思いのたねがふえた、これにくらべると、昔は何とわけ知らずの、単純なこころだったことよ、というほどの意味でしょう。従来もそう解釈されてきました。
しかし、私はこの歌の「あひみての」という語句に、複雑な皮肉の響きを感じます。そして作者が男であるという点でも、大いに興味を持たないではいられません。従来行われてきた素直な解釈は、あまりに女性的解釈にすぎる気もされます。
この男は、かねて恋い焦がれていた女と、とうとう、恋の一夜を持つことに成功した。
朝まだき、彼は馬に騎(の)ってか、あるいは牛車(ぎつしや)の奥ふかく身を隠してか、女のもとから帰ってゆく。そのとき男の胸にあるものは、あんがい、白けた思いかもしれない。恋の手だれであるこの男は、一つの恋がいま、はかなくうつろい、色あおざめ、しぼんだことに気づいたかもしれません。
あの女を望んで得られず、あんなに烈しく目もくらむ思いで、渇くがごとく欲していたとき、その気持は、今思えば、じつに浅はかで単純なものだった。あの女を得たというだけでいっぱいだった。しかしいま、その欲望は燃え尽き、充たされ、鎮められてしまった。たちまち心がわり、とまではいわぬけれど、冷たい、水のような醒めた思いが、男の胸をみたしはじめています。男は恋が生まれ恋が死ぬときの大きな動揺を感じています。
この男にとって、女は思いのほか物足りぬ人だったかもしれませんし、また、いったん躰を交わしたあとは、心ざまが急速に浅くなってゆく、男の性(さが)のせいかもしれません。

女のほうは昔より恋心が募り、男の方は反対の意味で「昔は単純だった」と思う。一つの歌が、女性的解釈と両方にとれるところが私には面白いのです。そして今の私には、男性的解釈のほうが、より現代的な感じで、現代の男も中世の男もかわらぬ男心、という点で面白く思われます。
作者の敦忠は、左大臣藤原時平(ふじわらのときひら)の三男で、世に時めく貴族でした。「世にめでたき和歌の上手、管絃(かんげん)の道にもすぐれたまへり」というわれた芸術家でもありました。
敦忠の美しい北の方(妻)は、もと、時の東宮(とうぐう)のお妃だった人でした。東宮と妃の恋の文使いをつとめたのが、若い日の敦忠だったのです。文使いの青年貴公子と妃のあいだに通いあう心があったのかどうか、東宮薨(こう)じたもうのち、妃は敦忠の北の方になりました。
敦忠は北の方を愛していましたが、あるときこんなことをいいました。〈私の一族はみな短命だから、私も必ず短命でしょう。あなたは、私が死んだら今度はきっと、あの文範の思いものになるでしょうね〉
文範というのは、敦忠の家に出入りする家令の青年でした。無論、北の方はびっくりして否定しました。〈思いもよらぬこと、そんなこと、そんなことは決してありますまい〉と誓いました。〈まあ、見ていてごらんなさいよ〉敦忠は笑いながら申しました。
間もなく彼は三十八歳の短い生涯を終えました。その後、果たして予言通り、北の方は文範を夫とする運命になりました。
敦忠はきっと、男女の愛の微妙なながれのゆくすえを、早逝者(そうせいしゃ)の直観で洞察していたにちがいありません。彼は醒めた人の眼で、世を見、恋を見ました。「むかしはものを思はざりけり」は、彼の皮肉なつぶやきだったかもしれません。
あつもり
「平家物語」は美しいほろびを謳う物語です。それぞれの人の最期を語るとき、最も美しく最も力強く、感動的な昂揚(こうよう)を示します。幼帝のご入水(じゆすい)、能登守(のとのかみ)の最期、忠度(ただのり)の最期、そして木曾義仲の最期。
なかでも、やはりいちばん感動的で美しく悲しく、ドラマチックなのは、敦盛(あつもり)の最期ではありますまいか。
一の谷の合戦で、破れた平家は浮足立って浜辺へ落ちてゆきます。坂東武者たちはそれを追って汀(みぎわ)へ追い詰める。源氏方の中に熊谷郎直実(なおざね)は、よき大将軍に組まばやと物色するうち、平家の武者一騎、馬を海へうち入れ、沖の船めがけて泳がせるのを発見します。萌黄(もえぎ)の匂いの鎧(よろい)に、鍬形(くわがた)打ったる甲(かぶと)、こがね造りの太刀(たち)という美しい武者ぶり、「まさなうも敵にうしろを見せさせ給うものかな、かへさせ給え」と扇をあげて招くと武者はいさぎよく取って返し、立ち向ってきました。
汀(みぎわ)でむずと組んだ屈強の侍の熊谷、なんなく取り押さえて、首をかこうかと甲をはねのけてみれば、これはいかに、
「年十六七ばかりなるが、うす化粧してかねぐろなり‥‥容顔まこと美麗なりければいづくに刀を立つべしともおぼえず」

わが子の小次郎ぐらいの年で、薄化粧して歯を染めている美少年です。熊谷はなさけを知る武士でした。この人一人助けたとて源氏が負けるものではあるまいと助けようとしますが、しかし「ただとくとく首をとれ」と若武者はけなげに言い放ちます。
武門の意気地、熊谷は泣く泣く首を討ち、のちにこのいたましい思い出が、彼の出家遁世(とんせい)の契機となったことは、ひろく世に知られる通りです。若武者は錦の袋に入れた笛を腰にさしていました。それで、この公達(きんだち)は、経盛(つねもり)の一子、無官太夫(むかんのたゆう)敦盛とわかったのでした。
このエピソードが、文楽に歌舞伎に謡曲に、とひろく愛されてきたのは、熊谷の人間味ある心と敦盛の散りぎわの美しさを、人は、いとおしまずにはいられないからでしょう。
敦盛は一騎打ちになって組み敷かれてから、「あはれ助けたてまつらばや」という熊谷の好意を武士らしく拒みます。さらには、その前に熊谷に招き返されて、すでに海に入れている馬の首をたてなおし、取って返します。
人は、その心ざまに打たれないではいられない。なぜ少年は敢えて引っ返したか。
江戸の笑い話に、敦盛のことが出ています。〈なぜ敦盛は取って返したか〉ということをみんなで論じている。おいらなら委細かまわず逃げてゆくがなあ、ということになって、結局〈敦盛も熊谷とは思わなんだのさ、何かうしろからおいおいと呼ぶから手拭いでも落としたのかと思ったんだ〉という笑い話です。
敦盛が熊谷に「かへさせ給へ」と声を掛けたとき、彼は恐怖よりも、男の、武士のプライドでその心をいっぱいにしたことでしょう。
浜や汀(みぎわ)には、雑兵(ぞうひょう)が見ていたかもしれない。あるいは、誰も、熊谷とこの若武者に気づかぬ乱戦の最中だったかもしれない。
しかし敦盛はどちらにしても引き返すプライドを選んだのです。
〈それは男のええかっこや、僕は、逃げるのがプライドや〉と現代の若い男性がいいました。
たしかに、引返して討たれる方がたやすく、満場注視の中で逃げ出す方がむつかしいということもあります。そして、後者の方が、より強い男の誇りなくては、かなわぬ場合もあります。人間の強さ、男の誇りは、一見、格好のわるい卑怯(ひきょう)みれんな振舞いの場合にこそ要るのでしょう。しかし敦盛は格好よさの絶頂で花と散る誇りをえらびました。それは人々が夢見る一つの男の死の典型なのです。それ故にこそ、敦盛の最期は、人々の心にいつまでも熱く燃えるのです。
北浜の米市
井原西鶴(いはらさいかく)という人は、どんな顔をしていたのでしょうか。残された画像でみると、傲慢(ごうまん)な表情を浮かべています。私は、西鶴が誰かから話を聞いている、つまり、取材している表情などが一番、想像しやすいのです。
いったい、西鶴という人は、元禄という社会の上から下まで、裏から表まで、見透し知り尽くしたかに思えます。武家社会も町人世界も、男も女も、彼にとっては抱くなき好奇心と、貪婪(どんらん)な知識欲の対象でした。彼は人間社会のことなら、どんなことにでも、猛烈な興味と関心を示しました。
彼の小説には、だから、社会のありとあらゆる階層・職業の男女が登場します。
大名も乞食も、坊主も商人も、やくざ、遊女、丁稚、奥方、浅葱(あさぎ)うら――つまり地方武士――太鼓持ち、豪商、陰間役者、百姓、漁師、いろんな人間が、泣いたり笑ったり、怨んだり恋したり、さまざまの人生模様をくりひろげます。
オレの知らぬ人生、人間などあるものか、といった西鶴の傲岸(ごうがん)な、尊大な自負心が、いたるところに躍動しています。
さぞかし現実の西鶴は、屈折の多い、ひとすじ縄ではゆかぬ、いやな中年男だったでしょう。
意地悪く、そして自ら恃(たの)むところゆえに、他の作者や文学者を声高くおとしめて憚(はば)からぬ、不遜(ふそん)な自信家でもあったでしょう。その彼が好奇心の塊になって、
「それからどうした! え!」などと、つめよらんばかりに迫ったりするのですから、取材される側はたじたじとなる。
「いやですねえ、旦那」
などとへきへきしながら、つい彼の強引さにひきずられて、浮世の苦労、人の身の上の流転(るてん)などを喋ってしまう。西鶴は乞食のムシロ小屋の中であろうと遊女の床であろうと、商家の店先であろうと、何処へ出かけていって、人の世のこぼれ話を楽しんだことでしょう。彼は面白さに有頂天になり、フムフムと夢中で聞いて、かくして彼の小説的財嚢(ざいのう)はますますふくらんでゆく、といったふうだったかもしれません。それが彼の傲慢不遜な作風と人がらを支えたかもしれない。しかし、傲慢な自信だけでは作家の資質として完全とはいえますまい。彼の文章は、決してそれだけではないことを示しています。

西鶴の文章はリズミカルで、しかも言葉が豊富多彩、その上、内容がびっしりつまっていて、要するに中身が濃いのです。それが惜しげもなく、ツルベ打ちに出てくるのですから、その面白さに、読むものはあっけにとられます。――私の大好きな一節を取り出しますと、「日本永代蔵」の巻一「波風静かに神通丸」の章、大阪は北浜の米市、中の島の米問屋がたちならぶあたりの風景描写です。さかんな商いのありさまを、彼は口いそがしく、こう活写します。
「難波橋より西、見渡しの百景。数千軒の問丸(とひまる)、甍(いらか)を並べ、白土、雪のあけぼの奪ふ。杉ばへの俵物(ひようもの)、山もさながら動きて、人馬に付けおくれば、大道とどろき地雷のごとし。上荷・茶船、かぎりなく川浪に浮かびしは、秋の柳にことならず。米さしの先をあらそひ、若ひ者の勢ひ、虎ふす竹の林と見へ、大帳、雲をひるがへし、そろばん、あられを走らせ、天秤(てんびん)、二六時中の鐘にひびきまさつて、その家の風、暖簾(のれん)吹きかへしぬ」
なんていう、的確でしかも、勢いのほとばしるような文章でしょう。秋十月、西国筋の各藩の米は一せいに大阪北浜の蔵屋敷に廻送されてきます。上荷は二十石積の運送船、茶船は十石積のそれの名称です。北浜・米市の活況は元禄の浪速商人の誇りであり、感激であったでしょう。それはそのまま西鶴自身の誇りと感激でもありました。彼は商いの活気を愛し、人のいとなみの盛んないのちを愛しました。彼の小説の底にあるのはそれです。西鶴はどんな小説にも「生きている喜び」を謳わずにはいられない作家なのでした。
少女と物語
少女が地方官である父の任期みちて、草ぶかい上総(かずさ)の国から、あこがれの京へ戻ってきたのは寛仁(かんにん)四年(一〇二〇年)、彼女が十三歳の秋でした。「更級日記」は、少女の眼でみた、みずみずしい感性ゆたかな旅日記からかきおこされます。そしてそのまま、長い女の一生の旅へと、筆は進みます。少女が京に憧れたのは、まだ見ぬ物語・小説が、京にはどっさりあるように思えたからでした。小説好きな、夢見がちな女の子は、噂に聞く「源氏物語」を、どうかして読みたいものだと、熱望していたのです。
やっと京へつき、おとなたちが旅装を解くまもなく、〈ねえ、早く物語の本をみせてよ、見せてよ〉と少女はせがみます。京とはいえ、本は手から手へ写すほかなかった千年前のこと、物語・小説のたぐいは貴重なもの、どこにでも売っている物ではありません。そのうち、やっとのことで叔母が「源氏の五十余巻、櫃(ひつ)に入りながら、ざい中将、とほ君、せりかは、しらら、あさうづなど(と)いふ物語ども、一袋とり入れて」少女にくれます。
この一族の人々はみな教養高く、中でも私の好きなのは、この叔母さんの言葉です。叔母さんは少女へのみやげに、「何をか奉らむ、まめまめしき物は、まさなかりなむ、ゆかしくし給ふなるものを奉らむ」と、物語をくれるのです。実用品はつまらないわね、ほしいと思っている物をあげましょう。このひとことで、心優しく、自身もまた、おとめ心を失っていない、女らしい叔母さんの心情が伝わります。

少女は狂喜しました。天にも昇るここちというのはこれでしょうか。
「得て帰る心地のうれしさぞ、いみじきや。はしるはしる、わづかに見つつ、心も得ず心もとなく思ふ源氏を、一の巻よりして引き出でつつ見る心地、后の位も何にかはせむ。昼は日ぐらし、夜は目のさめたる限り、火を近くともして、これを見るよりほかのことなければ‥‥」
古来、有名な一節で、これあるがために「更級日記」は千年の命をいまに伝え、人々の愛着と共感をよぶくだりです。
少女は昼となく夜となく、むさぼり読みました。その少女の歓喜と陶酔を簡潔に、実にリズミカルに描いた名文です。それにしても、少女の心の、千年前といまと、なんと変わらぬこと!
后の位も問題ではない、と思う喜びは、私の少女のころは、「風と共に去りぬ」であり、パール・バックの「大地」でした。さらには古屋信子氏の少女小説の数々‥‥「花物語」「桜貝」「毬子(まりこ)」「からたちの花」、幾度、読み返して読み返し、そして次の章へうつるのが惜しく、あとどのくらいあるかと、本の厚みをはかりながら、みんな読み終えてしまうのが惜しくて、おいしいお菓子を少しずつ食べるように、いとおしみ、心をうち入れて読む、でも、あとは明日のお楽しみということができないのです。夜を徹してでも読みつくさねばいられないのです。それほどふかい酩酊(めいてい)を与えられば、やがて夢の世界か現実とわかちがたくまぜられてゆくのは当然でした。私自身も、「更級」の少女も…‥。
「物語のことをのみ心にしめて、われはこのごろわろきぞかし、盛りにならば、かたちも限りなくよく、髪もいみじく長くなりなむ。光る源氏の夕顔、宇治の大将の浮船の女君のやうにこそあらめと思ひける心、まづ、いとはかなくあさし」
いまこそ、私も、まだ器量がよくないが、年頃になったら容貌も美しく髪も長くなろう。光の君に愛される夕顔や、宇治の大将・薫の君恋人、浮船のようにもなるだろうと、頼りないつまらぬことを考えている少女なのでした。
物語というものがこの世に出てきてから、どのくらいの少女がこう空想したことでしょう。そして彼女らはそのほとんどが現実に裏切られ、見はてぬ夢を心の底に抱いたまま終わります。彼女もまた、「今はむかしのよしなし心もくやしかりけり」とつぶやく中年女になるのでした。
男の友情
男と女のあいだに真の友情はあるものでしょうか。私にとってはいつも尽きぬ、興味のある小説のテーマです。「平家物語」や「源氏盛衰記」にみられる木曾義仲と巴御前(ともえごぜん)の物語は、私には男と女の友情のように思えてならないのです。
巴は義仲の実質的な妻であり、義高という子供まで持ちました。また義仲にとっては最愛の恋人であり、妹のような幼馴染でもありました。
義仲は二歳のときに戦火に追われて母のふところに抱かれたまま、木曾谷に逃れました。木曾谷には乳母の夫の中原兼遠がいたのです。
兼遠はゆくすえ、源氏の棟梁(とうりょう)とも仰がれるべきこの幼な児をたのもしく引き受け、心をこめて養育しました。そして息子の樋口兼光、今井兼平、娘の巴たちも、あげて義仲の無二の友となり、最初の、そして最も忠実な家来となりました。
治承四年(一一八〇年)、いよいよ時が来て、義仲が平家打倒の旗をあげたときも、それから連戦連勝、平家を打ち破って京へ入ったときも、つねに彼ら乳兄弟は、義仲のそばを離れなかったのです。
けれども朝日将軍とよばれた義仲の得意絶頂の時代は短かく、たちまちに今度は、範頼、義経の鎌倉勢に追われる身になります。
六条河原で木曾勢はめざましく戦ってほとんど玉砕、山科、四の宮河原をすぎるころには、ついに主従七騎になってしまいました。しかもその七騎の内にも巴は討たれずに残っているのです。
「平家物語」によれば、彼女は、
「いろしろく髪ながく容顔まことにすぐれたり」
木曾谷の美しい女鹿のような彼女は、また打ち物とっては鬼をもひしぐといわれた強力の女丈夫でした。剛弓を引き、荒馬をのりこなし、「度々の高名、肩をならぶものなし」という、凛々しい女武者であったのです。
巴その日のいでたちは萌黄(もうぎ)おどしの腹巻に五枚甲の緒をしめ、連銭(れんぜん)葦毛(あしげ)の愛馬「春風」に金覆輪(きんぶくりん)の鞍(くら)を置き、黒髪をうしろに流し、額には天冠をあてるという、美しくもいさましい武者姿、彼女は、夫であり恋人である義仲を守って、敵をけちらしながら、ここまで逃れてきたのでした。
義仲は、乳兄弟・今井四朗兼平の行方を案じていました。
「幼少竹馬の昔より、死なば一所で死なんとこそ契りしに、ところどころでうたれん事こそかなしけれ。今井がゆくゑをきかばや」
四朗は勢田(せた)をかためていましたが、これも義仲を心配して都へ引き返す途中、大津の打出(うちで)の浜でゆきあいます。
「互に、なか一町ばかりよりそれと見知って、主従、駒を早めて寄りあふたり」
どんなに主従手を取りあって喜んだことでしょう。「契りはいまだくちせざりけり」最後の一戦をと、敗残の兵を集めて思うさま戦います。
義仲このとき三十一歳、色白き美青年です。その日の装束は赤地錦の直垂(ひたたれ)に唐綾おどしの鎧をきて、鍬形打ったる甲の緒を締め、いか物づくりの大太刀をはき、石打の矢を負い重藤(しげとう)の弓をもって「きこゆる木曾の鬼葦毛といふ馬の、きはめて太うたましくゐに、金覆輪の鞍をいてぞのッたりける」

今日が最期と観念した木曾義仲の戦いぶりはすずやかで壮快でした。「あぶみふンばり立ち上がり、大音声(だいおんじょう)をあげて」名のりかけます。
「昔はききけんものを、木曾の冠者(かんじゃ)、今は見るらん、左馬頭兼伊予守、朝日の将軍 源義仲ぞや。甲斐(かい)の一条次郎とこそきけ。たがいによい敵ぞ。義仲うッて兵衛佐(ひょうえのすけ)に見せよや」
一条の次郎の勢は、すわこそ、「只今名乗るは大将軍ぞ。あますな者共、もらすな若党、うてや」とどっとうちかかり、乱戦になりました。こちらは名代の屈強の木曾勢三百余騎、攻め手の六千余騎の中を、たてさま・よこさま・蜘蛛手(くもで)・十文字にかけわってけちらし、け破って出たころには、味方は五十騎ばかりになっています。なおも迎える敵勢のかこみをかきわけわりかけわりゆくほどに、ついに主従五騎になってしまいました。
その五騎の内にも、巴はまだ討たれずに残っているのでした。
義仲は巴にいいました。
「おのれは疾(と)う疾う、女なれば、いづちへもゆけ。我は討死せんと思ふなり。もし人手にんらば自害をせんとずれば、木曾殿の最期のさいに、女を具せられたりけりなンどいはん事も、しかるべからず」
義仲はもう死の覚悟をきめています。武者の最期の時まで女を連れていたと言われたくない、と巴を去らせるのです。彼は、巴だけは生き残らせてやりたと思ったのでしょう。
巴は「なほ落ちもゆかざりけるが、あまりに言はれ奉(たてまつ)りて」最期の働きをお見せしてからと、敵勢の中にかけ入り、首を一つ切って、別れがたき義仲と別れます。
駒敏郎氏は「泣く泣く戦場をあとにする巴を見送ったとき、義仲は(木曾が去った…‥)と感じたことだろう」(保育社刊「木曾路」)とのべていられます。駒敏郎氏の「木曾路」には、木曾義仲の一生が簡潔に紹介されてありますが、たいへん美しい名文です。
義仲にとっては巴を去らせることが、最大の愛情だったのでしょう。けれども、巴は、義仲と共に死にたかったのです。
童女の日から、兄とも恋人とも夫とも頼んだ義仲という男への愛は、強い友情に支えられていたのです。
共に生き共に戦い、男と同じ条件で、ここまで生き延びたものを、しかし最期には、男と女として、隔てられたのです。
やがて義仲は、四朗と主従二騎になってしまいます。
「日頃は何とも覚えぬ鎧が、今日は重うなッたるぞや」と義仲は述懐します。四朗は声を荒げて励ますのです。
「御身もいまだ憑かれさせ給はず、御馬も弱り候はず。何によッてか、一両の御着背長(おんきせなが「鎧」)を重うはおぼしめし候べき。兼平一人候とも、余の武者、千騎とおぼしめせ。矢七つ八つ候へば、しばらく防ぎ矢つかまつらん。あれに見え候、粟津(あはづ)の松原と申す。あの松の中で御ン自害候へ」
しかし義仲は四朗のそばを離れようとせず、いい切ります。
「義仲、都にていかにもなるべかりるが、これまで逃れくるは、汝と一所で死なんと思ふためなり。所々で討たれんよりも、ひとところでこそ討死をもせめ」
そして馬の鼻を四朗の馬と並べ、敵中にかけ入ろうとしますので、四朗は馬からとびおり、主の馬の口にとりついてとどめます。
「弓矢とりは年ごろ日ごろ、いかなる高名候へども、最後のとき不覚しつれば長は疵(きず)にて候なり。御身は疲れさせ給ひて候…」
四朗は、さきに義仲を励ますときは、まだ御身も御馬も疲れてはいられぬものを、と叱咤しました。でもいまは最期です。〈よくここまで戦って来たものです、おたがいに…。花を咲かせた一生だったではありませんか。やることはやったのです。あなたは疲れられたのだ‥‥〉男のやさしいいいたわりと、あつい友情が感じられる四朗の言葉です。四朗はなおもとききかせます。名もなき雑兵にうたれたりなされては、口惜しいではありませんか。
義仲はやむなく粟津の松原さしてただ一騎かけこみます。四朗は五十騎ばかりの敵勢の中へかけ入り、名乗りを上げて、射残した矢を射かけ、打ちものとって馳せ、さんざんに打ち破って時をかせいでいました。けれども義仲は深田の中へ馬を乗り入れ、足を取られた所を射切られ、ついに首をとられました。その勝ちなのりを聞いた四朗は、
「今は誰をかばはんとてか、戦をばすべき。是を見給えへ、東国の殿原、日本一の剛の者の自害する手本」
と太刀の先を口に含み、馬をより逆さまに飛び落ち、貫いて自害しました。今井四朗兼平行年三十三、義仲より二つ上の乳兄弟は、かねての契りのとおり、もろともに滅んだのです。
男たちの友情は、共に美しく死に滅ぶときのためのもの、――そして、男と女に、もし友情があるとかれば、それは共に生きるときのためのものではないかと‥‥私は、義仲と巴、義仲と四朗を並べたとき、思うのです。
心あひの風
あるとき、私が越前・福井駅に降りましたら、元気のいい高校生の少年が数人、剣道の道具をかついで、やってきました。その道具には「武生高校」とありました。そういえば、武生はここから遠からぬ町、私はとても懐かしかったのです。現実の武生市は知りませんが、古い昔の唄に、こんなのがあるのを思い出したからです。
道の口、武生の国府に
われはありと 親に申したべ
心あひの風や さきむだちや
これは催馬楽(さいばら)の唄の一つです。
催馬楽は、おもに平安期ごろ、貴族たちに愛された歌曲なのですが、もとは、庶民のひなびた里うただったのです。それを管絃(かんげん)にのせて調子やメロディーをつけて、貴族たちは宴会でうたいました。だからこの文句も、流れ流れてゆく浮かれ女(め)の哀愁がこもっています。
道の口というのは、地方へ下る道の、ほんのよりくち、という意味。越前は京にちかいところです。武生には国司の役所があり、人々の交通もさかんで、遊び女も集まったことでしょう。
「あたしは武生の国府にいると親に伝えておくれ…仲よしの風よ」
というわけです。「さきむだちや」というのは、はやし言葉です。
柳田国男さんは、「アイの風」または「アユの風」とは、海岸に向かって吹く、航海によい風、船を港入れさせ、くさぐさの珍かなるものを、なぎさに向かって吹き寄せてくれる、人間にとって、なつかしい、仲よしの風という意味のことを「海上の道」で、いっておられます。
この唄を口ずさんだのは、武生の国府の町まで売られ売られてきた遊女でしょうか、少年でしょうか。私のような年ごろの女はふと、映画「アヘン戦争」で唄われた淋しい唄を、思い出さずにはいられないのです。
風は海から吹いてくる
沖のジャンクの帆に吹く風よ
情けあるなら教えておくれ
わたしの姐さんどこにいる
アイの風はやさしく港へ吹きつけ、また船を送り出してくれる。
風の便りというけれど、わが思う人に伝えてくれないものかしら、あたしがここに生きているって‥‥。古い、古い唄でありながら、今の流行唄とすこしもかわらない、ほんとうに人間の発想というのは、千年前も、いまも、さして違わないものです。
こんな唄を唄わずにいられない人たちの身の上を、あれこれと考えると、私はやっぱり「山椒大夫(さんしょうだゆう)」の物語を思い浮かべたりします。
おどろおとろしい中世の闇
鬼か夜叉(やしゃ)のような人買いの横行。武者ばらのいくさ、人もなげにはびこる物盗り、引きはぎ。中世はくらい、蒙昧(もうまい)な、闇の世代でした。
もしそれ、力のない女や子供たちがひとたび恐ろしい運命に捲(ま)き込まれたら、「山椒大夫」の邸に売られた安寿(あんじゅ)と厨子王(ずしおう)のような、からい目にもあったことでしょう。五百年ほどあとの室町時代の唄にも、こんなのがあります。
人買い船は沖を漕(こ)ぐ とても売らるる身を
ただ静かに漕げ 船頭どの

(閑吟集)
現代でも人買い船は、西に東に走っています。
東南アジアの少女たちだけでなく、心ならずも、あるいはわが心からふるさとを離れて流浪する運命に、身を委ねている人はたくさん、います。道の口、武生の国府に、
われありと 親に申したべ
心あひの風や
ふと、面を打つ風に、心あらばたよりをことづけたいと思う人は多いでしょう。
あね・おとうと
朱鳥(しゆちよう)元年(六八六)夏もすぎようとする早秋(はやあき)のたそがれ、伊勢の皇大神宮の神域からほど遠からぬ、斎宮(いつきのみや)の御所は、時ならぬ人馬の物音で、静寂を破られました。飛鳥(あすか)の都からの旅人が到着したのです。人影は闇にまぎれて、斎宮の御所の階(きざはし)を慌ただしく駆け上るのでした。〈姉上、大津(おおつ)です!〉
まだ馬上の息の乱れもととのわぬまま弾んでいう声に、斎宮の大伯皇女(おおくのひめみこ)は驚かされました。戸口いっぱい、塞がるような逞しい青年が、日に焼けた顔で笑っているのでした。
〈どうして、また突然に出てきたの、大津‥‥〉
〈急にたまらなく姉上に会いたくなって‥‥それだけのことだ、思い立つと矢もたてもたまらぬ私の性質(たち)は、姉上もよくご存知のはず〉
〈まあ大津‥‥いつまでも幼な児のようなことをされてはなりませぬ〉
大津皇子は哄笑(こうしょう)して、うれしそうに姉の皇女をしっかりと抱きしめるのでした。
〈そうやって、姉上に叱られたかったのですよ。ああ、会いたいと思ったのは、このためだったのですよ〉
〈大津よ。わたしとて、あなたのことを考えぬ日は一日もありませんなんだ‥‥ことにお父さまのご病気が悪いととう都の噂を聞いてからは‥‥〉
大伯皇女(おおくのひめみこ)は、十三の歳から十三年間、清い斎宮して神に仕えて伊勢にいました。夫も子もない彼女にとっては、弟の大津ひとりが愛する対象でした。
その大津はいま、飛鳥浄御原(あすかきよみはら)の宮廷で、むつかしい立場におかれていました。その風聞は、俗世から遠く離れたこの地まで伝わってきます。皇女は密かに弟のために心を痛めずにいられませんでした。
父・天武天皇は皇太子に草壁皇子(くさかべのみこ)を、その輔佐(ほさ)者に大津皇子をきめました。しかし、人望は大津皇子により多くあつまり、才幹も人間的器量も大津皇子の方が優れていました。天皇もひそかに大津のほうを愛していました。しかし草壁は年長でもあり、また、皇后(うののさららのひめみこ)のちの持統天皇のただ一人の所生の皇子でもありました。
皇后はわが子草壁のライバル、大津の存在を複雑な思いでみています。しかもこの皇后はなみならぬ政治能力に恵まれた、勢威ある婦人です。微妙な政治権力のもつれは、皇位継承問題をめぐっていよいよ紛糾し、重臣・豪族たちの思惑は入り乱れ、怪しい情報が飛び交うのです。
大津皇子自身がいかに抑制してふるまおうとも、四囲の政治状況は皇子をつき動かし、どこへ運んでゆくか、誰にも予測はつかないのです。しかも大津皇子を陰に陽に庇ってくれる、父・天武天皇はいま、死の床にありました。
――国をあげて天皇の快癒(かいゆ)を祈る行事がおこなわれています。連日の炎天のもと、数百人の僧侶の潮騒のごとき読経の声はたえず、神々という神々のやしろには、熱烈な祈願が捧げられています。
都はいま、狂気してどよめいていました。あたかも不吉な騒乱の前ぶれのように‥‥。
〈そんなときに都を抜け出て、咎めや疑いをうけることがありはしませぬか?〉
皇女は不安にわななくように囁きました。
〈どうか自重しておくれ。大津よ。おん身の上に万一のことがあれば、わたしも生きている心地はせぬ〉
〈姉上の思い過ごしというものだ、それは。お案じになることは何一つない〉
大津は、皇女の白いやわらかな手を、いかつい男の大きな手ではさみ、力づけるように握りしめてほほえむのでした。
〈私こそ、暑ければ暑いとて、寒ければ寒いとて、姉上がつつがなく暮らしていられるかと、思わぬ日はありませんよ〉
豪快で奔放で、才気にあふれ、人々に期待され、また畏怖(いふ)されている大津皇子も、姉の皇女の前では、心優しい、しめやかな愛にあふれた一人の青年でした。
〈姉上が七つ、私が五つ‥‥ですね、母上のみかまかられたときは‥‥〉
〈あなたはおぼえていますか?〉
〈いや。さだかな記憶はない。私には、姉上と母上が重なって思える〉
佩剣(はいけん)を解いてくつろいで坐った大津は、熱い酒を飲みました。旅の疲れに酒をすばやく体中をめぐり、青年を感傷的にするのでした。
〈私は小さい時から、美しい姉上が自慢だった。今でも、あなたほど美しい女人を見たことがない。もし、この世を去るときも、私の心はあなたのほうへ向いて、呼び続けることでしょうよ〉
〈今夜は不吉なことをいうのね、大津‥‥〉
〈私は酔った。酔って、姉上に世話をかけたい。私を、甘えさせて下さい、姉上。私が心からうちとけられる場所は、あなたの前だけなのです〉
〈かわいそうな大津。どんなに辛いことがあるのでしょう。そんなに、苦しそうにして。甘えてちょうだい、昔、小さかった日に、あなたがよくわたしに無理をいって困らせたように‥‥〉
皇女は酔い伏した弟のあたまを膝(ひざ)にのせました。清艶(せいえん)な皇女は灯影(ほかげ)で見ると、なお美しくやさしく、大津にはこの世のものならぬ、女神かと思われます。
長い夜が明け、しめやかに暁がおとずれました。
早い出発のときでした。
窓の下では従者たちのひそひそ話し声がし、馬のいななきも聞こえます。
〈ああ、もうこれでいい、お目にかかれて気がすんだ。では…‥〉
大津は馬に騎(の)りました。皇女は領巾(ひれ)を振っていつまでも見送りました。けれども大津の方は、さすがに男らしく、ついに振り返りませんでした。朝霧は屈強な男たちの一行の姿を。すぐ隠してしまいます。
わが夫子(せこ)を大倭(やまと)へ遣るとさ夜更けて、暁(あかとき)露に我が立ち濡れし
二人行けど行きすぎがたき秋山をいかにか君がひとり越ゆらむ
大伯皇女のこの歌には姉弟の情を超えた、ほとんど男と女の官能愛にちかい、物狂おしい愛が、妖しく息づいています。
皇女は、弟皇子が去ってから、しだいにその不安がかたちをとって明らかになる気がしました。――大津は、愛する弟は、最後のわかれを、わたしに告げに来たのではあるまいか?
皇女は恐ろしい予感におびえ、神の前に身を捨てて必死に祈りました。――どうぞ神よ、いとしい弟をお守りください。泣き母君よ、お救いください、愛する人を。
皇女の不幸な予感は的中しました。
九月九日、天武天皇はついに崩御。
急転直下した運命は、大津皇子を押し流し、九月二十四日、謀叛(むほん)が発覚したと公表されました。事実のあるなしは不明のまま、大津皇子および共犯者の一味三十余人が捕らわれ、十月三日、大津皇子に死を賜わったのです。
大津皇子はその運命を知っていたのです。
磐余池(いわれのいけ)の畔(ほとり)で処刑されたとき、年二十四。
百伝(ももつた)ふ磐余の池に鳴く鴨を今日のみ見てや雲隠りなむ
池の堤で死にのぞんで彼はそう歌いました。
大伯皇女は斉宮の任を解かれ、大和へ帰京しました。いかにその足は重かったことでしょう。
見まく欲り我がする君も在らなくに何しか来けむ馬疲るるに
わたしの逢いたい人はもういないのに、なぜ都へかえってきたのだろう。――馬が憑かれるだけなのに‥‥。
涙にくれた佳人を迎えたのは、大津皇子のなきがらを葬った、葛城(かつらぎ)の二上山の塚でした。落日は二上の峰を染め、空は、大津の最期(いまわ)のときの血のいろにいろどられます。
うつそみの人なる我や明日よりは二上山を兄弟(いろせ)と我が見む
磯の上に生(お)ふる馬酔木(あしび)を手折(たを)らめど見すべき君が在りといはなくに
この世に生きているわたくしは、あの世へおもむいた大津とはもう逢うことはできないのだ‥‥明日からは、あの二上山を大津と思って眺めよう。
磯の上に生えている馬酔木の花の、ま盛りなのがあまりに美しくて、思わず手折ろうとしたけれど、それを見せて共に賞(め)でる大津はもうこの世にはいないのだ。大津よ、愛するものよ、あなたはもう、この世にいないのね。あの夜、やはりあなたは最後のおわかれに来たのね…‥。
大伯皇女の歌は人々の胸をしめつけ、涙を流させました。非情な政争の嵐にまきこまれた不運な皇子を、人々はあらためて惜しみ、いたみました。しかし皇女にとっては、どんな慰めも心を安めはしなかったでしょう。年若くして非命に斃(たお)れた弟を、彼女は生涯、忘れることはできなかったでしょう。
都の華やかな暮らしも、人々のいたわりも煩わしく、皇女には、かつての神さびて俗塵(ぞくじん)をはなれた、清い斉宮の生活のほうが、どれほど慕わしく思えたことか。
神風(かむかぜ)の伊勢の国にも在らましを何しか来けむ君もあらなくに
「何しか来けむ」――何のために私は都へ帰ってきたのだ。愛する者もいないのに‥‥「萬葉集」巻二に載せられた歌の、皇女の通惜は、千三百年のちの私たちを泣かずにはおかぬものでした。
大伯皇女それから十なん年を生き、四十になる前に、ひっそりと死にました。
皇太后のおん靴
そで袖に咲く朝顔の花をみて髪くしけづる時のおくれぬこの楚々(そそ)としたやさしい歌は、昭憲皇太后のお作です。
背の君の明治天皇も、お歌をよくされましたが、皇太后もたくさんのお歌を、そして美しい擬古文の文集を残していられます。
もとより、皇太后の宮は、御身分がらといい、また先(さき)つ世(よ)のかたでもあられるわけで、したしくお見上げすることはできませんが、幸いにお写真で、しのぶことができます。
お写真の皇太后は、私にはじつに好きなタイプの美女でいらっしゃいます。
きさいの宮を美女というのは失礼ですが、まことに明治美人の典型のような気がされます。細面の、秀でた男眉(おとこまゆ)に、りりしい気品がみなぎり、すこしほそての、美しく切れ上がったまなじりのおん目の美しさ。
明治美人というのは、東洋の美の精粋をあつめたようで、それに威厳と気品が加わっているのですから、皇太后のお美しさは無類です。
皇太后はおん子をお持ちになれませんでした。大正帝は、柳原二位(にいの)局(つぼね)をご生母として降誕された皇子でした。
そのせいでか、皇太后のお美しさには、国母陛下のご慈愛というよりは、深い九重の奥ふかく、王朝の姫さながらに生(お)いたたれた、高貴な女人の、美しさと気高く強く出ています。
宝冠や、勲章などの重みにも、え堪えねかのごとく、たよたよとした、水草のようなお姿。ほそくて、しかも鋭い、内なる勁(つよ)さを秘めた、なだらかなおん頸(くび)からおん肩の線。
円地文子氏の「女坂」にも、明治の高官の夫人たちが鹿鳴館(ろくめいかん)で間近く皇太后に拝謁するくだりがありますが、皇太后を、お綺麗で美少年のような、と作中人物に批評させていられます。
明治の日本に来たフランス海軍士官、ピエル・ロチは、皇太后に拝謁して、その美と優雅さと気品と聡明さにおいて、世界最高の貴婦人の一人、と賛嘆したそうです。
私はもうずっと前、皇太后の御遺品を拝見したことがありました。服装史展のようなものの、特別展覧室に、皇太后のお召しになったローブデコレテの礼服と、そのときのお靴がありました。
ローブデコレテは胸の開いた、トレインのないもので、裾丈(すそたけ)は床につくぐらいのもの、しっとりとした、縮緬(ちりめん)のような絹で、色は、うすいブルーらしいのですが、黄ばんでグレーのようでもありました。腰からは襞(ひだ)があったように思われます。お袖は、なかったようでした…‥ようでした、というのは、お靴のほうにすっかり心を奪われてしまったからです。
それは白繻子(しゆす)のハイヒールの可憐な靴で、ほんとに小さいのです。まるで、てのひらに乗りそうな…‥。
皇太后のおみあしが、どんなに華奢(きゃしゃ)でいられたかが、しのばれました。
皇太后の御集(ぎょうしゅう)でみると、背の君・明治天皇とのおん仲はむつまじそうです。
明治天皇はどこかへ行幸の際にはかならずおみやげを持って帰られたり、またときには、皇太后を(明治の世ではむろん、皇后であられます)伴われることもありました。
明治二十三年十月二十六日の水戸大演習のときも、明治天皇のおすすめで、皇太后も行啓されました。
「みづから(ご自分のこと)も従ひ奉るべく、かねておほせごとありしかば、いとうれしくていでたつ。この大御代ならずば、いかで女の身にてかかることを見むと思ふに、おのづから心もいさみたちて、うちゑまれぬ」
上野停車場から汽車は水戸へと向かいます。
いまも明治村には、行幸・行啓のための、芸術品のように美しいご料車が展観されています。つづれ錦で張り巡らされ、螺鈿(らでん)や七宝をちりばめられた、さながらそれ自体、一つの宝石のごときご料車。私はそれを見たとき、皇太后の御文集にある、おふた方のたのしげな旅のあれこれを、思い出したのです。
むろん、この水戸へのご旅行は遊山(ゆさん)ではなく、近衛兵の演習をごらんになるためでしたけれど、皇太后にとっては、きっと、お心はずむうれしい旅だったことでしょう。
翌二十七日、秋晴れの野に大演習がはじまります。明治帝は「金華山」と名づけられた御馬にめされ、有栖川宮(ありすがわみや)や北白川宮や、あまたの人を従え進まれます。皇太后は馬車でつづかれるのでした。
「岩間村にいたらせ給ふころ、遠近(をちこち)に煙たちのぼり、砲(つつ)の音こヽかしこに聞えて、赤白の旗、風にうちなびき、馬のいなヽくこゑもところどころにきこえたり。戦ひたけなはならむと思ふところは、砲の音もたえまなきに、み心いさませたまひて、折々はことかたに御馬すヽめさせつヽ、ねもころに御覧じたまふ」
二十八日も成井村でひきつづき行われます。筑波山が近く見え、景色のよい所でした。大方は昨日のようでしたが、今日は敵が近いとみえ、「大砲小銃のおとはげしく、広き原にも響きわたりぬ」
「上(天皇のこと)には、例の御馬にて、道も定めさせたまはず、森の中、松の林などにわけいりて見めぐらたまふに、木の枝の御あぶみにかヽるもいとかしこし。みづからも、車よりいでて小銃の連発又は大砲のうちかたなども見ずやと、附添へる士官のいふに、さらばとておりたつ。黒けぶり立ちのぼる中に火気見えて、はげしき音のきこえたる、いといさまし。事あらむ日は、親妻子をもかへりみず、君のため命をすてヽたヽかひなむと思ふに、いとたのもしくあれど、又いたはしくて、胸もふたがるこヽちぞする」
というのが、はじめて演習をごらんになった皇太后の女らしい可憐なご感想でした。
演習の後の観兵式も果ててから、天皇は県庁へ臨幸されましたが、皇太后は、天皇のおすすめで常盤公園の好文亭を見学されました。かえりに弘道館のあとへも寄られ、興をもようされました。
「げに珍らしきところをみしかな。是も上のおほせごとなくばと、いとうれしくて、時の過ぐるも覚えず。人々夜更け侍(はべ)りぬべしといふに、おどかされていそぎかへる」
「御まへに参る。上には、六時ばかりに帰りましましきときヽて、おくれ侍りぬなど奏するに、うちわらはせたまふ」
まるで古いオルゴールの、ゆるゆるとした音をきくように典雅なご文章です。観菊の宴、歌会はじめ、華族女学校への行啓‥‥明治の錦絵をみるような場面が、繰り広げられてゆきます。
「夜の長きころなれば、上には書(ふみ)どもとりいでさせたまひて、むかし今のことども、おぼしあはせられて、み心しづかにましますほど、やうやう十一時ばかりにもなりるに、御文机のうへのものどもとりあつめさせて、やがて大とのごもりにたれば(おやすみになるひと)、女房どももみなすべりいでぬ」
これは「菊始開」(菊、初めて開く)という題のご文章です。
おましどころのお庭の、とりどりの菊がまだつぼみなのを、今日ひらくか明日ひらくかと女官たちと興じられたあと、明治帝と皇太后は秋の静かなまどいを楽しまれます。
あくる朝、「風なつかしううち薫るに、よく見れば、二つ三つばかりさきいでたるなりけり」
「上(うえへ)、聞こしめしつけて、まことにやとのたまはするに、早うみそなはせとそそのかし奉れば、朝風なほ寒けれど、しばし、はし近ういでさせたまひぬ。色をわきて咲きたる菊のみゆるにぞ、ことの外に興じたまひて、天長節には必らず盛りならむと仰せらるる、そのみ言葉につけて、千代田の宮の秋の盛りと、みづから言ひいでつれば、、うちゑませ給ふもいとかしこし」
天長節というところが、私にはなつかしかったのです。明治の御代の天長節は、なるほど、秋でした。
皇太后のお歌には、人間的なのびやかさがうかがわれます。
ともし火に近くよりつつ見るふみも目がねをたのむ身となりにけり
ご聡明なかただけに、一面、諧謔(かいぎゃく)を解される愉快なとこがおありでした。「電話」と題したお歌に、
白雲のよそなる人の言の葉も家にゐながらきく世なりけり
「飛行機」という題で、
たくみなるわざの開けて神ならぬ人も天(あめ)とぶ世となりにけり
明治天皇はこんなお歌をごらんになって、思わず破顔したまい、どんなに皇太后の躍動した才気をかわゆくお思いになったことでしょう。お話はたのしくはずんだにちがいありません。
皇太后は、愛する背の君に後(おく)れたたまうこと二年ののち、蒙じられました。東洋の美女の典型のおもかげを写真にとどめられて‥‥。
十二単(ひとえ)
女のおしゃれごろや虚栄は、熱狂するとどまる所を知らず膨れあがってゆくものです。「栄花物語」を読むと、面白い個所がたくさんあって、しかも女が読むと面白いのですが、男性にはわかりにくいのではありますまいか。「栄歌物語」は、藤原一門、ことに道長の全盛時代をピークにした栄華のさまを、冗長な筆で叙した歴史物語ですが、こと女の衣裳、容貌、おしゃれの記述になると俄然(がぜん)、生彩を帯びます。そして読んでいる私も、女としてつい、ひき入れられて、衣裳の色め、紋織の柄など、熱心に思い浮かべたりしているのに気付きます。
「栄花」の作者はどうも女性らしく、女たちが、おしゃれに狂奔しているところなんか描写するのが、じつに巧みで、この巧みだということは、意地悪さがあるからかもしれません。たとえば巻二十四「わかばえ」の章。万寿二年正月二十二日、皇太后、姸子(けんし)の主催にかかる大宴会は、派手ごのみの皇太后のこととて、たいへんな盛会でした。とりわけすごいのが、お邸に仕える女房たちの盛装です。
あの十二単衣のものものしい衣裳を、彼女たちは競って十枚二十枚と着込んで飾りたてたのです。当日、女房の部屋や詰所は大騒動、各々のパトロンや恋人の男たちもうろうろ出入りして、手伝ったり世話をしたりしています。もう時刻も迫ったというのに、まだ物を縫っている女もあり、〈どうしましょう、まだ髪もできていないわ〉と悲壮に叫び立てているのがあるかと思うと、一方ではすっかりお化粧し衣装をつけ、心のどこかに最後の仕上げのお歯黒をつけているのもあります。
自分の扇を他人と見比べたり、衣装を自慢し合ったり、あるいは食べ物を取らず、着物を着ようとして、そんなことをなさったらお体がもちません、とたしなめられているのもあります。それも道理、彼女の着る衣裳一式は、長持ち一ぱいあって、やっと二人で担いでくるという大層なもの、果たして、すっかり着つけてしまうと、立てないで、崩れてこんでしまう女も出るほどです。
やっと宴の席へでようとしてよろよろ歩きかけましたが、「扇も、えさし隠さず、衣のこちたく厚ければ、たをやかなる気(け)もなし」
あまり着ぶくれて、さながら小山のゆるぎ出したごとく、却って風情も何もありません。彼女らが御簾(みす)の下からずらりと着物のつまを出し並べているのを見ると着物の重なりは一尺ばかり、袖口もあまりの厚さに丸くふくれて、まるで火桶(ひおけ)の小さいのを据えて並べたようにみえた、といいます。

桜、山吹、柳などの色目の衣をとりどりに重ね、金銀のぞうがん、金箔、刺繡(ししゅう)、それに、長い黒髪、緋(ひ)のはかま、けんらんとして美しいけれども、あまりの衣裳の仰々しさに、向かいの席についている貴族殿ばらも、
「あさましう、目もあやにて、かたみに御眼をみ交わしてあきれたまへり」
というほどでした。心ある元老の大臣などもにがにがしげに、
「すべて、かかる事をなん聞き見ざりつる」
今までこんなことは、聞いたこともない、とたしなめられるありさま。
「なでう人の衣(きぬ)か、廿着たるやう候(さぶら)ふ」
どんな人だって二十枚も着物を着るということがあるものか、と、さしも栄華になれた貴族たちも咎めるくらいでした。女房たちはというと、長時間、重い着物に埋もれていたので、もうぐったりとなり、
「ゐすくみて、立つ心地いとわびし」
それぞれの居間に帰るやいなや、
「物も覚えでより臥(ふ)しぬ」
というありさま。そのてんわんやのさわぎを「栄花」の筆は、おもしろそうに描写していますが、その筆の意地悪さと共に、作者の同性としての理解と共感を感じないではいられません。男どもが何といおうと、顔をいろどり衣を競わないではいられない、〈これが女というものなのよ〉という気負いが、「わかばえ」のこの章のいきいきした力になっています。
年上の女
捨てはてんと思ふさへこそ悲しけれ君に馴れにしわが身を思へば和泉式部(いずみしきぶ)の歌から好きな一首をあげよといわれれば、私は目うつりしてためらいながらも、この一首を選びたい気がします。
式部は「恋多き女」として、その生前中も死後も、浮名を流した人です。しかし決して好色多淫な女ではなく、純情で真実な恋を求めたということでしょう。彼女の歌や、自伝的小説ともいうべき「和泉式部日記」をみれば、そう思えます。
数ある恋の中で、最も運命的で、彼女の心に深い刻みめをつけたそれは、冷泉(れいぜい)天皇の皇子、帥(そち)の宮・敦道(あつみち)親王との恋でした。宮は二十二歳、式部は三十前後、この恋は世間を騒がす一大スキャンダルとなり、式部は夫から離縁せられ、親兄弟からも縁を切られます。
年上の女の恋は、紫式部も「源氏物語」の中で、六条御息所と源氏との関係で描いていますが、「和泉式部日記」も、じつになまなましく、せつない息づかいを伝えます。
多感で誠実で、美貌の青年プリンスと、一方はあたまの恋を遍歴して浮名をながした恋の手練れ、悪名高い女、しかも美しくて情趣ふかく、打てばひびく才気のある女。双方ともに、恋におぼれ、もはや世間の非難も身内のいさめも耳に入りません。宮はついに邸に女をひきとり、妃は居たたまれず、邸を出てしまわれるという騒ぎ、年上の女の分別で、式部は、この狂い恋の始末は自分からつけるべきだと知りつつも、若い帥(そち)の宮が可愛いくていとしくて離れられないのでした。
「宮のおんさま、いとめでたし。御直衣(おんなほし)に、えならぬ御衣(おんぞ)、いだしうちぎにしたまへる、あらまほしう見ゆ」
「年かへりて正月一日、院の拝礼に、殿ばら数をつくりして参りたまへり。宮もおはしますを見まゐらすれば、いと若う美しげにて、おほくの人にすぐれたまへり。これにつけても、わが身はづかしう、おぼゆ」
と、「和泉式部日記」にはあります。若い貴公子の、かがやくような美しさを、すこしさかりのすぎた年上の女が、愛執と賛嘆と、ほろにがいかなしみでみつめている、その、ほうっと太い吐息さえ聞こえてきそうです。
宮廷でもこのスキャンダルでもちきりでした。宮のご家庭は破壊されようとしています。二人は世間の石つぶてに打たれながら、それでも離れられません。宮にも式部にも、生涯、最初で最後の恋だったのです。
その恋をひき裂いたのは、宮の病気ち、その死でした。帥(そち)の宮は二十七歳の若さで世を去られました。あたかも恋が身を滅ぼした如く。
式部はひとり残され、伏しまろびのたちまわります。年下の男への断ち切れぬ恋の思い出にさいなまれ、涙もかれはて、涙もかれはて、心もくれまどい、血をしぼるような歌が、彼女のくちびるをついて出るのです。
黒髪の乱れも知らず打ちふせばまづかきやりし人ぞ恋しき
黒髪、という言葉が、官能的なひびきをもたらすのが式部の歌らしいところですが、
捨てはてんと思ふさへこそ悲しけれ君に馴れにしわが身と思へば
という歌には、さらに、哀傷と慟哭(どうこく)の裏に、どきっとするような、エロティシズムが匂い立ちます。宮さまに死におくれた者は、いっそ尼になろうと思うけど、この身を捨ててしまうのも悲しい。私の子の体は、今もわたしだけのものではなく、宮さまのものでもあるものを。あのひとが愛撫(あいぶ)し、あのひとが抱きしめ、あのひとが口づけ、あの人の指が探ったからだあるものを‥‥。「君に馴れにしわが身と思へば」というつぶやきには、やはり、年下の男への甘さが感じられるように思われます。
愛を待つ女ではなく、みずから積極的に愛し、いとしみ、妄執(もうしゅう)にちかい狂恋を経験した人の言葉です。「年上の女」という恋愛関係は現代でも流行みたいですが、千年前の式部の歌は、その点でいまも新鮮な命を保っています。
つづく わが愛の磐之媛(いわのひめ)